内田樹先生と三砂ちづる先生の往復書簡による、旧くてあたらしい子育て論。ともに離婚により、男手で女の子を育てあげた内田先生と、女手で男の子を育てあげた三砂先生。その経験知をふまえた、一見保守的に見えるけれども、実はいまの時代にあわせてアップデートされた、これから男の子・女の子の育て方。あたらしい世代を育てる親たちへのあたたかなエール。
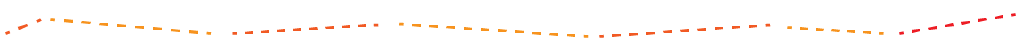
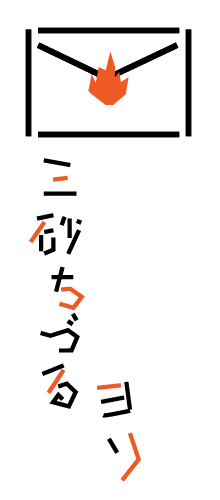
第6便・A
「女の文化」と「男の文化」の絡み合い
内田先生
お便りありがとうございます。
お彼岸でしたね。
内田先生は、東京で育ち、阪神間(のシンボルのような神戸女学院大学)で働き、暮らして来られた方、私は、内田先生と逆に、阪神間で3歳から成人する頃まで育ち、今、東京で暮らしています。父が兵庫県西宮市の人で、「三砂」という姓は、西宮神社由来、ときいていまして、西宮には結構、「三砂」という家があるようです。墓は西宮市内にありますので、お彼岸にお墓参りをしました。母や妹は市内におりますが、新型コロナパンデミックの中、積極的に会おう、と彼女たちにいうのは、気が引けるところもあって、特に連絡をしていませんでした。
祖父母や父の眠るお墓に着いてみると、だれかが父の墓に花を供えています。妹と、ばったり、父の墓で、結局、出会ってしまったのでした。内田先生とも、隣町珈琲でばったりお目にかかりましたが、妹にも父の墓でばったり会い、まあどちらとも、会って不思議はないところで会っているわけですが、このようにタイミングが合うのって、文字通り、ギフトだなあ、と思ってしまいます。そういう天啓は受け取った人のものですから、その天啓のくれる幸せに憩う阪神間でのお彼岸の日々、となったのでした。東京にいると、山はあんなに近くに見えず、海もあんなに近くには、ありません。今や、人生で一番長く暮らした街は東京となりましたが、幼い頃とティーンエイジを過ごした場所には、今も多くを負うています。阪神間の、あの山と海の感じと、言葉のなかで育てられてきたのです。
フランスで谷崎の『細雪』や『陰翳礼讃』が熱心に読まれていることについて前便に書いてありましたね。「フランスでよく読まれている日本人作家は谷崎潤一郎と村上春樹と夏目漱石で、この三人の作家に共通するのは、「何かたいせつなもの」がとりかえしのつかない仕方で失われたトラウマ的経験をめぐる物語を代表作とする」、と。うーん、確かにおっしゃる通りですね。当初、思想がない、とか、時代と格闘してない、とかいわれたことまで、谷崎と村上春樹はなんだか似ているところがあるような気さえ、してしまいます。谷崎は活躍の場として、村上春樹は育った場所として、阪神間に深く根ざした人たちでもあり、心より敬愛しています。村上春樹は、隣の小学校の人で、春樹少年が自転車に乗ってプラモを買いに行った、という西宮商店街は、阪神大震災で様変わりしてしまいましたが私も文房具を買いに通いました。彼がジュヴァイナル(少年・少女向けの本)を貪るように読んだ、という西宮市立図書館で、私もまた小学校の頃、本をよみあさりました。同じ読書カードに名前を書いたかもしれない、と思い、どきどきする一村上ファンです。
西宮の家では、大阪船場から嫁してきた祖母と同居していました。時折、谷崎の『細雪』を文字通り、ぱらっとめくりたくなるのは、東京にいてそれこそ今はない(私が暮らしていた頃にすらすでになかった)、阪神間の雰囲気と、あの独特の会話にふれたいのだと思います。ああいうお嬢さんたちのありようとは、全く関係のない暮らしでしたが、その言葉、空気感がスイッチになって、自分のそれこそ「失ったもの」の記憶が想起されるんですね。谷崎の『卍』も、あの語り口が、大変よろしい・・・。なんとなく、だれもいないところで、こっそり、一人で声を出して読んで、なつかしむのです。谷崎作品で、唯一、同性愛を扱っている、なんて書かれていますけれども、内容は、別に、なんでもいいんです。『卍』の語り口がなんとも素敵で、一人朗読会、を、勝手にやって、その世界に漂うのです。
西宮の小学校の5、6年の時の担任だった神戸大の文学部を出た若い女性の先生(のち詩人になられました)が、いっとき、谷崎が住んでいた、という家を間借りしておられたことがあって、岡本あたりだったか、と思うばかりで、おぼろげな記憶なのですが、その二階家から外を眺めたことは記憶に残っていて、ああ、谷崎もここから外を眺めていたのなあ、なんて思いましたね。なんでも、阪神間には谷崎が住んでいた、という家が、なんだか山ほどあるらしいですから、その一つだったのかもしれませんが、真偽の程は分かりません。気難しく、機嫌が悪く、自分の世界に閉じこもっていた一人っ子(歳が離れた妹が生まれたのはその後のことだったので)だった私に、啓蒙思想だとか、徒然草だとか、源氏物語だとか、教えてくれた先生で、その先生のイメージと谷崎の住んでいた家、というのが、阪神間の記憶とともによみがえります。
「おんな社会」がなくなったこと。女の世間であり、女の社会であり、女の文化。『細雪』に微に入り細に入り描かれていたのは、そういうことですよね。男の文化、女の文化が存在して、その絡み合いこそが、重層的な人間のありようを作っていた。それがなくなった今、男の子をどう育ててれば良いのか、という切実さをどう扱えば良いのか、というのが、この往復書簡のお題として、いただいたものであることも、書きながら思い出します。
内田先生のお手紙に書いてある「家族の同窓会」のことを読んで、思い当たることがありました。夫を亡くして、ひとりものになったとき、長男の結婚前に、長男、次男、わたし、の3人でやった、「集中的な家族旅行」は、まさに「家族の同窓会」であったのだ、ということに、気づいたのです。
我が家の二人の息子たちの父親はブラジル人で、離婚して、10歳と8歳の子ども達と日本に帰ってきました。知り合いの紹介で見合いして、日本人の夫と再婚して、4人で「家族」としての暮らしを東京で15年ほどやったのですが、2015年に、その再婚した夫は亡くなりました。夫が亡くなった頃、次男はまだ関西学院に通っていましたから、東京の自宅にいなかったし、長男は就職して会社の寮にはいっていたので、それぞれがばらばらで、結果として、みんな、ひとりもの、の3人、だった時期があったのでした。
夫が亡くなって3年くらいしてから、最初は、私の還暦祝い、ということで、私がずっと行きたがっていたバリ島旅行を長男が企画してくれて、そのあと、まことに集中的に、ものすごくディープに何度も、「3人で旅行」をしたのです。ふつう、やらないですよね。20代の男の子二人と、母親との、3人での旅行・・・。いくら半分ブラジル人の家族とはいえ、この3人の組み合わせの旅行は、なかなか珍しいもののように思いました。2年弱の間、新型コロナパンデミックが始まるまで、バリ島に二回、箱根、台湾、沖縄・・・。なんだか、必死になって、時間を見つけては、3人で出かけました。
ものすごく楽しかったのです。
最初にバリ島に行った時、ああ、これだった、と、思いました。息子たちも同じように感じていたと思います。熱帯の海とプールの記憶。ココナッツウォーターと熱帯の果物の記憶。私たちが暮らしていた北東ブラジル、セアラ州フォルタレザは、南緯三度、一年中、三十度の気温、朝6時に日が上り、夕方6時に日が暮れます。本当に、毎日、毎日、そのようにして10年が過ぎていました。毎日、暑い。大西洋の外海に面したサーファー好みの海岸のすぐそばに住み、週末には判で押したように車で家から30分ほどのところにある別荘に出かけました。別荘なんて、贅沢な、と思われるでしょうが、ブラジルのいわゆる都市に住む中産階級は、大体週末を過ごす小さな別宅を海のそばに持っていて、そこに家族が集まり、一日中水着(女性は、必ずビキニです)を着て、ハンモックに寝て、お祝い事があれば、シュラスコ(バーベキュー)をやる、というのが休日の過ごし方なのです。友人たちもお互いに訪ね合い、幼い子どもたちはみんな一緒にサッカーしたり、プールで泳いだりして、日がな過ごすのです。
我が家の別荘にも、小さなプールがありました。小さいプールですが、深い。私でも足が届かなかったので、2メートル近い深さだったのではないかと思います。そのようなプールで子どもたちは泳ぎを覚えたのでした。特に次男は、1歳7ヶ月くらいの頃、周りの大人が、ひし、と子どもたちを見守っている中、プールに飛び込みました。大人たちはすぐそばにいて、何かあれば、すぐ救いあげることができる距離にいる。そんな中、次男は、すぐに自分でぷかぷかと浮いてきて、本能的に泳ぎ始めたのです。人間って、本能で泳げるんだな、と、みていて、驚きました。大人たちは次男が泳げるようになったことを喜び、次男はそれから8歳でブラジルを出るまで、週末ごとに2メートルのプールで、長男と二人で、あるいは他の友人たちと、日がな、ぼーっとプールで浮かんだり、泳いだり、潜ったりして、過ごしました。海にもよく行きましたが、外海で波が荒いですから、泳いでいたのはもっぱら、プールでした。
別荘には、深い緑をたたえたマンゴーの木が何本もあり、黄色やオレンジの、ピーマンのような大きさの実をつけるカジュー(カシューナッツが取れます)の木もあり、ヤシの木もあって、ココナッツウォーターを楽しみ、アセロラの実を摘みました。プールのそばの赤い花には、ハチドリ(本当にいるんだ、と感心しました)がやってきて蜜を吸い、木の上には、タマリンというのでしょうか、小さな猿も来ます。犬も猫もいて、子犬や子猫がたくさん生まれました。ぼんやりと暑い中での海とプールの記憶。深いプール。海と水の記憶。両生類みたいにブラジルのリトラル(海岸)でくらしたこと。それが、私たち3人が「失ってしまった」共通の記憶なのだ、と、バリ島で気づいたのです。たわいもないことを話し、美味しいものを食べ、温泉やプールに入りながら、3人で、二年間、何度も旅行を続けました。
そのあと長男は結婚し、我が家は、今、また、別のフェーズに入りました。次男と「あれは、ちょっとすごい時期だったね」と話します。私たちは、確かに、あの時期に「失ったブラジルの日々」を求めていた。そして私たち3人は、あの、ブラジルのリトラル、熱帯の水の暮らしをこそ、共有していたことに気づいた、その風景を私たちだけが日本語で語ることができる、ということに気づいたのだと思います。ブラジルの家族たちとは、ポルトガル語で話すから、文脈が少し違います。あの熱帯の日々を「日本語で」話せるのは私たち3人だけ。その、3人、という強固な何か、を感じた。私たちがどういう記憶を共有しているか、そしてその記憶が、今の私たちをして、私たちにしているか、ということがわかった。あらためて、「家族」であることを再確認したように思います。その時に、わかっていたのではなく、内田先生から「家族の同窓会」という言葉をもらって、「あれはそういうものだったんだな」と、理解するのです。
「国際結婚」では、離婚したからといって、子どもたちをどこに連れて行ってもいい、というわけではありません。子どもたちをブラジルから連れて出るのは、そんなに簡単なことではありませんでした。いわゆる子どもの連れ去りを禁止している、ハーグ条約、とかが関わってくるんですね。日本はまだその頃はハーグ条約を批准していませんでしたが、ブラジル側は、していました。具体的にどういうことになるか、というと、ハーグ条約を批准している国では、片親だけで勝手に子どもを連れて外国に出ることはできません。日本の感覚で言えば、「お母さんは留守番するけどお父さんと海外旅行する」とか「お母さんだけとちょっとどこかに行く」とか、別に全然違和感ないと思いますけれども、多くの国ではそうではありません。片親だけと国外に出る場合は、家庭裁判所に出向き、両方の親がサインをしなければ、片親だけで子どもを連れて国外に出られないのです。
私が子どもたちとブラジルを出た時、父親は子どもたちが私と日本に行くことについて合意し、家庭裁判所で署名していたから、ブラジルを出られたのです。それだけで、大ごと、でした。その後、ブラジルの弁護士も立てて、正式にブラジル側の親権も取りました。日本にいれば、日本の親に日本側の親権はありますけれど、ブラジルの親権も取らないと、私に何かあって、子どもたちが突然ブラジルに戻らなければならない、なんていうことになったら、かわいそうですから。
それって、なかなかにたいへんなことでした。当時、まだwhatsappもskypeもない頃で、高い値段の電話を払ってブラジルの弁護士と話し合い、DHLで書類をやり取りして、合意に至るまで、結構エネルギーのいるプロセスでした。あんまり自分の人生で自慢できることないですけど(子どもがいるのに離婚した時点で、子どもに関して何か、自慢できる、とか、完全にアウトですよね・・・)、この、異国の親権をとった、ということはちょっとがんばった、ということだった、と、思います。現地の腕のいい弁護士を探して、ポルトガル語で説明して、文書作って、交渉して・・・。結構タフなことでありました。次男がブラジルの成人である18歳になったときは、本当に安堵したものです。
ロンドン大学で10年給料もらったり、ブラジルで地元の州保健局や保健省相手に長く働いたりしましたし、あまたの国で“国際協力”の仕事をして来たりしましたけど、「仕事」は「仕事」なので、これとくらべたら、それほどたいへんじゃなかった。個人的なレベルでのさまざまな困難をスムーズにはこぶためにこそ、仕事して経験積むんじゃないか、と思うくらいでした。これを経験したので「国際結婚」する人たちには、ほんとうに、差し上げられるアドバイスはなんだってしたい、というお節介モードになっています。まずはおめでとう、文化の違う人と暮らすことの豊穣を楽しんで欲しい。願わくば、ずっと幸せであって欲しい。でも、その国の様々な制度を少しずつ勉強しておくことは、必要なことだよ、とは、言いたいですかね・・・。
「家族の同窓会」話から、結構いろんなことを思い出してしまいました。もう少し時間が経つと、亡くなった夫との4人の家族の時間のことを、あらためて、あとづけることもあったり、ブラジルの家族と、ブラジルの時間をとらえ直したりする「同窓会」をやることがあるのかもしれません。家族はまさに、「失った時間を共有」するものですね。内田先生に名付けられたから、あれこれと、家族の話を思い出しました。
自分のことばかりで、長くなってしまいました。新型コロナはデータを見ているとどうやら「季節性」がありそうですね。2021年の秋は、少し、動ける状況になってきて、また、冬に向けて、別の波が来るのでしょうか。引き続きご自愛ください。
宮藤官九郎脚本のテレビドラマ『俺の家の話』、みてみます。それでは、また。
三砂ちづる 拝
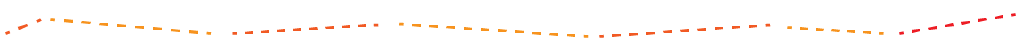
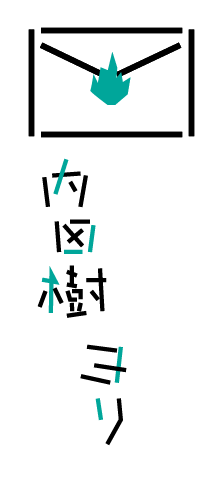
第6便・B
「女の社会」にも「男の社会」にも逃避できること
三砂先生
こんにちは。内田樹です。
第六信拝受しました。
バリ島の「家族旅行」で、ブラジルのことを次々に思い出したというお話、佳話ですね。『失われた時』のマドレーヌじゃないけど、記憶がよみがえるきっかけって、皮膚にじかに触れてくる空気の感覚とか湿度とか食べ物の味わいとか植物の匂いとか、そういうものなんですよね。目は閉じて、外界の情報を遮断することができますけれど、皮膚は閉じられないから、どんどん流れ込んできてしまう。
香港とかバリ島とかは飛行機が空港に着いて、入国審査に向けて歩き出したところで、もう空気の匂いと湿度で「ああ、着いた」という実感がしますね。なんだか、巨大な母親に、逃げようがないくらいの圧力でぐいっと抱擁されたような感じがします。
僕もバリ島が大好きなんです。もうしばらく行ってないですけれど、また行きたいなあ。何もしないで、ただビーチやプールサイドに寝転んでるだけです。推理小説を読んだり、寝椅子に転がって友だちとおしゃべりしたり、昼前からピニャコラーダを飲んだり、冷房の効いた部屋で昼寝をしたり…ただ、そうやってだらだらと時間が流れてゆく。バリ島にいると外の湿度や雨水と自分の体液が相互浸透して、自分と世界とが「ぐずぐずと」一体化したような独特の感じがします。ハワイや地中海だと、たぶん乾燥しているせいでしょうけれど、なかなかそこまで「ぐずぐず」した感じが得られない。バリ島にいると「ああ、『レイドバック』というのはこういう感じなんだな」としみじみ思います。
書いていたらまた行きたくなりました。いつになったら海外旅行ができるようになるんでしょうね。
三砂先生も『細雪』がお好きだと知って、うれしいです。
神戸女学院大学に就職が決まって、東京から関西に引っ越しした時に「住むなら芦屋」と決めていました。
第一の理由は芦屋が谷崎潤一郎と村上春樹の「聖地」だったからです。
もう一つの理由は母親の生まれた土地のそばだったからです。
母親は王子公園近くの生まれで、摩耶小学校を出て、神戸市立第一高女というところに通っていた典型的な戦前のブルジョワ阪神間女子です。だから、『細雪』に出てくる昭和13年の阪神の大水害も経験しています。
母にとっては『細雪』に出てくる景勝地もホテルやレストランも、どれも子どもの頃に両親に連れてゆかれた場所ばかりでした。
僕が子どもの頃、昭和二十年代から三十年代にかけてですけれども、敗戦国日本がほんとうに貧しかった頃、母は時々書棚から古い版の『細雪』を取り出して、懐かしそうに読んでいました。そして僕と兄に向かって、「あんたたちは、こんな美味しいものを食べたり、こんなきれいなものを観たりすることが、もうできないんだね」と哀しげに語りかけました。
そういう時代だったんですよね。戦争に負けて、何もかも失って、日本人が戦前ならちょっと背伸びすれば味わえたあれこれの「贅沢」がもう二度とできなくなった…多くの日本人がそう思っていました。母にとって、『細雪』は「戦後の日本人がもう二度と経験することのできなくなった、失われたものの長大なリスト」だったのです。
それが戦後45年経って、縁あって母親が育った場所のすぐ近くで女の子を育てることになった。文学作品と家族の記憶に引き寄せられるようにして、ある土地に住むようになるというのは、なかなか経験できないことでしょう。幸運なことでした。
どこを「故郷」として選ぶのかについてはかなり自己裁量が許されているような気がします。僕は生まれたのは東京都大田区下丸子で、17歳までそこで過ごしましたが、今はその町を「故郷」として懐かしく思い出して、時々行ってみたくなる…ということはありません。もちろん、小さな頃の家族の風景や家の中や、通学路の風景はありありと回想できるのですが、それはもう脳内にしか存在しません。町の様子はもうすっかり変わってしまっている。ですから、かつて自分の家があった場所に連れてゆかれても、「ここに家があった」とはっきりと思い出すことさえできないだろうと思います。
それよりは7歳の娘と二人だけで、友だちも知り合いもいない見知らぬ土地でひっそりと暮らした芦屋市山手町に「故郷」に近いものを感じます。今も宝塚まで髪を切りに行った帰りには、山越えをして芦屋に出て、山手町のかつての住まいの横を通るのですが、家の外に幼い頃の娘が心細げに立って、僕の帰りを待っている風景が幻視されて、そのつど胸が詰まるような思いがします。そこと通ると「懐かしさで胸が詰まる」という場所は芦屋市山手町以外にはありません。
娘は東京世田谷区上野毛の生まれで、関西に来て芦屋と神戸に住んで、18歳からはずっと東京です。果たして彼女はどの街を自分の「故郷」だと思っているんでしょう。
そういえば、東京に出た後、娘は友だちとバンドを組んで、「くほんぶつ」というバンド名を名乗っていました。九品仏というのは僕が最初に結婚して、彼女が生まれる直前まで住んでいた町の駅名です。「九品仏浄真寺」という名刹が駅のそばにあって、上野毛に住んでいた頃に、娘の手を引いて、よくお参りに行ったり、除夜の鐘を撞きに行ったりしていました。もしかすると「九品仏」は彼女が自分で選んだ故郷なのかも知れません(彼女自身は一度も住んだことがない町なんですけど)。
そういうものかも知れないと思います。何十年住んでも「故郷とは思えない土地」があり、住んだことがなくても「故郷のように思える土地」がある。その土地に何かの「縁」で結びつけられていると感じる土地、そこに立つと誰かに「おかえり」と言ってもらえるような気がする土地がその人にとっての「故郷」なんでしょうね。
なんか感傷的になってしまいました。すみません。でも、子どもはもう大きくなって、遠くに暮らしているので、「子育て」について書こうとすると、自動的に「懐旧談」になってしまうんですよね。
前便で三砂先生が書かれた中でちょっとどきっとしたのは次の箇所でした。
「おんな社会」がなくなったこと。女の世間であり、女の社会であり、女の文化。「細雪」に微に入り細に入り描かれていたのは、そういうことですよね。男の文化、女の文化が存在して、その絡み合いこそが、重層的な人間のありようを作っていた。
ほんとにそうだよな、と思いました。ジェンダーだけでなく、国籍であれ、人種であれ、宗教であれ、出自であれ、政治イデオロギーであれ、属性によって差別がなされて、就学や就職の機会が制限されることに僕は強く反対します。でも、それは、そういう集団属性が「どうでもいい」ものだと思うからではありませんし、人間は集団属性に規定されないと思うからでもありません。どんな人も帰属する集団属性によって、決定的な仕方で規定されます。
すべての個性は等しく尊重されるべきであるという命題と、ある集団に属する者はその集団に固有の属性を具えている(だから、個人としての個性はかなり抑圧される)という命題は、二つ並立させる他はないということです。
人間が集団に属してしか生きられない以上、どちらか一方を諦めろというわけにはゆきません。
ややこしい話です。
三砂先生がおっしゃる「女の世界」のややこしさというのはそういうところにあると思います。集団としての女の権利と地位と尊厳を守ろうと思ったら、「女というもの」は「男というもの」とはっきり差別化されているという話にしないといけない。「女の世界などというものは存在しない」ということになると、「女の集団」を守ることができなくなる。
でも、今の日本社会はそうではありません。
「性差による差別は認められない」と主張する人たちは、しばしばそれと同時に許されるのは「社会的能力による差別だけである」という主張を口にします。「なぜ無能な男性上司の下で、有能な女性が能力の発揮を抑制されているのか?」という抗議はまったくその通りなのですけれども、同時にそれは「すべての人間はその能力によって格付けされるべきである」という命題に同意署名することを意味しています。僕はこの「メリトクラシー」の考え方に恐怖を感じるのです。「全人類はその能力によって1位から70億位まで格付けされることが可能である」という考え方が怖いのです。
今の日本では、「女の世界」の解体は「男の世界」に吸収合併されるというかたちで進行しています。男の世界において価値あるとされているものとは違うものに価値を見出すのが「女の文化」であると僕は思いますけれど、今追求されているのは、もっぱら「男と共に、ハンディなしに権力・財貨・威信の奪い合いの競争に参加できる権利」です。
シモーヌ・ド・ボーヴォワールは『第二の性』で近代フェミニズムの基本的なアイディアを提出しましたが、これは1930年代にパリで開講されていたアレクサンドル・コジェーヴのヘーゲル『精神現象学講義』を換骨奪胎して作り上げたものです。コジェーヴのヘーゲル講義には当時のフランスの知識人たちが文字通り門前市をなしました。聴講生リストにはレイモン・アロン、ジョルジュ・バタイユ、ジャック・ラカン、モーリス・メルロー=ポンティ、レイモン・クノー、ロジェ・カイヨワ、ジャン=ポール・サルトルら、戦後フランス思想界を牽引する知識人たちの多くが名を連ねています。
ボーヴォワール自身はこの講義を聴講していませんでしたが、聴講したサルトルやメルロー=ポンティを経由して、コジェーヴのヘーゲル解釈には深く親しんでいたようです。
コジェーヴはそのヘーゲル講義で『精神現象学』を祖述して、人間は他者からの承認を求めて命がけの闘争をすると論じました。「生死を賭して」とは言いますけれど、相手からの承認を求めての闘争ですから、相手が死んでしまっては意味がありません。死んだ人間からは承認されませんし、欲望されることもないからです。だから、この闘争では、相手が生きており、かつ「承認を求める闘争に負けた」と認める必要があります。つまり、この戦いに負けた方は生きていて、かつ意識もはっきりしているのだけれど、「自立性」を失っている。それが「敵を奴にする」ということです。
承認を求める闘争での勝者が「主」となり、敗者が「奴」となる。ヘーゲルは世界史とはこの主人と奴隷の承認を求める戦いの歴史であると述べました。
ボーヴォワールはヘーゲルにおける「主」を「男性」に、「奴」を「女性」に読み替えれば、それがそのままフェミニズムの理論になることに気づきました。これは卓越したアイディアだったと思います。
「男性=主」は「女性=奴」を保護し、居場所を与え、仕事を与え、その代償として自由を奪う。多くの女たちはこの生き方に安住している。ボーヴォワールはそう考えました。「これは安逸の道である。」女たちは奴の生活に安住することによって、実存的な苦悩と緊張を免れる。そして、男たちも女にそういう生き方を勧奨する。「女たちは男たちと競争すべきではない。なぜなら、女たちは男たちとは価値観を異にする『他者』だからである」というのが、男たちの言い分でした。これは実は女たちの自由を奪うために男たちがしつらえた奸計なのだが、女たちの耳には快く響いた、というのがボーヴォワールの考えでした。
ですから、「男にとっての他者」の地位に安住している女たちに向けて、あなたたちは因習的な奴隷状態に安んじているに過ぎない。男たちとの「命がけの戦い」に参加すべきだとボーヴォワールは訴えたのです。
「女性のドラマとは、つねに本質的なものとして自己措定しようとする主体の根本的な権利要求と、女性を非本質的なものとして構成しようとする状況の要請との間の確執なのである。」
ボーヴォワールにとって人間の正統的なあり方は一つしかありません。自分もまた主人になるために戦うことです。より強大な権力、より大きな自由、より広い可動域、より高い地位、より多くの収入を求める争奪戦に身を投じることです。
でも、このヘーゲル主義的フェミニズムの難点は「世の中には主と奴しかおらず、全員が主になろうと戦っている」という前提をそのまま受け入れてしまったことでした。
たしかに「ヒエラルヒーの頂点めざす競争に性差はあってはならない」というのは正しいのです。ものすごく正しい。でも、だからと言って「万人はヒエラルヒーの頂点をめざして、他人を蹴落とすために競争すべきである」というのは無条件に受け入れてよい命題ではありません。
「権力も位階も、格付けも競争もなく、みんなが支え合う社会があってもいいじゃないですか…」というかすかな声はここではかき消されてしまう。でも、このかすかな声は久しく多くの女たちが小さな声でつぶやいてきたことでした。僕はこの声は、性差にかかわらず、女が口にしようと、男が口にしようと、決してかき消されてはならない声だと思います。
ヘーゲル主義的フェミニズムの難点は「資源の争奪のための競争におけるフェアネスを求める」ことが自動的に「資源の争奪のために競争するのはよいことである」という弱肉強食宣言への同意署名することになるという点にありました。このアポリアを解決する正解はありません。ですから、ボーヴォワールは正直に「当惑」してよかったと思います。「困ったことになった」と頭を抱えてよかったのにと思います。競争におけるフェアネスはたいせつだが、競争することそれ自体は決して「よいこと」ではないというわかりにくい言明のうちにとどまることが必要だったと思います。
言っていることの半分しか正しくないというのは、誰にとってもあまり愉快なことではありませんが、この問題については、それを認めるしかない。
三砂先生が書かれている「女の社会」「女の世間」「女の文化」という「他者の領域」は毀損されてはならないと僕は思います。そちらに片足を乗せたまま、「男の社会」のヒエラルヒーの頂点をめざす戦いにもコミットする。
どうして女ばかりそんな「損な」ことを強いられなければならないのかと怒る人がきっといると思いますけれど、二つの価値観に片足ずつ乗せて生きるというのは、それほど悪いことじゃないと僕は思います。男だって逆のことをできるし、した方がいい。ヒエラルヒーの頂点を求める競争から脱落すると「男の社会」では敗者、落伍者と査定されますけれども、「女の社会」に逃れ出れば、そんな格付けは意味を持たない。
僕は離婚してひとりで子育てをすることになった時に、「男の社会」での競争優位をめざすことを断念しました。もうコンスタントに論文を書いたり、学会発表をしたり、学界内部的な評価を高めようとか、そういうことは諦めることにしました。してもいいけれど、それだけの時間を確保しようとしたら、四六時中何かに急き立てられ、時間に追われ、憔悴するに決まっています。そしたら、いずれ子どもを「自己実現の妨害者」だとみなして、無意識のうちにつらく当たるようになる。そんな不機嫌な人間に育てられたら子どもも気の毒です。だったら、あっさり「男の世界での競争」は諦めて、子育てに専念しようと決めました。これからは母親になる。家事を「本務」とする。研究は「副業」。子どもに三食栄養のあるものを食べさせて、きちんと洗濯して、アイロンの効いた服を着せて、日に干して温かい布団に寝かせてあげられたら「母として100点」を自分に与える。もしそのあとにまだ時間が残っていたら、それは「ボーナス」としてありがたく頂く。本を読んだり、翻訳をしたり、論文を書いたり、自由に使ってよい。でも、それはあくまで「ボーナス」なので、ノルマとか目標とか締め切りとかそういうものは設けない。
そうやって「競争から降りる」と腹をくくったら、気分がずいぶん楽になりました。だって、毎日「今日の自分に100点」なわけですから。そうなると、わずかな「ボーナスタイム」での仕事がずいぶん捗ります。ですから、意外にも、12年間の僕の「母親」時代というのは、結果的には学術的にもわりと豊かな時間だったのでした。
もし、あの時期を「男の社会」に軸足を置き続けて、「家事労働に費消していなければ研究に使えた時間」を「損失」に計上していたら、ずいぶん不機嫌でいやな感じの男になっていたと思います。
あの時に「女の文化」に逃避できたことで、僕はずいぶん救われました。晴れた午後にエプロンかけてリビングに座って、モーツァルトを聴きながらアイロンをかけたり、娘の体操着の胸の名札を縫い付けている時なんか、しみじみ「母であることのしあわせ」を感じたものです。
人間、一生の間ずっとヒエラルヒーの頂点をめざして他人と競争しているわけにはゆきません。そんなことに全身全霊をあげて集中できるのは、一生のうちごくごくわずかな時期です。そんなことばかりしていたら、ふつうは身体が持ちません。だから、誰にでも逃げる先が必要なんです。「女の社会」「女の世間」「女の文化」というのは、僕にとって「アジール」でした。そう感じる男たちは他にもたくさんいるような気がします。
また今回も長くなってしまいました。ごめんなさい!
内田樹 拝
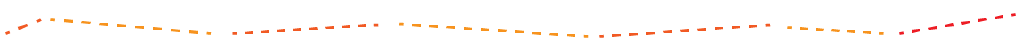
 内田樹(うちだ・たつる)
内田樹(うちだ・たつる)
1950年東京生まれ。凱風館館長。神戸女学院大学文学部教授。専門はフランス現代思想、映画論、武道論。著書に『「おじさん」的思考』『こんな日本でよかったね』『コモンの再生』『日本習合論』など多数。『私家版・ユダヤ文化論』で第六回小林秀雄賞を、『日本辺境論』で2009年新書大賞を受賞。
三砂ちづる(みさご・ちづる)
1958年山口県生まれ。京都薬科大学卒業。ロンドン大学Ph.D.(疫学)。津田塾大学多文化・国際協力学科教授。著書に『女たちが、なにか、おかしい おせっかい宣言』『自分と他人の許し方、あるいは愛し方』『オニババ化する女たち』『死にゆく人のかたわらで』『自分と他人の許し方、あるいは愛し方』『少女のための性の話』など多数。

