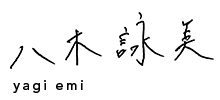『空芯手帳』『休館日の彼女たち』、ユニークな小説2作を発表し、国内外で注目を集める作家・八木詠美。本書は著者初のエッセイ連載。現実と空想が入り混じる、奇妙で自由な(隠れ)レジスタンス・エッセイ。
また、あたった。
宝くじの話ではない。食べ物のことだ。
3月の終わり、窓の外では桜のつぼみがふくらんでいるらしい。散歩でよく歩く川沿いに行けば、遊歩道は温くなった水のにおいと生き物の気配に満ちているのだろう。天気はすばらしく、マンションの部屋の中まで透明な明るさに浸されている。天井に流れる光の文様を眺めながらわたしは一人、寝室で横になっていた。ウイルス性胃腸炎だった。
見当はついている。2日前に食べたフレンチだと思う。結婚記念日ということで夫とお邪魔したお店はクラシカルなフレンチレストランで、コースをお願いしていた。メインの牛肉のシンタマのローストもおいしかったし、個人的には2皿目のさっとソテーしてガスパチョソースと合わせたイカがすごく好きだった。いくつかの料理ではジビエや生の貝類が出て、自分にとっての黄信号が途中で何度か灯った。けれど別にアレルギーがあるわけではないし、何度か来たことのあるお店だから大丈夫だろうとそのままコースを横断した。夫もおいしそうに食べ、その後も変化がないから、お店の調理に問題があるとは今も思わない。良い夜だと思いながら帰宅した。
けれどそれはやってきた。夜中に痛みで目覚めると、お腹の中で何かがのたうち回っているのがわかった。哀れな胃腸は暴れるそれを進ませることも戻らせることもできないようだった。薬を飲もうにも体が動かず、なんとか隣で眠る夫を起こし、胃腸薬を持ってきてもらった。薬を飲んだ後もそれはしばらく暴れ続け、明け方に痛みが通り過ぎるとようやくわたしは再び眠った。そして目覚めると熱があった。
思えばずっと、一人で何かにあたっている。一番の宿敵は、今回は食べなかったけれど生牡蠣だ。ちゅるりとしたその身にレモンをしぼり、頬張ってから白ワインを飲む。とてもおいしい。とてもおいしいから、友人がオイスターバーに誘ってくれる。夫が仕事で知り合った養殖所から送ってもらう。大いに食べる。とてもおいしかったから、幸せな気持ちで帰宅し、眠りにつく。腹痛で夜中に目が覚め、トイレに駆け込む。翌朝になると発熱し、病院に行く。とてもおいしかったな、と思いながら診断名を告げられる。それを繰り返している。一緒に食べた人たちは何事もないというのに。
そう話すと、親切な人たちはまず「アレルギーなんじゃないの?」と言い、いや、牡蠣フライなど加熱したものだと大丈夫なんですと返すと次に「じゃあここの生牡蠣なら絶対にあたらないよ」と言っておすすめのお店や養殖所を教えてくれる。「絶対にあたらない牡蠣」と「絶対にあたるわたし」の戦いが始まる。結果は今のところ、わたしの完勝である。真っ暗な寝室で目覚めて痛みと気分の悪さに悶え、「また勝ってしまった」と思いながらトイレへと急ぐ。完勝だけど、状況としては完敗である。
けれどわたしは、具合が悪い日に本を読むのが好きだ。子どものときもそうだし、今も好きだ。今日は学校や仕事を休むのだと決めこみ、母や夫に準備してもらった温かい湯たんぽを抱えながら昼間のベッドに潜りこむ贅沢。眠るためにカーテンはしめるけれど光を完全に締め出すことはできず、寝室の天井や壁は夜のそれらとはちがう穏やかな表情を浮かべている。もちろん起き上がっているのがしんどいわけだからこうして眠って体を休ませるわけだけど、眠りと眠りの間の、しかし次の眠りはしばらく来てくれなさそうだというときに、傍らに置いていた本をぼんやりと読む。具合は悪い、しかし数日で回復するだろうという自信によって支えられている、ずいぶんと安楽な趣味だと思う。
よいのか悪いのか、文学者の中には病弱な人が多く(数えたことはないけれど、不健康なアスリートよりは不健康な作家の方が多いと予想する)、健康な作家が書いたものも含め、小説には軽い風邪から結核やペストまでさまざまな病気が登場する。ベルンハルト・シュリンクの『朗読者』は、帰宅途中の少年・ミヒャエルの嘔吐から始まる。ミヒャエルは介抱してくれた年上の女性・ハンナと恋に落ちる。ハンナは実は第二次世界大戦中にユダヤ人の強制収容所で看守をしており、そして文字が読めない。そうとは知らず、ミヒャエルはハンナに乞われてさまざまな物語を朗読する。ハンナはあるとき、ミヒャエルの前から姿を消す。
『朗読者』を読みながら、ハンナは病気のときは何をしていたのだろうと考える。わたしはこうしてベッドで本を読んで回復を待っているが、文字の読めないハンナならどうするのか。物語を読むことは、ここではない世界があることを思い出させてくれる。もちろん、人によっては読書でなくてもそんなことは簡単に思い出せるのかもしれないけれど、病気で体が思うように動かないときは読書がもっとも親切な友人であるようにわたしは思う。自らの過去を話して周囲に心を開くことも叶わず、読書をして他の世界へと思いを巡らせることもできずにベッドに臥せるハンナを想像する。その様子はやがてぴたりと固く口を閉じた孤独な二枚貝へと変わる。けれど貝の様子を思い浮かべるうちにわたしの頭は次第に鈍り、また眠ってしまう。ひどく暗い夢を見る。
そういえば小説の新人賞に応募をした日の夜も、わたしは懲りずに牡蠣を食べていた。締め切り当日の夕方に原稿を送ったものの印刷に不備があったことに気づき、もう一度印刷し直して夜中も営業している郵便局に出しに行った。帰ってきたのはもう少しで日付が変わるというところで、家にあった牡蠣を夫が蒸してくれて食べた。加熱すれば大丈夫かと思ったが駄目で、翌日の夕方、会社で打ち合わせをしているときに吐き気がしてトイレに行った。
トイレから戻ったわたしの顔色がよほどよくなかったのか、打ち合わせをしていた同僚は「早く帰って休んだ方がいいのでは」とすすめてくれた。その言葉に甘え、「帰って薬でも飲もうと思います」と話すと、同僚は「薬はあまり飲み過ぎない方がいいと思う」と小さな声で言った。どうやら妊娠のつわりだと思われていたようだった。
妊娠したと主人公が周囲に嘘をつくその小説で、わたしは小説家になった。