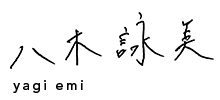『空芯手帳』『休館日の彼女たち』、ユニークな小説2作を発表し、国内外で注目を集める作家・八木詠美。本書は著者初のエッセイ連載。現実と空想が入り混じる、奇妙で自由な(隠れ)レジスタンス・エッセイ。
学生のころ、一度だけ単位を落したことがある。確か「ヨーロッパ文化の礎」という講義だった。月曜日か火曜日の4限の講義だったと思う。
といっても、さぼっていたわけではない。どちらかといえばそれなりにきちんと参加していたように思う。毎週講義に出て出席カードの裏には感想を書き、必要に応じて図書館で本を借りていて読んでいた。
おかしいと思ったのは、メールが届かないことだった。課題や休講についてのメールが受講している学生宛てに送られているらしいのだが、なぜか届かない。講義の後に教授に相談すると、「じゃあ確認するから、僕のところに一度メールを送って」と言ってアドレスを書いたメモをくれた。わたしはさっそくメールを送る。Y先生、とメールの冒頭に書いて。わたしが受講登録しているのはY先生の「ヨーロッパ文化の礎」のはずだった。
しかしすぐにやってきた返事のメールはこう始まっていた。
「僕の名前は、Oです」
そこでようやく気づいたが、わたしは隣の教室の講義を受けていた。Y先生の「ヨーロッパ文化の礎」は隣の教室だったのだ。普通に気づきそうなものだけど、わたしが間違えて受講していたのは古代ギリシャとローマ帝国の講義だった。やけにギリシャとローマの話ばかりだなとは思っていたが、それだけヨーロッパ文化というものは古代ギリシャとローマ帝国によって決定された部分が大きいのだと納得し、ギリシャ彫刻やローマの地下墓地の画像を熱心に見ていた。
そのようにして自分の誤りに気付いたのは、もうキャンパスに半袖のTシャツがあふれて期末レポートの課題が発表されるタイミングだった。今から講義に出ても出席数が足りず、内容的に追いつけるとも思えなかった。それでも何とかならないだろうかと事務所で相談をしてみると、事務員の方は指サックをつけたまま奇異なものを見る目でこちらを眺め、わたしはすごすごと帰った。その後は本来受講すべき「ヨーロッパ文化の礎」にも、今まで熱心に出席していた古代ギリシャとローマ帝国の講義にも参加しなくなり、わたしはひっそりと単位を落した。
その前からうっすらと気づいていたが、わたしはあまりにぼんやりしているというか、ものを知らない。お札の「透かし」のことを知ったのも大学生のときで、何となしに千円札を持ち上げたら中央に老人(夏目漱石)の顔が浮かび上がってきたので、腰を抜かしそうになった。
そう話すと、どうしてそれまで気づかなかったのと言われるけれど、自分以外の人たちがそれぞれの人生のどこかのタイミングでお札を透かして透かしに気づいたり、家族や物知りな友だちが「そういえば日本のお札というのはね……」と言いながら透かしを見せて教えてくれたりする瞬間があることの方にむしろ驚き、わたしたちはこんなにもわかりあえないのに、お札の透かしのことを知るシーンは同様にあるという事実に果てしない気持ちになってしてしまう。
ジャイアント馬場とアントニオ猪木が別人であることはごく最近知った。文字にすると不思議なことのような気がするけれど、本当に1人の人間だと思っていた。同じ人間が2つの名義を持っていると思っていたわけではない。ただ、ジャイアント馬場という名前を聞くとアントニオ猪木の存在を忘れてしまい、アントニオ猪木の名前を聞くとまた逆のことが起こり、1人の人物として頭の中の同じ場所に収斂されてしまうのだ。「名前を付けて保存」ではなく、「上書き保存」というかその都度ファイルの名前が自動で変更されていた。
だから夫がジャイアント馬場とアントニオ猪木の試合の画像を見せてくれたときは「2人もいる!」と本当に驚いた。当たり前のことだけど。ジャイアント馬場とアントニオ猪木は別の人間だから。
けれど小説を書いていると、自分が「知らない」人間でよかったと思う瞬間もある。もちろん社会や歴史については知っていた方がいいし、知識がないことを盾に人を傷つけることは絶対によくないのだけれども、ものごとを、それも基本的なことや普遍的なことを知らないから、その一片でも知りたくて小説を書いているのではないかと思うことがある。
例えばさっきは「2人もいる!」と驚いたことを書いたけれど、そもそもわたしは「1人の人間がいる」ことがどういうことなのかよくわかっていない。ある人が死んでしまい、けれどその死を知らない人の中でその人の存在があるのであれば、それは1人の人間がいることになるのか、ならないのか。そうしたことを自明のものとして語る人の言葉を、わたしはあまり信用しないのではないかと思う。大して説明もしないうちに「結局さ」と、結論めいたものを突然話し出す人を目にすると、いつもそっと心が冷える。
わからないから書き、わからなさを比喩にし、どうしてかわからないけれど物語が動く瞬間がある。その一行に、わたしは驚いていたい。
夏と呼ばれる季節が来る。わたしが隣の教室の講義を受けていたことを知り、事務所をすごすごと退散して空を見上げたときの、あのあっけらかんとした眩しさをぴたりと名指す言葉をわたしは知らない。