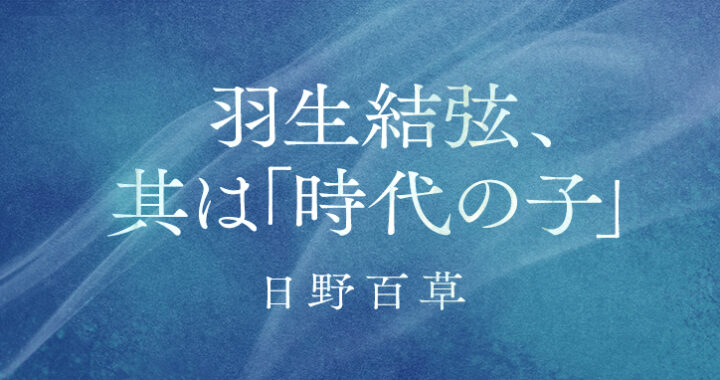稀代のフィギュアスケーター、羽生結弦。いまだとらえがたいその実像と業績を、歴史のなかに位置づける。文筆家の日野百草がおくる渾身の羽生結弦論。
時代の子
「さあ第二幕、私たちも彼と共に壁の先を、羽生結弦という芸術の高みを見よう」
2022年7月19日、私は『そして伝説へ…引退・羽生結弦が紡いだ”芸術のバトン”』(※1)の中でそう書いた。同日の羽生結弦によるプロのアスリート、プロフィギュアスケーター転向会見を受けての原稿だった。
それは羽生結弦とその時代、まさしく第二幕の幕開けだった。
いまとなっては時代の先、歴史の幕開けだが、いまは措く。
私はその中で歴史に名を残す人物はまず「記録」「記憶」「結果」であると書いた。これらに「時代の子」という要素が加われば「歴史の人」、やがて「伝説」になると。そう単純なものでなさそうに思えるが、案外、歴史というのは人が創るものなのでシンプルなものだ。
そうした「歴史の動向を継続的に規定している要因としての「一般的雰囲気」を理解し、析出すること」(※2)を歴史学(比較史)のアナール学派マルク・ブロックは説くが、これが歴史全体でなく、特定の人物史となると尚更シンプルなものとなる。もちろんシンプルにも「その先」があるのだが、実態としてはこの「記録」「記憶」「結果」に「時代」「歴史」そして「伝説」、果ては「神話」という法爾の大河には変わりない。
羽生結弦という存在をいまさら説明するでもないが、まずは連載にあたり簡便に記す。この「記録」「記憶」「結果」を端的に綴る。その躍動こそまさに「時代の子」そのものであった。
羽生結弦、1994年12月7日宮城県仙台市に生まれ、4歳からフィギュアスケートを始めた彼は瞬く間に日本の、いや世界でもっとも優れたフィギュアスケートとなり、男子フィギュアスケート競技100年の歴史上、ギリス・グラフストローム(1920年、1924年、1928年)、カール・シェーファー(1932年、1936年)、リチャード(ディック)・バトン(1948年、1952年)以来となる冬季五輪男子シングルの連覇(2014年ソチ、2018年平昌)を成し遂げた。この偉業は戦前戦後まもなくのグラフストローム、シェーファー、バトンから遥かに半世紀以上を経ての達成であった。
また男子シングル唯一のスーパースラム(五輪、世界選手権、グランプリファイナル、四大陸、世界ジュニア、ジュニアグランプリファイナル)の達成者でもある。時代によっては存在しなかった大会もあるため厳密ではないのだが、それでも結果として羽生結弦が「男子シングル唯一」のスーパースラム達成者であることは事実である。
これらを総じて、羽生結弦はまず「記録」「記憶」「結果」を成し遂げたということになる。その他、数字としての「初」「当時の最高点」は数え切れないため割愛するが、歴史における「稀有な存在」であることは確かだ。
しかし「稀有な存在」の先に「唯一無二の存在」という命題も待ち構えている。それは単に「一人ひとりが唯一無二」「誰と比べるでなく唯一無二」といった話でなく、歴史という大河における人物史、比較史における「唯一無二の存在」である。それぞれのジャンルでその時代に代えがたい存在、その場合「時代」が命題となる。つまり「時代の子」ということになる。
たとえば20世紀のアーティストで言うならチャールズ・チャップリン、ビートルズ、ココ・シャネル、パブロ・ピカソだろうか、マリリン・モンローもそうだろう。それは「時代のアイコン」という言葉でも表される通り、その時代の象徴としての存在でもある。そして「記録、記憶、結果」の備わった先にある「時代の子」という命題、それを達成するために必要なもの、私は常々それを「社会性」と説く。
この「社会性」もまた一般的な「◯◯さんは自分勝手で社会性がない」とか「◯◯さんは成長して社会性が身についた」といった使い方でなく、あくまで芸術における「社会性」である。社会性俳句で知られる文化功労者、金子兜太はこの社会性について、
「社会性は作者の態度の問題である。創作において作者は絶えず自分の生き方に対決しているが、この対決の仕方が作者の態度を決定する。社会性があるという場合、自分を社会的関連のなかで考え、解決しようとする「社会的な姿勢」が意識的にとらえられている態度を指している」(※3)
としている。それはアーティストが自ら実践することもあれば、その時々の歴史の、時代によって発揮せざるを得なくなることもある。いずれにせよ「時代の子」として歴史に「残る」人物に不可欠な要素である。内的な動機以上の外的な動機、ときに衝動による創作である。それは戦争だったり、災害だったり、苦しむ人々と社会全体の理不尽さだったり、自己の問題と同時に他者の、社会の問題を作品に表現する。利他の芸術、としてもいいだろう。
先の例で言えば、チャップリンとはまさにそういう人だ。もちろん彼の同時代でも記録、記憶、結果で彼と匹敵する俳優はいる。喜劇で言えばバスター・キートンやハロルド・ロイド、スタン・ローレルやオリヴァー・ハーディ(ローレル&ハーディ)もそうか。みな当時の喜劇界における大スターである。しかしその創作に明確な「社会性」があった、そしてその態度が時代を象徴する作品を生み出し、それによって社会もまた一歩先に進んだ。ときにそうした時代に、社会に翻弄されながら――それはチャップリンにおいて他はない。
すでに人気コメディアン、映画俳優で監督でもあったチャールズ・チャップリンは1937年ごろからナチス批判のための喜劇映画『独裁者』の構想を練り始めた(※4)。
第一次世界大戦からしばらく、アドルフ・ヒトラーらによるナチズムはドイツを、そしてヨーロッパを席巻していた。とくにナチスのユダヤ人などの特定民族、そして障害者などの弱者に対する差別主義に反感を抱いていたチャップリンは(※5)、そうした差別による支配と侵略を支持する社会に自分の喜劇映画で一石を投じる態度を示す。ナチスの行進や熱狂のリズムを無機質で恐ろしいものに変えてしまうという、ファシズムの恐怖と本質を捉えたチャップリン(※6)はナチズムの本質が暴かれる前からその「恐怖」を見抜いていた。
そうして完成した映画『独裁者』は総統ヒトラーに喧嘩を売るような内容だった。すでにドイツ国内では反戦主義的なテーマ性やヒトラーと似た「チョビ髭」だとして彼の作品はドイツ国内で上映禁止となっていたが(※7)、本作は決定的なナチズム批判の作品だった。それもラストは約6分に渡るナチズムに対する批判演説であった。
このラスト、映画芸術としては「蛇足」である。言いたいことを全部しゃべってしまっては映画本編の意味がない。しかしチャップリンは訴えたかった。言わなければならないことがあった。ナチズムの危険と差別の恐ろしさと悲劇、人間の愛を伝えるためなら、ときに芸術性など振り払っても構わない、彼にとって命より大切な映画でも。これこそ「社会性は態度の問題」における「態度」の発露、自分に課した使命であった。この態度の表れとその姿勢もまた「作家性」である。
私は羽生結弦とは、そうした「時代の子」に運命づけられた人物と確信している。なぜなら羽生結弦のフィギュアスケートもまた、そうした「社会性」を内包している。それは彼自身の被災という運命、そしてその後のショウやプログラムといった創作における「自分を社会的関連のなかで考え、解決しようとする態度」が、とくにプロ転向後のアイスショウやプログラムで明確に表現されている。規定や採点といった制約から解放されて以降の羽生結弦の作家性とその発露こそ「時代の子」の証左であった。それこそ「使命」かのように。
まずはチャップリンという他ジャンルから引いたが、これも大げさでも何でも無く、羽生結弦とはそうした歴史上の比較でしか語ることができないが故である。
もちろんこの「時代の子」はフィギュアスケート、広く舞踏芸術の世界にも歴史上の人物として存在する。ソニア・ヘニー、カタリナ・ヴィットはそうだろう。イサドラ・ダンカン、ヴァツラーフ・ニジンスキー、アンナ・パブロワ、ルドルフ・ヌレエフなどもそうだ。重ねるが羽生結弦はそうした歴史上のスケーター、ダンサーとの比較論でなければ定義できない存在である。これはこの国にとっても本当に凄いことなのだが、いずれその凄さも語ることとしよう。
まずはヴァツラーフ・ニジンスキー、私は羽生結弦がこの国から世界に、時代に、歴史におけるニジンスキーのような「伝説」となることもまた、確信している。それは先に述べた要素の数々だけでなく、同じ時間を、時代を共有した人々の思いの強さという共通点にある。
つまり、羽生結弦と共にある人々=私たち、のことである。私たちもまた、羽生結弦という時代を生きる、時代を創る存在にある。その僥倖に、使命にある。
(続)
- 参考文献
※1 日野百草著『そして伝説へ…引退・羽生結弦が紡いだ”芸術のバトン”』みんかぶマガジン、2022年7月19日配信。https://mag.minkabu.jp/life-others/25178547038/?membership=1
※2 マルク・ブロック著・高橋清徳訳『比較史の方法』講談社,講談社学術文庫,2022年3刷,88頁.
※3 金子兜太著『金子兜太集 第四巻』筑摩書房,2002年,189頁.
※4 大野裕之著『チャップリンとヒトラー メディアとイメージの世界大戦』岩波書店,2015年,77頁.
※5 前掲書・大野,86頁.
※6 前掲書・大野,76-77頁.
※7 前掲書・大野,40-49頁.

1972年、千葉県野田市生まれ。日本ペンクラブ会員。出版社勤務を経てフリーランスで横断的な文筆活動をおこなうかたわら、京都芸術大学大学院芸術研究科芸術専攻で舞台芸術を研究する。2018年、評論「『砲車』は戦争を賛美したか 長谷川素逝と戦争俳句」で日本詩歌句随筆評論協会賞奨励賞を受賞。みんかぶマガジンに「ファンしか知らない羽生結弦」を連載。