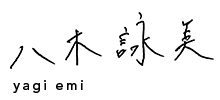『空芯手帳』『休館日の彼女たち』、ユニークな小説2作を発表し、国内外で注目を集める作家・八木詠美。本書は著者初のエッセイ連載。現実と空想が入り混じる、奇妙で自由な(隠れ)レジスタンス・エッセイ。
新卒として入社した最初の数年間、殺伐とした部署にいた。
どのくらい殺伐としていたかは今も同じ会社に所属しているのでなかなか書きづらいが、在籍したメンバーのうち半数以上はすでに退社し、ついでに部署そのものも解体されるようにいくつかに分かれ、今は存在しない。大勢のメンバーがいる前で上司が一人を大声で叱責する姿を目にするのは珍しいことではなく、配属前の顔合わせで「なんでも遠慮なく聞いてね」と言ってくれた先輩は仕事中ずっと耳栓をしていたので、直接質問するのは早々に諦めた。
もちろん嫌なことばかりではなく、学ぶことや楽しいこともあったが、その部署にいて一番よかったのは、自分は後輩と呼ばれる人にできる限り親切にしようと思うようになったことだ。
そんな新卒生活を支えてくれた存在、それは人ではなく煮物だった。肉じゃが、筑前煮、切り干し大根の煮物、筍の土佐煮、エトセトラ。一人暮らしをしていたわたしは、週末にまとめて煮物を作り、平日はそれを5日間かけて少しずつ食べながら細々と魚を焼いたり味噌汁をつくったりして生き延びていた。
煮物はすごい。まずおいしい。
煮物はすごい。作った後何日かもつ。
煮物はすごい。ある程度鍋の世話をすればあとは放っておいても完成する。
しかし煮物のすごいところはそれだけでない。
コロナ禍前で会社での飲み会もそれなりにあった当時、残業をしていると「飲みに行かない?」と誘われることがときどきあった。しかし今日中に終わらせなくてはいけない業務はまだ残っている。そんなときに活躍するのが煮物だ。
「すみません、作って5日目のかぼちゃの煮物が家にあるんです」
相手が料理をする人ならば「5日目か~それはそろそろ食べなきゃね」と言って断念してくれる。料理をせずあまり意味が届いていなさそうな人には「〇〇さんに飲みに誘われるのを待っている人は他にもたくさんいますが、かぼちゃが待っているのはわたしだけなので」と続ければ大抵は遺恨なく断ることができる。いや、本当は遺恨はあったのかもしれないが、気にしないことにしている。そのケアの分までの給与はもらっていない。
けれど夜9時くらいまで残業しているとさすがに小腹が空いてくる。何か食べたい。が、わたしはコンビニのおにぎりやお弁当が苦手だった。一口目はおいしいと思う。けどその後干からびる。日ごろ地味な自炊生活をしていると、コンビニの商品の塩分量に耐えられなくなる。
そんなときに助けてくれるのも、やはり煮物だ。
わたしは冷蔵庫から里芋の煮っころがしを持ってくる。残業が多くなりそうな期間は家で作った煮物を会社に持ってきて、給湯室の冷蔵庫に置いていた。本当は温めたいが、レンジ不可の容器であることが多かったのでそのまま食べる。おいしい。煮物だからだ。
夜の会社で煮物を食べていると話しかけられることもある。
「え、何食べてるの?」
「里芋の煮っころがしです。コンビニだとお金かかるので」
しょっぱいから、とは言わないでおく。話しかけてきた相手も残業をしていて、大抵はコンビニのビニール袋をぶら下げているから。
よほど不憫に思われたのか、そのビニール袋の中から相手が何かを取り出し、差し出してくれることもある。
「これ、あげる」
ありがとうございます、と言って受けとったそれはチョコとかグミとか小さなお菓子で、デザートだ、とわたしは思う。主食に里芋、デザートにチョコ。糖質の取り過ぎだとは思っても、そういう日は少しだけ残業が苦でなくなる。
それからもう十年近くが経ち、わたしは部署を異動した。異動先の部署では残業が減り、ついでにここ数年はリモートワークという形で自宅で働く日が多くなった。それと並行して小説を書き始め、今では小説家としての仕事の方が生活の中心になりつつある。また、デビューする前年に結婚をし、一人暮らしではなくなった。2人で食べると煮物はあっという間になくなってしまうし、以前より料理をする余裕ができたので、作り置きはあまりしていない。
今思えばあんなに疲れていたのにどうして自炊にこだわっていたのかうまく思い出せないが、とにかくわたしは週末になるといつも煮物を作っていた。多くは日曜日の午後。翌日のスケジュールを思い出してげんなりしながら野菜や肉を切り、狭いキッチンに調味料を並べ、シューシューという音とともに落し蓋が少しずつ下がっていくのを眺めていた。
「自分で自分を大切にする」ことが謳われるようになって久しいが、わたしにとって煮物を作っていたあの時間は自分のためのケアであり、同時にサバイバルの一つだったのだと思う。鍋からたちのぼる湯気は肌を保湿するスチームであり、十数時間後には必ずやってくる平日に立ち向かうための狼煙でもあった。できあがった煮物はわたしのお腹を満たし、誘いを断るための盾にもなった。
煮物はいつだってサバイバルの味方だった。少なくとも煮物はわたしが困っているときに耳栓をして聞こえないふりをすることはない。
けれどよく考えれば、煮物がサバイバルの味方ということは昔から知っていた。「おせち」だ。お煮しめ、黒豆、昆布巻き、手綱こんにゃく。保存性が求められるおせちには酢でしめるものに加え、煮て作るものがたくさんある。
「おせち 由来」と検索すると「神様へのお供え」「一年の豊作と家族の安全の祈願」「かまどの神様に休んでもらう」「主婦の休養」など出てきて(最後の「主婦」は本当に休養できているのだろうかと思いつつ)、新たな年をなんとか生き抜いていくために煮物が活躍するのは割と普遍的なことなのだと励まされる。わたしもこれからなにか煮よう。
みなさま、よいお年を!