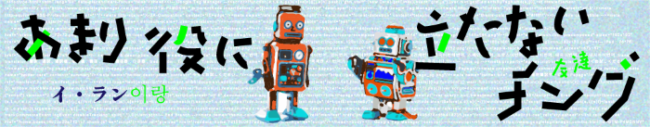アーティスト、イ・ランによる世界初(?)のAI翻訳日記。韓国語で書いた日記をPapago翻訳機で日本語に翻訳する。誰かに会えなくなってしまうきっかけは日常に溢れている。今すぐ会えない誰かとつながるために「あまり役に立たないチング(友達)」を使ってつづられる、人間とAIの二人三脚連載。
最近最も多く、長い間考えていることは、私の話の根源はPTSD [Post Traumatic Stress Disorder:心的外傷後ストレス障害]だということだ。 私がどうしてこんなに絶えず話を作るのか、話に興奮して狂奔して執着するのか。 その上、なぜ他人の話まで引き出したくてやきもきしているのか、ずっとその理由を探していた。 もしかしたら、私は抜け出したい怖い瞬間、その瞬間から話を作り出し、その話の中で安堵したかったのではないか。 そして、その始まりは新生児の時からだと思う。 私はインキュベーターベイビーだ。
「ランは3週間くらい早く出たと思う。
破水して、自然分娩ができないので、帝王切開をするしかなかった。
ランはインキュベーターにいた。2800gだったと思う。
後で家に連れてきたら毎晩たくさん泣くから 背中におんぶして寝た」 - お母さん
もちろん、あの時私が置かれていた環境は全く覚えていない。母親の話は一日に一度病院に面会に来てみると、育ちが良くない子供が背を向けて死んだように横になってばかりいたという。ガラスドアの外で私を見守っていた母親と他の大人たちは「あの子が果たして生きていくのか?」という話を交わしたという。私を愛してくれる、私と親密になる可能性を持った人々がいくつかのガラスの外側にいた時、私は何も知らずに一人で話を作り出していたのではないか。新生児が作り出せる話とは何だろうか。もしかしたらこんな考えから始めたのではないか。
「ここはどこ? これはなんかとっても大きな間違いのようだ」
新生児に「間違い」という概念があったかは分からないが、8〜9ヶ月間過ごした空間(母親の中)と違う空間に置かれた後、きっと何か「違う」という感覚はあったはずだ。その違いを感知した後、不慣れさ、恐怖、回避、抵抗感のような多様な感情が急速に進化しただろう。それらは物語を作る上で非常に重要な材料となっている(現在も同様)。
赤ちゃんは子宮の中で子宮外の生活を夢見るだろうか。 それともその他の人生に何の興味もないだろうか。赤ちゃんはなぜ体を動かして産婦のお腹の外でも簡単に気づくほど自分の存在を知らせてくるのだろうか。赤ちゃんが小さな足でお腹を蹴ると大人たちは「赤ちゃんが早く出たくて」と言っていたが、もしかしたら赤ちゃんは外に出るつもりは全くないのに、ただ狭いからではないだろうか。
私が泊まる空間はいつも狭かった。それで私は時々すっきりとした大きな空間に行くのが好きだった。 誰もいない大劇場の練習室のように天井が高くて涼しい場所。 普段、私の空間が狭いという感覚を持っているからか、私は家の中に秘密のドアを発見する夢をよく見た。夢の中の秘密のドアを開けると、突然家の中に隠されていた非常に広い秘密空間が出てきた。幼い頃、私の家族は引っ越しをたくさんした方だが(少なくとも10回)、17歳で独立して以来、私一人でも10回以上引っ越した。 数えてみると、計20回以上引っ越した。 幼い頃から引越しを一度もしたことのない人がいることを知った時はかなり衝撃だった。
幼い頃は死ぬ想像をたくさんした。母親とショッピングモールに行けば、母親が買い物をする間、ベンチに座って待ちながらショッピングモールの建物が崩れる想像をした。人々が建物の残骸に下敷きになり、様々な姿で死を迎えるそんな想像をしながら一人で静かに涙を流した。 その時、私の目の前の風景と私の頭の中に浮かぶ風景に乖離感があり、まるで水中にいるかのように周辺の空気の重さが変わる感じだった。私はおそらく自分が愛されていることを確認したくて死についてよく想像していたようだ。私の死を悲しむ人々を想像すると、いつも涙が出た。 実際、今でもよくそうだ。日常の中で絶えず私が死ぬ場面を想像する。 自転車に乗っている途中、車にはねられて倒れたら、その知らせが誰に一番先に届くだろうか。逆に「バイバイ、また会おう」と手を振って消える人々を見てもそうだ。人々が死に、去る想像をあまりにも多くしているため、このような効果もある。 今誰かに会いたければすぐ見に行く。 運転をするようになってからはもっと簡単に動く。 食べたいものを思い出す時も早く食べる。
私は即興で歌を作って歌う子供だった。 名節に集まった親戚の大人たちの前で歌を始めれば、私の歌がいつ終わるか分からなくて大人たちが少し戸惑った。姉と他の従弟たちは結び目が確実な「童謡」を歌った。 私より2歳年上の姉がよく歌っていた童謡は< 丈の低いの花>だ。歌だけでなく話もたくさん作った。私が幼い頃に書いた童話がどれだけ多かったのか、その童話でどれだけ多くの賞をもらったのか分からない。作文賞状を飽きるほどもらったが、残念ながらどんな童話を書いたのかは覚えていない(資料もない)。しかし、赤い四角形のある200字原稿用紙を鉛筆で早く埋めていったその感じはよく覚えている。 背が伸び続ける花の話を書いたのをかすかにも思い出す。 他の花の友達とは違って、一人だけ背が伸び続け、友達とあまりにも離れてしまった花の話。育つのを止めてほしいと祈り、最後は背を捨てて友達を得る話だったようだ。
どうしてこんなにいつも寂しいんだろう。解消されないこの寂しさのせいで、これからもずっと話を作り出すことになるだろうか、私は。想像力があって寂しいのか、寂しいから想像力が生まれたのか。 鶏が先か卵が先か。
※ご愛読いただきありがとうございました。本連載「あまり役に立たないチング」は今回で終了し、単行本の制作に入ります。どうぞお楽しみに。
(このページはPapago翻訳で翻訳されました。機械翻訳は完璧性が保障されていないので、翻訳者の翻訳の代わりにはなりません)
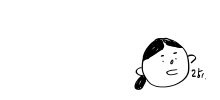
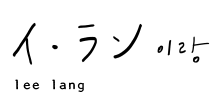 1986年ソウル生まれ。ミュージシャン、エッセイスト、作家、イラストレーター、映像作家。16歳で高校中退、家出、独立後、イラストレーター、漫画家として仕事を始める。その後、韓国芸術総合学校で映画の演出を専攻。日記代わりに録りためた自作曲が話題となり、歌手デビュー。2ndアルバム『神様ごっこ』(国内盤はスウィート・ドリームス・プレスより)で、2017年韓国大衆音楽賞「最優秀フォーク楽曲賞」を受賞。3rdアルバム『オオカミが現れた』で2022年韓国大衆音楽賞「今年のアルバム賞」を受賞。最新著作はいがらしみきお氏との往復書簡『何卒よろしくお願いいたします』(甘栗舎訳、タバブックス)。そのほかの著作に『話し足りなかった日』(呉永雅訳、リトル・モア)、『アヒル命名会議』(斎藤真理子訳、河出書房新社)、『悲しくてかっこいい人』(呉永雅訳、リトル・モア)、『私が30代になった』(中村友紀/廣川毅訳、タバブックス)。ストリート出身17歳の猫、ジュンイチの保護者でもある。
1986年ソウル生まれ。ミュージシャン、エッセイスト、作家、イラストレーター、映像作家。16歳で高校中退、家出、独立後、イラストレーター、漫画家として仕事を始める。その後、韓国芸術総合学校で映画の演出を専攻。日記代わりに録りためた自作曲が話題となり、歌手デビュー。2ndアルバム『神様ごっこ』(国内盤はスウィート・ドリームス・プレスより)で、2017年韓国大衆音楽賞「最優秀フォーク楽曲賞」を受賞。3rdアルバム『オオカミが現れた』で2022年韓国大衆音楽賞「今年のアルバム賞」を受賞。最新著作はいがらしみきお氏との往復書簡『何卒よろしくお願いいたします』(甘栗舎訳、タバブックス)。そのほかの著作に『話し足りなかった日』(呉永雅訳、リトル・モア)、『アヒル命名会議』(斎藤真理子訳、河出書房新社)、『悲しくてかっこいい人』(呉永雅訳、リトル・モア)、『私が30代になった』(中村友紀/廣川毅訳、タバブックス)。ストリート出身17歳の猫、ジュンイチの保護者でもある。