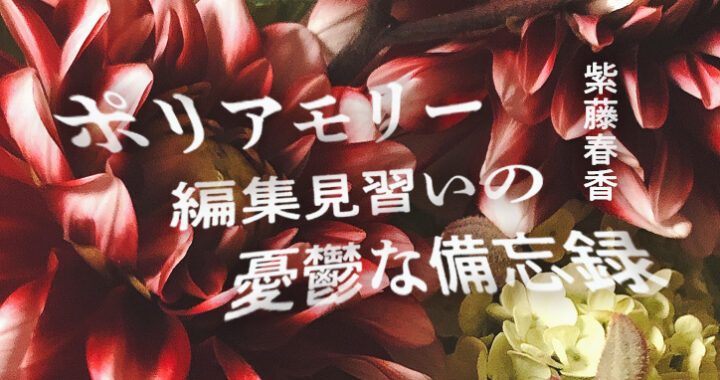気の迷いと偶然で飛び込んだ出版の世界。そこで直面した矛盾と葛藤。マイノリティを支援し社会的な課題の解決を目指すことと、商業的に利益を上げることは両立可能か? 毒親もヤフコメ民やアンチフェミニストからのクソリプも飯のタネ。片手で社会的ルールを遵守しつつ、もう一方の手で理不尽な圧には抵抗する。宗教2世、精神疾患当事者、ポリアモリーという特質をそなえた編集者(見習い)による、「我らの狂気を、生き延びる道を教えよ」の叫びが聞こえるエッセイ。
とにかく定時に帰る。これは不本意ながら雇われの身に堕ちた私が実行することができる、ささやかなアクティヴィズム(社会運動)だ。
私が勤める会社は裁量労働制かつ年俸制を採用している。その割に給料は安く、出社時間が決められているのは理不尽としか言いようがないのだが、残業代が出ない分、定時に帰るモチベーションは爆上がりする。これは良いことだと思う。
私が定時に帰りたいのは、もうひとつ理由がある。同居人と一緒に夕飯を食べたいからだ。同居人は基本的に残業がない会社に勤務しており、定時ぴったりに終業することが多い。そして私たちの定時はふたりとも18時。なので18時までに意地でも仕事を終わらせて(終わったことにして)、家の最寄りの駅で同居人と待ち合わせて、大戸屋やはなまるうどんなどのチェーン店で一緒に夕飯を食べ、一緒に帰宅する。これが私の絶対に守りたいルーティンだ。死守したい。これができない職場環境は人権侵害である、とすら考えている。
何を大袈裟な、と思われるかもしれない。今時、夕飯なんて一人でコンビニで済ませたってなんのことはないだろう、と。しかし私はいたって真剣で、切実で、必死だ。
*
5年前のこと。私は司法試験の受験のため法科大学院に通っていた。全体の一割程度が単位を取れず、脱落していく中、不肖の私はなんとかほうぼうの体で修了式を迎えた日。クラスメイトたちはこれから迎える司法試験への緊張と輝かしい法曹としての未来への希望で、ギラギラしていた。来る日も来る日も10時間以上机に向かう、あまりに抑圧的でストイックな2年間。ようやく収穫の時が来たのだ。私の出身校は7割近くが試験に合格して、弁護士か、検事か、裁判官になる。私自身の成績は下から数えるほうが早かったが、中には試験を受ける前から大手法律事務所に数百万円の前払金付きで内定をもらっている成績優秀者もいた。
そんな奇妙な興奮の熱気をたたえた飲みの場で、クラスで慕われていた実務家教員の刑事裁判官・中村先生が締めの言葉を求められ、立ち上がった。プライドが高くて気難しいおじさんが多い法曹界においてはめずらしく、オープンマインドで、声が大きく、親切で、面倒見が良い先生だった。プライベートでも学生と一緒に仲良く高尾山に登るような気さくな人柄で人気があった。この日も学生に負けず劣らず、たっぷりお酒を飲んで、目が真っ赤に充血していた。相当に酔っ払っている。
「いいですかぁ、みなさん」
ろれつも怪しい。
「代わりのない仕事なんて! この世にはぁありませぇん!! みなさんの代わりは、どこにでもいます。命より大事な仕事なんて、ありませぇん!!! 卒業おめでとう!!!! 乾杯!!!!!」
*
あなたの代わりはどこにでもいる。そう言われることは、とても酷なことだという認識がある。「おまえの代わりはどこにでもいるんだよ!」と吐き捨てるパワハラやモラハラや派遣切りのように、生活を人質に生存が脅かされるようなことは、断固として許してはいけない。
しかしもう一方で、別の地獄もある。「これを頑張れば、あなたは特別な人間になれる。世間から必要とされる。お金もいっぱいもらえる」とニンジンをぶら下げられて、延々と過酷な競争に身を投じなければならない、そんな生き地獄だ。
法科大学院のクラスメイトは競争を勝ち抜いてきた選りすぐりたちだった。12歳で中学受験を経験し、都内の中高一貫の進学校に入り、東大一橋早慶国立医学部以外はゴミという価値観のコミュニティに属しながら大学受験をし、卒業して、東京大学の法科大学院に入る。そこでまた数々の競争を勝ち抜いてきた者同士で競い合う。「大人になったら楽できるから」と耳元で囁かれながら勉学に励むが、楽になることはない。一つの競争に勝ち抜いたら次のステージに連れて行かれ、選りすぐりたちとまた別の競争をする。競争のレベルは上がり、どんどん過酷になる。
それでもなかなか競争からは降りられない。競争の最中に繰り返し投げかけられるのは、生存者バイアスのかかりまくった先輩や先生たちの語りだ。「いまだけの辛抱だから」。いま耐えれば、後になってこんなに稼げる。こんなに名誉でやりがいのある仕事に就ける。俺たちはその他大勢の、ワーキングプアとは違う人生を送るんだ。だから頑張れ。
そうした語りの中で、自然と敗者への見下しの目線も刷り込まれる。敗者になることは恐ろしい。あんな風につまらない人間になってはいけない。こんな風に同級生から先輩から、後輩から嘲笑されることは耐えられない。無様な姿を晒すわけにはいかない。
常に向上しなければならない、完璧でなければならない、成功しなければならないというプレッシャーに晒される環境では、ありのままの姿を見せている場合ではないのだ。「いつか何者かになれる」という夢は、人を死ぬまで働かせる最強の魔法だ。
*
法科大学院の卒業から7年が経った。一人の自死と、四人の休職の知らせに接した。これが他の業界に比べて多いのか少ないのか、私にはわからない。ただ多くの優秀な同級生が、大手の弁護士事務所で1500万円程の年収を得ながら、朝の2時、3時まで働くということが常態化している。弁護士は実態はどうあれ、雇用契約ではなく業務請負契約とされることが多く、過労死や自死にはなんら補償されることもなければ、社会問題化することもない。高給取りが世間の同情をかうのは難しい。
しかし高級取りだからと言って、若者が命を落としてまで働く環境が野放しにされていいものだろうか。貧富貴賤を問わず「命より大事な仕事なんて、ありませぇん!!!!」と誰かが叫んで伝えなければならないのではないか。俺はおまえの能力ではなく、いまそこにいるということ、それ自体を愛しているのだ、と。誰かが。
血走った目の中村先生があの言葉に至った経緯を聞く機会は、その後、ついぞ訪れなかった。
*
常に生産性と効率性を求められる資本主義社会では、非生産的な行為はそれ自体、抵抗運動となる。私の定時帰宅は戦いである。明日出社するエネルギーをチャージするために夕飯を食うのではない。ただただその瞬間の空腹を満たすために飯を食う。
人が「何者かになりたい」と欲望するとき、そのほとんどが「仕事によって人一倍成果を上げ、社会的に承認されること」を意味するのは不思議なことだ。かけがえのないふわふわの愛猫を抱きしめること、一汁一菜の自炊を続けること、パートナーとテレビを見ながらみかんを頬張ることは「何者か」を構成する要素には含まれていない。私たちは生まれ落ちたその瞬間からとっくに代替不可能な「何者か」であるはずなのに、社会はそれを顧みようとはしてくれない。
そんな社会に中指を立てるため、今日も定時に帰って家でご飯を食べる。「こいつ仕事も終わってないくせに帰りやがって」という社会の声を内面化した自責と戦いながら、定時という一線を守ること。それが私のアクティヴィズムのひとつだ。
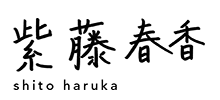
某出版社勤務。複数愛者(ポリアモリー)。文筆と編集。寄稿「図書新聞」/『みんなの宗教2世問題』(横道誠編、晶文社)/朝日新聞社「かがみよかがみ」山崎ナオコーラ賞大賞/note「女の子なんだから勉強しなくていいよ、と言った父は死にかけるまで仕事をやめられなかった」他。