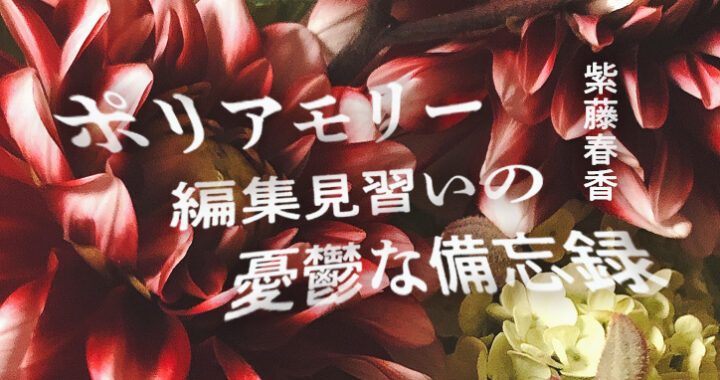気の迷いと偶然で飛び込んだ出版の世界。そこで直面した矛盾と葛藤。マイノリティを支援し社会的な課題の解決を目指すことと、商業的に利益を上げることは両立可能か? 毒親もヤフコメ民やアンチフェミニストからのクソリプも飯のタネ。片手で社会的ルールを遵守しつつ、もう一方の手で理不尽な圧には抵抗する。宗教2世、精神疾患当事者、ポリアモリーという特質をそなえた編集者(見習い)による、「我らの狂気を、生き延びる道を教えよ」の叫びが聞こえるエッセイ。
「やっぱり前に出てくる編集者って、嫌だよな~」
SNSに書き込まれた作家さんのつぶやきが、ちくちくと眼球に刺さる。それは、そうですね。本当にそうですよね。私もその意見には大賛成。
編集者は、どこまでいっても黒子。裏方。サポーター。ケアラー。本を作り、本を売るのが仕事だから、書き手を前に立てるのが本来だ。編集者になんて注目してもらっても困る。あくまで著者自身がスターになってくれなければならない。
にもかかわらず、恥ずかしながら当時の私は、前に出てしまっていた。出まくってしまっていた。現在Xを自称するTwitterで、私は、バズり、レスバし、炎上しまくっていた。大量の「いいね」とクソリプを浴びながら、なぜこんなことになってしまったのかと、途方に暮れながら爆走していた。
*
去年の夏。私は一冊の翻訳書を担当していた。
その書籍は、邦訳を出版すること自体が「社会運動」と呼べるような、鋭い批判性を持ったものだった。その本が書店や家庭の棚に並ぶのを想像すると、わくわくした。新しい言葉が生まれる。新しい概念が立ち上がる瞬間に立ち会うことができる。
しかし、著者は海外在住であり、日本語ができるわけではない。そのため、日本語圏でのPR活動は、翻訳者と、担当編集者である私が担うことになった。この一冊でヘルジャパンを変えてやる。そういう意気込みで、せっせと発信に励んだ。
だが、発信の中で、思わぬ反応があった。
著者や書籍に関する誤情報が広まったのだ。
フォロワーの多い著述家や研究者を名乗るアカウントによって、あっという間に噓が拡散されてしまう。書籍は人目に晒されることを前提に制作されるものであるから、多様な解釈や批判は自由だ。しかし、本の価値を貶めるような明確な事実誤認などは、端的に業務妨害。なので、それらの影響を少しでも小さくすべく、担当編集である私が、一つひとつ引用しながら訂正して回ることになってしまった。
しかしこの時、私も身に染みて思い知ったのだが、誤情報を拡散した人というのは、その時点でもう引っ込みが付かなくなっているので、担当編集者の私が訂正し、撤回するよう求めても、態度は硬化するばかりなのだ。なにかこちらに攻撃できる材料はないか、目を皿のようにして探し、数年前の投稿まで遡って粗を探して反論してくる。
誤情報の訂正、といえば聞こえがいいが、その実際は、激しいレスバだった。
それに当該書籍が扱うテーマは、SNS上では特に「炎上」しやすい、ジェンダー、特に女性の人権について取り扱ったものだった。とかく昨今は、「女性には自由と権利がある」という当たり前のことを主張すると、「女性に男性と同等の自由や権利を与えるべきではない」「現代の女性はつけあがっている」「女性が男性を虐めている」「女性が男性の権利を奪っている」「女はわきまえろ」と考え荒ぶるアカウントから、執拗な攻撃を受けやすい。この本もまた、彼らからしっかり目を付けられ、気がつけば大量の誹謗中傷を受け取っていた。
私も、もし担当書が、小説やエッセイ、詩歌だったら、できうる限り裏方に徹したいと思う。文芸の作家は、作品を通じて神殿を建設する創造主(クリエイター)だ。編集者の我々は、その神殿のお庭の植木を整えたり、建物の内部を掃除したり、玄関にお花を飾ったり、来客者を丁寧に案内して回るのが仕事といえる。しかし、ことアクティヴィズムを体現する書籍については、そんな悠長なことは言っていられない。それはただそこに存在するだけで、誰かが排除しようとする。石を投げる。だからその思想をもっとアグレッシブに伝える伝道師が必要だ。そして伝道師は、時に闘士であることが求められる。
当該書籍の著者は優秀な伝道師であり、闘士だった。そもそも書籍の成り立ちが、彼女がSNSに連投したポストをもとにしたものであり、優れたインフルエンサーだった。しかし彼女は日本語で発信することができない。そこで、彼女の日本語訳された文章を一番読んでいる私が、その役を担おうと思った。幸運なことに、素材は豊富にあった。彼女の論理は、簡潔かつ明快で、簡単にトレースすることができた。そして彼女のあくまでも朗らかでナイスな佇まいは、大いに私をエンパワメントした。やれる、と思った。
結果的に、その予測は当たった。翻訳者の協力も得ながら、私は間違いを訂正し、当該書籍の主張を喧伝し、ありがちな反論には再反論をした。上述したように、女性の権利の話題になると多くの人が感情的に反発するのは、古今東西同じだ。英語圏でも本書の著者はたくさんのバックラッシュを正面から浴びていた。しかし彼女は百人組手の様相で、それらを見事に捌いて打ち返していた。お手本はたくさんあった。
多くの友人が心無いリプライや、会社への電話・封書、長文の抗議メールを受け取る私のことを心配してくれた。誹謗中傷は、反応するとますます激化するのだから放っておくほうがいい、と老婆心で忠告してくれる人もいた。私のことを思ってのことだから、ありがたく受け取ったが、そのどれにもピンとは来ていなかった。私は疲れていたけれど、同時にいきいきともしていた。
私は恵まれている。どれだけ多くの女性が唇を噛んで泣き寝入りせざるをえない状況に置かれてきたか、私は知っている。女性が、出産したら仕事を続けられない、進学や就職で男性よりも不利な状況に置かれる、賃金が低い、痴漢や性暴力に遭えば被害者に落ち度があったにちがいないと勘ぐられる、パートナーが避妊をしてくれない、孤立出産で逮捕される――そしてそれらについて男性は一切責めを負わない――ということ。これらについて私は怒り続けているが、同時に私は声を上げられる立場にいる。私はたまたま、現在紛争のない地域に住んでおり、こうした理不尽を言語化する能力を身につけることができる教育を受ける機会を得て、パートナーに殴られておらず、ひとりで暮らせるだけの経済的・社会的地位があり、言論の自由を行使しても職場をクビになることもないし、逮捕されることもない。私は「声を上げる」という特権を行使しているのだ。
私にも、このような特権がない時代はあった。父と母と暮らしていた時だ。
*
両親は、私が塾の宿題ができないでいると、「じゃあ塾なんてやめろ!」 食事の味付けが口に合わず、今後からは少しこのように代えてほしいと伝えると「じゃぁもう食べなくていい!」 家庭の方針に少しでも口を出すと「誰が食わせてやってると思ってるんだ!」 家の信仰を継げないと告げると「もうこの家は終った。あなたのせいでこの家は潰れる」
毎日のように不機嫌でコントロールされ、喧嘩をすれば謝罪するまで正座させられ、毎週のように食卓が冷え込んで、誰一人言葉を発しないまま終わる。言葉を発するということは、常に平穏が失われる可能性を孕んでいた。対話など存在しなかった。言葉のキャッチボールなんてない。言葉のドッチボールのルールしか知らない大人に囲まれて育った。そして、それをおかしいことだと教えてくれる人は誰もいなかった。
私がSNS上で匿名の人と行った大量のやりとりは、本来であれば父や母と交わしておきたかった言葉の応酬でもあった。彼らが私に与える権利には、いつも義務がつきまとっていた。彼らにとって「(都合の)いい子」であること。お隣さんや親戚に自慢できるくらい高学歴で、彼らの言うことをよく聞き、逆らわず、心身が健康であること。そうであり続ける限り、私は彼らの子どもとしての権利を得ることができた。
それは、決して満点を取ることのできない試験を受け続けるようなものだ。よき娘であり、よき妻であり、よき嫁であり、よき母であり、よく働き、いついかなる時もダイエットとお化粧に励む美しい姿であり続け、聡明で、控えめで、奢らず、男性の面子を立てながらも男性よりも成果を上げる、そんな女性が不可能であるように。私はずっと怒っていた。
ずっと言ってやりたかった。権利は義務との引き換えで得られる報酬ではない。私は自由で、個人として尊重されるべき存在だ。それは私に生まれながらに備わっている、所与の前提のはずだった。私は本来、誰にも跪く必要はない。誰が何と言おうと、私は私であるだけで、神聖な存在なのだから。
私の声は両親に届くことはなかった。私は彼らとの対話を諦めた。黙って、怒りを溜め込んで、嵐が通り過ぎるのを待つことにした。そして彼らの前から去った。彼らから十分な距離ができると、様々なことがクリアになって見えるようになった。彼らは特殊な存在ではなかった。彼らは、社会のある側面を、強調して私に伝えていたにすぎなかった。家父長制という化け物が、彼らを通じてしゃべっていたのだ。私を支配する強大な抑圧者は、ただのパペットに過ぎなかった。だから私は、実家を出てからもずっと、家父長制の前に立ちはだかり、声を上げ、手を振りかざすことで、彼らとのコミュニケーションを続けることにした。
そうしているうちに、次第に聴衆(オーディエンス)が集まるようになった。たとえ反論をした相手が納得しなかったとしても、考えを変えなかったとしても、そのやりとりの目撃者たちが励まされたり、考えを改めたりするようになった。明確に手を差し伸べてくれる人もいた。私はもはや孤独ではなかった。家に取り残された孤立無援の子どもではなくなっていた。
私にとって、レスバは自由の象徴だった。言論の自由の行使だった。仕事の一環であり、――もちろん会社から強制されたわけではない――同時にライフワークだった。だからあの時、私にはレスバしない、という選択肢はなかった。もちろん最適な手段とはいえないが、それなりに切実さと必然性を伴った表現方法だった。
押入れの中でひとりで泣いていたあの日の少女が癒えるまで、私が黙ることはないだろう。そして残念ながら、そんな時が来るのはずっとずっと先のことだと、私は確信している。
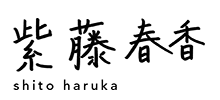
某出版社勤務。複数愛者(ポリアモリー)。文筆と編集。寄稿「図書新聞」/『みんなの宗教2世問題』(横道誠編、晶文社)/朝日新聞社「かがみよかがみ」山崎ナオコーラ賞大賞/note「女の子なんだから勉強しなくていいよ、と言った父は死にかけるまで仕事をやめられなかった」他。