日本人で文学好きの母と、瞬間湯沸かし器的にキレるセネガル人の父の間に生まれた亜和(愛称アワヨンベ)。祖父母、弟とさらにキャラの立つ家族に囲まれて、ときにさらされる世間の奇異の目にも負けず懸命に生きる毎日。そんなアワヨンベ一家の日常を綴るハートフルエッセイ。アワヨンベ、ほんとに大丈夫?
目白駅で電車を降りたのは何年ぶりだろうか。構内にあったミネストローネが美味しいパン屋はすでになく、女子大生が好みそうな品々が並ぶ雑貨店になっていた。凍えるよう3月が過ぎたかと思えば、4月の今は真夏の真似事のような暑さである。12時に会場の前で集合しようとメッセージを書いていたYは、あまりの暑さにいったん家に着替えに戻ったようだ。私以外、誰も時間通りに着きそうにない。約束の時間に必ず遅れると評判の私が、珍しく20分も早く着いたのは、ここが自宅から2時間近くもかかる小旅行地であるからだった。久しぶり過ぎて時間を見誤ってしまった。こんなところまで毎日辞書を2冊担いで通っていたなんて、今ではとても信じられない。駅を出てすぐの広場には人が集まっていた。警察がイベントのようなものをしていて、親に連れられた子供たちが、おっかなびっくり白バイにまたがったり、ぬいぐるみと戯れたりして、休日の昼下がりを楽しんでいる。相変わらず品の良さそうな親子連ればかりだ。そこから横断歩道を渡ってすぐの「西門」から大学内に入ろうとしたが、なぜか閉まっていた。駅から徒歩30秒の駅近大学と謳っているクセに、肝心のときには正門まで歩かせる。こんな暑い日になんと意地悪なのか。敷地に沿って続いている脇の細い道路を、私はフラフラと歩き始めた。
桜は2週間以上前に満開したと知らされていた。ほとんど葉桜になりつつある桜の木から、今日の強風に乗った花びらが惜しみなく飛んでくる。日差しと比べ、まだいくらかひんやりとしている風の匂い。大学内のホールから、オーケストラが演奏するハチャトゥリアンの「仮面舞踏会」が聞こえてくる。ちなみに、この曲が「仮面舞踏会」ということなど、このときの私は当然知らない。迫力のある演奏にポカンと口を開けて「この曲なんだっけ? トゥーランドット?」などとしばし考えただけである。私は、タイトルをわからないクラシック曲をすべて「トゥーランドットだ」と思ってしまうクセがあるらしい。本物のトゥーランドットがどんな曲なのか、実際は誰かに聞かれたって口ずさむこともできない。曲に限ったことではない。私にとってトゥーランドットという言葉を思い浮かべることは、読みもしない参考書を小脇に抱えて歩くことに似ている。なにか小難しいことを思い出そうとしてそれがかなわなかったとき、私はとりあえずそこに「トゥーランドット」という言葉を嵌めておく。そう考えると、仮歯のようなものだとも言える。本当の情報が手に入ったら、トゥーランドットを取り除いて差し替える。今、本当に正しくトゥーランドットが正解である部分にも、この仮歯のようなトゥーランドットが刺さっているはずなのだが、本物のトゥーランドットを当てはめるべき場所が一体どこなのか、私はもはや分からなくなってしまっている。とにかく、ホールから聞こえる美しい演奏は私の心を浮足立たせた。誰に聞かれたわけでもないのに、自分の“トゥーランドット思考”について書き始めてしまったのも、私はかつて仏文科の生徒で、毎日役に立つかもわからない小難しいテクストを読み込んでいたことを思い出したからだろう。今日は大学を挙げたお祭りの日で、大学の現役生や卒業生、それに付属する初等科の子供たちや中等科の学生たちもやってくる。この広大な敷地の森林が豊島区にある緑の3分の1を占めているという話を、学生だった時代に聞いたことがある。そういえば、古い校舎の裏側に大きなキノコを見つけて驚いたこともあった。
3分ほどノロノロと道を歩いて正門にたどり着いた。現役生だった頃は、たいがい西門から登校していたので、正門までやってくるのはそれこそ入学式か卒業式くらいだった。大きな門が聳え立っている様子はやはり立派で、かつてこの学校に通っていたことを少し誇らしく感じる。なんでもない顔でさらりと門をくぐりたかったが、高鳴った気持ちが抑えられずに、大きく大学名が刻まれた柱の写真を一枚だけ撮って中へ進んだ。敷地内に入ったところで、サークルのグループLINEの通知音が鳴る。
「もうちょいで着く。バッケ駅前きといて」
「やっと正門着いたから無理」
「キモすぎ」
「喫煙所見てくるわ」
サークルの仲間たちは、私のことをバッケと呼んでいる。これは私の名前にくっついている父の一族の名字で、正式な書類でないかぎり表に出すことはない。だが、サークルのメンバーは私を「伊藤」とも「亜和」とも呼ばない。もはや大学の仲間内でしか使われることのないこの呼び名は、私にこの環境でしか現れないひとつの人格を作り出したようだった。男でも女でもないような、学内でときどき目撃される、奇妙なキャラクターのような存在。私が所属していたサークルには男子学生も女子学生も同じようにいたが、私が行動を共にしていたのは主に男子学生たちだった。ややお嬢様気質が多い女子学生のグループと、若干思いやりに欠ける私の相性はあまり良いものではなかったのかもしれない。授業の合間に楽しくおしゃべりすることはあったものの、休日に一緒に出掛けたりすることはほとんどなかった。「男子といたほうが心地が良い」と書くと、自分が男勝りだと思い込んでいる痛々しい女と思われても仕方がない。それでもやはり、私にはそのほうが気楽だった。彼女たちの心を無意識に傷つけてしまわないためにも、私は容赦なく暴言をぶつけ合う男子たちと喫煙所にたむろすることを選んでいた。そこでも、男子同士の付き合いにあまりずうずうしく入っていくべきではない、と気を遣っていたつもりだが、実際、私はかなり図々しかったと思う。あのヤニ臭くて汚い部室に誰よりも長く居座っていたのは、他でもなく私だったのだから。
部室棟の目の前にあったはずの喫煙所はなくなっていた。真っ先に向かったそこがただの広場になっているのを見て、私はまさか学内で煙草が吸えなくなったのではないかと不安になったが、すこし歩いて部室棟の裏へ回ってみると、新たにパーテーションが立てられた喫煙所がきちんと残されていた。ホッとしながら赤いレンガで作られた低い囲いに腰を下ろしていると、向こう側から先ほど私に「駅前にきて」と連絡してきたSがスタスタと歩いてきた。背が高く瘦せ型で、堀の深い目元には、相変わらず太陽の光でできた濃い影が乗っている。この暑さでも一応、サークルのOB会であることを意識してきたのか、かっちりとしたジャケットを羽織っていた。そろってパーテーションの中に入り、アイコスのスイッチを押す。
「そういえばあれ、見たよ、テレビ」
「あぁ、ありがとう」
「一緒に出てた人、あれ誰だっけ」
「紗倉まな?」
「あれ? 紗倉まなだっけ? 紗倉まなってあれじゃん、演歌歌う子」
「それ、さくらまやでしょ」
「あは、まやか」
くだらないことを話しながら、Sは「そういえば」と言って働いている会社の名刺を渡してきた。一応、私も「頂戴します」と言って両手で受け取る。
「バッケお前名刺ないの?」
「作ったんだけど、忘れた」
「こういう時こそ持っておかなきゃだろ。いろんな人来るんだから」
卒業から5年が経ち、会社に就職した同級生たちはみんな順調にキャリアを進めていた。一方で私は、いろんな道を進んでみては後戻りを繰り返すような、責任のないフラフラとした生活を続けている。物書きとして少々軌道に乗ってきた今だから、こうして多少得意げに大学に顔を出せたものの、去年の今頃のままだったらきっと、ほとんどフリーターの自分が恥ずかしくて参加を断っていたはずである。仲間が“社会人”としてまっとうな大人になっていく姿を見るのは、やはりまだこそばゆい。Sから大人のまっとうなアドバイスを受けて、私は苦し紛れにふんと鼻を鳴らした。
パーテーションを出て再びレンガの上へ座り、他のメンバーの到着を待つ。目の前を、上品なフォーマルのワンピースを身にまとった女性と、その子供が通り過ぎた。子供のほうは、汚いレンガの上で、暑さに項垂れながら座る私たちを不思議そうに見ていた。私はSに聞く。
「初等科の親ってさぁ、毎日あんな恰好しなきゃいけないのかね」
「そうだろ。さすがにTシャツにジーパンってわけにはいかねぇんじゃねえの」
「大変だなぁ」
初等科から大学まで、エスカレータ式に登ってくる「内部生」と違い、私たちは大学から入ってきた「外部生」である。家柄の良い内部生たちに比べたら、私たちはガラの悪い庶民だった。大学を聞かれて答えると、たいてい「あそこは“ごきげんよう”と挨拶するんでしょう」と言われるが、少なくとも外部生にそんな習慣はない。4年間通っていたにも関わらず、私たちは校歌もロクに歌えないのだ。
ふたりで新校舎を見学しに行ったり、懐かしい部室棟の中をうろついてそれぞれの部室をのぞき込んだりしているうち、家に着替えに戻ったYと、とくに理由もなく遅れてきたJとKがフラフラとやってきた。結局全員が集まったのはOB会が始まる10分前で、私たちは「北棟ってどこだっけ」などと言いながら指定された教室へと向かった。
演習の授業で使われている少人数用の305号室には、他の教室の何倍もの人間たちがひしめき合っていた。入り口で名札を貰って首から下げる。参加の返信をするまで、自分が55期のメンバーであることも知らなかった。私とSとYが55期、ひとつ上の学年のJとKが54期というわけだ。この会場にいるそれより上は、なぜか唐突に17期とか、14期とか、中年以上の紳士淑女たちばかり(もっとも歳が上だったのは、3期生だという矍鑠とした老紳士!)が集まっていた。OBのなかでもひよっこの我々は、余った椅子にお行儀よく座り、現役生による活動の報告と、次回の記念パーティーの予定について聞いた。横にいるKは、四角いフレームの眼鏡をかけ、真面目そうな顔で書類に目を落としていたが、ときどき何かが面白くなったようにニヤニヤと笑っていた。緊張感のある空気の中、交互にニヤついている不届き物はKと私だけだった。みんなが真剣な顔をしている状況に耐えられないから、私たちは個人事業主なのだろうか。
(続く)
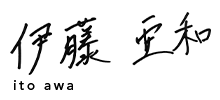
伊藤亜和(いとうあわ):文筆家/モデル。1996年 横浜市生まれ。学習院大学 文学部 フランス語圏文化学科卒業。Noteに掲載した「パパと私」がツイッターで糸井重里、ジェーン・スーなどの目に留まり注目を集める。「きらきらシニアタイムス」「エレマガ。」にて連載中。趣味はクリアファイルと他人のメモ集め。

