日本人で文学好きの母と、瞬間湯沸かし器的にキレるセネガル人の父の間に生まれた亜和(愛称アワヨンベ)。祖父母、弟とさらにキャラの立つ家族に囲まれて、ときにさらされる世間の奇異の目にも負けず懸命に生きる毎日。そんなアワヨンベ一家の日常を綴るハートフルエッセイ。アワヨンベ、ほんとに大丈夫?
パパの白目は、どうして黄色を帯びているのだろう。小さいころから疑問に思っていた。私もいつかそうなるのだろうかと不安で、こまめに目薬を点したり、サングラスで護ったりして過ごしている。健康上の要因は別として、目が黄色いことが悪いとは思ってはいない。そうは思っていても、私を怒鳴るパパの目は黄色だった。大きく見開かれた目に床が割れるような怒鳴り声、黒い肌のうえで光る黄色い目。幼い私は、パパに怒鳴られるたびに過呼吸を起こした。息ができず声も出なくなって、涙と鼻水を垂れ流しながら、必死に「おみず、おみず」とママに訴えるのがいつものことだった。しゃくりあげながら泣く私に、パパは目を見開いて唇に人差し指をあて、「静かにしろ」というサインをした。蛇に睨まれた蛙とはまさにこのことで、私はあの目を見ると恐怖で固まってしまっていた。
そのことが影響しているのか、私は人と話すときに目を合わせるのが苦手だ。相手が話しているときはそれほど苦ではないのだが、私が話しているとき、つまり、相手が黙っているときは、どうしても相手のヘソのあたりに視線が動いてしまう。口を閉じられていると、怒りの感情を日本語に変換できないまま、行き場を失った感情が目から噴き出してくるかのような顔をしたパパを思い出すからだ。よく、「娘は父と似た人を結婚相手に選ぶ」と言われているけれど、私からしてみたらそれは絶対にありえないことだ。絶対にパパみたいな人を好きになったりはしない。私の好きな有名人は、カズレーザーと、神木隆之介と藤井聡太だ。
もうひとつ苦手な視線がある。港区に出入りしているバイタリティー溢れた経営者がするような、相手に有無を言わさず納得させる威圧感のある視線にも耐えられない。自分の価値観を信じて疑わないような、「教えてやるよ」とでも言いたげなあの目。苦手と書いたが、これは「苦手」というより「嫌い」である。自分がどういうときに苛立ちを覚えるか考えてみると、それはたいてい「君はまだ若いから」「経験が浅いから」「女の子だから」といったニュアンスを相手の視線から感じ取るときだ。それを察知すると、私の中の短気の遺伝子が反応してしまい、必要以上に好戦的になってしまう。見た目によって「難しい日本語はわからないだろう」と決めつけられてきた経験は、自分でも気が付かないうちに黒い感情の琴線になり、どんどん波紋を広げて「難しいことはわからないだろう」というところにまで反応するようになったのかもしれない。
先日、青森の親戚の家に行った。家の中に入って畳の上に座ると、おじさんはちゃぶ台の上にみっつ並んで置いてあったリンゴをひとつ手に取って、果物ナイフとともに私に差し出した。私がどう皮を剥こうか考えていると、おじさんはかすれた声でなんの気なしに「まだ独身なのか」と私に聞いてきた。おじさんがもうほとんど見えていない目で私を見つめる。電車もろくに来ない町に体の自由もきかずにたったひとりで暮らす年寄りを、いったい誰が女性差別だ時代錯誤だと責め立てることができようか。田舎の高齢者の単純な疑問にすぎないというのに、ひねくれた私の思考回路の中では、その質問は即座に「リンゴもうまく剥けないおなごは嫁さいけねぇぞ」という言葉に変換された。そして、リンゴも剥けない女だと思われたくなかった私は、自分で勝手に追い詰められた末にナイフを手放し、そのままリンゴにかぶりついたのだった。SNSではこの出来事を格好つけて書いたために賞賛のコメントが数多送られてきたが、実際はごらんの通りの、被害妄想の結果起きた情けない暴走にすぎない。それほど私の「ものを知らない」コンプレックスは激しいのだ。
言葉、時事、雑学、マナーに至るまで、無知や間違いを指摘されることがあれば一生の恥と思ってしまう。だから私は人より少し多くのことを知っている。「そんなことも知らないのか。ならば教えてやろう」と思われないように。知らないことがあるのは、それほど深刻なことではないと、頭ではわかっているのに、頭がショートして体が熱くなると、私はやらかしてしまうのだ。だから、しばしば好きな男性のタイプを聞かれることがあれば、私は真っ先に「目力のないひと」と答える。目力の強い男性がみなパパと同じく短気で暴力的ではないし、宗教的な経営者のように偉ぶった人ではないということは重々わかっている。その逆も然りで、眠たげな目をした男性がみな寛容で穏やかでなわけではない。ただ、私は相手の「視線」を簡易的な判断材料にして、私が理性的でなくなるような予感のする相手はなるべくは避けて過ごしていたいのだ。
私にとって、先に書いたふたつの視線を避ける理由はそれぞれ「恐怖」と「嫌悪」に分けられる。相手から怒りを受ける視線と、私の中の怒りを沸き立たせる視線。私を委縮させてしまう視線と、暴走させてしまう視線。
今夜、日付が変われば私は27歳になる。パパと喧嘩別れをしたのは大学に入ったばかりの18歳のころだったので、間もなく9年が経とうとしている。パパのフェイスブックを見ると、大学の入学式に撮った私の写真に「Awa!Go Go!」とコメントが添えられた投稿が残っている。大学でフランス語の学科を選んだのは、パパとのコミュニケーションを豊かなものにできれば、と思ってのことだったが、それ以降、パパのアカウントに私の話題が投稿されることはなくなった。父親に対してのはじめての反抗が、まさかこんなにも長い冷戦を招くとは正直思いもしなかった。しかし、パパの怒りから遠ざかった今日までの日々はあまりにも快適で、好きなものを食べ、好きなお酒を飲んで、好きに泊まって好きな時間に帰る。こんなに自由なのに、いまさら関係を修復しようという気にはなれないのだ。それに、私たちはお互い、うまく話し合って共存するという機能を持ち合わせていないように思う。通じるのはごく短いセンテンスだけ。どちらも100パーセント主張が通らなければ納得ができないのだ。私自身、爆発する前にパパと話し合って、自由にしたい部分を落ち着いて話してみるとか、そういうことができたなら、こんなことにはならなかったかもしれない。でも、できなかった。パパの黄色い目が怖くて、限界が来るまで、うんうんと良い子のふりをすることしかできなかった。
大喧嘩をする前日、その数日前から私たちの空気はにわかに不穏だった。弟が無邪気にも私に彼氏ができたことをバラしてしまったり、バイトから帰る時間が遅くなった私にパパが苛立っていたのに対して、私が「じゃあもう迎えに来なくていい」と言ったり、原因はいくつかあったように思える。パパが運転をしながら私にこう言った。
「娘は、絶対にお父さんに逆らっちゃいけない。そういう決まりなんだよ。」と。
これは、パパが私にはじめて言葉にしてはっきりと示した主張であった。私はこれまで「怒られている」ことはわかっていても、「なぜ怒られているのか」はよくわかっていなかったのだと思う。とにかくパパが発する咆哮のような怒鳴り声におびえて息を詰まらせていたのだ。このひとことが、これまでのパパの怒りのすべてだったのだと、私は理解した。理解したと同時に、これまで得体の知れなかった「恐怖」が、はじめて形を成した明確な「嫌悪感」に変わったのがわかった。生まれてはじめて、パパに「はぁ?」という気持ちになったのである。逆らっちゃいけないだと?冗談じゃない。私はアンタの価値観の中で固められたことだけを口移されて咀嚼していろと言うのか。私は私の歯でかじって、味わって、そうやって生きていくんだ。ふざけんな。
バックミラーに映った黄色い目と目が合う。ミラー越しにその目を睨みつけた。パパの見開かれた目はわずかに動揺しているように見えた。ハンドルを握っている状態のパパを怒らせたら命が危ないと思い、その場では無言を貫いたが、いつもとはなにかが違う、何かが変わってしまうのだと、お互いに感じたのかもしれない。
こうして翌日、私たちは警察沙汰の大喧嘩をすることになる。あれから9年たって、もしこの先仲直りするようなことがあったとしても、その先にまたおなじような暴力的な争いが起きることは避けられないと私は思う。あの日、きっと私の目は黄色だった。あなたと同じ、黄色に染まっていた。怒りに我を忘れたときはあなたと同じ目になるように感じるのだ。本当の姿でいることが尊いと本やテレビは言うけれど、私はそんな本当の自分を、できるだけ分厚い理性でくるんで隠して誰にも見られないようにしたい。そうできない相手はできるだけ遠ざける。それしかないと思う。中学校の卒業式、親に向けて書いたメッセージが体育館の壁に張り出された。私は、ママと離婚してもう家にはいないパパに向けて「言葉はあまり通じないけど、絆はほかの親子にも負けないと思ってます。」と書いた。父の読めない日本語で書かれたそのメッセージは、事実を書いた手紙というより、中学生の私から、理解できないまま私たちから遠ざかっていったパパへの、すがるような確認だったように思う。そのころの私は、まさか自分からパパを突き放すことになるなんて思いもしなかっただろう。
長年の疑問の答えはネットで案外簡単に見つけることができた。なんでも、体にあるメラニンの濃度が高いと、それが眼球にも影響して白目が黄色くなるらしい。これから体内のメラニン濃度が大幅に変わることはないだろうし、加齢によるもの以外では、私の目は黄色く染まることはないようだ。少し安心したと同時に、つくづく私には短気なこと以外パパに似たところがないなと、ほんの少しだけ淋しさを覚えた。私が成人したらセネガルに帰ると言っていたパパは、いまだに近所のアパートにひとりで住んでいる。大学で一生懸命勉強したはずのフランス語は、もうすっかり忘れてしまった。鏡にはいつも通り、ママに似た眠たげな二重の目が映る。これが私の顔。
パパ、私、27歳になったよ。
(了)
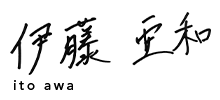
伊藤亜和(いとうあわ):文筆家/モデル。1996年 横浜市生まれ。学習院大学 文学部 フランス語圏文化学科卒業。Noteに掲載した「パパと私」がツイッターで糸井重里、ジェーン・スーなどの目に留まり注目を集める。「きらきらシニアタイムス」「エレマガ。」にて連載中。趣味はクリアファイルと他人のメモ集め。

