日本人で文学好きの母と、瞬間湯沸かし器的にキレるセネガル人の父の間に生まれた亜和(愛称アワヨンベ)。祖父母、弟とさらにキャラの立つ家族に囲まれて、ときにさらされる世間の奇異の目にも負けず懸命に生きる毎日。そんなアワヨンベ一家の日常を綴るハートフルエッセイ。アワヨンベ、ほんとに大丈夫?
パパが家からいなくなって何年か経ったあと、ママに彼氏ができた。
彼氏だったかどうか、本人に確かめたわけではないから、彼氏じゃないのかもしれない。私はまだ子どもだったから、男女の関係については一緒にテレビゲームをする友達か、いずれ結婚する付き合いをする恋人のどちらかしか知らなかった。27歳になった私の周りには、さまざまな男女の関係を含んだ生活があって、当人のあいだの認識すら、ときには同じとは言えない温度の差がうかがえることもある。ママとその人が実際どういう関係だったのかはわからない。だから、私にわかっていたのは、あるときから知らない男の人が家に来るようになった、ということだけだった。
その人のことを、ママは「トシ」と呼んでいたような気がする。坊主頭で、体格はわりとがっちりしていて背が高かった。顔はパーツがそれぞれしっかりした濃い顔立ちだったけれど、いわゆる「外国人」のような彫の深い顔というわけでもなかった。トシのことを思い出そうとすると、ぱっちりとした大きな目をいちばん最初に思い出す。パパもスキンヘッドだったから、私は子供ながらに「ママは髪がない男の人が好みなのか」と勝手な推測をしていた。たぶん、そんなことはない。だけど、最近もテレビに安田顕やISSAが出ていると静かにジッと見ているので、どちらかというと顔がはっきりした男が好きなのは間違いなさそうだ。
トシはだいたい夜に私たちの住むアパートにやってきた。大型のバイクでやってきて、そうでない日は酒を飲んでいるのか、顔を赤くしてヘラヘラと笑顔を浮かべながら家に入ってきた。弟はまだちいさくて、当時のことはきっと憶えていないだろうけど、狭いアパートに心を許していない男が気安く侵入してくることが、私は正直言って、とてつもなく不快だった。トシは私たちと距離を縮めようと、しきりに話しかけてきたりお菓子を買ってきたりしたこともあったが、私は一向に心を開かず冷たくあしらっていた。今思えば、彼女の前夫との子供に対して、いつも機嫌よく接してくれていたトシは、きっと悪い男ではなかったのだろう。連れ子を虐待する交際相手のニュースは定期的に目にするが、トシは私たちを邪険に扱うことはなかった。いちど、酔っぱらって馴れ馴れしく触ろうとしてきたトシの股間を力任せに思いきり蹴り上げたことがあった。しかし、なぜかトシには全くそれが効かず、何度やってもトシはニコニコと笑っているだけだった。おばあちゃんに「変な男がいたらオマタを思いっきり蹴って逃げなさい」と教えられてきた私は、唯一の必殺技が効かないこの男に言い知れぬ恐怖を感じ、こいつを倒すにはどうしたらいいのか、それからずっと考えていた。
私と弟とは別の部屋で、ママとトシが寄り添って眠っているのをみると、こいつがこのまま家に住み着いたらどうしようと、うまく言い表せない不安に襲われた。それに、離婚したとはいえ、パパはこのアパートのすぐ近くに住んでいる。パパが使っている駐車場はこのアパートの目の前だし、3日にいちどは私たちの様子を見にこのアパートにやってくる、トシもそのことはわかっていて、毎回来るときはそれを気にしてコソコソとやってくる。もし鉢合わせでもしたりしたらどうなるか、そんなことは想像に難くない。私はトシがアパートにいるあいだ「突然パパが訪ねてきたらどうしよう」ということばかりが気になって、四六時中落ち着くことができなかった。後々、この不安は的中してしまうことになるのだが、それはもう少し後のことになる。
ほかにトシのことで憶えていることと言えば、トシの乗っていた大きなバイクのことだ。家族の中でバイクに乗る人はいないので、私はトシ本人のことは嫌いつつも、トシの乗ってくるバイクには興味津々だった。間近ではじめて見る大型のバイクは、ゴツゴツとしていて、光っていて、仮面ライダーが乗っているバイクそのもののように見えた。運転席のうしろには同乗者用の小さな座席がついていて、私は乗せてもらいたくて堪らなかったけど、トシに自分からお願い事をしたら、こいつを家族の一員として認めてしまうような気がしてどうしてもできなかった。
もし、このままトシが家族になって、私たちの「パパ」になったとしたら、パパは一体どうなってしまうのだろう、トシがパパになったら、今のパパはパパじゃなくなってしまうのだろうか。このアパートを訪ねることも、私と弟を連れてディズニーランドにも行けなくなって、本当の意味で家族から弾き出されてしまったら、パパにはきっと、この国にいる意味さえなくなってしまうんじゃないだろうか。だからママとトシがどれだけ仲良くなっても、弟がどれだけトシに懐いたとしても、私だけはすでに壊れてしまった家族の瓦礫を、大切に持っておかなければならないのだ。私はまだ、ママがパパのことを少しは好きなんじゃないかと、心のどこかで思っていた。離婚の手続きが済んで、パパが引っ越しの作業をしているとき、ふたりが食器棚を整理しながらふざけあっているのを見た。あのときは、これから別々に暮らすと自分たちで決めたのに、どうしてこの期に及んでこんなに楽しそうにしているのかと、なんだか腹が立つような不思議な感覚になったのに、今はその記憶が大切な拠り所のような気がして、幼い私は「まだ完全に壊れていないかもしれない、パパとママが私の手を片方ずつ引いて、せーので大きくジャンプさせてくれたあの日が、またいつか来るのではないか」と、夢見るような気持ちで考えていたのだった。
あるとき、私とママとトシは、弟が保育園に行っているあいだ、最寄りの駅で待ち合わせをした。ママが少し歩いた先に買い物に行くというので、図書館に本を返した私とトシはふたりきりになった。トシはこの日も大きなバイクに乗ってやってきた。なるべく口を利かないように黙っていると、トシの電話にママから買い物が終わったと連絡がきた。トシは今行くよ、と返事をして、大きなバイクのエンジンをかけて、それから私のほうを見て笑顔を作りながら「乗る?」と聞いてきた。私は嬉しくなって、思わず「乗る!」と返事をした。ヘルメットを被せてもらい、トシの後ろの座席にまたがってみると、思っていたよりも高くて足がつかず、少し怖くなった。「俺の背中にしっかりつかまって」と言われて、控えめにジャンパーを掴んでいた腕を、思い切って抱き着くようにトシの腰に巻き付けた。バイクが激しく振動しながら大きなエンジン音を立てて大通りへ飛び出す。冷たい風が顔に当たって、まるでホウキで空を飛んでいるような疾走感が全身を包んだ。道路の白線が目で追えないほどのスピードで、次々と後ろへ飛んでいく。振り落とされそうなスリル感が堪らなく楽しくて、私はトシに自分の命を完全に預けてしまっているうしろめたさも忘れて、トシの背中で笑いながらキャーキャーとはしゃいだ。ほんの100メートルほどの短い距離だったけれど、降りたあともしばらく胸が高鳴って、バイクに乗ったよ、こわかったよと、ママになんどもなんども話した。子供らしく屈託なく喜んでいる私を見て、トシも嬉しそうにしていた。これからこうやってバイクに乗せてもらえるなら、トシがパパになってもいいかもしれない、そんなふうにさえ思った。
その少しあと、おわりの日はやってきた。
その日、トシは珍しく明るいうちから家にいた、たぶん、土曜日か日曜日だったのだと思う。なにをしていたかは憶えていないけど、部屋の中には相変わらずブラックミュージックのCDが流れていた気がする。その頃うちにあった縦長のコンポには、CDが3枚入るようになっていた。1枚を再生し終わるとコンポの中で3枚のCDを乗せたプレートが、メリーゴーランドのようにクルリと回転しては次のCDを再生し始める。私は、こんなにおもしろいマシーンはきっとうちにしかないと思って、違いも分からないくせに、山積みになった中から面白そうなCDを引っ張り出してはしきりにコンポの中身を取り換えていたのだった。きっとその日もそんなことをしていたと思う。
アパートのインターフォンがなった。我が家のインターフォンは、押すと「ピン」と鳴って、指を離すと「ポン」と鳴る。だから、そのピンとポンの間の長さで、だいたい誰が来たか見当がつく。ピンポンのンが抜けているような速さで、鋭い音が乱暴に鳴った。パパだ。そう直感した。
全員がピタリと黙り込んだ。ママがゆっくりと玄関のほうへ行き、ドアの前で務めていつも通り、はーいと言った。ドアを開けるベルの声が聞こえて、パパの低い声がかすかに聞こえた。奥の部屋でジッとしていた私たちには、どんな会話をしているのかまで聞き取れなかったと思う。それでも、パパの様子から察するに、トシが来ていることはバレていないようだった。家の中には入ってこないだろうし、このままやり過ごしていれば大丈夫だろう。そう思ったのとほとんど同時に、玄関からパパの凄まじい怒鳴り声が聞こえてきた。それから物がバタバタと倒れる音がして、ママの叫び声が聞こえた。玄関に男物の大きなスニーカーがあることに、パパは気づいてしまったのだ。いつもは用心して靴箱にしまっていたのに、今日に限ってトシの靴は脱いだまま置きっぱなしにされていた。怒鳴り声が近づいてくる。私は弟と一緒にとっさに押し入れの中に隠れた。ふすまの隙間にパパの姿が見えて、入ってきた勢いそのままトシを殴り飛ばしたのが見えた。後ろにひっくり返ったトシを、パパは何度も何度も殴る。ママはパパの後ろで半狂乱になりながら「やめて」と叫び続けていた。真っ暗な押し入れの中で泣きはじめる弟を必死でなだめる。私だって泣きそうだった。
トシが逃げようとして、押し入れのほうに近づいてきて、それを追いかけて蹴とばそうとしたパパの大きな足が、私たちが隠れている押し入れのふすまを突き破った。大きな穴が開いたふすまは、そのまま敷居から外れてバタンと部屋の中へ倒れた。ママが弟を抱き上げたのを見て、私はそのまま玄関へ走っていき、息ができなくなるほど嗚咽しながら裸足のまま外へ飛び出した。そしてそのまま家の裏にある長い石の階段を駆け上がって、公園にたどり着き、恐怖で跳ね上がるように脈を打っている心臓を落ち着けようと、ブランコに座ったまま膝におでこをくっつけるようにしてうずくまった。反対側の丘のほうで夕日が沈んで、辺りが少しずつ暗くなっていく。私が逃げたあとどうなったのか、もしかしたら、トシは殺されたかもしれない。冗談じゃなくそう思った。どれだけ時間が経ったか分からない。それほど長くはいなかったと思う。それでも、その時の私には、もう何時間もここでジッとしているように思えた。裸足の足は、砂だらけだった。かろうじて持ち出していた携帯電話に、騒ぎを知ったおばあちゃんから着信がきて、私は呆然としたままフラフラと家の方角へ戻った。泣きながら駆け上がってきた階段の上から家のほうを見下ろすと、何台かのパトカーが来ていて、集まった警官たちの輪の中には、囲まれるようにしてパパが立っていた。その姿を、私はまたその場に留まって、いつまでも見ていた。
トシはもうそこにはいなかった。部屋にあったコンポは壊れて、プレートを小刻みに振るわせながら同じCDを再生し続けた。
トシは、それから二度と来なかった。
(了)
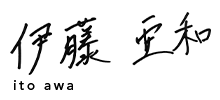
伊藤亜和(いとうあわ):文筆家/モデル。1996年 横浜市生まれ。学習院大学 文学部 フランス語圏文化学科卒業。Noteに掲載した「パパと私」がツイッターで糸井重里、ジェーン・スーなどの目に留まり注目を集める。趣味はクリアファイルと他人のメモ集め。第一作品集『存在の耐えられない愛おしさ』(KADOKAWA)が好評発売中。

