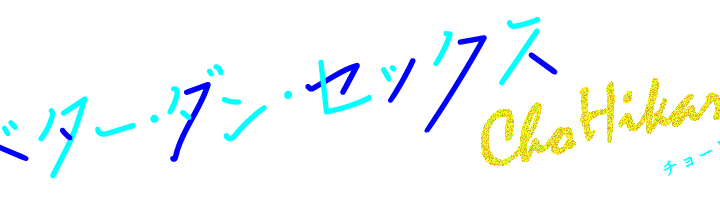まもなく小社から刊行が予定されているペイントアーティスト・チョーヒカルのエッセイ集より、一部の内容を先行公開! 恋愛、モテ、差別やコンプレックス―――現代社会の不条理さや日常やり過ごしてしまいがちな違和感と戦えるようになるまでの成長譚。
どこに旅行に行くときも、無理をしてまで持っていくものがある。ゲーム機だ。PlayStation4かNintendo Switch、どんなにスーツケースの容量を占めようともどちらかは絶対に詰めていく。大学院に行く前は、1日4時間は確実にゲームをしていたし、ことあるごとにリアル脱出ゲームやボードゲーム会の予定を立て、アメリカに住んでいる間も、ほぼ毎週末オンラインでゲームナイトを友だちとやっている。それくらいゲームが好きだ。
中学受験のため塾に通っていた頃、私は発売されたばかりのDSゲーム、「おいでよ どうぶつの森」にハマっていた。宿題の合間に必死で化石を掘り、魚を釣り、虫を捕まえた。それだけではどうしても時間が足りず、夜、布団に潜って最小音量で真っ暗な中、村を駆けずり回って住人に挨拶をした。そんなことを続けていたものだから当然成績は落ちていき、真っ暗な中で画面を見つめすぎたせいか1・5あった視力は一気に0・4に落ちた。似合わないのに何故か赤縁のメガネを買い、あだ名はしばらく「ザマス」になった。
そんな苦い経験があったので、私はつい最近まで自分にゲーム禁止を課していた。特に絵に打ち込み出してからは、ゲームは時間の無駄だと疑わなかった。何時間も仮想の世界で過ごして、そこで何かスキルを得たとしても現実世界では何にもならない。生産性がない。手探りすぎる将来探しに忙しくて、ゲームに興味すら湧かなかったし、ゲームに夢中な友だちを不思議な気持ちで眺めていた。一生ゲームにハマらないのだろうと思っていた中で、いきなり状況が変わることになる。
それは大学を卒業して少し経った頃、大学時代の友だちとお酒を飲んだときだった。ちょうどニンテンドースイッチが発売されて少し経った頃で、みんなその話で持ちきりだった。私はフリーランスを始めたばかりで日々不安に苛まれていた。周りは就職をしたばかりで慣れない職場に四苦八苦していたが、私は何に四苦八苦していいのかも分からず、ずっと真っ暗な中で手探りをしているような気持ちだった。上司の愚痴が言える仲間たちが羨ましかった。仕事も忙しいほどない中、パソコンの前にボーっと座って頭の中で自分の状況を責め続ける、そんな時間が何時間もあった。
「チョーさんも一緒にスイッチでスプラトゥーンやろうよ!」
「いや〜今更ゲーム始めるのもなあ」
「なんでよ、楽しいよ」
「う〜ん」
「忙しい?」
「いや、全然忙しくはない」
「じゃあ暇な時間、何してるの?」
ハッとした。暇な時間、私はただひたすらに無駄なことで悩んでいる。ゲームは時間の無駄だとか言っておきながら、空き時間を少しも有効活用していないじゃないか。じゃあ私はなんのために楽しいことを節約しているんだ?
みんなと別れて家に帰る電車の中で、品薄のスイッチをAmazonで購入した。数日後に届いたスイッチで「スプラトゥーン」を始めると、それはそれは見事な沼だった。スプラトゥーンは端的に説明すると、かわいくデフォルメされたイカとタコのキャラクターが銃や絵画の道具(筆やローラー)から発せられるインクで敵を倒すというゲームで、デザインのかわいさもさることながら、バトルの爽快感が秀逸だ。死んでもすぐに生き返るし、1ゲーム自体が割と短いため永久に繰り返し楽しめる。久々に溢れるアドレナリンに脳が高揚しすぎて、正気を少し失った。
具体的な例を出すと、ゲームを始めたばかりの頃、私は画面の前から3日間、ほとんど動かなかった。水は飲んだし最低限トイレには行ったが、それ以外は睡眠もご飯も風呂もなしで、三日三晩ゲームをプレイし続けた。結果5キロ痩せた。ちなみに同じく沼にハマった友だちはご飯を食べずにプレイし続けたせいで栄養失調になり、体が動かなくなって救急車一歩手前までいった。類友ここに極まれりである。同じ体制で座り続けたせいでギシギシの体で、私はめちゃめちゃ幸せだった。
いつの頃からか、自分の糧にならないものは無駄だと思っていた。ただの現実逃避だと。楽しいことに時間を割くよりもスキルを身につけるべきだと。自分はまだまだ足りていないから、何も達成できていないから、幸せになる権利がないのだと、どこかで思っていたのだ。でも、気づいたのである。人生って私たちが思うよりずっと無意味なのだ。全てを「有意義に」使うなんて無理なのだ。なんだか絶望的な気付きだが、そんな絶望を経て私はようやく自分に楽しみを許すことができるようになった。
ゲームを再び楽しめるようになってからの毎日は、確実に少し楽しくなった。依存しやすい性格ゆえにやり過ぎてしまうことも多々あるけれど、息をしているだけで結構大変なのだから、娯楽がないとやっていけない。逃避であってもいいじゃないか。人生は大して素晴らしくなくて、だからこそ私たちは好き勝手楽しく生きるべきなのである。今は「Apex Legends」というFPSゲーム(シューティングゲーム)の沼にズブズブにハマっている。
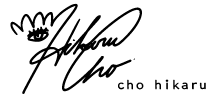 1993年東京生まれ。2016年武蔵野美術大学・
1993年東京生まれ。2016年武蔵野美術大学・