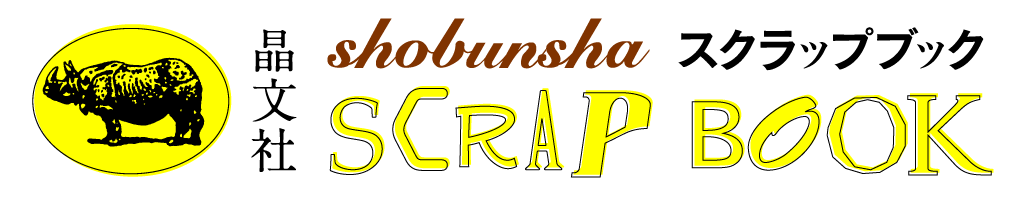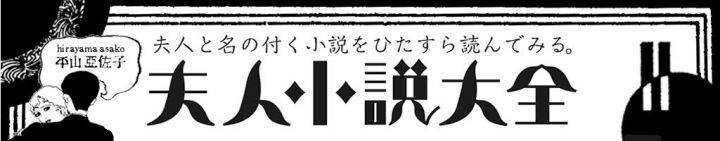真珠夫人、感傷夫人に黄昏夫人……明治以来、数多く発表されてき
作品名:『或る夫人の手紙』三宅やす子 1926(大正15)年
『或る夫人の手紙』の著者三宅やす子は、1890(明治23)年に京都師範学校長とその権妻(妾)の間に生まれた。妻妾同居の家で育ち、正妻を母、実母をばあやと呼んでいた。16歳で父が死去し、叔父で枢密顧問も務めた加藤弘之の世話になりながら「良妻賢母主義全盛時代」(三宅やす子「目標の推移」)のお茶の水高等女学校(現お茶の水女子大学附属高等学校)を卒業する。その間、雑誌『女子文壇』などに投稿もしていた。卒業後、見合いで昆虫学者の三宅恒方と結婚。四児をもうけ二児を失う。学究肌の夫とは性格が合わずひたすら迎合に努めるが、夫の仕事上の不遇な立場を文章にすべく夏目漱石の門をくぐる。漱石亡き後は小宮豊隆に師事するも、11年の結婚生活を経て31歳のときに夫と死別、二児を抱え本格的に文筆で立つこととなる。
このような境遇の女性作家によくあるように、やす子は猛烈に仕事をしている。さまざまな媒体に大量の原稿を書き飛ばし、講演や座談会、雑誌『ウーマン・カレント』の運営などに奔走しているが、そのわりに三宅やす子の業績や作品はあまり知られていない。
その理由とも考えられる点について平塚らいてうはこう喝破した。曰く〈やす子さんの生活は若〈も〉しくは生活態度はその一歩から常識的であり、世間的であり、打算的であり、実際的であります。いかにもイィジィゴォイングであります〉〈忌憚なく言えば作家としてのやす子さんの天分にはあまり多くの期待を持ち得ないでしょう〉〈やす子さんの思想又は意見は要するに時代と歩調を共にすること、時代に妥協し迎合して行くことこれ以上でないようです。新しい思想を説き又新しい思想に共鳴するのではなく、既に時代がこうなって来たからこうすべきだというのが総てのようです〉。(「私の見た三宅やす子さん」)。
確かにやす子は歴史に残るような革新的な論を展開することはなかったが、当事者による『未亡人論』(文化生活研究会、1923年)などは、世間の「未亡人」への貞淑であれというレッテルや無神経なおせっかいに真正面からもの申した、いわば人権宣言のような一書で、戦後に復刊された際にも戦争未亡人たちを勇気づけたと思われる(但し、未亡人をポルノグラフィに繋がるイメージとして確立させたと小田光雄は書く)。大上段に構えた女権論者ばかりが偉いということはないのだ。
さらに翌年、らいてうの筆はやす子の作品の登場人物にまで及ぶ。〈彼女たちは徹頭徹尾コンヴェンショナルな女性である〉としつつ、〈しかしそれにしても氏の作品の中の母はどれもこれもあまりと言えばあまりに母らしくない母ばかりである〉〈その母子関係は、あまりに冷たく、寂しく、厭わしく、時として恨めしく、呪わしくさえ思われる〉。もっとも、〈氏が母性の尊重者でも、又母愛の礼賛者でもないことは氏のお書きになった感想などで私は以前から察していた〉とし、とある女性だけの会合で、ある人が自分の子どもに対して可愛くてたまらないから世話や教育をするので義務からするのではないと言ったところ、やす子は自分は愛ばかりで世話をしていない、責任感からであると言ったらしく、そのことをらいてうは〈不思議にはっきりと私の記憶にのこっている〉と書く(「三宅やす子氏の創作の中の女性に就いて」)。筆者には、理想論ばかり言っている女性たちに比べてやす子の方がよほど地に足がついているように見える。子どもが可愛くてたまらないから世話をするのであれば、何かのきっかけで可愛くなくなったらどうするのだろうか。どう考えても責任感は必要だろう。ともあれ、さすがに小説にまで口を出されて腹に据えかねたか、やす子は翌月に「らいてう氏の蒙を拓く」として八つの点を挙げて反論。なかでも四の〈「世間と容易に妥協し得る女」と云われるが、妥協は或る意味で決して容易ではない。少くとも無反省な反抗よりも、意識した妥協の中には消し切れないものがある〉は本意だろう。また〈母性愛礼賛などという古めかしい事は、文部省の母性愛映画にでも任せておけば足りる〉はなかなか痛快である。なお、らいてうはさらに小馬鹿にしたような反論「『らいてう氏の蒙を拓く』を読みて 三宅やす子さんに」を書いているが、長くなるのでここでは省く。ただ、〈ずいぶんお怒りになりましたね、ほんとうに意外です〉〈あれが私の知っている三宅さんかしらと可成り驚きました〉については意外でもなんでもない、らいてうは最初から見誤っているのだと言いたい。
もっとも大きな見誤りは、最初の記事「私の見た三宅やす子さん」のなかで〈こういうやす子さんは恋愛を経験するには恐らく最も不向きな人でしょう。その過去に恋愛の情熱に自分を燃やしたような経験をもたないらしいこの人は多分今後の生活に於ても持ち得ないのではないでしょうか〉と書いている点。
実はやす子、この時期密かに大恋愛の真っ最中だったのだ。
その辺りのことも著書と著者が一致しているやす子らしく「偽れる未亡人」として隠さず書いている(著者急逝により未完。タイトルは編集部作)。
相手は夫の一番弟子で小説のなかでは「牧」、吉屋信子のエッセイ「偽れる未亡人」のなかでは「Y理学士」とされる2〜3歳下の男性。
亡き師の後片付けなどで通ううちに親しくなり交際に発展、彼の弟がやす子の雑誌を手伝うなどほとんど家族ぐるみの関係だった。当時、まさに「或る夫人の手紙」と同様に彼に縁談が持ち上がってやす子に見破られて断るということがあったらしい。
小説「偽れる未亡人」のなかの芳子(やす子)は〈「私が、得心のゆくお嫁さんを貰って頂戴」〉〈(引用者注:縁談は)早晩来ることなんだから。只其時が一寸いやなだけね。何でもないわ。行ってらっしゃい。そうして私に何でも話して頂戴。私にわかる事は、また何でもお手伝いしてよ」〉と気丈に言うものの、牧の帰った後に〈「黙って泣いて居ます」〉という手紙を出している。「或る夫人の手紙」よりはあっさりしているが、言うに言えない本音を小説にしたのかもしれない。その後、長女が15、6歳になる6年後に結婚しようと話はまとまった。
それから牧はロックフェラー財団によるスカラーシップで2年のアメリカ留学に向かう。ちょうどこの頃「或る夫人の手紙」を収載したやす子初の単行本が出ている。つまり、彼の帰国後の結婚、未亡人から夫人への転身を強く信じていた時期に書かれた「或る夫人の手紙」の終わりが急転直下の駆け落ちになっているのも今でいう「匂わせ」だったのかもしれない。
小説「偽れる夫人」の方はここで途絶しているが、吉屋信子によれば、留学中のY理学士からの手紙は次第に遠のき、帰国時期になっても連絡がないので同僚に聞いてみるととっくに帰国して京都の大学に戻っていた。しばらくして訪ねてきた本人の口から婚約破棄を言われたという。夫の七回忌の際、未亡人から新たな道を行くようなことを皆んなの前で宣言した矢先だった。
彼がどこかの女性と結婚する日、〈やす子はわが家の椅子に身を投げかけて式の挙げられる時間に刻々針の進む時計をじっと睨みつけて動かなかった〉(吉屋信子「偽れる未亡人」)。
その後、風采のいいAなる男性との恋愛に入るが〈原稿料や印税も、もっぱらその人につぎ込まれていくようだった〉(舟橋聖一「三宅やす子」)という歪な関係で、〈Y氏との恋愛破綻の鎮痛剤としてA氏を服用した〉(吉屋信子「偽れる未亡人」)とは吉屋信子の見立てである。
やす子と仲が良く、ふたりで恋愛話に興じていたという宇野千代はAについて「あんな男、どうしてやめないの」と聞いたときのやす子の答えを書いている。曰く〈「好いじゃないの、どんな偉そうな男だって、馬鹿な半玉か何かに平気でだまされてるじゃないの、あたしみんな分かってるんですもの」〉。
常識的で迎合的だと揶揄された三宅やす子は恋に溺れつつ、それを客観的に楽しむことのできる女性だった。
確かに師匠漱石に「大味」と言われるような作品であり性質でもあったが、率直で行動的なやす子の主張は当時の女性たちを鼓舞した。
吉屋信子はやす子を〈時々ガーガー鳴ったりした古い大型ラジオ〉と形容するが〈いまなお私の記憶にしかと腰を据えてこの未亡人は生きている〉と書く。
それは残された作品だけを読む者には窺い知れない、人間というものの持つ複雑さなのだろう。
〈おもな参考文献〉
和泉あき「三宅やす子著『未亡人論』解説」『未亡人論』(不二出版、1986年)
岩見照代「第27巻解題 三宅やす子『真実に歩む』」『時代が求めた「女性像」ー「女性像」の変容と変遷ー 第27巻 時代を映す「女性像」1』(ゆまに書房、2014年)
平塚らいてう「私の見た三宅やす子さん」『婦人公論』10(1)(112)(中央公論社、1925年)
平塚らいてう「三宅やす子氏の創作の中の女性に就いて」『婦人公論』11(8)(132)(中央公論社、1926年)
三宅やす子「らいてう氏の蒙を拓く」『婦人公論』11(9)(133)(中央公論社、1926年)
吉屋信子「偽れる未亡人」『自伝的女流文壇史』(中央公論社、1962年)
宇野千代「三宅やす子さん」「三宅さんを憶ふ」「三宅さんと戀人」『女の愛情』(鱒書房、1939年)
舟橋聖一「三宅やす子」『わが女人抄』(朝日新聞社、1965年)
三宅やす子「自叙伝の一節」『未亡人論』(不二出版、1986年)
小田光雄「古本屋散策(101)三宅やす子『偽れる未亡人』『未亡人論』」(『日本古書通信』(973)、2010年)
小田光雄「古本屋散策(102)『ウーマン・カレント』と文化生活研究会」(『日本古書通信』(974)、2010年)
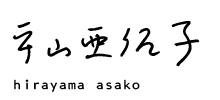 兵庫県生まれ、東京育ち。文筆家、デザイナー、挿話蒐集家。著書『20世紀破天荒セレブ――ありえないほど楽しい女の人生カタログ』(国書刊行会)、『明治大正昭和 不良少女伝――莫蓮女と少女ギャング団』(河出書房新社)、近刊に『戦前尖端語辞典』(左右社)、『問題の女 本荘幽蘭伝』(平凡社)。2022年3月に『明治大正昭和 不良少女伝』がちくま文庫となる。唄のユニット「2525稼業」所属。
兵庫県生まれ、東京育ち。文筆家、デザイナー、挿話蒐集家。著書『20世紀破天荒セレブ――ありえないほど楽しい女の人生カタログ』(国書刊行会)、『明治大正昭和 不良少女伝――莫蓮女と少女ギャング団』(河出書房新社)、近刊に『戦前尖端語辞典』(左右社)、『問題の女 本荘幽蘭伝』(平凡社)。2022年3月に『明治大正昭和 不良少女伝』がちくま文庫となる。唄のユニット「2525稼業」所属。
Twitter