セクハラ被害を言語化することはむずかしい。ましてや、それが「よきことをなす人」たちの組織内で起きたときの場合は、さらに複雑な事態となる。そもそも、セクハラはなぜおきるのか。「よきことをなす」ことが、なぜときに加害につながるのか。被害を言語化するのにどうして長い時間が必要になるのか。セクハラをめぐる加害・被害対立の二極化を越え、真に当事者をサポートするための考察。
ひさびさの更新になる。前回から3か月近くが過ぎてしまったことを申し訳なく思っている。
これまでweb上で連載してきたものはいくつもあるが、単発性というよりも全体のおおまかな構成を念頭に書いてきた。そのときどきに感じたことをエッセイ風に書くこともあったが、たいてい構造と構成を意識して書きすすめてきた。しかし今回それを再考する必要に迫られた。
第一回を開始したきっかけが、コロナ禍で起きたいくつかのできごとだったことはすでに述べた。たとえばべてぶくろやsoarでの性被害の告発などである。その中のひとつとして東京シューレにおける性暴力事件(以下本件とする)を取り上げ、シューレ側の発言を引用した。直後からそれに対する反響はtwitter上で何件かあり、その多くは明らかな抗議であった。セクハラという言葉で明らかな性暴力をくくることは、むしろ加害の程度を減衰させる効果を持つのだから、被害者に対する二次加害ではないかといったものもあった。
第一回を書き始めるときに、私の意図はいくつかあった。目下、第7波の感染者急増を迎えているコロナ禍が、私たちにどのような影響を与えたのかの例証のつもりだった。数字に表れた女性の自殺者の増加、DV相談件数の増加、といった可視化されたものだけでなく、家族関係や職場の中で隠されていた何かを露わにしたのではないか。中でもこれまで表面化することを妨げられてきたものが覆いを外されたかのように一気に表舞台に登場した。そのひとつがセクハラではないか、というものだ。
名前も与えられなかった経験、体調を崩したり精神的不調を呈する背後にある経験を性被害と同定するまでの長い道のりを、可能な限りうねうねと描き、いまだに責任が自分にあるのではないかと苦しんでいるひとたちに、セクハラ被害と自己定義する後押しをしたい。これが本連載の動機だった。そんな女性たちに何人かお会いしてきたこともあった。
皮肉にも、そんな私の意図は、本件の被害者にとっては、まさに自己定義権の侵害になっていたのである。
本件をはじめとする例はすべて係争中であり、終わってなどいない。法的にも「被害者」として闘っているという事実があったのに、それを無視したことになる。少なくともセクハラという定義の範囲からは外すべきだった。それは私の情報収集の不徹底によるものであり、本件および他の事例の被害者に対する配慮の欠如によるものだ。ひいていえば読者に対する誠実さを欠いていたことになる。すべて私の落ち度であり、私の責任である。
「セクハラ」と呼ぶことの意味の適用範囲から、例に挙げた事案、中でも本件を除外したい。関係者の方から示唆されて、改めて本件に関するネット上の情報を読み、詳細を知った。ただただ驚くばかりだった。
東京シューレは、カウンセリングで不登校の子どもを持つ親御さんとお会いすることも多いため、間接的にその活動を知っていた。しかし本件については、マスメディアを通した情報しかなく、それがどれほど限られた情報だったのかを再認識した。下記の記事をすべて読み、初めて20年近くにわたる被害者の闘いを知ったのである。
ログハウスシューレ性暴力加害事件(2021年7月28日より随時更新): もぐらの会 (seesaa.net)
東京シューレにおける性被害事件について/ひとつの証言として (maigopeople.blogspot.com)
東京シューレ性暴力被害者原告による要望書|郡司 真子 Masako GUNJ I |note
【号外】「女子校のプールの水になりたい」弁護士に性暴力被害者が伝えたいこと | なんかなんか通信 (theletter.jp)
読めば読むほど、否認し、無視し、握りつぶそうとしたシューレ側の姿勢がよくわかる。それでもだめだとわかると、口外禁止として外部に漏れないようにし、さらに被害者側からの要請によって公正を期すための第三者委員会を立ち上げたにもかかわらず、そのメンバーが非公開だったりした。その中にはシューレの理事らが入っていたのも驚きだった。最後の記事を読むと、委員である弁護士らから「誹謗中傷だ」と逆ギレされたりしている。
非公開は、被害者のプライバシー保護のためという大義名分によって、実は加害者を守るために行われる常套手段だと思っている。
本件の被害者(原告側)からすれば、20年近い歳月において、社会的に「よきことをなす」とされ、不登校の業界では草分け的存在であるシューレを相手に闘ってきたのだ。それを私の連載において「セクハラ」のひとつとして定義され、おまけに責任を取るどころか自己保身のために逃げ切ろうとし続けているシューレの言い分だけが取り上げられていたことになる。
自分が何の被害者なのかは、被害者の自己決定が最優先されるべきだろう。自己決定と言っても、長い歳月において揺らぎ、外部から妨害され、足元を崩され、それでも周囲の支援者からの支えによって不断に決定され続けなければならない。それは最後の砦、最終的尊厳に近いと思う。それを私が「セクハラ被害者」として定義する範疇に収めてしまった、それがどれほど被害者にとって大きな打撃だったか、まさに二次加害と呼ばれても仕方がない。傲慢かもしれないが、私が性被害者の立場に立って発言していると信頼を得ていたからこそ、そのショックは大きかっただろう。それを思うと言葉を失う。
さらに私の連載記事が、訴えられている側(加害者側)に利用される危険性もある。「自分たちがやったのは性暴力じゃない、セクハラにすぎない」という根拠になるかもしれない。
ほら、この連載に書いてありますよね、と資料にされたら、私の連載の存在そのものが有害になってしまう。
一連の経過を知ることで、被害者に対して「加害者」が責任を取ることとはいかなることかを深く考えさせられた。
本件におけるシューレ側の対応は、すべて「責任をとらないこと」の具体例だった。認めない、訴えた側の落ち度だと責める、むしろ自分の側が被害者だと主張する、などは、DV加害者プログラムを実施してきたので手に取るようにわかるが、親密圏ではなくひとつの団体・組織が同じような対応をすることに驚いた。被害者支援の弁護士にとっては半ば常識かもしれないが。そこには、シューレという団体が社会的名声と「よきことをなす」という評価をバックにしているから生じる「権力」と「自己保身」が見え隠れする。それは当事者
(シューレの利用者)に対する権力であり、私もその一員である援助の世界における専門家権力にも通じるものだ。
そして、私も同じことを問われていると思った。
自らの加害性・加害者性に直面することがどれほど困難なことか、被害者という自己定義よりもさらにそれは困難を極める。
本連載に寄せられた抗議に対して、私の中でスルーすればいい、無視すればいい、という声がなかったかと言えば嘘になる。毎回徹夜状態でキーボードを叩いていると、「こんな大変な思いで書いているのに」という被害者意識がむくむくと湧いてくるのも自覚できた。
しかし、DV加害者プログラムにかかわってきたことが影響した(幸いだった)。責任を引き受ける、責任を取るとはどのようなことかを知識として知っていた。DV加害者プログラムの場合、責任を取ったかどうかは、法廷ではなく被害者が判断するというのが原則である。
それが、まさに自分の身において試されていると思った。月並みな言葉だが、抗議や批判に対して、誠実に対応しようと思った。
つまり、私自身が自分の行為の加害性を認め、そのことを率直に謝罪しようと思った。反省します、ごめんなさい、という定番どおりの筋書きではなく、何に対して、自分の行為のどの部分に対して謝罪するかも具体的に提示しなければならない。これが説明責任である。
繰り返しになるが、本連載でセクハラという言葉の具体例として「本件」を挙げたのは不適切だったことを伝えたい。ログハウスシューレで起きた性暴力の事件の被害者に対して、私の書いた内容が衝撃を与えたことは想像に難くない。それに対して申し訳なく思っている。
私のカウンセラーとしての姿勢は、力の弱いほうの立場に立つことを基本としてきた。それが時として二次加害的影響を与えてしまうことに対して、あまりに無自覚だったと思う。率直に批判し抗議してくださったひとたちによって、このような気づきを得られたと思う。
絶えず裏切られ、誰一人信じられなくなる。性被害の深部には、このような世界から見捨てられたという絶望がとぐろを巻いている。少なくとも、私はその絶望に手を貸すことだけはしたくない。そう思って今回の謝罪文を書いた。
*今回の件は、編集担当の情報確認の不徹底によるものでもあります。あらためてお詫び申し上げるとともに、今後はこのようなことのないよう、配慮の行き届いた編集を進めていきますので、今後の連載も継続してお読みいただけるとさいわいです。(編集部)
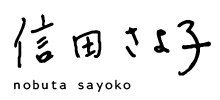 1946年生まれ。公認心理師・臨床心理士。お茶の水女子大学大学院修士課程修了。1995年に原宿カウンセリングセンター設立、現在は顧問。アルコール依存症、摂食障害、DV、子どもの虐待などに悩む本人や家族へのカウンセリングを行なってきた。『母が重くてたまらない』(春秋社)、『DVと虐待』(医学書院)、『加害者は変われるか?』(筑摩書房)、『家族と国家は共謀する』(KADOKAWA)、『アダルト・チルドレン』(学芸みらい社)、『家族と災厄』(生きのびるブックス)など、著書多数。
1946年生まれ。公認心理師・臨床心理士。お茶の水女子大学大学院修士課程修了。1995年に原宿カウンセリングセンター設立、現在は顧問。アルコール依存症、摂食障害、DV、子どもの虐待などに悩む本人や家族へのカウンセリングを行なってきた。『母が重くてたまらない』(春秋社)、『DVと虐待』(医学書院)、『加害者は変われるか?』(筑摩書房)、『家族と国家は共謀する』(KADOKAWA)、『アダルト・チルドレン』(学芸みらい社)、『家族と災厄』(生きのびるブックス)など、著書多数。

