セクハラ被害を言語化することはむずかしい。ましてや、それが「よきことをなす人」たちの組織内で起きたときの場合は、さらに複雑な事態となる。そもそも、セクハラはなぜおきるのか。「よきことをなす」ことが、なぜときに加害につながるのか。被害を言語化するのにどうして長い時間が必要になるのか。セクハラをめぐる加害・被害対立の二極化を越え、真に当事者をサポートするための考察。
スターのような
やっぱりすごい、Fさんの映像は全然違う。43歳のB子さんは通勤電車でYouTubeを見ながらつくづく感嘆した。3年前に評判になった某地方都市における技能実習生のドキュメントは、YouTubeで何万人ものviewがついていた。
ひとまわり年上のFさんは、B子さんの勤務するテレビ局の中でも、骨のあるドキュメントを経営陣に抗して作り続けている社員として知られていた。どこのテレビ局も、このところ若者のテレビ離れが著しいので番組編成に頭を悩ませているが、55歳という第一線を退いてもいい年齢のFさんは、文章もうまく対外的発信力があるために、その制作姿勢はなんとか大目に見られているというもっぱらの噂だった。いわゆるスター社員として厚遇されていたのは事実だろう。
目が合った
31歳で結婚し、息子がやっと小学校3年になったB子さんは、もう少し仕事に本腰を入れられたらと考えていた。あまり関係のよくない実母だが、同じ敷地の中に住まわせてもらっていて、孫のめんどうもよく見てくれるので結果的には助かっている。
一昨年の4月、新しい企画が立ち上がり、B子さんもチームの一員として加わることになった。メディア各社がコンプライアンスという慣れない言葉を使い始めたのがもう15年ほど前になる。そして今度はSDGsである。目新しいコンセプトのもと、お茶の間に受け入れられるようにバラエティーの要素も取り入れるにはどうすればいいのか。Fさんにもアドバイザーとして加わってもらうことにした。コロナ感染拡大のため緊急事態宣言が発出されたが、テレビの放送を止めることはできない。手探りで感染防止を図りながらB子さんも出勤を続けた。
第一回の会議の席上、Fさんの発言の仕方が思ったよりずっとマイルドだったことに驚いた。これまでも同じ社内で姿を見かけたことはあったが、どこか雲の上のひとのように思っていた。海外赴任経験もあり、ドキュメンタリーの中に鋭い政治的批判が内包されているのが持ち味となっていた。チームの同僚によれば、アフリカに出張した際にはずいぶん危険な目にも遭ったとのことだった。
席上で、たびたびFさんと目が合った。マスク姿だから余計意識されたのかもしれない。B子さんはコンタクトレンズを付けているが、それでもときどきぼんやりしか見えないくらい近視がひどい。視力のせいかと思ったが、目が合うことは不愉快どころか注目されているようで悪い気はしなかった。
強引な誘い
それから数日後Fさんからメールが届いた。
「企画チームのアドバイザーとしてお役に立てているかどうか気になっています」という書き出しに続けて、次のような言葉が書かれていた。
「ぶしつけに見つめてしまい、もし不快に思われたらごめんなさい」とあった。社内メールだったし、会社自体がハラスメント防止には神経をとがらせる雰囲気だったので、そこに何か意図があるとは考えられなかった。Fさんのような社会問題に精通したひとが、ハラスメントのことを知らないはずはないとも思った。何より今回の企画主旨がジェンダー平等にかかわるものだった。
それに目が何度も合ったことは、B子さんも記憶していたので、返信はきわめて丁重に「そんなことはありません」と書いて送った。
翌週、Fさんから食事に誘われた。
すこし強引にも思えたが、尊敬する先輩でもあり、あのような社会正義に溢れた番組を作り続けてきた人だという信頼があったので、食事をすることにした。
イタリアンのレストランで、おいしそうにチーズを食べながら、Fさんは饒舌に語った。
「とっても素敵だ」
「週一回のあのアドバイザーの時間だけが楽しみだ」・・・
B子さんは驚いてしまった。もともと尊敬していた人だし、今後も企画実現のためにはお世話になるだろうと思って、できるだけ心証を害しないように、今起きていることを好意的に解釈しようと努力した。何度も自分の左薬指の結婚リングを見せつけるようにして、ナイフとフォークを使った。
カードで支払いを済ませたFさんは、地下鉄の駅まで歩きながら、来年には退社しフリーになる予定だと言った。知名度も高く、ドキュメンタリー映像作家からも尊敬されているのだから、フリーになればもっと活躍の場が広がるだろう。パンデミックの衝撃も、たぶん彼は作品の栄養にしていくだけの力量を持っているはずだ。そんな想像が湧いてきたが、それを伝えるのは出過ぎているような気もした。
別れ際に「退社されることはとても残念です」と伝えたら、Fさんは「そうなったら個人的に会えばいいから」と言った。そこにはなんの葛藤もなく、当たり前のことのような自然さがあった。
別れてから、Fさんの心証を害さないようにできただろうかと何度も思い返した。そして、尊敬するFさんの数々の発言は、あの世代の男性には「よくあること」「単なる軽口」ではないかと思おうとした。
からかいなのか
その後Fさんからのメールは頻度を増した。
食事をともにしたからなのか、文体もくだけたものになり、「ときめいてしまった」「ほんとに素敵で若いころのようにドキドキした」と書かれるようになった。そして、少しずつ内容も変わってきた。
「もっとリラックスできるところで飲みましょう」
「自分の振る舞いに気をつけないと、なんだかタガが外れそうだ」
この文章を読むに至って、B子さんの困惑・混乱は極度に高まった。
この混乱を誰かに相談できるとも思えず、ずっと抱えるしかなかった。
食事場面で何か勘違いをさせるような言動をしてしまったのではないか、いや結婚指輪を彼は見ているはずだし、子どもの話題も出したはずだ。私が既婚者で小学生の息子がいることも知っているはずだ。これまでずっと尊敬してきたFさんが、まさか自分を女性として誘うことなどありえない。私が何か誤解されることをしたからなのか。でもずっと気を遣っていたからそんなはずはない。とすればあのメールは何だろう。そうか、あれは彼がからかっていたのだ。私をからかってみただけなのではないか。その反応を楽しんでいるのだとすれば…。B子さんはだんだん腹立たしくなってきた。私をからかいの対象とするなんて、それはあんまりだ。でも考え違いかもしれない。
彼がいったい何を意図していたのか、ちゃんとそれを確かめてみなければならない。
そして「ごめん、からかってしまって」と彼があやまってくれれば、百歩譲ってなんとか許せるだろう。
このようなことを来る日も来る日も頭の中でぐるぐると考え続けた。
ショックのあまり
そして夏休み前のある日、短時間カフェでFさんと会うことにした。
ずっと考え続けてきたことを思い切って尋ねてみた。もちろん「失礼かもしれませんが」「こんなことを聞いて気分を害されるかもしれませんが」といった丁寧すぎるほどの前置きは忘れなかった。
それに対して、Fさんがどういう言葉を返したのか、実はあまり記憶がない。それくらいショックを受けたからだろう。確かなのは、「からかってなんかいない」という部分だけだ。それに加えて、「会議中になんども僕と目が合いましたよね」と何度も言われたのである。
会社が夏休みに入り、息子が塾に通うようになり、研究職の夫がオンライン授業の準備でいらいらしていたことも重なり、B子さんは食欲を失っていった。もともと夏に弱い体質だったが、体重も徐々に減っていった。
夏休みが過ぎ、9月になっても食欲は不振のままで、体重が3キロも減ってしまった。不眠も始まり、在宅勤務の時間は起きていられずに倒れるように横になったり、涙が突然流れ始めて困るという事態も出現した。
ハラスメントの構造
ここまでお読みになってどう思われるだろうか。
もちろんB子さんは架空の人物である。リアリティを増すために具体的な設定を書いているが、それらもフィクションであることは言うまでもない。
「いや、こんなの大したことじゃないでしょ」「よくあることですよ」「この女性、特に何かされたわけじゃないですよね、触られてもいませんし」と反応される方も多いだろう。
しかしB子さんの例を取り上げたのは、怒鳴られたり、身体を触られたり、卑猥な言葉を投げかけられたりなどされていないからなのだ。具体例として示されるようなわかりやすいハラスメントではないぶんだけ、どこかハラスメントの本質(というものがあるとして)がよく表わされていると思うからだ。
彼女が苦しむようになるのは、Fさんに対する深い「尊敬」があったからだ。彼の行ってきた仕事、それに対する社会的評価の高さ、社内的立ち位置の独自性、すべてにおいてB子さんの憧れであり尊敬の対象だった。
本連載で前回とりあげたキーワードは「尊敬」だった。B子さんの困惑、混乱、身体的症状のすべては、まさに尊敬ゆえに生じたと考えるべきだろう。Fさんという男性への尊敬と、自分に対する彼の言動をどのように整合性をもたせればいいのか。この矛盾・両立不能性をどのように抱え込めばいいのか。巨大で深いギャップをどのように埋めればいいのかについて、日々懊悩するしかなかったのである。
ハラスメントの被害者たちは、その場ですぐに「自分はハラスメント被害を受けた」と思うわけではない。もちろん例外的に即座に反応するひともいるかもしれないが。
多くは事後的に、B子さんのように、自らの経験がなんであるかについて苦しみぬいた末に「ハラスメント」という言葉にたどり着くのである。しかしその道は平たんではない。山あり谷ありどころか、二つの落とし穴がある。これは避けることのできない陥穽である。まず1番目の落とし穴について述べよう。
「私が誘った」という落とし穴
一番よく陥るのが、自分が誘ったのだという解釈だ。尊敬する相手は「そんなことをするはずがない」ひとなのである。とすれば私がそうさせてしまったのだ。あんな行為をさせるように私が誘ったのかもしれない。そう、私が誘ったのだ!そう考えると、整合性が生まれる。それに伴って、あれもこれも、相手を誘う行為に思えてくる。整合性とひきかえに、自分が途方もなくひどい人間に思えてくるのだ。
このような思考のプロセスは、性暴力被害者にほぼ共通のものだろう。たとえレイプされたとしても、まず思うのが「隙があった」のではないかである。それくらい、深く女性たちは身を守らなければならないと思わされてきた。
今でも、鉄道の駅に貼られた痴漢防止のポスターには、「防止の責任は女性にある」という主張が繰り返されている。そんなに胸が開いた服装は危ない、スカートが短い、といった警告は日常的だ。男性とふたりで酒を飲むこと、暗い夜道をいっしょに歩くことは、性的同意であると男性には翻訳されてしまうらしい。こうやって女性の側が誘ったという説は、昭和の時代からほぼ変わらず生き続けている。
精神分析の祖と言われるフロイトが、多くの近親姦(性虐待)被害を訴える女性たちを診ていたことはよく知られている。その中から、彼の有名な「誘惑説」が誕生した。父や兄から性虐待を受けたというよりも、むしろ彼女たちが無意識的に誘ったのだと唱えたのである。このフロイトの説があまりにひどいのではないかと言われるようになったのは、つい最近(1990年代に入ってから)である。今でもこの説を信じている専門家は少なくないのではないかと思う。19世紀末のウイーンでは多くの人々から支持されたことは言うまでもない。
「そんなことをするはずもない尊敬の対象」の言動によって、多くの被害者は、「矛盾」「両立不能」を解決して「ギャップ」を埋めるために、自分が誘ったのだと考え、深くそんな自分を責めるのである。自責の果てに、体調を崩し、不眠状態に陥り、感情が不安定となる。それは外部からは見えない。他者に相談すれば、尊敬の対象を壊してしまうのではないかと怖れるのである。B子さんのように、すべては被害女性の頭の中(記憶の整合性)で起きているので、周囲からはまったく理解不能である。その孤立感が、ますます被害者を追い込んでいく。
多くのひとたちは、セクハラを騒ぎ立てる風潮に内心では反感をおぼえているだろう。おおげさだ、これまで平気だったのに急に言い募るなんて逆ハラスメントじゃないか、などと。
B子さんの例が示すものは、「そんなことをする人じゃない」という尊敬(信頼)と矛盾する言動が、どれほど深い影響を与え、どれほど長期化するのかということである。
次回はもうひとつの落とし穴(陥穽)について述べてみたい。
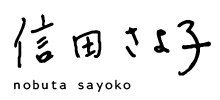 1946年生まれ。公認心理師・臨床心理士。お茶の水女子大学大学院修士課程修了。1995年に原宿カウンセリングセンター設立、現在は顧問。アルコール依存症、摂食障害、DV、子どもの虐待などに悩む本人や家族へのカウンセリングを行なってきた。『母が重くてたまらない』(春秋社)、『DVと虐待』(医学書院)、『加害者は変われるか?』(筑摩書房)、『家族と国家は共謀する』(KADOKAWA)、『アダルト・チルドレン』(学芸みらい社)、『家族と災厄』(生きのびるブックス)など、著書多数。
1946年生まれ。公認心理師・臨床心理士。お茶の水女子大学大学院修士課程修了。1995年に原宿カウンセリングセンター設立、現在は顧問。アルコール依存症、摂食障害、DV、子どもの虐待などに悩む本人や家族へのカウンセリングを行なってきた。『母が重くてたまらない』(春秋社)、『DVと虐待』(医学書院)、『加害者は変われるか?』(筑摩書房)、『家族と国家は共謀する』(KADOKAWA)、『アダルト・チルドレン』(学芸みらい社)、『家族と災厄』(生きのびるブックス)など、著書多数。

