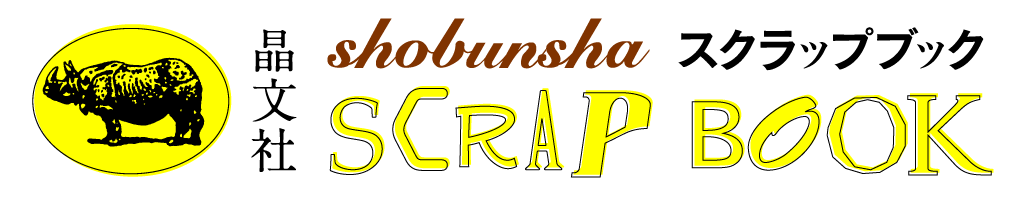セクハラ被害を言語化することはむずかしい。ましてや、それが「よきことをなす人」たちの組織内で起きたときの場合は、さらに複雑な事態となる。そもそも、セクハラはなぜおきるのか。「よきことをなす」ことが、なぜときに加害につながるのか。被害を言語化するのにどうして長い時間が必要になるのか。セクハラをめぐる加害・被害対立の二極化を越え、真に当事者をサポートするための考察。
みなさま、1年半ぶりに戻ってきました。長らくの休載申し訳ありませんでした。
さて、この間に本連載のテーマに関する多くの出来事が起きた。第6回を書き終えたときには全く想像もできないことばかりだ。旧ジャニーズと書く日がやってくるなど、誰が考えただろう。「性加害」という言葉が、インターネットやさまざまなメディアをとおして飛び交い、推しのジャニタレをとおして、あらゆる年齢層のひとたちが「性加害」について考え、想像し、自分なりの考えを形成するように迫られるようになろうとは、これも想像できなかったはずだ。
風見鶏のように
さて、今回は「被害」を認めること、「加害」を認めることについて考えてみたい。最近「加害」という言葉が簡単に使われ、その途端に加害者=悪であり、「文句なしにひどい人」として片付けられてしまう気がするからだ。どんなときでも、二つに分けてきっちりと整理してしまうことに私は抵抗をおぼえる。DV加害者プログラムを長年実施し、DV被害者のグループカウンセリングを実施してきた私だが、その思いはずっと変わらない。
世の中がさまざまな加害に厳しくなればなるほど、まるで風になびく柳や風見鶏を見ているような気がする。つい10年前まで、「される方が悪い」、被害者のほうに責任があると言わんばかりに被害者からの訴えを退けたひとたちが、くるっと変わって「加害者は人間じゃない」と断定して責める側に回る光景を見ると、敗戦後の日本で天皇陛下バンザイからアメリカ民主主義バンザイへと速やかに位置取りを変えた人たちとどこが違うのかと思う。
とはいえ、性暴力に関する法律が変わり、性暴力・セクハラ被害の認定も進み、さまざまな組織における被害者への相談体制が充実してきたことは何よりうれしい、そう思っていることに違いはない。
被害者にも加害者にも苦しみはある
前回(第6回)は「謝罪文」を書いた。本連載における私の記述に関する当事者からの批判や指摘があったからだ。詳しいことはもういちどお読みいただければと思う。手っ取り早く言えば、私の記述が被害者にとっての二次加害になることが指摘されたのである。謝罪文を書くかどうか、書くとしたらどう書けばいいのか、ほんとうに苦労した記憶がある。お読みくださった方たちからのおおむね好意的な反応によって、その苦労も報われた気がしたが、やはり苦しい作業だった。これらの経験から気づいたことがある。
被害を認めること、被害者だと自己定義することの苦しさは言うまでもない。そのことを書いた本はたくさんあるし、トラウマ関連の専門書もこのところ多い。被害の苦しみがやっと理解され、社会的に承認されるようになったのがこの5年ほどだろう。
それに比べると、加害を認めること、自分が加害者と呼ばれることを受け入れる苦しみに関する記述はほんとうに少ない。たぶん書きながら自己弁護になってる気がしてくるからだろう。もしくはそう批判される気がするからではないか。あるとすれば、最初から反省モードで「もうしわけありません」を連発する内容がほとんどだ。うがった見方をすれば、とにかく謝ればいい、ひたすら頭を下げつづければいい、そう考えているだけに思える。
苦しみの比較によって生まれるもの
被害者にしてみれば、「とにかく認めるのが先でしょう」「自分がやったことの加害性を認めろ」「被害者の苦しみを考えたことがあるのか」と憤りしかないだろう。そこには、やはり被害者の苦しみに「比べれば」加害者の苦しみなんて……という比較が働いている。
このような「苦しみの比較」によって生まれるのは何だろう。
加害者と名指されることによる苦しみ、自分を加害者と定義する苦しみについて考えることが、被害者の苦しみに比べればという比較によって抑制され、時には禁止されてきたのではないだろうか。PC(ポリティカリーコレクトネス)的には当然のことかもしれない。何より、まったく責任のない被害者こそ、まず救済されなければならないからだ。加害者の内的な逡巡やら苦しみなど、被害者へのケアや説明責任に比べれば、どちらでもいい。何より先決なのが被害者救済なのであり、加害者に対しては法的な裁断によって、しかるべき処罰を下されることが第一義的なのだろう。
しかし、それは大きな欠落につながるのではないか。謝罪文を書いた際のあの苦労を考えると、加害者が「真に」加害を認めて、責任をとるためのプロセスを歩み始めるためにも、「苦しみの比較」を排さなければならないと思う。
鎮圧のための比較
つねづね私は、「苦しみ」の比較に意味はないと考えている。カウンセラーとして、時には有害だとさえ思う。Aさんの苦しみとBさんの苦しみを比べて、軽重を判断することなどできないのだ。
苦痛や痛みといった不快な感覚は、きわめて個別的なものである。近代科学はそれを数量化し、客観化することに邁進してきた。医療の発展は、症状の軽減は痛みの除去であるとして、さまざまな薬剤を開発してきた。鎮痛剤はその典型であり。苦しみの比較は、このような近代科学の発展によって生まれたのかもしれないが、現実的には、もっと複雑な背景があると思う。
多くの人たちは、苦しいとか痛いと言うと、「もっと苦しい人がいる」と批判された経験を持っていないだろうか。批判する人は、たいてい自分より力において優位な立場に立っていることが多い。もしくは「もっと苦しい人がいるでしょ」と説教することで、優位に立とうとする。苦痛や痛みを訴えた場合、それを抑圧するために、はっきり言えば黙らせるために、その比較は行われるのである。まとめれば次のようなセリフになる。
「苦しいなんて言うけど、見てごらんなさい、あなたよりもっと苦しい人がいっぱいいるでしょ。その人たちのことを思えば、あなたの苦しみなんて贅沢だ。いつまでもそんなに文句ばっかり言ってるなんて、わがままで甘えてるんだよ」
食べ吐きを繰り返している摂食障害の娘に対して、父親はこう説教する。
「世界には飢えて死ぬ人もいるんだ。北朝鮮の人たちを見てみろ。そんなに過食するなんてほんとに贅沢だ。どれだけ自分が恵まれてるか、よく考えてみなさい」
旧ジャニーズの性被害を訴える人たちに対して、表立っては語られないが、暗黙裡に考えられているのが次のようなことではないか。
「被害・被害ってうるさいな。何年前のことだと思ってるんだ。どうしてもっと早く訴えなかったのか。それに性被害って、それで死ぬわけじゃないでしょ。虐待で殺された子どもたちに比べれば、生きてるわけじゃないの。それに大人なんだしね、今になってしゃしゃり出てくるなんて、何か別の目的があるとしか思えないよ」
虐待で亡くなった子どもや北朝鮮で餓死寸前の人たちとの苦痛の比較が、目の前で苦しみを訴えるその人を否定し、鎮圧するために利用されることがよくわかる。
家族では、このような苦しみの比較は頻繁に起こっている。たいていは親から子に向けてである。子どもがころんで泣きわめくと、「そんなくらいで痛いと言うな」「痛くないでしょ」と言う親は珍しくない。子どもの感覚を否定するのだ。
これまでの人生を振り返って、あまりの理不尽さから親に初めて要求を突き付けた娘に対して母親はこう言う。
「誰のおかげで大きくなったと思ってるの」「大学に行けない人だっているのに、ありがたいと思いなさい」「五体満足に産んでもらって、骨折したときに入院もさせてもらったじゃない。従弟の○○ちゃんは片足が動かなくなっちゃったでしょ、それに比べたらどれくらい贅沢な悩みなのかわかるんじゃないの」
自粛の本体
「もっと苦しい人がいるのにあなたはこの程度のことで泣き言をいうのか」「それは甘えだ」「大げさだ」「我慢が足りない」という批判を言外に感じたのが、2011年の東日本大震災のあとである。首都圏を席巻したあの空気感を今でも思い出すことができる。新宿の交差点で赤信号を待っているあいだに、うしろの若い男女が「東北のことを思ってみろよ、贅沢じゃん」と話していた。振り向くと、男性は金髪にピアスで、手を組んでいる女性の髪は真紅だった。
居酒屋も心なしか照明を暗くして営業しており、「被災地のことを思えば酒盛りなんて不謹慎じゃないか」「飲んで騒いだりすると、文句言われるんじゃないか」という雰囲気が漂っていた。笑ったり楽しそうにすることが、もっと苦しんでいる被災地のことを思えば不謹慎であるという自粛感が、東京中を覆っていたように思う。昭和天皇の逝去の際、同じような空気が東京を覆った。誰が強制したのでもないのに、街には暗くて周囲から批判されないように怯える雰囲気が漂っていた。
上方比較と下方比較
比較には二つある。上方比較と下方比較である。
上方比較は、自分より優れたものと比べることだ。「自分はまだまだだ」「あんなふうになれたら」「どうして及ばないのだろう」といった感覚や思いは、上方比較によるものだ。その結果、劣等感やコンプレックスも生まれるだろうし、いっそうの努力をしよう、追いつくようにがんばろうというモチベーションも生まれる。上を見ればキリがないというのは、よく言われる例えだが、これも「上を見る」上方比較をやめさせようとするものだ。。
いっぽうで「下方比較」とは、「下を見る」比較である。自分よりもっと苦しいひとたち、自分より不幸なひとたちと比べて、自分のほうがマシだと思うのも下方比較だ。しかしもっともよく見られるのが、不満を収めるために、現状で満足させるために苦痛の表出を抑圧・鎮圧する比較である。
「Aさんより私のほうが幸せだ」「Bさんよりずっと幸せにならなければ」と思うのは上方比較だが、「もっと苦しい人がいるのだから苦しいなんて言っちゃいけない」「苦しいなんてわがままだ」のは下方比較である。
下方比較の残酷さ
自然発生的に下方比較が生まれるわけではなく、その多くは常識として強いられていく。日本の被害者有責論(されるほうにも問題がある、自己責任じゃないか)の背景には、性暴力やセクハラにまつわる根深い常識がある。それらが被害者にとっての二次加害になるのは言うまでもない。しかし「それがふつう」「そういうのが常識」と口にするのは、たいてい力のある側である。家族であれば、親から子どもへ、夫から妻へと「それが当たり前」として植え付けられていく。「それがふつうだ」という言葉ほど、強制力を持つものはない。それに反すれば「私は常識がない」「ふつうじゃない」ことを意味するからだ。
「あの人に比べればこんなことで苦しいとは言えない」「私が被害者なんて言えないんじゃないか」「これくらいで苦しいなんて言えない」「この程度で苦しいと思うのは、わがままではないか」「勘違いじゃないか」「自分の感じ方がヘンじゃないか」……。
こう書くとキリがないほど、下方比較によって抑えつけられ、自己否定感覚を植え付けられる人は多い。
たとえば、能登半島地震の被災者に対して、あの人たちのことを思うとこんな小さなことで不満を覚える自分が贅沢に思える、と語ることは、一見思いやりに満ちているように思えるが、裏側には「あの人と比べれば自分はましだ」という比較によるものだ。より不幸な人と比べることで、現状に甘んじる糧にするのである。
このように、下方比較には二つの残酷さが存在する。ひとつは自分より不幸な存在と比べて自分のほうがましだと思う残酷さであり、二つ目は苦痛や不満の訴えが「より不幸な人と比べればましなほうだ」「だから文句を言うな」という論法で「抑圧」「鎮圧」される残酷さである。つくづく日本は「下方比較」の国だと思う。
グループカウンセリングでの経験
こう思うようになったのは、長年のグループカウンセリングの経験をとおしてである。AC(アダルト・チルドレン)の女性たちのグループカウンセリング、DV被害女性のグループカウンセリングをもう20年以上実施している。いずれも被害者を対象とするグループだが、そこで決まって語られる言葉がある。
「私、自分のことをDV被害者って呼んでいいんでしょうか。」
「もっとひどい経験をした方がいるのに、私なんか被害者という資格がないのでは」
「自分のことをACと思っていいんでしょうか、もっと苦しい経験をした人がいるんじゃないかと思うんです。」
これらはほぼ定番と言ってもいい発言である。参加当初だけではない。2年ほど継続参加した女性が、「今でも自分のことをDV被害者って呼んでもいいか迷うんです。自分の勘違いじゃないかって、不安なんです」と語るのだ。
それらの言葉を聞きながら、「不幸の比較をしてはいけない」と強く思うようになった。それは何ものも生み出さないどころか、有害なのだと。グループで彼女たちに対しては、いつも次のように伝える。
「あなたの苦しみの感覚はあなただけのものであり、他人の苦しみと比較はできません。あなたが苦しかったことは被害だと思います。ご自分のことをDV被害者と名付けてもいいのではないでしょうか。」
そう言われて、涙ぐむ人もいる。彼女たちは、他者からそのように言ってほしいのだ。被害者であることを確認するために、被害者じゃないのではと語るのだ。自分の被害を承認する他者を、心から求めているのだ。
彼女たちの定番の発言から学んだのは、苦しみの比較は意味がないことに加え、自らの被害を認めるには、他者からの被害の承認が不可欠だということだった。
「ビクティム・ジャーニー」と呼びたい
昨年のジャニー喜多川による性暴力事件の表面化について、あえて今回は触れなかった。次回以降に追って詳しく書くつもりである。
今回述べたことは、セクハラ・性暴力の被害にとどまらず、あらゆる被害について考える際の基本的視点についてである。
まるで風見鶏のように、簡単に加害者・被害者と分別し、加害者を徹底批判することで正義の陣営=安全地帯に身を置くような人たちがとても増えている。社会の啓蒙が進んで、被害者への理解が深まったことの表れだという前向きの解釈もできるが、まだまだ油断はできないと思う。それほど早く日本の常識や「ふつう」の基準が変わるとは思えない。時々、そんな岩盤のような常識が不意に顔を出すことがある。用心しなければならない。
被害を受けた・自分の経験は性被害だとわずかでも感じたひとは、援助を受けてほしい。援助を受ける、相談できる機関はどこだろう。それは「医療機関」だろうか。保険診療の金額程度なら支払えると考えるひとは多いだろう。
しかし、残念ながら「医療機関」の保険診療の範囲では不十分というしかない。10分診療でそれが可能だろうか。あのような診察室の構造で、医師がPC画面を見ながら話された内容を打ち込んでいく姿を見ながら、果たして何が語れるだろう。もちろん医療機関に雇われた心理職が面接することもあるかもしれないが。
よく考えてみてほしい。性被害は病気ではない。もちろん一部の性暴力被害は、婦人科による治療が必要になるだろう。しかし被害からの回復(こう呼ぶしかない)は長期にわたり、さまざまな援助が必要になる。医療機関はそのなかのごく一部にしか過ぎないのだ。
苦しみ(痛み)は個人的なものであるとすれば、長期にわたりその人に伴走する存在こそ必要だ。ガン患者のたどる長いプロセスを「キャンサー・ジャーニー」と呼ぶという。それにならって、私は依存症の回復過程を勝手に「アディクション・ジャーニー」と呼ぶことにした。被害からの回復の道のりも、同じように長い。だから私は「ビクティム・ジャーニー」とそれを呼びたい。
グループの意味
被害者のたどるジャーニーは援助者と2人だけでは不十分だ。繰り返し述べてきたように、入口の段階ですでに大きな壁につきあたる。「被害者」と認めるまでの困難さや社会の常識による二次加害も大きいからだ。
その際に必要なのは、グループではないだろうか。性被害の自助グループはすでに首都圏では活動が定着している。私がカウンセラーとして痛感しているのは、同じ経験をした他者の存在がどれほど助けになるかである。DV被害者と親からの被害者=ACのグループカウンセリングを長年実施しながらそう思う。
苦しみを苦しみとして受け止めてもいい、これを被害と名付けてもいいという承認は、援助者からも受けとることができるが、同じ経験をもつグループメンバーによって毎回承認を得ることができるとすれば、それにまさるものはない。一対一の援助関係がジャーニーのコアな部分を形成すると信じたいが、当事者によって運営されるグループがあればそれだけで十分かもしれないとも思う。
長年のアディクション臨床の経験から、専門家によるグループと当事者による自助グループは併存できるし、どちらが効果があるかという比較は意味がないと思っている。大切なことは、当事者による自助グループに対して専門家が介入することはあってはならないし、越権行為だという点だ。
いずれにしても、一対一の援助関係に加えてグループは必須ではないかとさえ考えている。アディクション臨床の経験は、グループの果たす役割、グループ参加がもたらす効果についての確信を私に与えてくれたと思う。
「私だけではない」
「同じ経験をもつ人がこんなにいる」
「言葉にならないことをちゃんと我がこととして受け止めてくれる人がいる」
あまりにありふれた言葉だが、このような存在を「仲間」と呼ぶ。そして、援助者は決して仲間にはなれないことを肝に銘じたい。
(了)
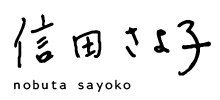 1946年生まれ。公認心理師・臨床心理士。お茶の水女子大学大学院修士課程修了。1995年に原宿カウンセリングセンター設立、現在は顧問。アルコール依存症、摂食障害、DV、子どもの虐待などに悩む本人や家族へのカウンセリングを行なってきた。『母が重くてたまらない』(春秋社)、『DVと虐待』(医学書院)、『加害者は変われるか?』(筑摩書房)、『家族と国家は共謀する』(KADOKAWA)、『アダルト・チルドレン』(学芸みらい社)、『家族と災厄』(生きのびるブックス)など、著書多数。
1946年生まれ。公認心理師・臨床心理士。お茶の水女子大学大学院修士課程修了。1995年に原宿カウンセリングセンター設立、現在は顧問。アルコール依存症、摂食障害、DV、子どもの虐待などに悩む本人や家族へのカウンセリングを行なってきた。『母が重くてたまらない』(春秋社)、『DVと虐待』(医学書院)、『加害者は変われるか?』(筑摩書房)、『家族と国家は共謀する』(KADOKAWA)、『アダルト・チルドレン』(学芸みらい社)、『家族と災厄』(生きのびるブックス)など、著書多数。