特権はマジョリティのもの?
近頃の社会学や社会運動に関わっている人たちの、あるいは哲学に関わっている人たちの間では、「特権」という言葉が用いられることが多くなっている。
辞書によれば、特権とは「特別の権利。ある身分・資格のある者だけがもっている権利」を意味する[1]。また、「貴族」のことは「一つの社会において、格段に高い政治的ないし法的な特権と栄誉をもつことを社会的かつ伝統的に承認された集団。」と定義されていた[2]。通常の用法では、特権とは貴族のように特別な地位を占める集団が保持しており、そして平民たちには与えられていない権利のことを示している。人数だけを見れば、特権を持っていない平民たちのほうが多数派であり、特権を持っている貴族たちのほうが少数派であることは、単純だが重要なポイントだ。特権とは、一握りの特別な人たちにしか与えられていない権利であるからこそ、特権なのである。
しかし、近頃に問題視されている「特権」とは、貴族のような少数派ではなく、ある社会における「マジョリティ」が持つものだとされているのだ。これには、社会学などでは、人数のうえでは必ずしも多数派でなかったとしてもある社会でより多くの権力を持っていたりより有利な位置を占めていたりする属性やグループのことが「マジョリティ」と呼称されることが関係している。
具体的な例を挙げると、アメリカでは「白人特権」(White Privilege)などが問題となっている。日本でとくに話題に上がるのは「男性特権」(Male Privilege)だ。本稿でも、主に男性特権について取り上げながら、特権という言葉がなにを意味してどのような効果をもたらしているかについて考察してみよう。
ニュートラルな状態を特権と呼ぶ不思議
男性が持っていて女性が持っていない特権とはなにか?
近年のニュースからは「入学試験での優位」を想起する人が多いかもしれない。たとえば、東京の都立高校や近畿の私立中学では「男女別定員制度」が設定されており、男子と女子は同じ試験を受けながらも、女子は女子の人数の枠内で他の女子たちと競い男子は男子の人数の枠内で他の男子たちと競うことになる。2021年度の都立高校入試では、男女合同定員制であれば合格していたはずの女子が約700人も不合格になっていたことが判明した。つまり、女子間の競争には負けたが、入学した男子たちよりかは高い点数を取っていた女子たちが失格させられていたのだ。一般的に中学入試や高校入試では女子のほうが高い点数を取れることが多いので、男女別定員制度は女子に競い負ける男子を優遇する制度であるといえる。また、東大をはじめとする国立大学や難関私立大学への合格者を多数輩出している進学校は、そもそも女子を入学させない男子校であることも多い。
さらに、2018年には東京医科大学の一般入試で女子受験者の得点を一律に減点して、合格者数が抑えられていたことが判明した(同様の事態は他の大学の医学部の入試でも起こっていると考えられる)[3]。問題が発覚したことを受けて女性の減点が廃止されたであろう2022年には日本で初めて女性が男性を医学部の合格者数で上回ったという事実は、2021年以前までは多くの男性受験生が下駄を履かされてきたことを示している。中学校受験から医学部受験に至るまで、試験で同じ点数を取っても男性は入学できて女性は入学できないことがあるという事態については、男性が特権を持っていると表現しても的外れではなさそうだ。
……ところが、近頃における「特権」とは、「入学試験での優位」のような積極的なものではなく、もっと消極的で間接的なものを表す言葉として使われているのだ。
たとえば、男性は女性に比べて、性に関する暴力や攻撃の被害を受けづらい。痴漢や強姦などの性的な暴力は、男性も受けることがあるとはいえ、実際の被害者の数は女性のほうがずっと多いことは明らかだ(そして、加害者の数も、男性のほうがずっと多い)。職場や学校におけるセクシュアル・ハラスメントに関しても、最近では男性の被害も注目されるようになってきたが、数や可能性としてはやはり女性のほうが被害に遭いやすいだろう。したがって、男性よりも女性のほうが性的な被害を受ける経験が多かったり、被害のリスクが高い環境に生きていたりする。
満員電車に乗るときには、多くの女性は痴漢の被害にあう可能性を想定して警戒したり不安になったりしているだろう。一方で、多くの男性は、電車に乗るときに警戒したり不安を抱いたりすることなく生きている。夜道を歩くときやクラブなどに行くとき、初対面の異性と会うときや異性の知人の部屋を訪問するときなどにも、女性はその身体的な性別のゆえに被害を受けるリスクに晒されていてそれによる精神的な負担も生じさせられているが、男性はそうではない。
……このこと自体は以前から言われてきたことであるし、わざわざ否定する人も少ないだろう。性暴力という問題に関して、一般的に、女性は男性よりも不利益を被っている。男性に比べて、より多くの女性が被害者になりやすいし、なっている。あるいは、これは「差別」という言葉の定義によっても変わってくるだろうが、性暴力という問題に関して女性は被差別者である、つまり差別されていると表現することもできるかもしれない。
ポイントは、自然に発想すれば、性暴力という問題における男女間の状況の違いを表現するときには、女性側に起こっているネガティブな状態のほうが注目されてそれが強調されるということだ。そもそもの前提として、女性にせよ男性にせよ、性暴力なんて受けないほうが望ましい。女性にとっても男性にとっても正常でニュートラルな状態とは、性暴力を受けていなかったり性暴力のリスクにさらされていなかったりする状態のことだ。通常、ニュートラルな状態がわざわざ注目されることはなく、名前が付けられることもない。何らかのモノや事態についてわたしたちが思考するときには、異常であるほうに注目することがデフォルトだ。
ところが、社会学や社会運動などでは、ネガティブな状態ではなくニュートラルな状態のほうを特徴付けるために特権という言葉が用いられる。性暴力という問題に関しては、女性が被害にあいやすいことではなく、男性が被害にあいにくいことのほうが強調される。つまり、性暴力の被害にあう可能性が低いことや、性暴力について恒常的に警戒せずとも生きていられることが、「男性特権」だと表現されるのである。
生得的な属性までも特権と言われる
性暴力のほかにも、「男性特権」として表現される事象は様々に存在する。たとえば、著述家の清田隆之は、男性は結婚したときに苗字を変更するという選択肢について考えなくて済まずに生きられることも男性特権であると指摘している[4]。社会の慣習や規範のために日本ではほとんどの場合に夫ではなく妻のほうが姓を変えているから、女性は若いうちからいつか結婚して姓を変える未来を想起させられながら生きているが、男性はそうではない。
このように、ネガティブな事態ではなくニュートラルな事態のほうを特徴付けるものとしての「特権」という言葉が広まるにつれて、「マジョリティとは自分の特権に気づかなくても生きていける人たちのことだ」といった物言いも盛んになされるようになった。
また、批評家の杉田俊介は、特権という言葉について以下のように説明している。
マジョリティが特権集団であるとは、その全員が金持ちだったり幸福だったりするという意味ではなく、マジョリティはただ単に存在しているだけでさまざまな一定の利益を得ているということであり、多種多様なマイノリティ集団のことを抑圧し、不利益を強いているということです。
ここで、抑圧と差別を区別しましょう。差別とは、何らかのアクティヴな行動のことです。抑圧とは、構造的に他者を抑圧し続けることです。たとえ言葉や行動によって差別しなくても、あるいは道徳的な善意を持っている場合ですら、マジョリティ集団が存在すること、生活を維持することそのものが構造的な抑圧を維持し、強化していることになります。
たとえば女性が男性に対してステレオタイプ的な見方をしたり、同性愛者が異性愛者に偏見を持ったり、在日コリアンが日本人を嫌悪したりすることはあるでしょう。しかし、それらの偏見や嫌悪は、ここでいう意味での構造的な「抑圧」ではありません。女性やマイノリティの中にも偏見やレッテルを拡散する人々がいる、という事実は、現在の社会には抑圧的な構造がある、という現実を相対化したり、打ち消したりするものではありません。
そもそも、マイノリティが日々自分たちのマイノリティ性に直面せざるをえないのに対し、マジョリティは日常生活のほとんどの場面で自分たちがマジョリティであるとことさら意識せずにすみます。自覚し、意識しなくても、生活を送れるのです。そのこと自体が最大の特権であり、優位性なのです。それはしばしば「水の中の魚」にたとえられます。水の中にいることが当たり前であるならば、自分たちが水の中に住んでいること、自分の周りに水が存在することに気づくことも難しいのです。(杉田、p.40-p.42)[5]
特権に関する議論に初めて触れる人であれば、「マジョリティ集団が存在することと生活を維持することそのものが構造的な抑圧を維持し、強化していること」というあたりにギョッとなるかもしれない。
これが「差別」に関する議論であれば、話は簡単だ。誰かを直接的に傷付けたり誰かに不利益を被らせたりする行動に対して「差別的だ」と批判する主張については、多くの人が賛同するだろう。「気付いていないかもしれないけれど、実はこういった理由から、あなたの行為は特定の属性の人に対する差別になっているんですよ」と言われた場合にも、そこで説明される理由に妥当性があるなら、多くの人は納得して、「これからはそういう行為を止めたり控えたりしよう」と考えるようになるはずだ(意固地な人や、自覚的な差別主義者である人ならそうもいかないだろうが)。行為に関する議論はわかりやすいし、解決や改善をしやすい。
しかし、特権に関する議論では、差別的な行為をまったくしない人であっても、マイノリティに対する抑圧構造が存在する社会のなかでマジョリティとして生きているだけで、抑圧に加担することになる。ここでは「構造」と同時に生得的な「属性」についても語られていることも重要だ。あなたが男性であったり、(アメリカやヨーロッパで)白人であったり(日本で)日本人であったりするなら、それだけで、あなたは構造的な抑圧を維持して強化していることになる。しかし、原則として、性別や人種や国籍などの属性を変えることはできない。差別的な行動や思考については問題を指摘されたときに反省して改めることができるのに対して、特権を指摘されたときに自分に改められることはないのだ。そのため、「特権に関する議論は、マジョリティとして生まれ落ちることを“原罪”であるかのように論じるものだ」といった批判もなされてきた。
また、特権について指摘する議論では、「特権を指摘された人たちの反応」に関する議論もセットになっていることが多い。たとえば、アメリカの社会学者ロビン・ディアンジェロの著書『ホワイト・フラジリティ──私たちはなぜレイシズムに向き合えないのか?』では、白人特権を指摘された白人が「特権なんてない」「不当な言いがかりだ」などと反応することが「ホワイト・フラジリティ(白人の心の脆さ)」と表現されているのだ。杉田も、著書のなかで特権とは「制度論的な事実」であると表現している。特権が存在するのは事実であるとされるからこそ、それを指摘されたときに否定するほうが間違っていることになって、否認する人には「フラジリティ」というラベルが貼られることになる。
だが、わたしには、「特権に関する議論は人に原罪を背負わせるものだ」という批判にも一理あるように思える。
多くの人は、「あなたには特権がある」と指摘されたとき、それを単なる事実の指摘だとは考えずに、自分に対する非難や批判として受け止めるはずだ。
実際のところ、特権に関する議論では単なる事実の問題に留まらず道徳や責任の問題についても論じられていることが大半である。男性が男性特権について語ることとは他の男性たちに「君たちもわたしと一緒に反省しましょう」と呼びかけることであり、女性が男性特権について指摘することとは「お前たちはわたしたちに対して責任があるのだぞ」と追求することである。
以下では、特権という単語にはどのような意味が含まれているのか、特権という単語はどのように機能するのかについて、掘り下げて考えてみよう。
「特権/抑圧」と「搾取/被搾取」の構造の違い
特権という概念の特徴のひとつは、それが引き算によって導出されることだ。
まず、社会のなかに「抑圧を受けている集団」が存在することが前提となり、社会からその集団を引いた残りの人々が「特権を持つ集団」ということにされる。
「特権/抑圧」の構造は、「搾取/被搾取」など、他の社会問題や道徳的な問題に関する構図と似たようなものに思えるかもしれない。
しかし、搾取とは、搾取者が利得を得るために非搾取者の利得を不当に侵害することだ。搾取とは目的を持って行われる行為である。「資本家による労働者の搾取」といった狭い意味での搾取だけでなく、「グローバル資本主義における先進国の消費者の、発展途上国の労働者に対する搾取」といった広い意味での搾取にも、このことは当てはまる。たとえばアフリカの児童労働によって収穫されたカカオを使ったチョコレートとそうでないチョコレートがスーパーに並んでいて、安いからという理由で消費者が前者のチョコレートを購入することも、搾取だと言うことはできそうだ。消費者は「チョコレートを安価に食べたい」という目的のために、それを選択して購入するという行為をしているからである。
目的を持って行われた行為が不当であったり不道徳であったりしたときに、その行為をした人には道徳的な責任があると見なすことは、ごく自然な発想だろう。したがって、搾取の問題について資本家や先進国の消費者を批判するのはもっともなことである。
一方で、特権に関する議論では、問題となるのは行為ではない。マジョリティが「抑圧を受けないこと」や「マジョリティであると意識せずに生きること」は、行為ではなく状態である。状態に目的はない。さらにいえば、それらの状態は、「抑圧を受けずに生きるぞ」とか「マジョリティであることを意識せずに生きていくぞ」とかいった目的に基づく行為の結果としてもたらされたものですらない。それらは、通常の議論では注目されないようなニュートラルな状態であり、世の中から「抑圧を受けている状態」を引き算した結果に名前が付けて特徴付けられたものでしかないからだ。
これだけを見れば、特権という単語は、世の中の状態についてトリッキーなかたちで「記述」する言葉であるようにも思える。「速記的表現」とも言えるだろう。「抑圧の構造があり、そのなかでマイノリティが不利益を被ったりマイノリティ性を自覚させられたりしながら生きているのに比して、マジョリティはそうでないこと」と毎回表現するのはまだるっこしいから、この長い一文を「特権」と言い換えているだけ、ということである。
しかし、先述したように、特権という言葉が使われるときにはほぼ必ず批判や非難が伴う。だれかに「あなたには男性特権がある」と言われたときに、「この人はわたしを責めているわけじゃなくて、ただ世の中の状態について記述しているだけなのだな」と受け取ることは的外れである場合が多い。特権という単語自体は記述的なものであったとしても、それが使われる文脈は規範的なものだ。
心理学と倫理学の両方を研究するジョシュア・グリーンは、「権利」という言葉について、以下のような指摘をしている。
……道徳家として論争しているときの私たちは、主観的感情を客観的事実の認識として提示できるために、権利と義務の言い回しが大好きだ。私たちが、権利と義務の言い回しを好むのは、主観的感情が、「そこに」あるものの心像であるかのように(実際にはそうでなくても)しばしば感じられるからだ。
……(中略)……
ある人にある権利があると言うとき、あなたは、その人に指が一〇本あるという事実のように、その人が所有するものについての客観的事実を述べているように見える。(グリーン、p.404-p.405)[6]
わたしが思うに、「特権」という単語にも、「権利」という単語と似たような性質が存在する。
たとえば、男性特権という言葉は「女性が受けている抑圧や被っている不利益を、男性は受けたり被ったりしていないこと」という状態を指すものであった。しかし、「男性特権」という名詞は、ことではなくモノを指しているかのように聞こえる。個々の男性たちが、特権を所有しているイメージが想起されるのだ。
ただし、権利が正当なものであるのとは異なり、特権とは不当なものである。男性たちが特権を所有しているとすれば、それは盗品を所有しているのと同じように不当なことだ。だから、「わたしには権利がある」という主張が事実の記述ではなく「わたしのモノに手を出すな」という要求として機能するのと同じように、「あなたには特権がある」という主張は事実の記述ではなく「あなたは不当にモノを所有しているのだ」という非難として機能する。
さらに、男性特権である場合には女性から盗んだモノであるかのような、白人特権である場合には黒人から盗んだモノであるかのようなイメージも伴うだろう。ある人がモノを不当に所有しているとすれば、そのモノを不当に奪われた人もいるはずだから。結果として、特権という概念自体は「抑圧」に関するものであったはずなのに、「搾取」に関するものであるかのようにイメージが滑っていく。そして、先述したとおり、搾取のような行為に対しては責任を問うことができる。だから、「あなたには特権がある」という主張を認めてしまうことは、女性や黒人に対して自分が行ったことにされる搾取についての責任を取らされることにまでつながりかねない。
ふつう、身に覚えのないことで非難をされたり責任を追求されたりした人は、その非難や追求に対して反発するものだ。自分はなにも不当に所有しているつもりはないのに、そうであるかのように非難されて、その責任まで追求されそうになったら、まず真っ先に出てくる反応は「それは違う、不当な言いがかりだ」だろう。……しかし、特権という言葉を使う人たちは、その自然な反応に「フラジリティ」などのラベルを貼る。彼や彼女は、特権を指摘することは実質的に非難や責任の追求として機能していることをおそらくは自覚しながらも、表向きには事実を記述する主張をしているつもりでいるからだ。
わたしの見立てでは、特権という言葉が反発を受ける背景には、上述したような構図がある。この見立てが正しいなら、特権に関する議論が拒否反応を招いている原因は、特権を指摘されている側ではなく指摘している側のほうにあるだろう。
自らのマイノリティ性の課題に向き合う?
心理学者の出口真紀子は、インタビューのなかで、以下のように答えている。
特権に無自覚だったマジョリティー側の人が、自分の世界観や信念を否定されるような情報にぶつかると、抵抗を示すことがあります。女性差別が語られる場で、男性が「差別されているのは自分の方だ」と主張するようなケースです。
抵抗の背景には、その人の抑圧体験があります。マイノリティー性に伴う問題で苦しんでいるときに、「あなたには特権がある」と言われても受け入れられないのも理解できます。自らのマイノリティー性の課題に向き合い、ケアをしない限り、自分の権力を弱者に行使し、加害行為に発展してしまう可能性もあります。男性の敵は女性ではなく、家父長制です。男性が生きづらさを感じているのであれば、女性に怒りをぶつけるのではなく、家父長制を形成している社会に怒りの矛先を変える必要があります[7]。
このような主張は、出口に限らず、特権について論じている人の多くが行なっているものだ。つまり、「男性特権を指摘されて抵抗を感じても、男性特権の存在を否定するのではなく、自分が持っている他の属性やマイノリティ性に起因する抑圧の経験に思いを馳せることで、女性の受けている抑圧のことも連想して共感することができる」といった議論である。
とはいえ、日本に生まれ育って日本の国籍を持っている男性のなかで、自覚できるほどの「マイノリティ性」を持っている人はなかなか少ないかもしれない。その点に関しては、ある意味、わたしは恵まれている。在日アメリカ人として日本に生まれて日本で育った経験のなかに、多かれ少なかれマイノリティ性が伴っていることは明白だから。というわけで、ここからは視点を変えて、わたし自身が経験した「抑圧」をテコにしながら、特権の問題について考えてみよう。
わたしが日常でマイノリティ性を感じるのは、なんといっても居酒屋やバーに行ったときだ(最近はコロナ禍で行く機会も少なくなったけれど)。白人の見た目で日本語が流暢に喋れる人は、2020年代の東京であってもまだ珍しい。そのために、とくに酔っ払いが多くいるような場所に行くときには、話しかけられたり絡まれたりすることを警戒しなければならない。だいたいは日本に滞在している期間とか日本語が上手に喋れる理由を教えて相手がそれに対して感想やコメントを言えば会話は終わるのだが、それで済まずに執拗に質問され続けたり不愉快なことを言われたりするときもある。バーは人との交流を期待して行く側面もあるから多少は我慢すべきだとしても、食事を楽しみにして居酒屋に入ったときにしたくもない会話をさせられることは、かなりキツい。店に入った瞬間に客の目つきや顔つきから酔っ払い具合や性格の雰囲気を察知して、「絡まれそうだ」と思ったらすぐに退散することもある。……おそらく、大多数の日本人男性は、飲みに行く店を選ぶときに自分が他の客から絡まれたり不愉快なことを言われたりするリスクを想定する必要がない。一方で、女性の場合には日々そのようなリスクを警戒しているであろうことは察しが付く。だから、この点に関しては、たしかにわたしは女性の感じている「抑圧」に共感することができる。
また、日本では賃貸物件の多くが「外国人お断り」であり、引っ越しをする際に部屋の選択肢が非常に限定されることも、わたしが感じたことのある抑圧だ。不動産業界による「差別」だと言ってもいいかもしれない。「いいな」と思った部屋がことごとく外国人お断りであり、しかもその情報がネットでも公開されていないために、選択肢が狭まるだけでなく部屋探しにかかる手間や時間もかなり増えてしまう。とくにリベラルで開放的なイメージのある高円寺で部屋を探していたときには、ほとんど全ての物件が外国人だからという理由で断られてしまい、面食らったものだ。……ちなみに、「外国人でもOKだが女性限定」ということで入居できなかった部屋もあることは言っておいていいだろう。賃貸物件の選択肢という点では、女性のほうがむしろ有利だと言える。
選挙の時期に友人たちがどこに投票するか話しあっているのを聞くたびに、自分には参政権がないことを思い知らされることも、抑圧と言えるかもしれない。永住権は持っているが日本国籍は持っていないので、どこに投票することもできないのだ。ヨーロッパの一部やニューヨーク州では外国人でも地方参政権が認められているらしいので、それくらいなら日本でもやってほしいものだと思う。……ただし、頭では参政権の重要さはわかっていても、気持ちとしては「寂しいな」「あったらいいな」くらいで、そこまで強く欲しているわけではないことも、打ち明けておかねばならない。自分の一票が加わった程度で選挙の結果が目に見えて変わるわけではないこともわかっているからだ。
なお、わたしが在日アメリカ人で白人であることを原因に様々な不利益を被っていたり抑圧を感じたりしているとしても、日本国内にいる他の国籍や人種の人たちはさらに多大な不利益や抑圧を受けていることには留意しなければならない。日本語を流暢に喋れるアフリカ系の人が居酒屋やバーで絡まれたり不愉快なことを言われたりする可能性は、白人よりもさらに高くなるだろう。不動産業者から部屋を紹介されるときに、「アジアの人ならダメだけど、欧米の人なら借りられるよ」と言われることもあった。歴史的な経緯から、参政権は在日コリアンの人々にとってとりわけ重要な権利であることも理解している。
特権を指摘しても問題の解決には結びつかない
さて、「絡まれる心配なく居酒屋に入れること」や「国籍を理由にして賃貸物件を断られないこと」や「参政権を持っていること」は、「日本人特権」になるのだろうか?
これまでに論じてきた「特権」の定義からすると、そういうことになるはずだ。マイノリティであるだれか(わたし)が不利益を被ったり「抑圧」を感じたりしているときには、それらの不利益や抑圧から逃れられている人は特権を持っているということになるのだから。……だけれど、居住の自由に関する権利や参政権を特権と呼ぶことは、馬鹿らしいレトリックでしかないように思える。それらは特権ではなく人権だ。もちろん、わたしのような外国人にもそれらの人権が制度的に保証されたとすれば有り難いことであるが、すでに日本人にはそれらの人権を保証されていることを特権呼ばわりするのは不毛である。
また、どこかの日本人男性が居酒屋に入るたびに「おれが外国人や女性のように絡まれる心配がなく居酒屋で飲めることは特権なのだな」と思いを馳せて罪悪感を抱いていたとしても、こちらとしてはなんの得にもならない。大切なのはわたしが絡まれることなく酒を飲めることであり、だれかに特権を自覚してもらうことではないのだ。
以上のように、自分自身のマイノリティ性に向き合って考えてみると、「特権」(や「構造」)という発想に基づく議論の役に立たなさや不毛さがさらに際立ってしまう。抽象的で曖昧な構造についてあれこれ考えて、だれかを非難することやだれかに罪悪感を抱いてもらうことよりも、個別の問題に目を向けてその問題の対処法を考えるほうがずっと生産的だ。
また、どの問題についても、それを解決することを難しくさせている理由があることから目を逸らしてはいけない。国民国家という制度の存在意義を考慮すれば、外国人の参政権には多かれ少なかれ制限が必要かもしれない。わたしには居住の自由に関する権利があるとしても、家主や不動産業者のほうにも契約の自由に関する権利がある。酔っ払いが人に絡むことを抑止するのはそもそも困難だ。これらの理由が存在するからといって、問題に向き合わないことが正当化されるわけでもないし、問題に対処することが不可能になるわけでもない。ただ、どんな問題であっても、それに対して実践的に向きあうためには道徳的なお題目や政治的なスローガン以上のものが必要になるということだ。
はっきりしているのは、わたし以外のだれかの特権をあげつらったところで、わたしが直面する問題はなにひとつ解決しないということである。
不毛な争いをもたらすだけ
なにをするにせよ、反発なんて、あるよりないほうがいい。女性やその他のマイノリティがこの社会の構造のなかで抑圧を受けているとすれば、その構造は変えられるべきだろう。だが、そのために、男性やマジョリティの反発を呼び起こす言葉をわざわざ使う必要があるとは限らない。
問題について指摘する側の人たちが「特権」という概念を好んでいる理由はいくつか考えられる。
まず、ネガティブな状態に注目する通常の発想からニュートラルな状態に注目する特殊な発想であること自体が、レトリカルで知的で気が利いていて、格好いい。一部の人は、「発想の転換」や「主客の転倒」という営み自体に魅力を感じるものだ。
また、表面上、男性特権などを指摘することには、「自分はこの問題には関係がない」と思っていた人に当事者意識を抱かせて問題に引き込むことができる、という効果が期待できるように思える。……しかし、これまでに説明してきた通り、多くの人に対しては特権を指摘することはむしろ逆効果だ。実際のところ、たとえば男性特権を指摘されて素直に受け入れられる男性とは、指摘される以前からジェンダー論やフェミニズムに親和的であって女性の直面している問題について関心や責任感を抱いているタイプの男性であるだろう。無知な人に問題について気付かせるというよりも、すでに抱かれている問題意識を再確認するために用いられているのである。
特権という言葉を広めるにしても、世間の人たちが自分たちの思う通りにこの言葉を使ってくれると期待してはいけない。
学問や社会運動に関わる人たちは、自分たちが使っている「抑圧」や「構造」や「権力」や「マジョリティ」といった言葉が特定の思想や理論を前提としていることを、しばしば忘れてしまいがちだ。他の人たちが自分たちと同じ目で世界を見ているとは限らない。SNSを検索してみれば、多くの男性が「女性特権」について語っていることが見てとれる。意趣返しや皮肉、嫌がらせとしてその言葉を使っている人もいるだろうが、なかには女性特権が実在していると本気で考えている人もいるだろう。彼らのなかには、男性ではなく女性のほうに権力があり、女性のほうがマジョリティであって、男性は構造的に抑圧されているとする理論や思想を構築している人もいるはずだ。
また、男性特権という言葉すらも、トランスジェンダー女性の人々に対して悪意や差別をぶつける文脈で用いられている場合があることを失念してはならない。
特権というレトリックが「ほんとうに抑圧されているのはどちらであり、ほんとうに権力を持っていてマジョリティであるのはどちらか」ということをめぐる不毛な争いをもたらすのは、火を見るよりも明らかだ。
この事態を避けるためには、そもそも特権なんて指摘しなければよい。
ネガティブな状態ではなくニュートラルな状態のほうをわざわざ特徴付けたり、発想を転換したり主客を転倒させたりする必要なんてない。様々な場面で女性が男性よりも不利益を被っていて、差別されていて、被害者であるという事実を、そのまま論じればよいのだ。そして、その事実が「不正義」や「不平等」「不公正」であることを論じて、改善されるべきだと主張すればよいのである。
ただし、個々の男性には事態の改善に協力することについての積極的な義務か消極的な義務が存在するかもしれないし、存在しないかもしれない。義務がなかったとしても、善行として事態の改善に協力することを呼びかけることができるかもしれない。いずれにせよ、ある事態に関してだれにどのような責任が存在するかというのは、かなり難しい問題だ。事実や状態について記述することとは違い、だれかの責任を問うこととは規範的な主張であり、それを正当化するためには段階をふまえながら多くの条件をクリアしなければならない。本来なら、倫理学や政治学などの規範論に基づきながら、慎重な議論を行うことが必要とされるはずである。それは、「特権」や「抑圧の構造」を指摘してお手軽に済ませられるような問題ではないのだ。


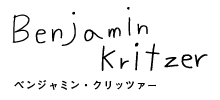 1989年生まれ。批評家。立命館大学文学部英米文学専攻卒業(学士)、同志社大学グローバル・スタディーズ研究科卒業(修士)。
1989年生まれ。批評家。立命館大学文学部英米文学専攻卒業(学士)、同志社大学グローバル・スタディーズ研究科卒業(修士)。