日本人で文学好きの母と、瞬間湯沸かし器的にキレるセネガル人の父の間に生まれた亜和(愛称アワヨンベ)。祖父母、弟とさらにキャラの立つ家族に囲まれて、ときにさらされる世間の奇異の目にも負けず懸命に生きる毎日。そんなアワヨンベ一家の日常を綴るハートフルエッセイ。アワヨンベ、ほんとに大丈夫?
カラフルトマトのカプレーゼ。お客さまのテーブルまで持って行って、料理名を言おうとした私の声を、大きな低い声が遮った。
「あんた、日本人じゃないだろ。どこから来たんだ?」
私は、言いかけた口をいちど閉じ、それからまた笑顔を作り直してから「ハーフですよ」と答えた。名刺を差し出すと、予想だにしていなかったであろう漢字の羅列を見たその人は「えぇ。顔に合わないなあ。別の名前が良いよ。キャサリンとか!」とニコニコしながら言った。
不思議なことに、こんなふうなやりとりは日によって連続して起きることがある。今日は少しファンデーションの色が濃いからだろうか。それとも、店の照明がいつもより暗いのだろうか。
いちどテーブルから離れて、人数分のお皿にカプレーゼを取り分ける。大皿の上には珍しい色の小さなトマトが、モッツァレラチーズのあいだを縫ってコロコロと転がり回っていた。あか、きいろ、きみどり、深いあか。それぞれ味が違うみたいだ。それぞれが均等に行き渡るように注意深く分配する。このトマトたちはみんな色が違う。つまり「みんなと違う」トマトはここにはいない。取り分けられた小皿の世界の上で、トマトたちは「みんなちがってみんないい」を体現していた。トマトの断面が幸福に満ちた笑顔に見えてくる。この世界がカプレーゼなのだとしたら、私は赤いトマトばかりの中に1粒だけ放り込まれた黄色いトマトだった。トマトたちは私を見上げている。
「カラフルトマトめ。いいなあ、いろんな色がいて。仲間にいれてよ」と、ひとりでブツブツ呟きながら作業をする私を、店長が遠くのほうから不思議そうに見つめていた。
週末、久しぶりにママと一緒に夜ご飯を食べていたとき、初めて会った人に「脚が長くて同じ人間とは思えない!隣に立ちたくない!」と言われたことを話した。ママは笑いながら言った。
「それ、アワが幼稚園のときにも似たようなこと言われた。’’うちの子の日本人体型が目立つからアワちゃんを隣に立たせないで〜”って」
「なにそれ。かわいそう、私」
当然だけど、脚は自分の身体についているものなので、私自身の視点ではその長さを他人と比較する機会はほとんどない。常々思う。隣に立ちたいのか立ちたくないのか、どっちなんだ、と。数年前にジムに入会したときなんて、大浴場の脱衣場で服を脱ぐやいなやマダムたちが私の周りを取り囲み、自分たちとの「脚の長さ比べ大会」が始まった。私は恥ずかしいような照れるような気持ちで、全裸のまま観光地の等身大パネルのようにジッとしていた。湯船に浸かるとお話好きのマダムがひっきりなしに話しかけてきて、黙浴を推奨されていたこの時期は、私を含めてたびたびスタッフから怒られてしまった。学校集会の、生徒たちの話し声の中で校長先生の怒りをいち早く察知していたタイプの私は、しばしば黙浴とお喋りの楽しさのあいだで苦しみ、結局半年ほどでジムを退会した。
私は常に目立っている。目立ちたくないときでさえ、知人は遠くからでも私を発見する。一時期探偵に憧れて求人を探していたが、当時のバイト先の店長に「無理に決まってるだろ。お前いちばん向いてないぞ」と言われて諦めた。ときどき目立ちたいときもあって、そういうときは張り切った服と化粧をして胸を張って歩く。それでも、やはり視線とは体力を消耗するもので、毎日胸を張ってツカツカと歩くことはできない。それでも、私の身体は縮んではくれないのだった。
私の出生体重は1720グラム。予定日の2ヶ月前に帝王切開で生まれた私は、伯父に言わせればパイナップル程度の大きさだったという。生まれた日は母の誕生日でもあったので、私たちは全く同時に針を振る2つのメトロノームのように歳をとっていくことになった。肺胞が潰れていたらしい生まれたての私は、すぐに鼻から管を通されて透明な小さな箱に入れられ、無事に育つかどうか、家族を大いに心配させたらしい。その頃の写真を見ると、枯れ木のような痩せこけた小さな赤ん坊が「あーあ。生まれちゃった。」といったような表情で身体をくねらせて眠っている。箱の外から入ってきたパパの黒くて大きな手が、私の頬を指で撫でていた。私の現在の身長は168センチ。両親のAとBをきっちり分けたAB型。体重は50キロ弱で、食べても食べなくても、大して増えも減りもしない。風邪も滅多にひかない健康体だ。両親の身長を考えればもっと背が高くなってもおかしくなかったのだが、出生児の発育不足の影響なのか、それとも中学生のときに自ら必死になって脳天を押さえつけ続けた成果なのか、私の身長はここで止まった。それでもこの国で「かわいい女の子」として生きていくうえで、このデカさはギリギリアウトである。
蜘蛛のように長い指と、深い夜に似た真っ黒の瞳。縮毛矯正で伸ばした髪。光を当てればくすんだ金色にも見える褐色の肌。小松菜奈に憧れて彫った顔のホクロ。左腕には鱗のような広い傷跡がついている。いつできたのかはわからない。ママは生まれつきだと言った。これが外から見える私の全部である。
自分の家族と容姿が周りと比べて特殊だと言うことは「あいうえお」を覚える前から察知していた。おそらく途方もなく広いであろうこの世界で、どうして私がこの手札を渡されてしまったのか。幼稚園の送り迎えの車窓から、まだ言葉をほとんど持たないなりに思考を巡らせていた記憶がある。その確率をもっと別のことに使ってほしかった。これはよく考えなければ苦労することになるぞ、とママが結んでくれたお団子頭を弄くりながら考えた。私のぐるぐる思考はおそらくこのときから癖づいていて、マッサージ屋にいけば施術師に憐れまれるほど、私の頭は常に凝り固まっている。ママは美人だ、他の子のママと比べて若いみたい。おばあちゃんはうるさい。おじいちゃんは甘やかしてくれそうだ。パパは、わからない。大きくてまっくろ。よくわからない……。
私のパパ、周りのパパとぜんぜん違う。5歳くらいの頃にいちど、パパの友達の家に遊びにいったことがある。家の中は、パパの体からするのと同じような、乾いた砂とスパイスの匂いがした。ソファーに座らされて、女の人が私の髪をライターの火で炙りながら細かく細かく編み込んだ。翌日から私は、ひまわり色のかわいい園服にピッチリとしたコーンロウで登園することになった。髪はピンクや水色のゴムで縛られていて、先生やママたちには大好評だった。好きな男の子にも「いいじゃん」と言ってもらい、痛かったけど頑張ってよかったなと思った。髪を編みおえた後で食べさせられた熱いヨーグルトのようなものはなんだったんだろう。あんまりおいしくなかったな。
きっとパパが周りと違うから、私も周りと違うんだ。パパはたまにどこかに電話をかけたり、パパにも電話がかかってきたりして、その電話の向こうの誰かと話すとき、パパは私が普段聞いている言葉と全く違う言葉で話した。大きな声で早口で捲し立てるように話すから「どうしていつも怒っているんだろう?」と不思議に思った。なんだか私も怒られているような気がして、電話が始まると、私は音を立てないように小さく縮こまった。パパはなんの仕事をしているんだろう。パパの名前は?パパは一体、どこからきたの?
パパから譲り受けた「周りと違う」というコンプレックスを、私は今でも長いブランケットのように引きずって歩いている。大人になっていく過程で、私はそれなりに恋をした。それなりに、とまるで互いに思い思われていたかのように上品には言ったが、大人しくて友達も少ない「陰キャ」ゆえに、人気者の男子に机から落ちた消しゴムを拾ってもらっただけで好きになったりしていた。中学生の頃には、3年間ほとんど話したことがなかった男子に卒業式前日に突然メールで告白し、案の定撃沈して静まり返った夜の街を泣きながら徘徊するという奇行もやってのけた。告白が成功するなんて期待してもいなかった。ただ好きだって知ってほしかっただけ。こんなヤセっぽっちのガイジン、誰も好きになんてならない。パパは国に帰れば普通の人になれるけど、私はどこにいっても変な奴なんだ。恋愛において必要なステップを踏まないことで起こった当然の結果を、中学生の私は自分の容姿に強引になすりつけ、片田舎の路上で悲劇のヒロインを演じたのだった。
高校生のとき、はじめて告白された。彼氏という新しい存在。毎日が楽しくて、無数の人の中で、私なんかをたったひとりに選んでくれる人がいたことに、胸がいっぱいになった。
「俺、アワさんと結婚しようと思ってるよ」
「ほんと?」
「ほんとに。親にも話した」
「なんて言ってた?」
「家系に外国の血が入るのは、気にしないよって」
「そっか」
そっか。なんだよ。嬉しいことじゃないか。認めてもらえたんだ。許されたんだ、私は。なのに、どうしてこんな気持ちになるんだろう。
結局2年ほど付き合って私たちは別れた。原因は彼の大学デビューによる見境なしの浮気だった。浮気相手のひとりだった女の子のツイッターを覗くと「あたしは純ジャパだから。勝ち。」と書いてあった。
大丈夫大丈夫。私は不遇なんかじゃない。中身を愛してくれる人はきっといる。「ガイジンってエロいよね」「俺、褐色フェチなんだ」
そうじゃない。そんなの聞きたくない。
私は私。黒人ハーフの女の子じゃなくて、伊藤亜和って名前なの。たくさんの人がすれ違いざま私を見るのに、これだけのことが、あまりにも伝わらない。投げた石はいちども跳ねずに水に沈んでいく。ママはパパのどこを好きになったの?私はどうして生まれたの?私もみんなと同じように日本語でものを考えているのだという当たり前のことを知って欲しくて、掠れていたボールペンのインクが突然吹き出したみたいに、私は自分の話をネット上に書き始めた。
今日もいろいろな人に会って視線を受ける。誰も私に悪意なんてない。ごく単純な疑問や憧れを伝えてくれる。私は照れたり謙遜したりして言葉を返す。そこに怒りを隠したりもしていない。悪意がないことに怒るなんて私はしたくない。そのせいで日本の価値観がアップデートされないなんて言われても「ごめんあそばせ」である。自分がなんとも思わないことに、わざわざ突っかかる体力も時間も私にはない。初期装備に意味を持たないまま生きるのが、今の私のポリシーだ。あの浮気相手の女の子は200%の悪意で私に向かってきたんだから、私もツイッターに「バカ」とか「小娘」とか散々書いてやった。あまりにも不毛な女同士の喧嘩だ。誰にも文句は言わせず、お互いの顔と名前できっちり殴り合った。彼女は今、広島に嫁いで幸せに暮らしている。最近私のインスタグラムの写真に「綺麗」とコメントをくれて、あぁ、私たち友達になれたかもしれないんだ。と、勝手に切なくなった。
「お姉さんかっこいいね、モデル?」
「違います」
「どこからきたの?なに人?アメリカ?」
「横浜です」
「やっぱり日本の男じゃダメなの?どういう男が好き?」
「どこからきたの、とか聞いてこないひと」
君はどうだろう。私の隣に立ってくれる?
(第1回 了)
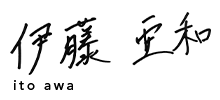
伊藤亜和(いとうあわ):文筆家/モデル。1996年 横浜市生まれ。学習院大学 文学部 フランス語圏文化学科卒業。Noteに掲載した「パパと私」がツイッターで糸井重里、ジェーン・スーなどの目に留まり注目を集める。趣味はクリアファイルと他人のメモ集め。第一作品集『存在の耐えられない愛おしさ』(KADOKAWA)が好評発売中。

