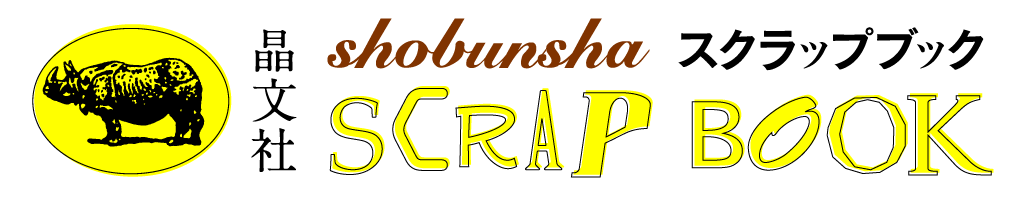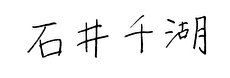信じられないくらい優柔不断、単に運が悪い、欲望に勝てない、決断を間違える……。文学ではキーパーソンとして読者に強烈な印象を残すことが多い「ダメ人間」。どうして、作家はダメな人を描くのだろう?
文学に登場するダメ人間たちに時に苛立ち、時に愛でながら、様々な生に目を向ける「人間讃歌」連載。
子供のころから、何をするにも鈍くさい。この連載も、気がついたら前回の更新から5ヶ月近く経っていた。いくらなんでも遅すぎるだろう。仕事がなくなったらどうしようと日々恐れているのに、どうにもこうにも進まないのである。筋肉少女帯の名曲「踊るダメ人間」が脳内をぐるぐる回る。ダメな人の本心を高らかに歌い上げて〈それでも生きていかざるをえない!〉というつぶやきで締めくくるところが好きだ。
今回取り上げるのは、ジョージ・ソーンダーズが2013年に発表した『十二月の十日』(岸本佐知子訳、河出書房新社)。10編を収める短編集だ。ダメな自分でも生きていかざるをえないときに、手にとってほしい。弱かったり不器用だったりして社会の隅っこにいる人たちが、虐げられても失わない優しさを描いている。
最初の「ビクトリー・ラン」は、15歳の誕生日を3日後に控えたアリソンと、彼女の幼なじみで異様に潔癖な両親の指令に逆らえないカイルが、ある事件に巻き込まれる話だ。アリソンはカイルも含めて地元の男の子たちを辛辣に批評しながら、{特別な誰か}との出会いを夢見ている。カイルは臆病でおとなしい良い子ちゃんを演じつつ、頭のなかは汚い言葉でいっぱい。ふたりとも思考と行動、理想と現実がかけ離れている。だからこそ、誰かのために走れてしまう。10代ならではの不安定さと純粋さを凝縮した語りが素晴らしい。
「棒きれ」は、子供を愛するのが絶望的に下手な父親の話。「子犬」は、幸せな家庭をつくろうとがんばっているのに報われない母親の話。「訓告」は、詳細は不明だが人道に反する業務によって社員が病んでいく会社の話。「アル・ルーステン」は、イケてる名士を選ぶチャリティイベントにうっかり参加してしまう冴えない男の話。「センプリカ・ガール日記」は、家計が火の車なのに娘のために素敵な誕生日プレゼントを用意しようと奮闘する父親の話。「ホーム」は、戦場で深刻な問題を起こしたらしい帰還兵が家族に会いに行く話。いずれ劣らぬ面白さなのだが、なかでも好きな3編を選んでみた。
まず「スパイダーヘッドからの逃走」。主人公のジェフは、罪を犯して服役中だ。彼が収容されている施設では、リモートパックを装着した受刑者にさまざまな薬剤を注入してデータをとっている。その人体実験の管制室がスパイダーヘッドだ。ある日、ジェフに注入されたのは、初対面の女性を熱烈に愛するようになる薬だった。言語中枢を強化する薬を併用して急激に豊かになった語彙で、ジェフが自分のセックスを鮮やかに実況してみせるくだりは可笑しい。愛情をコントロールする薬の治験は成功したが、恐ろしい追試が行われる。
1971年のスタンフォード監獄実験を思い出した。スタンフォード大学の心理学者が普通の若者を集めて、囚人役と看守役に分けたところ、看守役は囚人役を虐待するようになったという。現在は捏造が指摘されていて、研究結果は鵜呑みできないとはいえ興味深い心理実験だ。置かれた状況や役割次第で、人間は簡単に残酷になれる。そういう考え方は浸透していて、虐殺が絶えない人類の歴史を顧みれば説得力もある。
ジェフが与えられた役割は、スタンフォード監獄実験の看守役よりもずっとおぞましい。スパイダーヘッドの管理者は、治験にあたって必ず受刑者の許可を求める。自己決定権を認めているようだけれども、それは見せかけにすぎない。ジェフは破滅への道を自ら選ぶように追い込まれる。悲しくてやりきれない話なのに解放感をおぼえる。ろくでなしだったジェフが悪をなすことに抵抗し、〈おれだけの言葉〉を獲得するからだ。
「わが騎士道、轟沈せり」も、不思議な薬が出てくる話だ。主人公のテッドは、中世ヨーロッパを再現したテーマパークで働いている。〈松明ナイト〉の夜、職場のボスが〈洗い場〉担当のマーサを強姦した。ボスは被害者のマーサと、現場を目撃したテッドを昇進させる。給料を増やして口止め料代わりにしたのだ。テーマパークで〈歩哨〉を演じることになったテッドは、アドリブ力を高める薬を飲む。すると、役柄に合わせたのか、名誉を重んじ同胞を愛する騎士道精神が湧いてくる。思考と言葉を内なる騎士にのっとられたテッドは、取り返しのつかないことをしでかしてしまう。
テッドとマーサは貧しく、家族のためにも失業するわけにはいかない。ボスの性加害に目をつぶって、事件自体をなかったことにするのが最善と判断した。しかし、理不尽な暴力に耐えると、意識はしなくても心が深く傷つく。その傷を滑稽な騎士の姿で表出させるところが唯一無二だ。どん底に落ちたテッドを包み込む夕暮れの美しさも忘れられない。
そして、表題作の「十二月の十日」には、コミックのキャラクターの騎士に似た〈残念なおかっぱ頭〉の少年が登場する。名前はロビン。現実の学校ではいじめられているが、妄想の世界では地底人と戦う英雄だ。気温マイナス12度の寒い日、ロビンは凍りついた湖のほとりのベンチで、脱ぎ捨てられたコートを見つける。コートの持ち主である男、エバーは、病苦のために自殺しようとしていた。ロビンはエバーを追いかけて氷に覆われた湖を歩いて渡るが……。
本書のなかで贈り物にするとしたらこの話。ロビンの語りがものすごくかわいいのだ。たとえば地底人に〈ゴーモン〉されるくだり。
彼があおむけに寝かされ、流れる雲をながめてるあいだに、向こうがいろんなゴーモンをしてくるんだが、どれもこれも手ぬるい。奴らはまず歯には手出ししない。もっけのラッキーだ。なにしろこっちは歯石を取られるのだってイヤなのだ。あいつら、そういうところが抜け作なんだ。ちんちん、それから爪にも何もしない。彼はゴーモンに果敢に耐え、スノーエンジェルをやってみせたりして敵を挑発する。
拷問にしてはのんきすぎる雰囲気だし、〈もっけのラッキーだ〉という言い方もかわいい。ちなみにスノーエンジェルとは、註によれば〈雪の上に寝て手足を扇状に動かし、天使の形を作る遊び〉らしい。かわいい。いじめられているのに人も世界も呪わず、光属性の想像力しか持たない上に、誰かを助けたいと思っている。そんなロビンを応援したくなる。
結局、ロビンの救助作戦は失敗する。でも、失敗したからこそ、エバーは救われる。
この世界は、不条理なことだらけだ。どんなに努力をしても、しくじるときはしくじる。善かれと思って行動したことが、事態を悪化させることもある。ただ、どうせ生きざるをえないなら、ロビンやエバーのように優しくいられたらいい。
参考資料:https://bunshun.jp/articles/-/47360