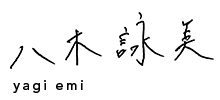『空芯手帳』『休館日の彼女たち』、ユニークな小説2作を発表し、国内外で注目を集める作家・八木詠美。本書は著者初のエッセイ連載。現実と空想が入り混じる、奇妙で自由な(隠れ)レジスタンス・エッセイ。
昨年の秋、イギリスに行ってきた。チェルトナム文学祭というイギリスでもっとも古い文学祭のイベントに招待され、いくつかの都市でもトークイベントを行うことになった。
イギリスでは2022年に自著『空芯手帳』の英訳が出版され、実際に本を読んだ読者の方々がインスタグラムなどで本の感想を書いてくれたり、ロンドンの名物書店のFoylesが紹介してくれていたりして気になっていたので、招待のお話をいただいたときは行きますとすぐにお返事した。なるべく現地の読者や対談する他の作家の方々の言葉を理解できるようになりたいと、勢いあまって英会話のGabaの短期集中レッスンにまで通った(確定申告に向けて、そのときの領収書を今血眼になって探しています)。
はじめて行ったイギリスは、当たり前だけれども都市によってずいぶんと雰囲気が変わった。最初に訪れたチェルトナムは美しい街並みで、温かい雰囲気の漂う文学祭も含めて大切な場所になったけれど、その次のイベントで訪れたシェフィールドは大きな大学もありさまざまな人種の人がいて、イベントの進行をしてくださった植松のぞみ先生と行ったトルコ料理のレストランもおいしくてリラックスし、白人系の人が多かったチェルトナムで自分が思いのほか緊張していたことを少し遅れて実感した。
その翌日行ったリヴァプールは潮の香りが漂いカモメが飛び交う港町だが、その活気と猥雑さが私の中では東京の池袋(特にサンシャイン周辺を含む東口)と勝手に結びついた。カズオ・イシグロやイアン・マキューアンを輩出したイースト・アングリア大学のあるノリッジは、滞在時間が短すぎて街の様子はわからなかったが、床がぎしぎしと鳴るライティングセンターの美しい建物は何度だって訪れたい場所になった。
ロンドンは切符や日本でいうSuicaのようなものを買わずにクレジットカードをタッチするだけで、チューブと呼ばれる地下鉄に乗れるのが気楽でいいなと思った。電車の中で本を読んでいる人の姿をよく見るのも嬉しかった。街の中にいる犬が全然吠えず、カフェに入ったり交通機関に乗れることにも驚いて、同行してくださった現地在住の財団の方に尋ねると、犬のトレーニング教室があるのだと教えてくれた。
ただ、旅としてはなかなかハードだった。イベントの数は当初の予定よりも多く、毎日とにかく移動した。出発前は移動中に小説を書けばいいかと思っていたけれど、いざ列車の中で書こうとすると時差ぼけによるだるさで小説はほとんど進まず、移動と本番を繰り返すサーカスの動物のような気分になってきた。頭も常にぼんやりとして重く、持ってきた頭痛薬を飲んでいたが、油分の多い食事に耐えられなくなった内臓の悲鳴により途中からはそこに胃腸薬が加わった。
そして時差のせいかどれだけ疲れていても深夜2時には目が覚めてしまい、イベントに来てくれた人たちはこんなに寝不足で自分でも思考が支離滅裂だと感じている人間の話を聞いて本当に楽しいんだろうかと心配しながら毎日登壇した。
観光をしたり食事を自由に楽しんだりということもほぼなく、ビッグベンも大英博物館もまったく見ることなく終わった。ビッグベンについては、Gabaのロンドン出身の先生が「ただの巨大な時計台。見なくてよい」と力強く話してくれたので諦めがついたが、スコーンについては滞在中に一度も食べられなかった悔しさが募り、帰国した翌日に近所のカフェにスコーンを食べに行った。
ちなみにここ数日は確定申告のために昨年の収入を整理しているが、一部のイベントの報酬がまだ支払われていないことに気づいた。
なんだか書いているうちにどうしてあんな旅に行ったのだろうと考え始めてしまったが、それでもずっとお会いしたかった翻訳者のルーシーさんや編集者のエリーさん、そして現地の読者の方々と直接交流できる機会はすばらしかった。どのイベントでも途中で打ち切らなければいけないほどたくさんの質問が出て、そのどれもが本に対する愛情に満ちていた。
ある人からは「あなたは日本文学の中では自身をどのような系譜として考えていますか?」という質問され、答える前に「あなたは読んでいてどのように思いましたか?」と尋ねると「私はあなたの作品は安部公房の系譜だと思います」と返ってきて、リヴァプールで安部公房の名前を聞くことに驚き、また自分が学生時代に『箱男』が好きだったことを思い出した。サインの時間では「電車の中でこのページを読んでいたら吹き出してしまったので、ぜひサインはこのページにお願いします」と笑いながら本を差し出してくれた人もいた。
その中でも一人、忘れられない読者がいる。最終日の夜にロンドンのFoylesで、小説のあるシーンについて解釈を求められたことがあった。説明する前に「その部分については日本でもわからない、わからないからつまらないという感想があって……」と私が言うと、前方に座っていた一人の女性が「私も」と手を上げて会場に笑いが起きた。私も思わず笑ってしまった。
けれど同時に私は感動していた。わからないと思った小説を「だからつまらない」と突き放すことはできるだろうし、矛盾しているように見える部分に対してどうしてそう書かれているのか考えることなく「ストーリーが破綻している」などこき下ろして終わりにすることもできるだろう。実際、本のレビューサイトなどを見ると自分が書いた小説に限らずそんな感想を目にすることはままある。もちろん、小説は「わかる」ことがその楽しみのすべてではない(そもそもある小説を「わかる」とはどういうことなのかという問題がある)が、「わからない」と思った瞬間に離れてしまうような小説の読み方をする人は一定数いる、それもどちらかといえば増えているように感じる。
そんな中、この女性はわからないと思った小説の作者が、それも無名の海外の小説家がイベントでやって来ると知り、お金まで払って平日の夜に書店まで足を運んでくれている。なんと豊かな、わからないものとの付き合い方だろう。結局、小説に限らず世界はわからないものばかりで、私たちはそのわからなさと交差し、そこに目を凝らさなければ、見える世界は少しずつ貧しくなってしまうのだから。
話し終わって次の質問を求めると、その女性は即座に手を上げて「ようやくわかった気がする」と話し出し「ありがとう」と結んでにやりと笑った。彼女のその表情を見たとき、私は頭痛も胃痛も時差ぼけも忘れ、ただ今夜ここに来てよかったと思った。