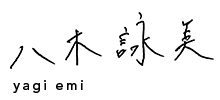『空芯手帳』『休館日の彼女たち』、ユニークな小説2作を発表し、国内外で注目を集める作家・八木詠美。本書は著者初のエッセイ連載。現実と空想が入り混じる、奇妙で自由な(隠れ)レジスタンス・エッセイ。
子どものころ、セーラームーンや魔女の宅急便の主人公に憧れたのは、変身して戦えたり魔法が使えたりするからじゃなかった。喋る猫がいたからだ。こんなふうに自分の気持ちを打ち明けて、ずっと一緒にいてくれる存在がいれば、他に何もいらないのにと思っていた。
わたしは友だちが少ない。この前まで4人くらいいたような気がするけれど、最近は2人くらいだ。このペースだと5年後は0人、10年後はマイナス2人になる計算だ。2人に強い敵意を持たれるとなれば、宅急便などの荷物を開封するときも注意した方がいいだろう。
小さいころから、友だちが少なかった。小学2年生まで、わたしは友だちになってほしい相手にはわざわざ「友だちになって」と言っていた。そういうふうに言わなければいけないルールなのだと思い込んでいた。たしか、絵本を読んだのだ。すごく意地悪な女の子がいて、主人公の女の子とケンカとか何かしらの起伏のある出来事を経て、ラストに仲直りとして「友だちになって」と言うシーンがある絵本を。いたく感動したわたしは友だちとはそういうふうにドラマチックに約束し合う存在なんだと思い、そして誰もわたしに「友だちになって」と言ってくれないので勝手に落ち込んでいた。
小学校の高学年や中学生になると、グループというさらに複雑なものが登場した。クラス替えの名簿が配られるたびに緊張した。いちいちそんなことを気にするのもいやだし、それを気にしていると思われるのもいやだった。昼休みにお弁当を食べるときはもちろん、遠足や修学旅行の班分け、文化祭の係決め。何も決めていないはずなのにアメーバの分裂のようにみんなその場できれいにグループに分かれていくのがおそろしかった。
けれど今、友だちが少ないことをそこまで嘆くつもりはない。悲しい、とも、すっきりする、とも思わない。大人になって忙しくなったから、とも言いたくない(思春期って暇だったから、とはもっと言いたくない)。ただ、生活に占める友だちの割合が減って代わりに「なるべく親切にしたい人」が増えた。
「なるべく親切にしたい人」は結構いる。かつての同級生も多くはそうだし、よくわからないうちに親しくなり、ときどき思い出すように連絡をする人たちもそうだ。小説やエッセイをいつも最初に読んでくれる編集者の人や、誰かの心ない毒ガスみたいな発言を耳にするといっしょに怒ってくれる会社の同僚、別の部署になってしまったけれど会うと最近食べたおいしいお菓子なんかを教えてくれる同僚にも親切にしたいと思う。場面によっては名前を知らない人や、初めてそこで出会った人もそうなる。
ちなみに「なるべく親切に」の範囲は難しいが、その人が何かのトラブルで小指を切り落とされそうになったとき(なぜかこの話題について考えようとすると、急に発想が「仁義なき戦い」みたいになってしまう)、代わりに進んで自分の小指を切り落とされるのは難しいけど、一緒に逃げ出すための何かはしたいと思うくらいだ。別に気持ちを打ち明けたりしなくていいから、ずっと一緒になんていなくていいから、その人たちが嫌な目や痛い目に遭わないでほしいと心底思う。
実際、もしもわたしのそばに喋る猫がいたら大変だったと思う。だって相手は喋る猫だ。かわいくて、喋れる。もうだめだ、絶対に何もしない。勉強もせず、働きもせず、ずっと家で猫と喋っていただろう。働かずに猫の生活を支えるために、あまり良くない世界に足を踏みいれていた可能性だってある。月野うさぎさんもキキさんも、喋る猫がいるのに学校に行ったり魔女修行をしたり自律した生活をしていて、本当に偉いと思う。
それに、と同時に思う。きっとしゃべる猫がいたら、わたしは小説を書いていなかっただろう。なんでも話し合える相手なんていたら、どうして一人で黙々と言葉を書き連ねることができるだろう。
自分が小説を書くのは、さびしいからだと思う。ふと思いついた想像の切れ端、見たものや聞いたもの、そこからにじんだ心のうちの何かを誰かに伝えたいのにどうすればいいのかわからなくて、でもそれらをなかったことにしたくなくて、行き場なく蓄積していくうちに、言葉がこぼれる。物語が始まる。
あるいは、と考える。喋る猫だってずっと一緒にはいられないのだ。物語の中盤でキキさんが黒猫のジジと話せなくなり、それにより成長していくように。
喋る猫はきっと、自律できそうな人のもとにやってきて、その人が自立し、さびしさも不安も自分で抱きしめられるようになると喋る猫としての役目は終える。一番近くにはいなくて、でもそばにいる。
昔買ってもらったジジのぬいぐるみは、実家の自分の部屋に置きっぱなしになっていた。なぜか梁の上に飾ってしまい、なかなか取れないのだ。先日久しぶりに実家に帰ると、かつてのわたしの部屋は父の寝室になっており、父はジジに見守られながら毎晩眠っているらしい。