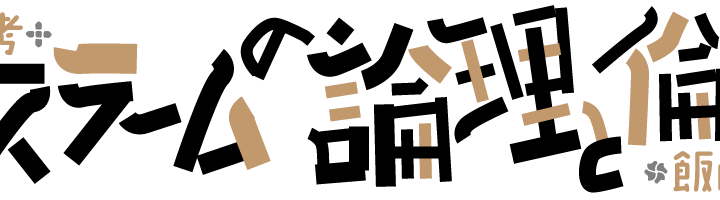戦わなければ現状は打開できない
飯山陽
明らかになった主張の違い
ここまで9本の書簡を通して、中田先生と私の主張の違いは明らかになったと思います。
一般にあるテーマについて、二人の研究者の主張が異なる場合、その理由は各々の主張の立脚する根拠の違い、方法論や解釈、理解の違いに求められることが多いと言えます。しかし中田先生と私の場合、両者がほぼ全てのテーマについて全く異なる見解を示しているのは、立場の違いに起因するところが大きいと言えるでしょう。
私は女性であり、非イスラム教徒です。博士号はとりましたが、大学に籍をおかず学会にも属さず、肩書も権威もない、いわばフリーランス研究者です。
一方の中田先生は男性であり、イスラム教徒で、「同志社大学神学部元教授」という立派な肩書をお持ちです。しかもメディアにおいてしばしば、「日本におけるイスラーム学の第一人者」として紹介されています。
しかし中田先生を単に「研究者」として紹介するのは、語弊があります。なぜなら中田先生は何よりも第一に、カリフという唯一の指導者がイスラム法によって世界を統治する「カリフ制」の再興を目指す、という明確な政治的目標を掲げ、それを広める活動にいそしむ「活動家」だからです。
内田樹氏との共著『一神教と国家』(集英社新書)において中田先生は、中東などでは「うかつに体制を全否定するカリフ制のことなど口走ったら大袈裟ではなく本当に生命が危険です。しかし、日本はイスラームに関しては中立ですから何でも言えるのです」「で、日本をカリフ道の発信地にしようとたくらんでいるわけなのです」と述べています。ご自身でこう述べているのですから、間違いありません。中田先生の「たくらみ」、先生にとっての「優先順位」は明らかです。
ですからこの往復書簡に納められた中田先生の原稿を含め、先生の全ての発言、あらゆる記述は、日本にイスラム教の素晴らしさを広めるため、カリフ制再興という目標実現のための活動の一環であると認識されるべきです。
「カリフ」という日本人にほとんど馴染みのない、あるいは「世界史で聞いたことがある程度」の用語のせいで、カリフ制の危険性は日本人に認知されにくいように思います。カリフ制とはすなわち、イスラム絶対体制です。それを採用し実践しているのが「イスラム国」です。第二書簡では中田先生自身も、「私がイスラーム国に足を運んだのも、移住する前提」だったと述べています。少なくとも制度的、外形的には、「イスラム国」は中田先生の目指す「カリフ制再興」を既に実現させている、イスラム絶対体制の具現者です。
中田先生はカリフ制再興、つまりイスラム絶対体制の実現を目指すイスラム教徒ですから、日本人に対して、とにもかくにも「イスラム教は素晴らしい」と主張しなければなりません。日本では言論の自由が広く保証されているので、「カリフ制再興!」と叫んだり訴えたりしても、逮捕されることはありませんが、この自由は世界中で享受できる類のものではありません。
第七書簡で記したように、カリフ制というのは民主主義にも自由主義にも世俗主義にも反するイスラム絶対体制です。それは中田先生自身がお書きになったように、既存の「体制を全否定する」ものです。ですからその危険性を熟知した国々では、カリフ制再興を目指す活動は国家転覆を目す極めて危険な犯罪行為と認定されます。加えてカリフ制再興を実現させた「イスラム国」は、多くの国々が今現在もそのテロ攻撃に晒され、実際に戦火を交えている相手でもあります。敵のイデオロギーがあたかも正義であるかの如く公に宣伝する活動が、認められるわけがありません。
普遍的人間性か、イスラム的人間性か
中田先生が研究者というよりは活動家であることは、第二書簡において、カリフ制の基本は「ヒューマニティーと法の支配」だと述べ、賛美していることからも明らかです。ここで唐突に「ヒューマニティー」というカタカナ化した英単語を登場させたのは、日本語では出せないぼんやりしたプラス・イメージを漂わせることで、カリフ制と聞いてもピンとこない読者に対し、カリフ制は「なんとなく素晴らしい」という印象を与えるためでしょう。新奇な「横文字」単語の使用は、意味をぼやかしたり、相手の目を真実からそらせて誤魔化したり、印象操作をしたりする上で効果的です。
私のように、「カリフ制とは要するに『イスラム国』が採用している制度である」と説明すれば、それを「なんとなく素晴らしい」と思う人はほとんどいないでしょう。だからこそ、中田先生によってカリフ制を説明するために採用されたのがこの「ヒューマニティー」という英単語なのだと考えることができます。
ヒューマニティーとは「人間性」の意味です。何をもって人間性とするかについては様々な考えがあるでしょうし、全人類に共通する「普遍的人間性」というものがあると主張する人もいれば、ないと主張する人もいます。
たとえば私は、人間は誰しも「殺されたい」とも「拷問されたい」とも「虐待されたい」とも「奴隷にされたい」とも「差別されたい」とも「飢えたい」とも「貧困状態に陥りたい」とも思わないというのは、一定の普遍性を持った人間性だと考えます。
イスラム絶対体制で採用されるイスラム法においては、神への絶対服従が全ての基本となります。イスラム教では人間は生まれつき全員がイスラム教徒なのだと考えるので、人生の全てにおいて神に絶対服従し、神に命じられたことを理由など問わず遂行する、それこそが正しくイスラム的な人間性だと言えます。イスラム教において重要なのは、普遍的人間性ではなく、イスラム的人間性です。
イスラム法は、人間としての本性から外れた非イスラム教徒を敵と認定し、それと戦い、殺害することをイスラム教徒の義務と定めます。イスラム法が「殺人はよくない」という普遍的人間性に立脚しているならば、特定の人間集団を敵と見なし、戦争を義務付けたりはしません。しかしイスラム法は非イスラム教徒を「悪」と規定することで、非イスラム教徒の人間性を否定し、殺害対象と認定します。「イスラムか、非イスラムか」という、典型的な二分法です。
中田先生はカリフ制の基本はヒューマニティーだと主張することにより、あたかもそれは普遍的人間性を前提としているかのようにほのめかしていますが、イスラム法が立脚しているのはイスラム教徒だけに完全な人間性を認め、非イスラム教徒の人間性は否定するという二分法に基づく、極めて特殊な倫理観です。カリフ制が普遍的人間性たるヒューマニティーに立脚しているならば、あらゆる殺人、あらゆる差別が禁じられるはずです。つまり明らかに、イスラム法は普遍的人間性を否定しているのです。
近代法による支配と神の法による支配
「法の支配」というのも、近代的で秩序がありそうな、なんとなくプラスの印象を受けますが、イスラム絶対体制における「法の支配」とはすなわち「神の法(イスラム法)の支配」であって、近代法の支配とは全く異なります。
たとえば日本国憲法前文は、主権は国民に存すると定めますが、イスラム法の主権者は神です。イスラム法支配下では、人間には立法する権利もなければ、法を部分的にでも無効にしたり修正したりする権利もありません。
日本国憲法第14条はすべての国民が法の下に平等であるとし、性別による差別を禁じていますが、イスラム法は非イスラム教徒をイスラム教徒の下、女性を男性の下に位置づけます。『コーラン』第98章6節には「啓典の民の中の不信仰者、多神教徒は地獄の火に中に永遠に住む。これらは、衆生の中最悪の者である」、第9章29節には「神も終末の日も信じない者たちと戦え。神と使徒から禁じられたことを守らず、啓典を受けていながら真の教え(イスラム教)を認めない者たちには、かれらが進んで人頭税を納め屈服するまで戦え」とあり、第2章228節には「男は女より一段上位である」とあるからです。
日本国憲法第18条は奴隷を禁じていますが、イスラム法は奴隷を認め、女奴隷との性交も認めます。『コーラン』第23章5〜6節に「自らの陰部を抑えよ、ただし己の妻たちや右手の所有にかかるもの(女奴隷)を相手にする場合はかまわない。その場合には咎められることはない」とあるからです。
イスラム法は「イスラム教徒だけに完全な人間性を認める」と前述しましたが、より正しくは「成年自由人男性イスラム教徒だけに完全な人間性を認める」と言うべきでしょう。イスラム法は宗教や性別に基づく差別も奴隷制も正当化する、民主主義と全く相容れないシステムです。
日本国憲法第20条は信教の自由を保障していますが、イスラム法はイスラム教に入信する自由だけを認め、棄教する自由は認めません。『コーラン』第3章9節に「一度(イスラム教を)信仰した後で不信仰になり、不信仰を増長した者は、悔悟しても決して受け入れられない」とあるからです。ブハーリーの『サヒーフ』には、預言者ムハンマドの「宗教(イスラム教)を変更した者は殺せ」というハディースが収録されています。
日本国憲法第21条は言論の自由、表現の自由を保障していますが、イスラム法は神や預言者ムハンマドを風刺したり悪く言ったりする人を厳罰に処します。『コーラン』第33章57節に「神と使徒に害なす者は、この世でもあの世でも神の呪いを受ける」とあるからです。
これらはイスラム法が近代法とは全く異なることを示す、ほんの一例にすぎません。そこにあるのは完全な神中心主義であり、それは人間理性によって人間中心主義的に築き上げられてきた近代的価値観とは矛盾します。
カリフ制は普遍的人間性を否定する
私はもう20年以上、イスラム法の研究をしてきました。そして「イスラム国」の研究も続けてきました。その私から見て、2014年にカリフ制再興を宣言した「イスラム国」はかなりの程度、上述のようなイスラム法を文字通り施行していると言えます。
「イスラム国」が後藤健二氏と湯川遥菜氏という日本人二人を惨殺しただけでなく、世界中でテロを起こし、数万人の人々を殺害し、数百万人の人々の家や生活を奪い、女性を性奴隷にし、同性愛者を処刑し、異教徒を二級市民に貶めてきたことは、日本でも知られている通りです。これがイスラム的「ヒューマニティーと法の支配」の実態です。
しかし中田先生は「イスラム教は素晴らしい」「カリフ制こそ解決」と日本人に思わせるのが目的ですから、論点をたくみにずらし、問題をすり替えます。中田先生が移住目的でわざわざ足を運んだ「イスラム国」は、日本におけるイメージが悪いので、中田先生の論の中ではいつの間にかなんとなく「正しいカリフ制の体現者ではない」ことになっており、中田先生の言う通りに世界が進めば、中田先生の頭の中だけにある「理想的カリフ制」が実現されることになっています。狐に化かされたような、面妖極まりない主張です。
『往復書簡』における中田先生の文章は晦渋さと曖昧さに満ち、冗長で要を得ませんが、私は基本的にこうした文章を一切信用しません。はっきりとした論旨、明晰な言葉遣い、端的さや率直さに欠ける文章からは、読者を煙に巻く欺瞞の意図を強く感じとるからです。
中田先生の文章が「わからない」のは自分が悪いのだと思い、「わかったつもり」を装う必要などありません。「わからない」は、全く恥ずかしいことではないからです。曖昧な文章はどこまでいっても曖昧であり、それを「わかる」ことなどできないのです。
しかし日本人のなかには「わからない」のか「わかった」のか「わかったつもり」なのかはわかりませんが、中田先生の主張について「素晴らしい」「その通りだ」と感激する人もいるようです。中田先生を「偉人」として歓迎する日本の言論界や、イスラム絶対体制の危険性をほとんど誰も知らないという日本の特異性、それに日本で限りなく広く保障されている表現の自由を存分に生かし、公の場でカリフ制再興活動を展開しているのが中田先生です。
中田先生は「皆んなのカワユイ(^◇^)カリフ道」家元を自称し、ラノベやマンガ、ゲームなど、敷居を下げた「ゆるく」「やさしい」やり方でカリフ制の素晴らしさを広める活動を展開しています。内田樹氏、高橋源一郎氏などの著名人も、中田先生やその著作を「面白い」「ユニーク」などと言って絶賛しています。
しかし私には、どこが「カワユイ」でどこが「面白い」のか全く理解できません。非イスラム教徒の女である私にとっては、イスラム絶対体制であるカリフ制など、ただ恐ろしいだけです。中田先生が様々な媒体において自己愛的文章でカリフ制を賛美し、一部の人々がその中田先生を称賛するという構造を目にするたびに、私は恐ろしくてなりません。内田樹氏や高橋源一郎氏など中田先生を絶賛する人々には、カリフ制再興の暁には、自分が殺されるか、奴隷にされるか、二級市民に貶められるという認識など全くないのでしょう。
カリフ制は普遍的人間性を否定します。ゆえにもしカリフ制が再興されたとしても、そこに普遍的正義が実現されないのは明白です。しかし中田先生はその事実を否定します。カリフ制の素晴らしさを喧伝しその実現にむけて活動するのが中田先生の使命なら、カリフ制で全人類が救われることなど決してないと主張し続けるのが私の使命です。
「イスラームによる近代の超克」イデオロギー
第一書簡で中田先生は、大学で最初にイスラームについて受けた講義は文化功労者でもある板垣雄三・東京大学名誉教授のものであるとした上で、板垣氏は「イスラームが学ぶに値するもの」であり、「イスラームは西欧キリスト教的偏見を排することで合理的に理解可能である」と世に示してきた、と高く評価しています。
しかし私は板垣氏の著作から、西欧キリスト教世界に対する強烈な憎しみと、極度にイスラム教やイスラム教徒、イスラム世界を理想視する「イスラム的偏見」の傾向を読み取ります。西欧キリスト教的偏見を排しておいて、イスラム的偏見という別の偏見にどっぷりと漬かる様を、研究として「進んだ」と評価することは、私にはできません。
板垣氏は著書『イスラーム誤認』(岩波書店、2003年)の中で、「現在、索漠たる現実に覆い尽くされた世界が最も必要としているもの、それはタウヒードの論理なのではないか。タウヒードは、今日、近代性の行き着いた隘路を打開する『スーパーモダン』原理として眺めなおすことができるだろう」と述べています。板垣氏はタウヒードを、「イスラームの最も基本的な立脚点」であり、「一つにすること、一と数えること、神の唯一性の確信」の意味で、「多元主義的普遍主義」だと説明します。要するにこれは、「イスラームこそが近代を超克する」という「イデオロギー」です。
「板垣イデオロギー」に通底するのはもうひとつ、日本に対する強烈な嫌悪、憎しみです。2012年8月4日に東京大学東洋文化研究所で実施された公開インタビューでは、「植民地主義、人種主義、軍国主義、男中心主義という世界史の中での悪性腫瘍的な展開」は、もっぱら「ヨーロッパと日本」のせいだと明言しています。そして、日本の「植民地主義性、人種主義性、軍国主義性、男中心主義性」は欧米中心主義と重なり合っており、「敗戦後の天皇制」もまた欧米を真似た「欧米中心主義的な天皇制でしかない」と批判しています。
「日本は欧米と並ぶ近代世界の悪の元凶であり、イスラームによってそれを超克できる」という「板垣イデオロギー」は、現在の日本の中東イスラム研究者の中にも脈々と受け継がれています。中東イスラム研究業界においては、中東やイスラム教の現実を客観的に分析することより、研究者という立場を利用し、「板垣イデオロギー」に代表されるようなイデオロギーを積極的に発信していくことが優先されています。彼らはそのイデオロギーにあまりにも強くとらわれているために、物事のあるべき優先順位が入れ替わってしまっているという自覚すらないように見えます。
私は今回の往復書簡という試みを通し、中田先生もまた「板垣イデオロギー」の最も正統な継承者のひとりと言えるだろうという確信を強めました。第一書簡で中田先生は、「私の方法論的前提は飯山さんだけでなく、日本の、いや日本だけでなく、世界の全てのイスラーム研究者と違っている」と独自性を強調していますが、私には全くそうは見えません。
中田先生の目標とするカリフ制再興はまさに、板垣氏の言う「イスラームによる近代の超克」そのものです。
イデオロギーを投影し、主張するための道具
「日本に対する嫌悪」に関しても、中田先生は第四書簡で次のように述べています。
日本によってインドネシアを含むマレー・イスラーム世界が軍事的に占領され植民地化され、神道の天皇崇拝を強制されたのは、古老たちの記憶に残るリアルな「事実」です。私たちは、東条内閣の閣僚としてA級戦犯の被疑者になり公職追放になった岸信介の孫で、彼を尊敬すると公言し、靖国神社に参拝し、戦争放棄と戦力不保持を定める憲法九条の改正を目指すと公言する人物が首相を務める国の国民であることの意味をよく考えてみる必要があるでしょう。
このように唐突に「A級戦犯の岸信介の孫」として安倍晋三首相を持ち出し、自らが「反安倍派」「反体制派」にして「護憲派」であることを表明しています。さらに次のように続けます。
精神分析では、自分自身に認めたくない欲求や感情を無意識に他者へと転嫁して自己正当化することを「投影」と言います。イスラームが過度に侵略的で危険だと見える者は、自分自身の姿を相手に投影しているのではないか、とまず自分自身を疑ってみるとよいでしょう。個人であれ集団であれ、自己の実像を直視するのは誰にも難しいものですが。
ここで再度、唐突に「精神分析」を持ち出して急に論点をずらし、イスラムを侵略的だと危険視する者は、実は自分自身が侵略的で危険な存在なのだ、と問題をすり替えます。
この主張の妥当性を推し量るには、これをそっくりそのまま中田先生に当てはめてみればいいでしょう。中田先生は常日頃、国民国家と資本主義を偶像神だと批判しているので、実は中田先生自身が偶像神であり、中田先生はその自己の実像を相手に投影していることになります。中田先生によると、自己の実像を直視するのは難しいらしいので、中田先生にとってもそれは難しいことかもしれませんが。
私はイスラム教について論じるにあたって、自らの政治的信条、イデオロギーなど持ち出すべきではないと考えます。なぜなら私は、あるがままの事実を見つめ、客観的な分析結果を一般の人々に提示するのが研究者の役割だと信じているからです。
ところが中田先生をはじめとする日本の中東イスラム研究者は概ね、私とは真逆のスタンスをとっています。中東やイスラムについて論じるという体裁で、急に日本の体制批判や、憲法9条を守れという主張を混ぜ込んだかと思うと、日本は植民地主義だとか差別主義、父権主義だといって日本への嫌悪を露わにします。その一方で、イスラム教やイスラム世界を極度に美化して理想視し、最終的には「イスラームこそが近代を超克する」と言い切ります。彼らにとって中東やイスラムは、客観的な研究、分析対象ではありません。自らの政治信条、イデオロギーを投影し、主張するための道具なのです。
私に言わせれば、これは研究者ではなく活動家の所作です。
マックス・ウェーバーは『職業としての学問』で、大学の教壇を自らの政治的信条を吐露する場、価値判断をする場としてはいけないと戒め、「指導者」や「予言者」のように振る舞う知識人を批判しました。私はウェーバーの考えに大いに賛同しますが、中東イスラム研究者はそうではないようです。私の目に彼らは、ウェーバー曰くの「知的誠実さ」に欠けているように見えます。
日本の中東イスラム研究者の「客観的事実より自分の気持ち・イデオロギー」という傾向は、中東に対する眼差しにも顕著に現れています。中田先生も第一書簡で「私自身アラブ、特に私が留学したエジプトは大嫌い」と述べ、「あくまでも印象論」としつつ、「総じてアラブ研究者はアラブが嫌い(か大嫌い)、イラン研究者はアンビバレント、トルコ研究者はトルコ大好き(か好き)」と述べています。
好き嫌いは個人の自由ですが、中東イスラム研究者の場合、それが「研究者としての主張」に直結する顕著な傾向があります。中田先生は図らずも、中東イスラム研究者に国別の好き嫌いがはっきりとあることを暴露してしまいましたが、これは彼らの発言の信頼性を損なわせるに十分です。
好きだから持ち上げ、嫌いだから貶める
日本の中東イスラム研究者には、イランとトルコに極端に阿るような主張をする一方で、エジプトやサウジアラビアといったアラブ諸国を極端に貶める主張をするという傾向が見られます。なぜなら彼らは反米のイランとトルコが好きで、親米のエジプトやサウジが嫌いだからです。
研究者自身が好きだから持ち上げ、嫌いだから貶めるといった、そんな「研究」は一切信用に値しません。研究者の責務は「自分がどう思うか」を発信することではなく、実際に起きていることは何かを考え、分析し、自分の好悪は排して客観的事実を包み隠さず公開することであるはずです。
日本の中東イスラム研究者のイラン・トルコ好きは、中東で大きな事件が勃発するたびに露見します。第三書簡でテーマとしたトルコのシリア侵攻の際には、中田先生や日本のトルコ研究の代表格である内藤正典・同志社大学大学院教授らがトルコを全力で擁護しました。第七書簡でテーマとしたアメリカによるイランのソレイマニ司令官殺害の際には、中田先生やイラン研究の代表格である松永泰行・東京外国語大学教授や田中浩一郎・慶應義塾大学教授がイランを全力で擁護しました。すでに第三書簡、第七書簡で指摘したように、そこにあるのはトルコが正しい、イランが正しい、悪いのは欧米だというイデオロギー喧伝のみです。「トルコとイランが正しく、欧米が悪い」という結論は最初から決まっているので、事実を見つめ客観的に分析する必要などないのです。
中田先生の板垣氏譲りの「イスラム上げ」「日本下げ」は、第八書簡、第九書簡にも実に顕著に現れています。
第八書簡では、私が提案したイスラム教における異教徒差別という問題を中田先生は人種差別問題にすり替え、「彼らが西欧人・白人へのコンプレックスの裏返しとして、見かけからして違う『平たい顔の』東アジア人を見下すのは、名誉白人を気取った日本人による韓国人、中国人蔑視よりははるかに理に適っている」と、中東のイスラム教徒による日本人差別を擁護しました。
第九書簡では「トルコのコロナ対応」について、日本は「後手後手」で「医療崩壊」し、「ほとんど意味不明の自粛でお茶を濁している」のに対し、トルコは「素早く対応」し、「医療崩壊に陥っておらず」「帝国としての自負と矜恃」「NATOのメンバーである存在感を示した」等と絶賛し、日本は「老人が金と権力にしがみつく老人支配の国」だが、トルコは「老人を敬い、子供を慈しむ」国である、と急に倫理観にまで立ち入り、日本への非難、嫌悪をあらわにしています。
第八書簡のテーマを選んだのは私で、第九書簡のテーマを選んだのは中田先生です。
私は第九書簡で「トルコのコロナ対応」というテーマの指定を受けたとき、トルコで具体的にどのような対策がとられ、どのような問題が発生しており、それはどういった評価を受けているかなどについて、客観的事実に基づき原稿を書きました。
しかし中田先生はなぜか唐突に日本を引き合いに出し、奇妙なほどにトルコを賛美して日本を貶めています。さらに「トルコと日本を比較したついでにエルドアン政権と安倍政権を比べてみましょう」と脱線した上で、エルドアン氏を「独裁者とは程遠い」と擁護する一方、「安倍に出来るのはせいぜい花見や、学校や、マスクで身内にケチな利権を回すぐらいが関の山」と腐します。
中田先生が「トルコのコロナ対応」というテーマを選択したのは、トルコとエルドアン氏を称賛し日本と安倍首相を貶めるのが目的だったのだろうと、私は理解しました。ここにも中田先生の、「客観的事実より自分の気持ち・イデオロギー」という日本の中東イスラム研究者らしい特徴が顕著に現れています。日本の中東イスラム研究者にとって、中東イスラム研究は反体制活動の道具なのです。
日本の中東イスラム研究はイデオロギー発露の場
中田先生が見ようとしない客観的事実の例を挙げましょう。
この原稿を書いている2020年6月上旬の段階で、トルコのコロナ感染者数は約17万人であり、日本はその十分の一の約1万7000人です。なおトルコの人口は日本より少なく、日本のおよそ4分の3です。またトルコのコロナによる死亡者数は約4700人で、日本はその五分の一の約900人です。中田先生曰くの「後手後手」で「医療崩壊」しているはずの日本では、感染者数も死者数も「帝国としての自負と矜恃」を持つトルコよりかなり少なく抑えられているのが現実です。
もうひとつ例を挙げましょう。中田先生はトルコを「老人を敬い、子供を慈しむ」国と高く評価していますが、トルコでは子供に対する虐待が大きな問題とされ、しかもそれは悪化しています。
2018年5月にはトルコのミッリイェト紙が、トルコで虐待を受けた子供の数は過去4年間で33%増加したと報じました。2016年から2017年に性的虐待を受けた子供の数は、11歳未満の少女2,487人と少年124人、12歳から14歳までの少女3,688人と少年563人にのぼるとされています。同記事ではシリア難民の少女が持参金と引き換えに年上の男性に売られるなど、人身売買、児童買春の横行についても指摘されています。2018年1月には、イスタンブールの一つの病院だけで、5カ月間にシリア人39人を含む115人の少女が妊娠して治療を受けたと報じられました。
「恥ずべき行為」によって「一族の名誉」を汚したとして少女を殺害する名誉殺人も発生しています。2008年のトルコ政府の発表によると、2003年から2008年までに1000人以上の女性が名誉殺人の犠牲になったとされています。2017年には、「一族の名誉」を回復させるため「西洋かぶれ」の姉をドイツで殺害した罪に問われた二人の弟が、移住先のトルコで無罪判決を受けました。エルドアン氏は2014年、女性の本来の役割は母親であると述べ、女性は男性と対等ではないと主張したことでも知られています。
私は中田先生のように、トルコを「NATOのメンバーである存在感を示した」とか「子供を慈しむ国」だと評価し、賛美することはできません。研究者は「自分の見たい現実」だけを見て「見たくない現実」からは目をそらしたり、自分自身の個人的な好悪をあたかも客観的事実であるかのように粉飾したりしてはならないと考えるからです。
同様の理由で、イスラムについて論じているはずなのに急に「反安倍」「反体制」色を鮮明に出す中田先生のやり方にも当惑を覚えます。しかし中田先生は、「反安倍」「反体制」を掲げることが当たり前の中東イスラム研究者や「お仲間」たちに囲まれてきたため、イスラムについて語る体裁で反体制を論じるやり方に当惑する人間がいる、ということを想定すらしていないのでしょう。しかしそこに与することのない私にとっては、中田先生の所作は研究者としては邪道にして奇妙奇天烈であり、活動家の所作と考えれば納得がいきます。
日本において中東イスラム研究という場が、もっぱらイデオロギー発露の場になってしまっているのは、非常に大きな問題です。なぜなら中東イスラムに関心を持った日本人が手に取る本、目にする情報のほとんどが、客観性の欠如したイデオロギー志向のものになってしまっているからです。学校でも中東の歴史やイスラム教について教えられていますし、政治や外交においてもそれはひとつの重要な要素ですが、教科書を書く研究者も、政治や外交の場、メディアに招かれる研究者も、押し並べてイデオロギー志向だということです。
中田先生を初めとする日本の中東イスラム研究者は、あらゆる場で「大学教授」や「専門家」や「第一人者」という「権威ある立場」を利用し、「客観的で専門的な知見」の体裁をとりつつ、実は自分の気持ちやイデオロギーを語っているのです。
日本社会の不利益が増大するだけ
私は研究の道を志した当初、イスラム教について学ぼうと思って手に取った本がいずれも、過剰にイスラム教やイスラム教徒を美化し理想化する言説に満ち満ちていたため、大変当惑しました。それらはイスラム教についての客観的理解を深めるのには、全く役立ちませんでした。
もし私が研究者ではなく一般の日本人で、トルコがシリアに軍事侵攻した事情や背景について知りたいと思って目を通した記事に、トルコは悪くない、トルコには軍事侵攻する正当な理由があるのだ、とひたすらトルコ擁護論が書き連ねられていたら、大変当惑すると思います。
トルコのコロナ対応というテーマに興味を惹かれて目を通した文章に、トルコは素晴らしいが、それに引き換え日本の安倍政権は愚かなことこの上ない、などと書かれていたら、やはり私は大変当惑すると思います。
これでは誰の役にも立ちませんし、何の理解も深まりません。少数の「イスラム・ファン」「トルコ・ファン」を満足させるかもしれませんが、大多数の人には、現実の事象と「専門家」によって提示された解説の不一致に、誤魔化されたような、煙に巻かれたような、もやもやとした印象だけが残ることでしょう。
現在の中東イスラム研究者は、日本の一般社会にある需要を全く満たしていないのです。研究者として果たすべき役割を果たさない一方で、研究者という特権的な立場を利用し、自分の言いたいことだけを言っているのが実情です。
中東イスラム研究者がもっぱらイデオロギー喧伝者であるという実態は長年、日本の教育、研究、政治、外交など、様々な面に悪影響を及ぼしてきました。これまで中東イスラム研究者は、国から多額の科研費を獲得して大規模研究プロジェクトをいくつも行ってきましたが、それらは「日本や欧米はダメだがイスラムは素晴らしい」という「板垣イデオロギー」の強化のみに貢献し、その成果は一般社会には全く還元されてきませんでした。
日本社会では、「日本や欧米はダメだがイスラムは素晴らしい」という研究者の「気持ち」だけが中東やイスラムの現実とは乖離したところでぷかぷかと浮かんでおり、いまだに中東やイスラムについての誤解は広まったままです。新聞やテレビといったメディアでも、中東イスラムについての客観的解説を目にすることは滅多にありません。
私はこの現状を問題だと認識しています。そしてこの現状をひとりの研究者として、私自身が変えていくべきだと考えています。なぜならこのままでは、日本社会にとっての不利益が増幅するだけだからです。中田先生は私が問題視する日本の中東イスラム研究者を代表する象徴的存在であり、いわば敵です。今回、この往復書簡の申し出を受けたのは、敵と戦わなければ現状は打開できないと考えたからです。
しかし中田先生は早くも第一書簡で、「非ムスリムにムスリムの存在様態がイスラームの教えに適っているか、の判断を下すことが正当化されるでしょうか」とこれまた論点をずらし、問題をすり替えることによって、私のような異教徒のイスラム論考など無意味であるというレッテルを貼りました。私はもとより、「ムスリムの存在様態がイスラームの教えに適っているか、の判断を下すこと」など、全く目的としていません。私が目的としていないことを私の目的だと勝手に決めつけることで、私の分析など無意味だというご自身にとって都合のいい結論を導く、典型的なストローマン論法です。
差別の正統化、自由と平等の剥奪に他ならない
この往復書簡において、中田先生が私の書いたものになど全く興味を示さず、指定された分量を大幅に超えて、いたずらに面妖な文を書き連ねてきたことは、読者の方々もお気づきだと思います。
中田先生が私を「異教徒」「女」「大学教授ではない」という三重の意味での「劣位」に置かれた人間として下に見ていることを、少なくとも私はこの往復書簡やツイッターでのやり取りから常に感じてきました。この侮蔑の眼差しは20年前、私が東大イスラム学研究室で初めて先生にお会いした時から少しも変わっていません。
イスラム教において、異教徒はイスラム教徒の下にあり、女は男の下にあるのですから、当然です。中田先生自身も第三書簡で、「(イスラームは)宗教による差別は否定しません」と明言しています。
また中田先生が長年属してこられた中東イスラム研究業界において「大学教授」という地位・権威は絶対ですから、「元大学教授」で「イスラーム学の第一人者」が肩書のない私を見下すのも当然です。
しかし私はイスラム教徒ではなく、信教の自由、男女平等を憲法で保障する日本で生まれ育った日本人です。イスラム的差別を当然のものとして受け入れなければならない筋合いはありません。また私は中東イスラム研究業界には属していませんから、業界独特の権威主義も私には無関係です。
イスラム教徒として、異教徒の女で大学教授の肩書もない私をごく自然に見下す中田先生の決まり文句が、「カリフ制こそ解決」です。カリフ制再興というのは、多数派を占める人々が中田先生のように私のような仏教徒の女を見下し、しかもそれは不当だと主張することが許されない社会が実現されるということです。少なくとも私にとっては、カリフ制再興は解決でもなんでもありません。それは性差別、マイノリティ差別の正統化、自由と平等の剥奪に他なりません。
日本では中東イスラム研究業界はおろか、言論界、マスメディアにおいても、中田先生の主張に反駁する人はほぼ誰もいません。しかし絶賛する人は数多くいます。これは私にとっては大変「奇妙な現象」です。現実世界というのは、空想世界に勝るとも劣らないほど「奇妙な現象」に満ち溢れているので、これもそのひとつと言えばそれまでですが、私はこれを看過することはできません。
では翻って、日本の一般社会ではどうでしょうか。
公の場でおそらく初めて、中田先生の主張に反駁した私の論は、日本の一般読者にある程度受け入れられるのか、もしくは中東イスラム学界や言論界、マスメディアと同様に「肩書も権威もない非イスラム教徒の女の戯言」として一瞥だにされないのか。
判断は皆さんにお任せするしかありません。
どのような判断が下されようと、私はこれからも、自分が全うすべきだと信じる務めを果たしていくでしょう。本当の正解など、誰にもわからないのですから。

「人々は眠っている。死んではじめて気づく」
中田考
1.序
この連載も今回で最終回ですが、前々回、前回とパレスチナとトルコという個別の問題に焦点を絞って扱ったCOVID-19について、イスラームに絡めて巨視的に論じてみようと思います。
まず最初に言っておかなければならないのは、私の予想は大きく外れた、ということです。COVID-19自体の出現は誰にも予想できませんでしたので、それが予想外だったのは当然ですのでそのことではありません。
本連載で何度も繰り返しているように、現代のムスリム世界にイスラームは形だけしか残っておらず、国家のレベルでも社会のレベルでも個人のレベルでもイスラームの教えは実践されていません。それはヨーロッパの植民地支配によって骨抜きにされた現在に始まったことではなく、文明的にはイスラームの絶頂期とも言われるアッバース朝時代においてすらそうでした。しかしこの話をし始めるとキリがないので、詳しくは拙著『イスラーム学』(作品社2020年)、特に第6章「末法の法学」をお読みください。
現代のムスリム国家、ムスリム社会、ムスリムの行動は基本的に全て西欧の領域国民国家、資本主義、西欧近代科学の論理に基づいており、イスラームは表面的な文化的残滓以上のものではありません。外の人間にはまるで別物に見えても、違いは表層の見かけだけに過ぎません。それはちょうど「COVID-19」が、日本語では「新型コロナウィルス」、英語ではnovel coronavirus、中国語では「新型冠状病毒」と書かれるので、日本語、英語、中国語を知らない人間にはまったく別物に見えても、実は同じものであるのと似ています。
そのことはよくよく分かっていたつもりでしたが、それにしてもここまでだとは思っていなかった、という点で予想外だった、という意味です。また私は1982年に東大のイスラーム学研究室に進学し1983年にイスラームに入信して以来、イスラーム学研究室出身のただ一人のムスリム学生であり、ずっと自分の世界観、価値観が他の日本人とは違い、理解されないことを自覚して生きてきました。またエジプト留学以来、25か国以上のムスリム国を訪れましたが、そこでも日本文化の中で育ち13-4世紀のスンナ派国法学を専門とする古典イスラーム学者として、自分たちがイスラームを実践していると信じている現代の自称ムスリムたちとも全く別の世界観を生きていることを、いやというほど痛感してきました。しかしCOVID-19に対する日本、ムスリム世界の反応を見て、私自身の世界観と感性が、ここまで日本人とも現代のムスリムたちとも、勿論、それ以外の世界の人々とも、かけ離れていたのか、と我ながら驚かされました。今回はそれはなぜか、というお話をしていきましょう。
2.歴史の中の伝染病
生理学博士で進化生物学者でもあるジャレド・ダイヤモンド博士は『銃・病原菌・銃』の中で、ヨーロッパの植民地主義者たちによる南米先住民の抹殺において、伝染病の方が武力よりも大きな役割を果たした、と述べています。
「インフルエンザなどの伝染病は、人間だけが罹患する病原菌によって引き起こされるが、 これらの病原菌は動物に感染した病原菌の突然変異種である。家畜を持った人びとは、新しく生まれた病原菌の最初の犠牲者となったものの、時間の経過とともに、これらの病原菌に対する抵抗力をしだいに身につけていった。すでに免疫を有する人びとが、それらの病原菌にまったくさらされたことのなかった人びとと接触したとき、疫病が大流行し、ひどい ときには後者の九九パーセントが死亡している。このように、もともと家畜から人間にうつった病原菌は、ヨーロッパ人が南北アメリカ大陸やオーストラリア大陸、南アフリカ、そして太平洋諸島の先住民を征服するうえで、決定的な役割を果たしたのである」(『銃・病原菌・鉄』)
これまで多くの伝染病の流行がありましたが、かつては今よりはるかに人口が少なく医学も未発達でそれらの伝染病に対する有効な治療法もなかったにもかかわらず、人類が今日まで生き残ってきたという事実をふまえるならば、医学が発達し人口も急増し80億人に達しようとしている現在、人類というレベルで伝染病がその存続を脅かすリスクは限りなく小さいと言えるでしょう。14世紀のペストの世界的大流行では当時の人類の推定総人口4億5000万人が3億5000万人にまで減少したと言われていますが、それでも人類は生き残ったどころか、ヨーロッパでは労働人口の減少により労働条件の改善と農工業の効率化がはかられ、社会、経済が発展したとも言われています。最近の最大の伝染病の流行は1918-1920年のスペイン風邪(インフルエンザ)の流行で、当時の地球の総人口20億人弱のうち2千万人から4千万人が死んだと言われていますが、それによっても人類は滅びず、その後も人口は増え続け、今やむしろ多すぎる人口が問題となっています。
スペイン風邪のグローバルな流行は人類の滅亡が懸念されるほどの危機にはいたらなかったばかりか、民族の消滅、国家崩壊はおろか、さしたる社会問題も引き起こしませんでした。『銃・病原菌・鉄』は、伝染病は人類全体を滅ぼすほどではなくとも、民族、国家のレベルでは存亡の危機とも言える脅威となりうることを教えています。しかしCOVID-19は対症療法しかなくまだ誰も免疫を持っていないとされる(私は本当かどうか疑っていますが)状態でも感染者の致死率はシンガポールなどでは1%を下回っており、医療崩壊が起きている場合でも10%ほどでしかありませんので、地域的な民族、国家レベルでさえもその存在を脅かすほどの危機ではないことは明らかです。
私たちがよく知る世界史上の民族、国家レベルでの存亡の危機となった伝染病は、1346年から1352年にかけて流行し当時のヨーロッパの全人口の4分の1が失われイングランドやイタリアでは人口の8割が死亡し全滅した街や村もあった黒死病(腺ペスト)です。しかし既に述べたようにヨーロッパは医学的には有効な治療法を発見できないままにペスト禍を克服し、それどころか遡及的に分析するなら、後の産業革命、科学革命の準備をすることになりました。
3.イスラームと伝染病
前回述べた通り、イスラームは預言者ムハンマドとその弟子たちの正統カリフの時代にペスト(ターウーン)の流行に遭遇しています。そしてターウーン(伝染病、腺ペスト)に対しては、その地への人の出入りを禁ずる、とのロックダウンの法規定が定められています。実はこの規定は「天使たちは言う。『アッラーの大地は広大ではないか。その中で移住せよ』」(クルアーン4章97節)と、大地は全て神のものであると宣言し、「大地を旅し、(アッラーが)いかに創造を始めたかを考察せよ」(クルアーン29章20節)と、人間の移動の自由を認めるのみならず神の創造の御業を想うために世界を見て回ることを積極的に勧めるイスラームの教えの中で例外的に移動の自由を制限するものです。
クルアーンに「我ら(アッラー)は使徒を遣わさない限り、罰することはない」(クルアーン17章15節)、「律法(トーラー)が降示される前には、イスラエル(ヤコブ)が自分自身に禁じたものを除き、すべての食べ物はイスラエルの民に許されていた」(4章93節)とある通り、スンナ派イスラームは人間の義務負荷は理性ではなく啓示により、預言者によって法が与えられない限り人間は「自由」であり、すべては許されている、と教えます。
「自由」と「権利」について本格的に論じ始めると更に10回連載を続けても足りませんので、ザックリとした話をすると、イスラームは(近代ではなく)現代西欧的な人権は認めませんが、絶対的な自然権と啓示による義務の反射としての権利を認めます。
啓示による義務の反射とは、神が殺人、窃盗を禁じているので、生命、財産の尊重の義務が生じ、その反射として生命、財産の権利が生れることを意味します。イスラーム法理学はイスラーム法の義務の反射として生ずる権利を、身命、財産、理性、血統/名誉、宗教の法益に整理します。
絶対的自然権とは、人間が作ったのではない自然に対する処分の「自由」です。人は開いているところであれば陸であれ海であれどこでも好きなところに移動することも、留まることもでき、木の実であれ、魚であれ、動物であれ、石油であれ、好きに取って処分できることを意味します。私がこれを「絶対的自然権」と呼ぶのは、法を前提とする義務の反射ではないからです。ですからどこにでも行くことができる、と言っても、自分に移動手段があればの話で、体が不自由で動けなかったり、遠方で乗り物がなくてたどり着けなかったり、船がなくて海や川が渡れなかったからといって、誰かが連れていってくれるわけではありません。木の実にしろ、動物にしろ、魚にしろ、石油にしろ、自分で手に入れれば好きにして構いませんが、自分で取ってこなければ、誰も持って来てはくれません。
この「絶対的自然権」とは、「権利」というよりむしろ「事実」そのものに近い、西欧的な「権利」が発生する起源にある最も根源的な「規範」である「自由」としての「事実」です。イスラーム法の義務の反射として生ずる権利は、啓示の神への信仰を前提としますが、この「絶対的自然権」は、神の顕現に先立って生成する権利です。つまり絶対的自然権はイスラームの第一信仰告白「ラー・イラーハ・イッラー・アッラー(no god but Allah)」の前段「ラー・イラーハ(no god)」に基づくもので、無神論者、世俗主義者、理神論者とも共有できる政治的議論のプラットフォームだと私は考えています。私が国境の廃絶、領域国民国家の牢獄からの人類の解放としてのカリフ制再興をムスリム諸国のムスリムたちだけでなく宗教にかかわらず日本人相手にもずっと説き続けているのはこのためです。残念ながら、「絶対的自然権」、つまり究極の「自由」を信じないリヴァイアサンの偶像崇拝者、多神教徒には話が通じませんが、それは自称ムスリムでも、それ以外でも同じことです。
この連載でも、それ以外の場所でも、現在のムスリム世界がイスラームとは無縁、自称ムスリムたちが名ばかりで、実態はリヴァイアサンの偶像崇拝者でしかないことは繰り返し繰り返し述べています。ですから今更、COVID-19に対する対応がイスラームの教えに反しているからといって、驚きはしません。しかし、今述べたように、ロックダウンは絶対的自然権、「自由」の制限ですので、特別な、意味を持ちます。カリフ制再興を自らの使命と心得る私にとっては特に、です。そこでこの問題を少し掘り下げましょう。
前回詳しく述べたように、ハディースにある「ターウーン」の流行時のロックダウンが狭く「腺ペスト」を意味するのか、伝染病(ワバーゥ)一般の規定なのか、そしてまたロックダウンが厳密な移動禁止規定なのか、柔軟な行動指針としての推奨規定なのかは、イスラーム法学者の間でも見解が分かれています。私自身は、ハディースのターウーンは腺ペストを指しているが、他の伝染病にも状況に応じて類推して行動指針とすることができる、と考えています。
というのは、預言者の時代のアラブの間では都市は伝染病が多いことが知られており、特に伝染病の多くでは幼児の死亡率が高いため、新生児は乳母をつけて砂漠に送って育てさせる習慣があったからです。預言者ムハンマド自身も乳母ハリーマによって砂漠で育てられました。また預言者が移住した農村であったマディーナは岩山の商都マッカと比べても、より湿気が高く更に伝染病が多い土地であり、預言者ムハンマドと共にマッカから移住した教友たち(ムハージル―ン)たちはその気候を嫌っていました。それにもかかわらず新生児を砂漠に送って乳母をつけて育てさせるアラブ人の慣習は、慣習としては残りますがイスラーム法には組み込まれませんでした。ですから、通常の伝染病には状況に応じて個々人が理性で判断すればよく、共同体の存続を脅かすターウーン(腺ペスト)にだけ、絶対的自然権を制限し人々の移動を禁ずるロックダウンを行動指針として定めた、と考えるのが妥当だと私は思います。
スンナ派ムスリム世界はおおむね、ロックダウンを命ずるターウーンを典拠に国際線の乗り入れを全面的に停止したり、国内でもさまざまなレベルの移動制限を実施しています。私は個人的には、COVID-19は現存する数々の伝染病と比べてもターウーンと類推するほどの脅威ではなく、むしろ風邪やインフルエンザと同じような個人的な注意喚起の対応で十分であり、絶対的自然権を制限するロックダウンを強制するのは間違いだと思っています。そもそもイスラーム法は神と個人の関係を律するものであり、法人の概念は存在せず、国家によって強制されるものではありません。勿論、イスラームを知らない人間には近代国家の刑法のように映るものがイスラーム法にあるのも事実です。例えば手首切断刑が定められている窃盗罪については、クルアーン5章38節に「男と女の窃盗犯にはその手を切断せよ…」と書かれています。つまりこれは近代国家の刑法のような、窃盗犯の手首を我々が切断する、という国家による声明ではありません。そうではなく、礼拝をせよ、喜捨をせよ、といったムスリムに対する命令と同じく、窃盗犯に対してその手を切断せよ、とのムスリムに対する神の命令なのです。
この場合、命令形は複数形になっており、連帯義務を指します。連帯義務とは、誰かが行えば他の人々は免責されるが誰も行わなければ共同体の全員が罪に陥るような義務です。刑罰の執行はこの連帯義務であり、カリフとその代官が執行の義務を負い、彼らがそれを実行しなければ神に背いたことになります。ちなみに、窃盗犯は死後の最後の審判で裁かれ窃盗の罪で火獄で罰せられますが、悔い改めてこの世で手首の切断刑を受ければ、それが罪の償いとなり、来世での罰を免じられます。ただの窃盗の禁止なら、ムスリムに対する「盗むな」という命令になります。実際、普通のイスラームの規定に関しては、そのような形の命令だけで、違反者に対して刑罰を課す命令は定められていません。たとえば有名な豚肉食の禁止やラマダーン月の断食に関しては、現世でのカリフとその代理人による刑罰は特に定められておらず、禁止を守るかどうかは個人の良心に任されています。
クルアーンやハディースの中で、カリフとその代理人に対して違反者への刑罰の執行が命じられている規定、いわゆる「イスラーム刑法」をアラビア語で「フドゥード」と言いますが、フドゥードの法益は「フクーク・アッラー(アッラーの権利)」、それ以外の規定の法益を「フクーク・アーダミーイーン(人間の権利)」と呼びます。フクーク・アッラー(神の権利)と言うと、狭義の宗教儀礼のように勘違いされるかもしれませんが、そうではなくムスリム共同体全体にかかわる公益と定義されています。フクーク・アーダミーイーン(人間の権利)は婚姻法や商法などで、個々人の事情によって判断が大きく変わるもので、当事者間で解決するのが原則で、どうしても解決できず、裁判になった場合にのみ裁判官、行政官が介入することになります。
といっても、公然と禁を破った場合は、豚を食べたこと、断食を破ったことそのものではなく、公然と神の命令を破ることで、神の法の権威の否定、ムスリム共同体全体の法秩序に対する挑戦とみなされるため、フクーク・アッラー、公益に反する罪を犯したとされ、フドゥードの一つである背教罪で罰される可能性が生じますが、それはまた別の話であり、ここではこれ以上踏み込みません。
ターウーンのハディースも原文は「もしターウーンのニュースを聞いたなら、そこには行ってはならない。もしあなたがいるところにそれが発生したらそこから逃れてはならない」とあり、個々人に対する命令であって、カリフとその代官への都市のロックダウンを命ずるものではありません。これまでムスリム諸国ではターウーンのハディースを指針に都市のロックダウンなどを行っている、と書いてきましたが、正確には、ターウーンのハディースは、カリフとその代理人にロックダウンを命ずるものではなく、個々のムスリムに都市間の移動を止めるように命ずるもので、公権力による強制が命じられていない、という点で、近代国家の感覚だと都市間移動自粛勧告、といったニュアンスです。
近代国家にも国会の作る法律の他に、法律の下に行政府の発する行政命令があるように、イスラーム法にも、クルアーンとハディースに基づくシャリーア(天啓法)の規定の範囲内で、カリフには独自の状況判断に基づいて行政命令を下すことができます。しかし、預言者の後に無謬の宗教的権威の存在を認めないスンナ派イスラームでは(12代イマームが9世紀に神隠しにあってからは、シーア派も事実上同じです)、行政命令は必ずしも神の命令に沿っているとは限りませんので、ムスリムは最終的にはクルアーン、ハディースを参照しつつ、自分自身の判断で行政命令に従うか否かを決めなければなりません。同様にカリフとその代理人たちも行政命令の発布の可否を最後の審判において神に糾問されることになります。
伝染病の対策としては罹患した者を隔離するのが良い、というのは経験的にもハディースに照らしても間違ってはいませんので、ターウーンのハディースを典拠としたCOVID-19対策としてのロックダウンの行政命令は神の命令に明白に反する、とまでは言えません。しかし前回も述べた通り、非ムスリム諸国の対応と比べると、ムスリムの対応は神の命令に従うことを求めた結果ではなく、単なる覇権国の後追いであり、現在のムスリムは、非ムスリムと同じく死の脅威を煽られ不安に駆られ領域国民国家というリヴァイアサンの偶像の命令に唯々諾々と従う偶像崇拝者にしかみえません。
私はやはり絶対的自然権、移動の「自由」を制限するターウーンのハディースは、腺ペストのような人類レベルとまではいかなくとも地方の共同体の滅亡のレベルの脅威となる伝染病にしか類推(キヤース)しないのが正しく、ハディースの知恵は現在にも通じると思っています。
4.不安の伝染と自粛警察
分子生物学者の福岡伸一はCOVID-19について「エボラ出血熱やマールブルグ病のような致命的なウィルスが攻めてきたわけではない。むしろ致死率が高いウィルス病は、宿主を殺してしまうゆえに広がることが少ない」と述べ、「世界を混乱に陥れた」のは「急速に伝播されたのはウィルスそのものというよりも、人々の不安である。これほど大きな社会的・経済的インパクトが地球規模でもたらされるとは、誰も予想できなかった。」と述べています。私もこの福岡氏の「現実的な」意見に賛成です。危険度とは釣り合わない巨大な社会的・経済的インパクトを地球規模で及ぼし世界を混乱に陥れたのは、ウィルスではなくて人間の不安であり、不安を煽ったメディアです。
「コロナ禍」が起こる前には、不安を煽るのが商売のメディアの格好の題材がイスラーム・テロでした。「コロナ禍」の後では、彼らが煽ったイスラーム・テロなどたとえ起こったとしても、通常の犯罪の誤差として無視できる些末事だったことが誰の目に明らかになったかと思いますが、そもそも起こる確率自体が殆ど存在しませんでした。実際に日本ではイスラーム・テロなど一件も起きていません。まぁ、イスラーム研究者としては、そういうデマでも、文科省や外務省がイスラーム・テロ対策のポストを設けて、イスラーム地域研究者の若手の就職先が広がりましたので歓迎ですし、この連載自体がそうした言説の産物とも言えるわけですが。「コロナ禍」はイスラーム・テロとは規模が3桁違いますが、それでも共同体にデモグラフィックな変動をもたらすようなリスクではそもそもありません。それを、世界を分断し、政治・経済・社会的混乱を引き起こす大問題にしてしまったのは、COVID-19の危険を書きたて不安を煽ったマッチポンプのようなメディアの責任が大きいと私は思っています。
前々回、パレスチナで日本人がコロナと呼ばれて嫌がらせを受けた問題を取り上げましたが、中国で発生したとされるCOVID-19問題には最初から差別と他罰的行動がつきまとっています。自分は健康であり、COVID-19をうつす他者を隔離させる自分の行動は正しく、それに従わない者は悪である、というのがその論理です。それが民族レベルで表れたのが、新しい「黄禍論」とも呼ぶべき東洋人差別でした。欧米での感染者数、死亡者数が東アジアをはるかに超えた今も、2020年5月12日付のドイツの地方紙が、デュッセルドルフにあるミシュランの星付きレストランの料理長がSNS上で「中国人はお断りだ」と書きこみ、それに対して中国系をはじめとする多くのネットユーザーから「人種差別」との批判が噴出したと報じています。
14世紀のヨーロッパでのペストの大流行に際しては、当時のキリスト教会はペストをユダヤ人のせいにし、1391年には「ユダヤ人に対する聖戦」を煽動し暴徒がユダヤ人街を襲いおよそ4万1000人のユダヤ人を殺害したと言われる他、ヨーロッパ各地で多くのユダヤ人が殺されています。現在のヨーロッパではまだこのような事態は生じていませんが、中東、アフリカでCOVID-19が蔓延し、COVID-19の感染が疑われる難民が大挙してヨーロッパに押し寄せるようなことがあれば、ヨーロッパが「先祖返り」することは十分に考えられます。中世の宗教は現代では民族であり、民族浄化が「現在の魔女狩り」です。ユーゴスラビア内戦や、コソボ紛争などで起きた民族浄化を思い返せば、デモグラフィックな大変動を伴う民族問題が今日において大きな危険を秘めていることが分かります。
この「魔女狩り」が、内側に向けられたのが、「自分は健康であり、COVID-19をうつす他者を隔離させる自分の行動は正しく、それに従わない者は悪である」という「自粛警察」です。自分は陰性であると決めつけ、COVID-19陽性であるかどうかも分からない他人を家に監禁し、外出する時は他人から離れること、マスクを着けることを強要し、あまつさえ飲食店などの営業妨害をしてまわるのが「自粛警察」で、大日本帝国の隣組を思い出させます。サウジアラビアで暮らしていた私は、「ムタウワー」と呼ばれる「宗教警察」が頭に浮かびます。
そもそも病人は犯罪者ではないので犯罪者扱いすること自体が間違い、というより罪ですが、相手が罹患者であるかどうかも分からない、罹患者であっても接触したからといっても感染するかも分からない、また感染したからといって症状が出るかも分からない、しかも自分自身が罹患者かもしれない(陰性証明があっても、それが間違っているばあいもあれば、その後に罹患した可能性があるので同じことです)と、誤った前提にたって可能性の低い憶測の上に憶測を重ねた妄想から生まれたのが「自粛警察」です。視野の狭さと独善を特徴とするこの「自粛警察」現象は、残念ながら洋の東西を問わずどこにでも存在します。
アメリカの実験心理学者アーヴィング・ジャニスは、集団がストレスにさらされ、全員の意見の一致を求められるような状況下で起こる思考パターンを「集団的浅慮」と呼び、その兆候として、以下のような特徴を挙げています。(1)代替案を充分に精査しない、(2)目標を充分に精査しない、(3)採用しようとしている選択肢の危険性を検討しない、(4)いったん否定された代替案は再検討しない、(5)情報をよく探さない、(6)手元にある情報の取捨選択に偏向がある、(7)非常事態に対応する計画を策定できない。和田秀樹先生は、この「集団浅慮」に陥った集団には、(1)自分たちは無敵だという幻想が生まれる、(2)集団は完全に正しいと信じるようになる、(3)集団の意見に反対する情報は無視する、(4)ほかの集団はすべて愚かであり、自分たちの敵だと思う、(5)集団内での異論は歓迎されない、(6)異論があっても主張しなくなる、といった行動パターンが見られる、と言います。魔女狩り、ヘイトスピーチ、宗教警察、自粛警察を統一的に見る視点です。
5.連帯義務と公益
もちろん、何をしてもよい、ということではありません。イギリスではCOVID-19の自称者に唾をかけられた駅員とタクシー運転手がCOVID-19で死亡しています。殺意をもって故意に唾を吐きかける行為をとがめるのは構いません。COVID-19とは関係なく、他人に唾を吐きかける行為は、洋の東西を問わず礼節に反する悪行だからです。そういう行為をしたわけではなく、ただこれまで通りの行動をとっていた人たちには何の咎もありません。そして重要なことは、自粛警察が犯罪者扱いしている市民にとっての自粛警察も罹患者であるかどうかも分からない、罹患者であっても接触したからといっても感染するかも分からず、また感染したからといって症状が出るかも分からないという点で全く同じだということです。つまり「自分は健康=正しい」と思い込んでいる「自粛警察」自身も、彼が罹患しているか疑わしいので罪深いとして攻撃する相手も疑わしいという点で全く同じということです。違いはただ自粛警察の被害者が、感染の可能性は小さく日常生活を失うデメリットの方がより大きい、と判断して自ら感染して死亡するリスクを引き受けて外出して行動してるのに対して、「自粛警察は」、政府の「自粛要請」の「虎の威」を借りて、自分の判断を他人に強要しようとしていることです。リスクを避けたいなら外出しないデメリットを甘受してでも自分たちが外出しない、あるいは防護衣をつける、あるいは慰謝料を用意して止めてもらうように頼むのが筋です(ご不便をおかけします、という丁寧なお願いの言葉も慰謝料の一種です)。自粛警察の論理は、休業補償という自らの責任は果たさず、「自粛要請」という語義矛盾の理不尽な強要を行う政権と同じです。しかしおそらく日本人の大半にはこの論理の方が、私が「筋」と考えるものよりもすっきりと腑に落ちるのでしょうから、もはや大幅に字数をオーバーしていますが(いつものことですが)、少し丁寧に私が言うところの「筋」を説明しましょう。特に「自粛警察」に共感する人間は洋の東西を問わず、視野が狭く、独善的ですので。
問題の根本は、自粛警察は、自分たちが公益に従っており、「自粛」しない者が、公益を無視し私益に則って行動している、と思っていることです。しかしそもそも「公益」とは何でしょう。先に述べたように、イスラームでは「公益」とはザクっと言うと、「アッラーの権利」であり、共同体全体の存続にかかわることであり、それゆえ公権力が介入すべきことです。それ以外は私益です。勿論、イスラームでは、公益であれ、私益であれ、アッラーの法に照らしてその可否が問われることは当然の前提です。公益とは私益の総和ではありません。これはルソーが特殊意志の総和としての「全体意思」と「一般意思」を区別したのに対応しています。個人の私益、欲望の総和である「全体意思」を、共同体全体の福利によって矯正したものが「一般意思」です。ルソーの「一般意思」の正確な理解は難しいので、これ以上を知りたい人は自分で調べて考えてください。「人間は個人としては有限で無力だが、類としては無限で万能である」と言ったのはマルクスですが、個人は遅かれ早かれ死ぬものであり、重要なのは個人の生死ではなく、共同体の存亡です。まぁ、人類もそのうち滅びますが、まだもうしばらく時間があると思いましょう。そう思わないと話が終ってしまいますので。
COVID-19はかつてのペストのような「恐ろしい」伝染病と違い、人類レベルでも国家や地方都市のレベルでも共同体の滅亡をもたらすようなリスクはありません。そもそも医学が未発達で治療法もなかった時代のペストの流行で、人類の総人口が4億5千万人しかいなかったところに1億人が死んで3億5千万人にまで減っても人類は生き延びたのです。医学が発達し人類全体で80億人、日本には1億2千万人も人間が存在する現在、極端な話、人口が10分の1に減っても生物学的レベルでは共同体は生き残れるかもしれません。しかし問題は単純に人口総数ではなく人口構成です。日本の人口が1年に44万人以上減っているのは死亡数が出生数を上回り、その差が増え続けている、つまり高齢化が進んでいるからです。ですから日本で人口の9割が死んで10分の1に減っても各世代が一律に死んだのなら、その後に若者が尊重され希望が持てる社会になり出生率が回復しさえすれば日本は蘇ります。しかし人口の3割が死ぬだけでも、それが30歳以下に集中すれば日本は百年絶たずに滅亡するでしょう。その意味でも幼児死亡率が高いインフルエンザと違い、死亡者が高齢者に偏っているCOVID-19は大きな脅威ではありません。つまり、COVID-19問題は共同体の存亡にかかわるような公益に関する問題ではなく、個人のライフスタイルの好悪、私益の問題でしかない、ということです。公益に関する議論とは人口減、高齢化対策のようなものを言うのです。
私益が重要でない、と言っているわけではありません。逆です。私益は個々人にとってはかけがえなく大切なものです。中でも生命はそうです。しかし、それは自分にとってだけであり、他の人間にとっては大切でもなんでもなく、その尊重を求めることは倫理的に不可能だということです。ヴィトゲンシュタインなら「倫理の文法において」とでも言うところでしょう。他人に倫理的に求めることができるのはせいぜい人類全体、あるいは民族や国家の存続を脅かす行為を避けることだけです。もちろん、人類、国家、民族、共同体などどうでも良い、取りあえず周囲のものに迷惑をかけなければそれでよい、という価値観も存在します。ただそういう人たちとはそもそも倫理の議論が成立しないので、ここでは無視します。倫理学の議論に慣れていない読者のために、蛇足ながら補足を加えると、どんな共同体もどうでも良い、という人間とは倫理の議論が成立しない、ということはそういう人間を殺してしまえ、ということでもなければ、一緒に仲良く暮らしていくことができない、ということでもありません。飼い犬と倫理的な議論が成立しなくても仲良く一緒にくらしていけるのと同じ、というシンプルな話です。
客観的、理性的に公益を論ずることと主観的、感情的に私益を主張することは厳密に区別しなければなりません。人類の視点に立って倫理的に論ずる場合には、自分にとって得か、日本人の利益になるか、などといった私益を顧みず、シリア軍の連日の空爆で樽爆弾で殺されているイドリブの市民、イエメンでサウジアラビアとその同盟国によって包囲され飢餓と伝染病で命を失っているサナアの子供たちも自分と同じ一人の地球人として平等に扱われるために何をすべきか、を考えなければなりません。日本人として倫理的に論ずるなら縁もゆかりもなくとも、原発事故の被害によって未だに自宅に戻れない福島の人々、米軍基地の存在に苦しめられている沖縄の人々がどうすれば日本人として自分たちと同じ生活ができるかと心を配らなくてはなりません。
しかし私的領域では私たちは法が許す範囲で自分たちのことだけを考えればよく、遠く離れた見も知らぬ人のことなど考えなくても構いません。そもそも70億人を超える人類全体のことを考えることなど不可能ですから、知りもしない人間に同情するふりなどする必要はどこにもありません。イスラームは、公共の安全と秩序の維持に責任を持つカリフとその代理人には、「フドゥード(イスラーム刑法)」の執行と、私人間の「人間の権利(フクーク・アッラー)」を巡る訴訟の裁定においては、私益を離れてあらゆる人間をイスラーム法が定めるカテゴリーに則り平等に扱うことを命じていますが、私人にはすべての人間を平等に扱えなどとは決して求めません。むしろ預言者ムハンマドは「アッラーの道に費やした1ディーナールと、奴隷解放に費やした1ディーナールと、貧者に施した1ディーナールと、あなたの家族のために費やした1ディーナールの中で最も(来世での)報酬が多いのはあなたの家族のために費やしたものである」(ムスリムの伝えるハディース)と述べて、貧者への施しよりも家族の扶養を優先するように教えています。
COVID-19の話に戻ると、COVID-19は共同体の存亡のかかった公益の問題ではないので、公権力は医学、公衆衛生、経済などを総合的に考慮して他の伝染病とバランスのとれた扱いをすることが求められます。公益と私益を区別すれば、医療崩壊への懸念にも別の見方をすることが出来ます。COVID-19問題は、はからずも日本の人工呼吸器不足の実態を露呈させました。医療機関に人工呼吸器を充実させるべきだ、という議論は一般論としては異議はありませんが、COVID-19への対応としての妥当性には疑問があります。
たとえば、『ビジネスインサイダージャパン』は、「48時間治療をしても回復しなければ場合によって人工呼吸器を外す」といったニューヨーク州の人工呼吸器の使用方法に関するガイドラインの一部と「人工呼吸器があれば助けられるのに、人工呼吸器が無い……。一方で、あと数日で亡くなってしまう可能性が高い患者に人工呼吸器を使い続けている……」との新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の会見での武藤香織教授の発言を引用し、自分たち自身が「あと数日で亡くなってしまう可能性が高い患者から人工呼吸を取り外しその分を助けられる患者の治療にあてる」との「この究極の選択を問われる当事者であることを強く意識させる」と書いています。
こうした当事者面をしたお為ごかしの感情論の綺麗ごとがはびこるのも、視野狭窄の私益と公益の混同のせいです。患者の家族であれば家族のためにできるだけのことをしたいと思うのは当然です。また医者とは目の前にいる患者であれば1秒でも長く生かそうと務めるのが職業倫理です。しかしそれは私益であり、他の人間には関係のないことです。実はニューヨーク市周辺でCOVID-19患者2600人余りを対象とした大規模研究で対象となった患者の死亡率は21%でしたが、人工呼吸器が必要になった重症者の死亡率は88%、65歳以上の人工呼吸器使用者の生存率はわずか3%だったことが明らかになっています。要するにCOVID-19患者に限れば人工呼吸器の効果は極めて低いのです。
世界中のすべての病人の手に全ての必要な医療器具を届けることができる状況にあるなら、全てのCOVID-19患者に人工呼吸器を用意するのも良いでしょう。しかしユニセフ協会によると、2017年において8億4,400万人が清潔な飲料水にさえ事欠き、不潔な水を飲むことで命を落とす乳幼児は年間30万人、毎日900人以上にのぼっています。清潔な飲料水さえあれば死ななくて済む乳幼児を毎日900人も平気で見殺しにしておきながら、殆ど救命の役に立たたないCOVID-19患者につける人工呼吸器が不足していて誰に回すかを医者が選ぶことを「究極の選択」と深刻がってみせ、人工呼吸器を買い揃える権限と責任、それを患者に使う権限も責任もないただの部外者に当事者だと錯覚させるような詐術も公益と私益の混同から生じます。
6.ブラック労働への呪縛からの解放から公正な社会へ
権限も責任もない人間が、自分の私益にすぎないものを公益のごとくに見せ掛けて他人を支配する詐術の一つが、医療関係者や運送業者などを「なくてはならない」と持て囃しブラック労働に呪縛するお為ごかしの呪いの言葉です。こうした呪いの言葉は世界中で普遍的に見られますが、中でも特に主語が曖昧な日本でよくみられるように感じます。医療関係者にしろ、運送業者にしろ、高級を取っている役人や大企業の役員たちが快適で安全な暮らしを送るために、その人が「働かなければならない」理由は一つもありません。嫌なら辞めればよいのです。少なくとも、こういう呪いの言葉が口にされる「先進国」では辞めても生活保護が受けられ、死ぬことはありません。そうすることによってはじめてそれらの人々が、ブラック労働から解放され、その社会的有用性に相応しい給与と待遇を受けることができるようになります。
COVID-19に対する自粛要請の唯一の良かった点は、今までいかにも「しなくてはならない」と言われてきた仕事のほとんどが不要不急であったこと、そして多くの民間企業が大打撃を受ける一方で、COVID-19対策に国家が介入すべきとの声を利用し、「アベノマスク」のような無用の長物に不透明な巨額の資金が投入されたことが明らかになったことです。ですから、本当になすべきことは、現在の不正な搾取のシステムを支えている医療関係者や運送業者などに、「『外で働かなければならない』人たちのことを考えろ」などと猫なで声でブラックな環境に労働者を「呪縛する」呪いの言葉をかけることではなくて、「あなた方は不当な条件でブラックな職場で働き続ける必要などない、辞めて良いのだ」と解放の言葉を贈ることです。
ここでもイスラームの考え方を紹介しておきましょう。既述のようにイスラームでは、義務を全ての責任能力者が行うべき個人義務と、誰かが行えば他の人々は免責されるが誰も行わなければ共同体の全員が罪に陥る連帯義務に分けます。イスラーム教育やジハード(聖戦)、イスラーム刑法の執行のような宗教行為だけでなく、農業、製造業、医学など共同体に必要な仕事も連帯義務になります。自分が何の責任も負わず相手の立場に立ったふりをして呪いの言葉を述べるのではありません。連帯義務とは、他の誰もが行わなければ、自分も神の前で罪を犯したことになる、義務です。医療関係であれ、運送業であれ、「外に出て行わなければならない」のは今そこで働かされている人間ではなく、それを必要とする社会の全ての人間であり、その人間がブラックな環境に耐えかねて「職場放棄」をしたとしても、罪に陥るのは、その者だけではなく、全ての人間が連帯責任でその罪を負うのであり、全ての人間が実際に最後の審判で裁かれる当事者になるのです。イスラームの国法学者イブン・タイミーヤ(1328年没)は、ムスリムが連帯義務を負うような社会が必要とする仕事で、労働者が正当な権利を奪われ不当に働かされることがないようにすることが、為政者の義務であると述べています。
7.終りに
連載も最後なのでまだまだぜんぜん言い足りないのですが、また大幅に字数をオーバーしてしまったのでそろそろお別れです。最後に思いっきり大雑把な話をして締めくくりとしましょう。
COVID-19の感染には、韓国のキリスト教カルト「新天地イエス教証しの幕屋聖殿」や、イタリアのカトリック教会、イランのシーア派聖廟などがクラスターになって感染が広がったことが大きく報じられたこともあり、「宗教と科学の対立」というヨーロッパの啓蒙主義以来の議論が蒸し返されることになりました。日本の優れた宗教学者の中村圭志先生は、コロナ禍は相当な長期にわたって「端的に合理的に振る舞う」ことへの圧力が持続するため、宗教にとって大きな打撃となり、神学者・教学者はコロナ禍を切り抜けても、一般信徒は宗教に飽き、宗教の空洞化が進む公算が高い、と予想しています。
この連載でたびたび繰り返している通り、私は現在の世界には、自称他称のムスリムの実践を含めて実際に存在する宗教はほとんどリヴァイアサンとマモンの偶像崇拝でしかなく、そんな宗教の延命にはなんの興味もありません。しかし、コロナ禍によって科学が進歩し人類の行動が合理化する、という中村先生の楽観には与しません。というのは、科学は事実しか語らずそこにはいかなる規範も存在しないからです。「存在するものは合理的である」とは哲学者ヘーゲル(1831年没)の言葉ですが、科学の世界には善も悪もありません。存在するものはただあるがままにあり、次の瞬間にはただ消えさるのみです。
「知者の目は、その頭にある。しかし愚者は暗やみを歩む。けれども私はなお同一の運命が彼らのすべてに臨むことを知っている。私は心に言った、『愚者に臨むことは私にも臨むのだ。それでどうして私は賢いことがあろう』。私はまた心に言った、『これもまた空である』と。そもそも、知者も愚者も同様に長く覚えられるものではない。きたるべき日には皆忘れられてしまうのである。知者が愚者と同じように死ぬのは、どうしたことであろう。」(『旧約聖書』「コヘレートの書」2章14-16節)」
人間が科学的真理に則って暮らそうと、迷信と狂信に生きようと、清廉潔白を貫こうと悪逆非道を尽くそうと、愛する家族に囲まれて希望に満ちて幸せに生きようと、病苦と絶望のうちに孤独死しようと、科学的にはすべてただの粒子の離合集散でしかなく、その間にいかなる違いもありません。ただ無意味に生きて無意味に死んでいくだけです。そもそも科学的に生きることが、「現世的」に「有益」かどうかさえ疑わしいものです。世界の長寿者のリストを眺めても著名な科学者の名前はみつからず、ギネスの日本の最高齢の田中カ子さんは1903年、農家の9人兄弟の三女第7子として生まれ1915年に小学校を卒業後12歳から子守奉公をし1952年にキリスト教に入信し現在に至っており、第二位のシスター・アンドレさんは1904年生まれのカトリックの修道女です。幸せに長生きするのに科学的思考が必要と言うわけでもなさそうです。日本の宗教学者島田裕巳先生によると、職業別平均寿命は宗教家がダントツで第一だそうです。
それはともかく、「科学的であれ」という科学主義の主張は科学の命題ではありません。科学主義者にとって重要なのは科学の教える事実そのものではありません。科学主義者にとっての科学は依存症患者の酒、賭博、麻薬、SNSのようなものです。「科学依存」もまた、生きることには価値はなく、誰もが遠からず無意味に死ぬ、という事実から目を逸らす暇つぶしになる、ということです。科学もまたリヴァイアサンやマモンと同じく人間の欲望が虚空に映し出す幻影であり、人を奴隷にする偶像にすぎません。
中世ヨーロッパではペストの流行は、絵画の「死の舞踏」のモチーフを生み、古代ローマでは快楽主義的標語であった「メメント・モリ(死を想え)」を、死を日常的に意識する内省的なキリスト教倫理の格言に変えました。
人口が半減したような凄惨なペストとちがい、COVID-19はメディアのヒステリックな過剰反応とは裏腹に身の回りでほとんど死者を目にすることはありません。私自身、会う人毎に聞いていますが、直接の知り合いで陽性反応が出た者は一人もいません。知り合いの知り合いでのレベルで、入院して回復したタクシー運転手の知人が一人いるだけです。これではペストの流行のように万人が死と向き合う、といった実存的経験を日本社会全体に求めることは期待できません。しかし、自粛要請で、強制的に職場を離れさせられたことで、今まで「自分がいなければこの職場は立ち行かない」、「自分が働かねばならない」、「自分の会社が国を、社会を支えている」と洗脳されていた人たちの一部は、「不要不急」の烙印を押されたことで、無意味な虚業と無駄な消費に忙殺させることで現世のあらゆる欲望を無価値化する死を忘れさせる物質主義と資本主義の呪縛による微睡から一瞬であれ覚醒しました。
預言者ムハンマドは「人々は眠っている。死んではじめて気づく」との言葉を残しています。コロナ禍は、世界中に600万人を超える感染者、40万人にせまる死者を出し、航空会社の国際線の運航停止、外出自粛、ロックダウンなどのせいで1930年代の世界大恐慌以来の経済危機をもたらしたのみならず、失業、貧富の格差の拡大、人種・民族差別、排外主義の高揚、非常事態を口実とした国家権力の強化などの様々な社会問題を生み出しています。コロナ禍を奇貨として、自分がいつ死ぬかわからない儚い存在であることに気づいた読者諸賢が再び微睡に戻ることなく、いずれ死に逝く人間にとって本当に必要なものが何かを見出されることを望んでやみません。長い間、連載にお付き合いいただきありがとうございました。ではまたお会いする日まで。
「不幸に見舞われた時に『我らはアッラーのもの。彼の許へと帰り逝く』と言って耐え忍ぶ者たちに吉報を告げよ。」(クルアーン2章155‐156節)
ワッサラーム
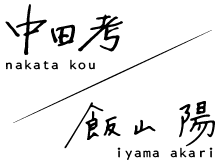 中田考(なかた・こう)
中田考(なかた・こう)
1960年生まれ。イスラーム法学者。灘中学校、灘高等学校卒業。早稲田大学政治経済学部中退。東京大学文学部卒業。東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。カイロ大学大学院文学部哲学科博士課程修了(Ph.D)。1983年にイスラーム入信、ムスリム名ハサン。現職は同志社大学一神教学際研究センター客員フェロー。『イスラーム国訪問記』『みんなちがって、みんなダメ』『カリフ制再興 ―― 未完のプロジェクト、その歴史・理念・未来』『13歳からの世界征服』など著作多数。最新刊『ハサン中田考のマンガでわかるイスラーム入門』(サイゾー)。
飯山陽(いいやま・あかり)
1976年生まれ。イスラーム思想研究者。アラビア語通訳。上智大学文学部史学科卒。東京大学大学院人文社会系研究科アジア文化研究専攻イスラム学専門分野単位取得退学。博士(東京大学)。現在はメディア向けに中東情勢やイスラムに関係する世界情勢のモニタリング、リサーチなどを請け負いつつ、調査・研究を続けている。著書に『イスラム教の論理』(新潮新書)、最新刊『イスラム2.0』(河出新書)。