天気・体・社会。そこに関わる予感と予測の力。農家も流通業者も病気の人も、天気の恵みにあずかりながらも、ときに荒ぶるその流れにいかに沿うか腐心してきた。天気は予測できるのにコントロールできないという点で身体に似ている。どうやったら私たちは、天気とともに暮らし、社会を営むことができるのか。天気・体・社会の三者の関係を考える、天気の身体論/身体の天気論。
自然と人体の関係を読む
私たちの体の状態は日々変化しています。つまり「体調」があります。
何が体調を変化させるのか。要因はさまざまですが、もっとも大きくまた普遍的な要因のひとつは「天気」でしょう。
医学の父ヒポクラテスも、季節の変化や空気や水や熱が人体に与える影響の大きさを力説しています。「医者は未知の町に着いたならば、その町の位置が風の点と太陽の昇りの点からいってどうであるかをよく吟味しなければならない」[1]。ヒポクラテスにとって「天文学の医学に対する貢献は絶大」なのです。
それまで、病気は迷信や呪術と結びついていると考えられていました。それを科学の領域にまで押し進めたのは、まさに「自然と人体の関係を読む」というヒポクラテスの観察的な態度でした。自然の中に、人体にとって重要な「兆候」を見出すこと。「以上のような具合に考察し、時期を予知するならば、個々についてもっともよく知り、もっともよく健康を得、もっともよく医術の施行に成功をおさめることができるであろう」[2]とヒポクラテスは言います。
近代医学が発達した今でも、私たちはしばしばこうした「観察」を行っています。日々変化する自然の中には、医師のような専門家でなくても気づくことのできる、さまざまな「兆候」があります。いやむしろ、そうしたアマチュアの観察眼の中にこそ、診察室からこぼれ落ちるものを救い上げる力があるのかもしれません。
「今年の梅雨は頭痛が特にひどい…」
「季節の変わり目はどうも夕方になるとかゆみが出やすいようだ…」
天気のせいで体調がすぐれなかったり、振り回されたりするのは、しんどいものです。さいきんでは「気象病」などという言葉も耳にするようになりました。
しかし見方を変えれば、それは私たちの体が地球と連動している証拠でもあります。惑星規模の大気の流れや水の循環が、地球からすれば芥子粒ほどのこの物体にも、着実に影響を及ぼしている。当たり前とはいえ、ちょっと不思議な気持ちになります。
地球をすみかとするかぎり、私たちは天気と無関係には生きられません。それが地球型生命の宿命だとしても、なんとかしてその変化とうまく付き合いたい。寒い日には温かいものを食べたり、頭痛が起こりそうな日はあらかじめ外出を控えたりします。
障害や病気があると、その種類によっては、天気との付き合い方はよりシビアになります。フィリピン沖で台風が発生しただけで耐え難い痛みを感じる人がいます。季節ごとに、まったく違うタイプの痺れを感じる人がいます。日々の体調の変化が激しすぎて、全く予定が立てられない人がいます。これらは、地球からの影響に対して、よりダイレクトに、ダイナミックに反応してしまう体です。
そのような体をもつ人々は、まさに古代ギリシアの医者たちのように、環境にあらわれる兆候を細やかにとらえながら、その波とうまくつきあうすべを探っています。観察を続けるうちに経験が蓄積され、知が形作られます。やがて知が共有され、コミュニティが生まれます。「気圧が下がってるね」「今日はてんかんが起こるかも」。天気により近いところで生きている人たちは、SNSなどでお互いの情報を交換し、ともに空模様を気遣うネットワークを作り上げます。
本連載では、このような「天気に巻き込まれながら生きる人々」が、そのことによってどのような時間感覚や空間感覚をもち、さらには天気を中心としたどのようなコミュニティを作り出しているか、また時計やカレンダーを基準とする近代以降の社会と自らの体をどのように調停させているのか、そのさまざまな事例を見ていきます。彼らはときに天気の変化を乗りこなすサーファーのようであり、ときに離れた町の情報を交換しあうスパイ集団のようでもあります。
でも彼らにもっともよく似ているのは、むしろ農業や漁業、あるいは林業を営む人たちかもしれません。山の色を見て田植えの時期を決める。海の匂いから漁に出るタイミングをさぐる。本連載は、私の研究上の専門である障害や病気を持つ人々の事例を中心的に扱いますが、そうした当事者たちの言葉と、農業・漁業・林業などに従事する方たちの言葉を同列に並べてみたいなと思っています。「気圧の変化で後頭部が痛むこと」と「雷雨で稲穂が倒れること」は、人間にとってどのくらい近く、あるいは遠い出来事なのでしょうか。
共通しているのは、やはり「兆候を読む」という態度です。面白いのは、そこには常に、ある種の「とどかなさ」があることです。
天気は、信じられないほど複雑な現象です。人工衛星とビックデータを駆使した天気予報ですら外れることがあります。だからこそ体に関しても「いつもならこの時期に出るはずの痛みが出ない」など、イレギュラーな出来事もしばしばでしょう。
私たちはつい、Aという出来事とBという出来事が繰り返し同時に起こると、その二つを「Aが起こったからBが起こった」という「因果関係」で結んでしまいがちです。けれども、この発想じたいがかなり人間的なものにすぎません。天気という現象には無数の要因が関係しており、さらにそれらが相互に依存しているという意味では、むしろ「縁起」に近いものでしょう。
その無限に変化する複雑な網のなかに、人は何らかの兆候を見たと思い、自分の体調や行動のヒントを探し求めます。まさに巻き込まれるしかない天気という相手。彼方からのしらせを聞き取りながら、ダイナミックな体のすがたを描き出してみたいと思います。
[1] ヒポクラテス(小川政恭訳)「空気、水、場所について」『古い医術について』、岩波文庫、1963年、7頁
[2] 前掲書、8-9頁
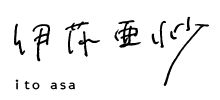 東京大学大学院人文社会系研究科美学芸術学専門分野博士課程修了(文学博士)。専門は美学、現代アート。現在、東京工業大学科学技術創成研究院未来の人類研究センター長。リベラルアーツ研究教育院教授。主な著書に『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社新書)、『目の見えないアスリートの身体論』(潮新書)、『どもる体』(医学書院)、『記憶する体』(春秋社)、『ヴァレリーの芸術哲学、あるいは身体の解剖』(水声社)、『手の倫理』(講談社選書メチエ)などがある。
東京大学大学院人文社会系研究科美学芸術学専門分野博士課程修了(文学博士)。専門は美学、現代アート。現在、東京工業大学科学技術創成研究院未来の人類研究センター長。リベラルアーツ研究教育院教授。主な著書に『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社新書)、『目の見えないアスリートの身体論』(潮新書)、『どもる体』(医学書院)、『記憶する体』(春秋社)、『ヴァレリーの芸術哲学、あるいは身体の解剖』(水声社)、『手の倫理』(講談社選書メチエ)などがある。

