天気・体・社会。そこに関わる予感と予測の力。農家も流通業者も病気の人も、天気の恵みにあずかりながらも、ときに荒ぶるその流れにいかに沿うか腐心してきた。天気は予測できるのにコントロールできないという点で身体に似ている。どうやったら私たちは、天気とともに暮らし、社会を営むことができるのか。天気・体・社会の三者の関係を考える、天気の身体論/身体の天気論。
ポテチショック
いつでもどこでも、食べたいときに食べたいものが食べられる。特に都会で暮らしている私のような生活者は、ついついそのような錯覚を抱いてしまいがちです。クーラーの効いた真夏のスーパーで、冬野菜の代表である白菜を手に入れることができる。もともとは春が旬であったはずのイチゴを、クリスマスケーキのために買うことができる。もちろん旬の野菜や果物の美味しさは格別ですが、消費者の「食べたい」という欲望は、夏だろうが冬だろうか、天気の条件にかかわらず叶えられるものだ。そんなふうに思ってしまいがちです。
ところが2017年春、そんな幻想を撃ち壊す出来事が起こりました。いわゆる「ポテチショック」です。まさにお菓子売り場の不動の王者と思われていたポテトチップスが、スーパーの店頭からも、コンビニの店頭からも、一斉に消えたのです。少ない商品をめぐって買い占めが起こり、一時はネットオークションで高値で売り出されるさわぎにまで発展しました[1]。
原因は、前年にじゃがいもの主要産地である北海道を襲った台風と長雨による影響でした。北海道といえば「梅雨がない」「台風が来ない」が常識です。しかしこの年は違いました。6月から7月にかけて晴れた日がほとんどないほどの日照不足だったのに加え、経験したことのない量の雨が降り続いたのです。河川が氾濫して多くの畑が水につかり、畝のあいだに水がたまってじゃがいもが腐ってしまった。メーカーは原料の7-8割を北海道産じゃがいもに依存していたため、この影響は大きく響きました[2]。
ポテトチップスといえば、「工場から出荷される」というイメージが強い食品です。もちろん実際にそうなのですが、その背後には、畑にたねいもを植えて育て、太陽の光をあびて大きく太ったいもを収穫するという、農業のプロセスがあります。にもかかわらず、生鮮食品として売られている野菜や果物に比べると「工業」の印象が強いため、なおさら「一年中いつでもどこでも食べられて当然」と思ってしまう。農業は自然とのかかわりであり、変動がつきものです。2017年のポテチショックは、そのことをまざまざと実感させた出来事でした。
そもそも、自然という思い通りにならないものと、高度にシステム化された人間の消費活動を結びつけるとは、いったいどのような営みなのでしょうか。確かにスーパーやコンビニの商品棚だけ見ていると、よくも悪くも季節を感じないほどまでに「いつでもどこでも」が実現されているように思えます。しかし、弱まったのはあくまで「自然感」であって、自然の変化そのものがなくなったわけではありません。商品の陳列棚が見せる「いつでもどこでも」のポーカーフェイスの背後には、変化する自然に緻密に応答し、そうすることで表面上は変化を見えなくするような、何らかの仕組みがあるはずです。
自然と人間的システムの接続。この問題を考えるために、今回は、実業家・松尾雅彦の思想に迫ってみたいと思います。松尾は、カルビー株式会社の三代目社長(1992-2005年)をつとめた人物であり、同社では「じゃがりこ」や「フルグラ」を世に送り出して、「カルビー中興の祖」と呼ばれました。
もっとも、松尾がカルビーで社長を務めていたのは二十年近くも前のことです。ポテチショックとも時期は違いますし、彼の思想は必ずしも現在のカルビーの方向性とぴったり一致するものではないでしょう。しかし、彼の思想を追っていくと、単なる一企業の営利活動という枠を超えて、天気の変動とうまく付き合い、そのズレを大量生産の仕組みのなかで吸収していくためのさまざまな創意と哲学が含まれていくことに気がつきます。以下では、あくまで彼個人のものとして、その思想を読み解いていきたいと思います。
「かせぎ」と「つとめ」
『日経ビジネス』(日経BP)2007年2月19日号に、取締役相談役時代の松尾への取材記事が掲載されています。記事のタイトルは「「頑張らない」姿勢が次の革新を生み出す」。大企業の取締役相談役としてはいささか意外な言葉が語られています。
私自身、営業が得意でなかったためもあり、カルビーにはいまだに「営業ノルマ」がありません。「頑張って」取引先に押し込むようなやり方では、革新が生まれないからです。
日本中どこのお菓子売り場でもおなじみのポテトチップスの会社に営業ノルマがなかった、というのはかなりイメージとは異なる印象を受けます。それどころか、無理して販売するようなことをしてはいけない、と言う。その理由を松尾は、2014年に出版された著書『スマート・テロワール 農村消滅論からの大転換』(学芸出版社)で、当時のカルビー会長兼CEO松本晃の言葉をひきながら、こんなふうに説明しています。
外資系企業出身者である松本晃カルビー会長兼CEOは、販売目標の評価について、「目標の達成率が一〇〇〜一〇一%だとマル評価、しかし一一〇%の場合はバツ評価」と述べています。
目標を超えるような成果を出すことが、どうしてバツ評価されるのでしょうか。その理由は、約束が一〇〇のところで一一〇になると、自分の欲は満足しますが、関係する多くの人々の計画が崩れ、ムリをしなければならなくなるからです。目標どおりであれば、休暇も計画どおりに取ることができます。長期的に見ればスタッフも無理せずにいられるので、全体にとっての利益につながります。[3]
ここにあるのは、人々の仕事を全体の連関のなかでとらえようとする、松尾の利他的とでもいうべき発想でしょう。一〇〇だった目標に対してそれを超える一一〇が達成されると、自分にとっては成功かもしれません。しかし、それは販売員や工場で働く人に無理を強い、生活から余暇を奪うことになってしまう。人々は不幸になり、その結果、物が売れなくなるとしたら、それはめぐりめぐって自分の首を締めることになるでしょう。利益の追求を至上命令と題した結果、、利益が失われてしまう。この本末転倒な負のスパイラルこそ、今の日本の流通業界が陥っている病だ、というのが松尾の見立てです。
このことを考えるうえで手がかりとなるのが、松尾が用いた二つのキーワードです。それは、「かせぎ」と「つとめ」。松尾にとって、これらの言葉は、地理的に異なる場に対応していました。
最初の「かせぎ」の方は、都市に活力を生む原理です。利益を追求するという経済的な活動が都市を活気づけ、多様性を生み出すのです。一方で「つとめ」は、農村に活力を生む原理です。それは暮らしの価値を生み出していく共同体の力であり、その根本にあるのは、暮らしの価値の源泉は自然環境からやってくるという自覚です[4]。
営業ノルマのために頑張ることは、「かせぎ」の原理です。しかし、それだけでは暮らしはよくなりません。にもかかわらず、現代では農村にまで「かせぎ」の原理が入り込むようになっている。松尾が例としてあげるのは、1980年代の軽井沢の例です。この頃、バブル経済を背景に、大手スーパーが軽井沢に店を出しました。その影響で地元の小規模の商店はのきなみ閉店してしまいます。ところがバブルが崩壊すると、大手スーパーはあっという間に撤退してしまう。「かせぎ」が中心の都会の企業は、自分の都合で出店し、事情が変われば撤退します。出店して地域の商店を潰し、撤退すると住民に不便を押し付けます[5]。
こうしたことが、軽井沢のみならず日本各地の地方都市で起こっていることは、わざわざ付け加えるまでもないでしょう。その土地に長く居続けるということが「つとめ」の始まりであり、「つとめ」を果たすからこそその土地に長く居続けられる。松尾は言います。「都市の経済とは異質の文化の柱を立てることが日本にとって重要なことを承知して関係を持ってください」[6]。
収穫は年に一度、鮮度は365日
では、「かせぎ」の原理である営業ノルマの代わりに、松尾がカルビーの社長として設定した目標は何だったのでしょうか。
それは、ずばり「鮮度」でした。ポテトチップス=工場生産のイメージにしばられていると意外な気がしますが、ポテトチップスにも鮮度があるのです。新鮮なポテトチップスを食べてもらうことが、カルビーが顧客とのあいだに交わすべき約束だ、と松尾は考えたのです。
その代わりに、店頭でのポテトチップスの鮮度を高めることを目標にしました。……古くなると油が傷むということで、お客様から信用されません。古い商品を店頭からはずし、お店にはたくさん買わなくていいから、売れた分だけこまめに補充してくれとお願いしました。そうすれば、鮮度の良いポテトチップスを消費者が食べられるようになります。
その実現のためには、工場からお客さまにいかに素早く届けるかが勝負になります。そこで、菓子業界の常識であった販売促進の制度を改め、流通のしくみを見直しました。つまり、売ることを目的とせず消費者に品質を提供することを目指したわけです。[7]
実際、カルビーの営業担当者の重要な仕事は「鮮度を確保すること」でした。今回の原稿を書くにあたって、現役のカルビーのマーケティング本部本部長の松本知之さんにお話をうかがうことができました。松本さんも、営業担当だったころは、「鮮度調査ばっかりやっていた」と言います。「上司が「鮮度の鬼」と言われていた人で、しょっちゅう指導されていました。売り上げが悪いのは別に怒られないのですが(笑)。担当している全店舗をまわって、他社商品もふくめて、店頭にならんでいる商品のうち製造年月日が一番古いものの日付を入力していくんです。古いものは買い取ってしまったり、回転の悪い商品は「景品をつけて週末に売ってみましょうか」みたいな提案をしたりしていました。きわめてきめ細かい店舗活動でした」。つまり、多く売るために鮮度を保つのではなく、鮮度を保つために売る量を調整していたのです。
ここで注意しなければならないのは、「鮮度を保つ」といっても、「工場からなるべく早くとどける」というような単純な話ではない、ということです。そもそも、「ポテトチップスの鮮度」というのは、ある意味では奇妙な概念です。なぜなら、そもそもじゃがいもの収穫は年に1回しかないからです。つまり、材料として使えるじゃがいもの総量は最初から決まっている。この決められた量のじゃがいもを、1年かけてとぎれなく、常に余らせず、決して足りなくさせず、毎日適切な量だけポテトチップスに加工して、店頭にとどけていくこと。松尾の言葉を借りるなら、この「農業」―「加工」―「流通」という3つのステップを一体的にとらえることが、「鮮度の良さ」のためには必要なのです。
だから、「カルビーのマーケティングは泥臭い」と松本さんは言います。一般にマーケティングといえば、キャッチコピー等を用いて商品をうまくブランディングしていく「広告」の仕事だと思われています。しかしカルビーの場合は、農業や物流のことも考えながら、今日売る量のことを考えていかなければならない。ある時期だけどーんと売れるようなことをしてはだめで、いかに365日途切れなく売っていくかを考えるようなマーケティングが必要なのです。じゃがいもが余りそうだったら店頭でキャンペーンをする。逆に足りなそうだったら店に並べる袋数を減らす。松尾が鮮度のために求めたのは、そんな畑の事情を意識したマーケティングでした。松尾は、需要と残席数によって価格が決まる飛行機のチケットのように、ポテトチップスの値段をそのつど変える構想まで持っていたそうです。
工場での加工のレベルでも、鮮度を保つためにさまざまな調整がなされています。まず、産地によって収穫のタイミングが違いますから、それに合わせて加工地や加工量が調整されています。さらに、すぐに使わない分のじゃがいもは貯蔵庫に入れられ、商品ごとに最適化された温度・湿度・二酸化炭素濃度環境下でしばらく「寝かされ」ます。しかし、完璧に寝かせることは難しいため、5月ごろに芽が出てしまうものもある。そのようなじゃがいもは早めに加工に回され、きれいに芽をとる処理をされます。
常に、じゃがいもの状態や売り上げの予測に応じて、そのときどきに適した原料、適した工場で加工を行っていく。そのため、カルビーのポテトチップスは、ひと袋ごとに「履歴」が違います。この「履歴」は、それを手に取った消費者にも分かるようになっています。袋をひっくり返すと、裏側の隅に「製造所固有記号」や数字と英字からなる記号が印字されています。QRコードから専用サイトに飛び、これらのデータを入力すると、袋の中身がどこの誰の畑で生産された何という品種のじゃがいもであり、どの工場で生産されたものなのかを知ることができます。
ここにあるのは、自然の恵みとしての収穫量を起点におき、それに合わせて細やかな調整を重ねていくようなビジネスのあり方です。これは言い変えれば、売り上げの少なさを自然のせいにしない、という発想です。収穫の量が多ければ多いときの売り方があり、少なければ少ないときの売り方がある。ポテトチップスに向かないじゃがいも多く獲れれば、「じゃがりこ」のような違うタイプの商品にすればいい。売り上げが少ないのは、自然の変化に人が対応しきれなかったからであって、先のポテチショックも、その本質は自分達がうまく調整をできなかったという理解をしているそうです。「いつでもどこでも」のポーカーフェイスの背後にあるのは、天気から切り離された人工性とは真逆の、天気の変動に沿おうとする細やかな応答の結晶なのです。
地域社会を育てる農業
ここまでですでに明らかなように、松尾は大量生産の世界でビジネスを行いながら、その根底には重農主義者としての価値観を持っていました。「かせぎ」一辺倒の世界でいかに「つとめ」を果たしていくか。松尾は述べています。「今、日本では「重商主義」が優勢で「重農主義」が侵されていることに大きな原因があることに気がついたのです」[8]。
その姿勢は、カルビーの農家との関係に具体的にあらわれています。同業他社が農協を介してじゃがいもを調達していたのに対し、カルビーは契約栽培制度をとったのです。契約栽培とは、加工する側があらかじめ購入する数量と価格を決めてから栽培に入る仕組みのこと。価格が事前に決まっているので、豊作で相場が下落しても、農家は買い叩かれる心配がありません。松尾は、世界で初めて冷凍フレンチフライの製造に成功したアメリカの実業家J・R・シンプロットにこの方法を学び、日本に持ち帰って全国展開しました[9]。
ただし、カルビーの契約栽培とJ・R・シンプロットの契約栽培では、決定的に違うことがありました。それは、天候リスクの扱いです。J・R・シンプロットのやり方では、天候リスクの受け持ちは会社と生産者でフィフティ・フィフティでした。ところが、カルビーの場合は、天候リスクのすべてをカルビーが引き受けることにしたのです。こうして農家は、天候のリスク、需給による相場の変動のリスク、為替レート変動のリスク、という農業の3大リスクから解放されることになりました。
重要なのは、こうした取引を、長期間にわたって同一条件で継続することです。そうすることで、農家とのあいだに信頼関係が生まれるからです。カルビーは、早くもポテトチップス発売の前年、1974年には北海道内3箇所に馬鈴薯貯蔵庫を4棟建設しています。土地に根を下ろし、「つとめ」を果たしていくという覚悟の現れと言えます。さらに1980年にはカルビーポテト株式会社を設立し、馬鈴薯調達部門を独立させました。松尾はその代表取締役を兼務しました。
ところで松尾はなぜ、前述の3つのリスクから農家を解放することが重要だと考えたのでしょうか。それは、小規模農家が、大規模農業を行う巨大企業に対抗できるようにするためです。通常、これらのリスクに対抗するためには、経営の規模を大きくする必要があります。しかし、巨大企業が参入すると、もともとの小規模農家が淘汰されるばかりか、農業が競争的な市場経済にさらされ、地域コミュニティが破壊されてしまう。そこで契約栽培を導入して農家をリスクから解放し、品質改善に注力できるようにしたのです。結果として、生産性も向上しました。
松尾は、農業と食に関わる者が、その地域の特性に根ざした知恵を交換する機会を非常に重視していました。カルビーではフィールドマンという制度を作り、個々の農家レベルでは見えてこない、地域を見渡す立場からのアドバイスをしていましたし、「プラットフォーム」と呼ばれる、農業と食に関わる者が知恵を交換する研究機関の構想も持っていました。
見えてくるのは、ローカルな地域コミュニティを徹底的に守ろうとする松尾の姿勢です。本連載の関心からすると興味深いのは、こうしたグローバル化の波に対抗するための主要な争点のひとつが天気であった、ということです。天気は、農業にとって恵みであると同時にリスク要因となります。近年は温暖化の影響もあり、そのリスクはますます増大していると言えるでしょう。天気のリスクを経営の大規模化でカバーするとすれば、それはグローバル化への道です。しかし加工の工夫と知恵の共有によってこれをカバーするとすれば、それはローカルなコミュニティの強化につながります。
松尾の地域重視の姿勢がよくわかるエピソードがあります。それは1988年のサッカーチップスの発売です。Jリーグの開幕が1993年ですから、それに先立つ日本リーグ時代に、サッカー選手のカードつきポテトチップスを発売したのです。
背景にあるのは、すでに販売して人気となっていたプロ野球チップスやプロ野球スナックへの不満でした。カルビーでは、カードにする選手の選択は子どもたちからの希望に応じていました。しかし、広島・近畿・中部以外の地域では、希望の80%がジャイアンツの選手に集中していたのです。松尾は、東京一極集中という弊害が子どもたちにまで及んでいることにうんざり。
一方でサッカーは、野球とは異なり、地域別にフランチャイズを張るチームが競い合っています。松尾は、みんなが地元のチームを応援するようになることを夢見て、サッカーのプロ化を後押ししたのでした。もっとも、サッカーチップスはほとんど売れず、どれほどの貢献があったかは分からない、と松尾は語っていますが[10]。
松尾が最終的に目指していたのは、地域で取れた農作物を地域で加工し、地域で消費するという循環型の自給圏を作ることでした。「スマート・テロワール」構想です。トーマス・ライソンが提唱したシビック・アグリカルチャーの考え方をとりいれながら松尾が構想したのは、消費地生産主義を徹底し、単なる生産の手段ではなく、それによって地域社会が豊かになるような農業のあり方でした。貿易赤字や少子高齢化といった難問を解決する鍵も、「スマート・テロワール」にあると松尾は考えていました。
もっとも、松尾のこうした考えは、財界人からすれば「理想的すぎて、現実的ではない」と見られることもあったようです。しかし松尾に言わせれば、「3ヶ月の決算で評価を問われる都市の事業家と、最低でも4年間の輪作の成果が問われる畑作農家とは、異質の世界です」。松尾ははっきりと、農業は理想にもとづいて行動する必要がある、と語っています。
農業と農村社会において理想的な循環社会を目指すことは「重農主義」の主張です。理想に近いことが競争有利をもたらします。生態系という生物システムと協働できることが競争力になる、これが農業の本質です。(…)
21世紀になって自然界の原理が次々に解明されていますが、それでもわずか5%程度といわれます。生態系の共生関係のうえに成立する食産業は、今後さらに進化しますから、現状でも理想論に基づかなければ後れをとることになる、というのが私の考えです。ゆえに農業は理想的と思えるものをベースに置かなければまったく意味がないのです。[11]
生態系という未知のものとの協働であるからこそ、理想に基づかなければ後れをとることになる。何とも示唆的な言葉です。冒頭の『日経ビジネス』の記事に帰るなら、これこそまさに「頑張らない」ということでしょう。「頑張る」は、「かせぎ」という既存の競争システムと評価軸の範囲内で自分の力を使うことを意味します。しかし、それでは現状の社会が抱えている問題は解決しません。だからこそ「頑張らない」姿勢が重要なのであり、理想にもとづいて生きなければならないのです。
確かに私たちは、現実中心主義的にものごとを見すぎているのかもしれません。生態系や、それと一体となっている環境、そして天気という、変動する未知なる相手とともに社会を営むためにはどうしたらいいか。そのヒントが、ここには隠されているように思います。
*本稿の執筆にあたり、神戸大学大学院経営学研究科の小川進先生およびカルビー株式会社マーケティング本部本部長の松本知之さんに多大なサポートをいただきました。記して感謝いたします。
[1] https://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ12HMG_S7A410C1TI5000/
[2] http://www.nouminren.ne.jp/newspaper.php?fname=dat/201706/2017060501.htm
[3] 松尾雅彦『スマート・テロワール 農村消滅論からの大転換』学芸出版社、2014、189-190頁
[4] 前掲書、246-247頁
[5] 前掲書、247頁
[6] 前掲書、247頁
[7] 前掲書、187頁
[8] 前掲書、38頁
[9] 前掲書、64-66頁
[10] 前掲書、95頁
[11] 前掲書、37頁
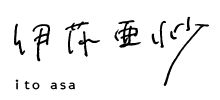 東京大学大学院人文社会系研究科美学芸術学専門分野博士課程修了(文学博士)。専門は美学、現代アート。現在、東京工業大学科学技術創成研究院未来の人類研究センター長。リベラルアーツ研究教育院教授。主な著書に『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社新書)、『目の見えないアスリートの身体論』(潮新書)、『どもる体』(医学書院)、『記憶する体』(春秋社)、『ヴァレリーの芸術哲学、あるいは身体の解剖』(水声社)、『手の倫理』(講談社選書メチエ)などがある。
東京大学大学院人文社会系研究科美学芸術学専門分野博士課程修了(文学博士)。専門は美学、現代アート。現在、東京工業大学科学技術創成研究院未来の人類研究センター長。リベラルアーツ研究教育院教授。主な著書に『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社新書)、『目の見えないアスリートの身体論』(潮新書)、『どもる体』(医学書院)、『記憶する体』(春秋社)、『ヴァレリーの芸術哲学、あるいは身体の解剖』(水声社)、『手の倫理』(講談社選書メチエ)などがある。

