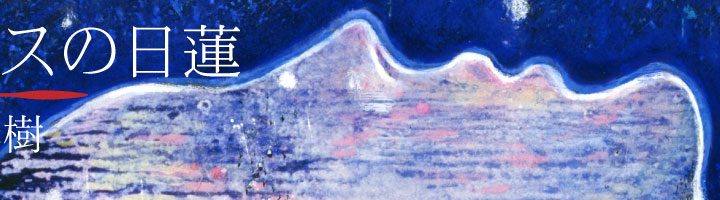法華宗の宗祖・日蓮(1222~1282)は、千葉の貧しい漁師の家に生を受け、蒙古襲来や鎌倉大地震など、あいつぐ戦乱や自然災害に見舞われた時代のなかで、数多の著作を編み、多くの弟子を育てた信念と信仰の人であった。その生涯は、幕府や他宗派との対立により、度重なる流罪、襲撃、焼き討ちなどに見舞われる非常に激しいものだったと記録されている。
この連載は、歌人であり東京下谷・法昌寺の住職でもある福島泰樹さんが、日蓮の足跡を辿りながら、彼の周囲に生まれた「生」=「エロス」の物語を、さまざまな形で現代に蘇らせていく試み。月1回の更新予定です。
昨年の春、大杉栄をテーマにした講演の依頼を受けた。依頼主は、新潟県新発田市を拠点に活動する「大杉栄の会」。新発田市は、軍人の子大杉が、幼年時代を過ごしたところである。
依頼状には、大杉が虐殺された「九月十六日」前後の日曜日に毎年、「大杉栄メモリアル――映像と言葉で日本の近現代史をふりかえる」と題する催しを続けてきたという。第一回開催は、十八年前の「一九八八年」。以後、藤原智子、鎌田慧、松下竜一、太田昌国、鈴木邦男などの人々が呼ばれた。まさに呼ばれて然るべき人々である。
なぜに、私にお鉢が回ってきたのであろうか。第一これまで私は一度たりと、大杉栄を論究したことがないではないか。ならば歌……。
「春三月縊り残され」リンネルの背広姿に黒い花散る
歌集をたぐり寄せてみた。二〇〇二年秋刊行の『デカダン村山槐多』(鳥影社)は、「大杉栄に」の詞書をもって始まる。
春三月縊り残され花に舞ふ
大杉畢生の句に出会ったのは、いつか。忘れもしない一九七〇年春。吉田喜重監督『エロス+虐殺』の画面においてであった。現代映画社制作のこの映画を私は、伊勢丹の斜め向かいにあった「アートシアター新宿文化」で観ている。細川俊之演じる大杉栄には、迫真のリアリティがあった。伊藤野枝の岡田茉莉子。池畔(井の頭公園であろう)を歩く二人に、鮮やかに桜が吹雪いていた。

この春、私は兵庫県尼崎にある法華宗興隆学林を卒業、昼は大塚にある宗務院に勤務していた。学生作家立松和平が、大塚に訪ねて来たのもその頃の事である。私がひそかに修業先の坊舎で纏め上げた処女歌集『バリケード・一九六六年二月』を、立松は占拠中のバリケードの中で読み、感動したという。立松は「早稲田文学」の学生編集号を企画、私に歌稿の依頼に来たのであった。
野枝さんよ虐殺エロス脚細く光りて冬の螺旋階段
しなやかな華奢なあなたの胸乳の闇の桜が散らずにあえぐ
愛と死のアンビヴァレンツ落下する花恥じらいのヘルメット 脱ぐ
くやしみの桜散りつつ血煙【ちけぶり】を描きし眼【まなこ】ふたたび閉じよ
数日を経て私は、処女歌集以後の作七十首ばかりを纏めて彼に渡した。中に「二月三月四月の桜」と題した作品がある。『エロス+虐殺』を観てからの作である。
一九六〇年代後半の激しい政治的嵐が一気に吹き荒れ、熄んで迎えた七〇年代のしらけた政治的状況の幕開けを私は、「野枝さん」への、なかんずく虐殺された大杉栄らへの呼びかけを通して、せめて激しく、エロスの炎を燃え熾そうとしていたのであった。
1
大杉栄は明治十八年一月――明治、大正、昭和の二十年代までは、年号で書き記すこととする――、愛媛県丸亀(いまの香川県丸亀市)に父・大杉東【あずま】母・豊【とよ】の長男として生まれる。生年の秋、父(丸亀連隊少尉)の近衛歩兵第三連隊転属にともない東京市麹町区番町に移り、二十二年五月、父の歩兵一六連隊への異動で、新潟県新発田に移る。新発田での幼年時代のことについては死後刊行の『自叙伝』(以下、引用は『自叙伝』)に詳しい。
明治三十二年四月、名古屋陸軍地方幼年学校に第三期生として入学(十四歳)するが、三十四年十二月、学友との決闘の咎で退校(十六歳)を命ぜられ、新発田へ帰る。

「僕の前には新しい自由な、広い世界がひらけてきたものだ。そして僕の頭は今後の方針と云ふ事に就いて充ち満ちてゐた」。
翌年一月二日、外国語学校に入るため上京。霏々と降る大雪の中、橇に乗り二人の俥夫に引かれて立つ栄を、母は玄関の外に立って「まあ、あんなに喜んで行く。」と涙ながらに見送った。十七日、栄は十七歳の誕生日を、東京市牛込区矢来町の四畳半の下宿で迎えた。フランス語の猛勉強が始まったのだ。
「何よりも僕は、僕にとつての此の最初の自由な生活を楽しんだ」。「又仏蘭西学校にはいつたのも、僕は自分の存分一つできめた。……僕が自分の生活や行動を自分一人だけで勝手にきめたのは、これが始めてであり、そして其後もずつと此の習慣に従つて行つた。と云ふよりも寧ろだんだんそれを増長させて行つた」。
アナーキスト大杉栄の誕生である。「僕は幼年学校で、まだほんの子供の時の、学校の先生からも遁れ父や母の目からも遁れて、終日練兵場で遊び暮らした新発田の自由な空気を思つた」。
この自由を焦がれ享受する想いが、自分ばかりではなく自分以外の人々の自由へ向かった時、さらに自由への想いが理論づけられ、社会へと拡張していった時、社会、歴史、国家との対立軸は自ずから鮮明となってくる。大杉栄の生涯の意志と行動の源が、静かに揺らめき波打とうとしていた。
「けれどもやがて、此の自由を憧れ楽しむ気持がただ自分一人のぼんやりした本能的にだけではなく、更にそれが理論づけられて社会的に拡張される機会が来た」のである。大杉は回想している。
それは晩春の或る寒い夕方であった。早稲田の学生五六人が、がやがやと外へ出て行く物音が聞こえ、そっと下宿の障子を開けてみると学帽を被った二十人ばかりの学生が、てんでんに幟のような旗や高張提灯を振り上げ、わいわい騒いでいる。やがて、一団は、「一二、お一二」の掛け声をあげ元気よく飛び出して行った。「谷中村鉱毒問題大演説会」と大きく墨書された幟と、スローガンを書き付けた高張提灯の赤い火影が揺らめいてゆく光景は、「一二、お一二」の掛け声と共にいつまでも記憶のうちに残るほど、社会を考え自分を考える大きな転機となるのである。
足尾銅山鉱毒問題に業を煮やした田中正造が、天皇への直訴に及んだのは大杉が上京する二十数日前のことである。直訴状は、幸徳秋水がこれをしたため田中が修正をほどこした。

田中正造
幟をかかげる学生たち、加えて安いだけの理由で購読を開始したという「万朝報」によって大杉は、次第に社会への視野を広げてゆく。紙面には連日、幸徳秋水、堺利彦が熱弁を揮っていた。
そして殊に秋水と署名された論文のそれに驚かされた。
彼れの前には、彼を妨げる、又彼の恐れる、何物もないのだ。彼はただ彼の思ふままに、本当に其の名の通りの秋水のやうな白刃の筆を、その腕の揮ふに任せてどこへでも斬りこんで行くのだ。殊に其の軍国主義や軍隊に対する容赦のない攻撃は、僕にとつては全くの驚異だつた。軍人の家に生まれ、軍人の間に育ち、軍人教員を受け、そして其の軍人生活の束縛と盲従とを呪つてゐた僕は、ただそれだけの事ですつかり秋水の非軍国主義に魅せられて了つた。
大杉は、昼は神田猿楽町の予備校に、夜は牛込区箪笥町の仏語学校に通い猛勉強に明け暮れていた。上京して半年近くたった六月、「母危篤」の電報に驚き新発田へ急行する。六月二十三日のことだ。家に着き母が、新潟病院で昨日死亡したことを知る。電報の差出し人の住所を見ずに来てしまったのだ。

大杉栄母・豊
室一ぱいに多勢の人達が座つてゐた、僕がはいつて行くと、皆んなは泣きはらした目をやはり先きの人達と同じやうに大きく見はつて僕の顔を見つめてゐたが、僕が又「お母さんはどこにゐますか」と聞くと、其の中の人達は又わあと声をあげて泣きだした。
『自叙伝』には、人の悲しみを自らの悲しみとして悲しむ、当時の人々のありさまが綴られている。
死因は「卵巣嚢腫」。十人目の子供を流産、卵巣に膿を溜めての死であった。気丈夫な母であったが、「苦しくてたまらないから早く死なしてくれ」「栄はまだか」と言い続けた。臨終に大杉が間に合わなかったわけは、受験勉強にさわるから知らせるなという母の言によった。箪笥を開けると遺された着物に、春、菊、松枝など娘の名が書かれていた。覚悟の入院であったのだ。
通夜は二晩か三晩続き、妹の春が到着すると葬式となった。位牌を大杉が抱き、葬列は賑やかな通りを寺へ向かった。母の人柄ゆえか、町中の人々が外へ出て母を送ったと、大杉は記す。葬式が終わると、棺は六人の人足に担がれて山の奥へ向かった。その後を、大杉と次弟伸【のぼる】が順った。
火葬の場に着くと、藁を敷き、その上に松の枝を折ってきては積み重ねた。棺をその上にのせると、また松の枝を積み重ねた。やがて人足たちは、離れたところに蓆【むしろ】を敷き、大徳利や重箱を並べ車座になった。朝まで飲みあかしながら、骸が骨になるのを待つのである。
僕は其の人足共の云ふままに、一束の藁に火をつけて、其の火を棺の一番下に敷てある藁の層に移した。藁は直ぐに燃えあがつた。其の火は更に、其の上の松の枝や葉に燃え移つた。そして僕は其の炎の炎々として燃えあがる焔の中に、ふだんのやうにやはり肉づきのいい、ただ夏のさ中に幾日も其儘置いたせいかもう大ぶ紫色がかりながらも、眠つたやうにして棺の中に横はつてゐる母の顔を見た。僕は其の棺箱が焼けて、母の顔か手か足かが現はれて出たら、堪らないと思つた。それでも僕はぢつとして其の焔を見つめてゐた。
ほどなく二人は、人足に促され山を下ってゆく。
大杉栄の母との死別であった。そして、この死別の悲しみは、八年後の大逆事件へと連なってゆくのである。以後、関東大震災、虐殺までの十二年間、大杉は、実に多くの同志たちの、無念の死を見送らなければならない。
人は死ぬ。人の死のその実相を、両眼を見開き、しっかりと凝視しようとする十七歳の大杉栄がいた。

2
伊豆流罪赦免の翌文永元(一二六四)年十月、日蓮は十一年ぶりに故郷安房国に帰った。胸中、さまざまの想いが去来したことであろう。石をもて故郷を追われた日蓮は、父の死に目にも会うことができなかった。父の墓参、母との再会を夢見ての帰郷であった。
日蓮は東海道十五ケ国の内、第十二に相当する安房の国長狭【ながさ】の郡東條の郷の海女【あま】が子也。生年十二同じき内、清澄寺と申す山にまかりて、遠国なるうへ、寺とはなづけて候へども修学の人なし。然るに随分諸国を修行して学問し候…… (「本尊問答鈔」弘安元年 五十七歳)

安房国東条郷片海①

安房国東条郷片海②
父母と別れた漁夫の子・日蓮が、清澄山の天台宗の古拙清澄寺【せいちょうじ】に預けられたのは数えの十二歳の時であった。師の道善房の下、十六歳で出家。名を是聖房連長と名告った。ほどなく鎌倉で修学。念仏、禅などを学び二十一歳で帰山、『戒体即身成仏義』を著【あらわ】し、さらに学問を求め比叡山に向かった。
叡山に勉学すること十年、八宗を兼学法華教理の深奥を究め絶対を確信した日蓮は一路清澄山を目指した。虚空蔵菩薩の霊前で「日本第一の知者」となしたまえと祈願を立ててから二十年、日蓮は三十二歳になっていた。
ついにその成果を師友、一座の大衆を前に発表する日が到来した。時に建長五(一二五三)年四月二十八日正午、清澄寺持仏堂南面に座した日蓮は、法華経帰一の絶対的一元論を説き、法然の浄土教・専修念仏を烈しく批判した。浄土念仏は、此所清澄山にも及んでいた。聴衆は日蓮の説法に驚き、地頭東條景信は激怒した。慌てた師は日蓮を勘当。兄弟子の浄顕房がこれをかくまった。日蓮は清澄山を、故郷安房を追われたのである。法華経「勧持品」には、こうあるではないか。
於仏滅度後 恐怖悪世中 我等當広説 有諸無智人 悪口罵詈等 及加刀杖 我等皆當忍(仏の滅度の後の 恐怖【くふ】悪世の中に於いて 我等當【まさ】に広く説くべし 諸々の無智の人の 悪口罵詈【あっくめり】等し 及び刀杖を加ふる者有らん 我等皆當に忍ぶべし)
この経を弘めようとする者には無智の人々がこれを罵り、刀杖の迫害を加えてくるであろう。これを忍んでこその法華経の求道者であるのだ。日蓮はその当初において、法難受難を体験することとなるのである。この日、早暁、頂きに立った日蓮は、太平洋を真っ赤に染めて昇る日輪に向かって「南無妙法蓮華経」を唱えた、と伝わる。
建長五年四月二十八日、立教開宗を宣言した日蓮が鎌倉入りをしたのは、建長八年八月を過ぎてからであった。日蓮は名越の松葉谷【まつばがやつ】と呼ばれる山間に草庵をもうけた。鎌倉の東南部にあたる名越は、房総地方、三浦半島から流入してくる人々の溜まり場であり、下層庶民の生活の地であり、死人を捨てる葬地でもあった。
鎌倉入りする直前には、暴風雨により河川が決壊、山津波がおこり多数の死者が出たことが『吾妻鏡』(巻第四二)に記録されている。九月には、赤斑瘡【あかもがさ】が流行、十月に「康元」と改元。十一月には北条時頼が退き、六代執権に長時が就任した。康元もわずが五ヶ月で、翌三月には「正嘉」と改元。この改元も功を奏さず四月には月蝕、五月には日蝕と天変地異が続出する。ついに正嘉元年八月二十三日、大地震が発生するのである。『吾妻鏡』は、鎌倉を襲った大地震の凄まじさをこのように伝えた。
山岳頽崩、人屋顛倒、築地は皆悉く破損。所々地裂け水湧出。中下馬橋辺の地裂破、其の中より、火炎燃出、色青云々。
日蓮は、一年を待たずして正嘉元年の鎌倉大地震に遭遇したのである。鎌倉の大路、小路には逃げ場を失った人々の屍が、雨に濡れ陽に晒され、行倒れた牛馬と共に累々と転がっていた。身寄りを無くし行場を失い、悲しみに打ち拉ぐ人々を、さらに襲い来る飢餓が追い打ちをかける。名越にあって日蓮は、山津波や洪水、家屋の倒壊、さらに飢餓など震災で行き倒れた死者たちへの回向をもって、法華経弘通の一歩を標した。その姿に打たれた人々が、日蓮の教えを聴くようになったのである。日蓮もまた被災者の一人であったのだ。
日蓮は折り重なる大禍の、その原因究明に向かった。大著『守護国家論』(正元元年)上梓のその翌年には、「災難興起由来」「災難対治鈔」の勘文(意見書)をなした。「国土に起きる大地震・非時の台風・大飢饉・大疫病・大兵乱等の種種の根源を知りて対治を加ふ可き勘文」が「災難対治鈔」の正式名である。対治とは、人力を超越した天変地異ばかりではない、その依って立つ時代社会・政治状況のすべからくを引き受け、すべての人間の現世と来世にわたる救済をさす。これは、鎌倉時代の祖師・法然(浄土宗)、親鸞(浄土真宗)、一遍、(時宗)、栄西(臨済宗)、道元(曹洞宗)との根底的相違の一つであろう。
日蓮は、さらにこれを経説(文証)によって、その起こるべき必然性(理証)をきわめ、現証(歴史的現実)を広く求めんとして、駿河岩本の実相寺の一切経蔵に籠もった。
旅客来たりて歎いて曰く、近年より近日に至るまで、天変・地夭・飢饉・疫癘【えきれい】、遍【あまね】く天下に満ち、広く地上に迸【はびこ】る。牛馬巷に斃れ、骸骨路に充てり。死を招くの輩【ともがら】すでに大半に超え、これを悲しまざるの族【やから】、あえて一人【いちにん】もなし。
鎌倉入りしてから四年、文応元年七月十六日、『立正安国論』(三十九歳)は前執権北条時頼に上奏された。巻頭のこの一節こそが、日蓮が鎌倉で目にした、骸骨が路を塞ぐありのままの惨状であった。正法(法華経)違背の国には、「星宿変怪」、「日月薄蝕」、「非時風雨」、「過時不雨」、「人衆疾疫」、「自界叛逆」、「他国侵逼」の七難が起こると「薬師経」に説かれている。すでに、五難までは起こってしまった。更に六の「自界叛逆(内乱)」の難、七の「他国侵逼(外敵襲来)」の難の二難も必至であろうと記し、これを予言した。第一回目の国家諫暁であった。
だが、幕府はこれを黙殺した。
国主の御用ひなき法師なればあやまちたりとも科【とが】あらじとやおもひけん。念仏者並【ならび】に檀那等、又さるべき人々も同意したるとぞ聞へし。夜中に日蓮が小庵に数千人押し寄せて殺害せんとせしかども、いかんがしたりけん、其の夜の害もまぬがれぬ。(下山御消息 建治三年 五十六歳)
国主がこれを黙殺したのであれば、危害を加えても咎めはあるまいと考えた念仏者信徒ら武装集団が群れをなして名越の草庵を焼討ちした。世に言う、「松葉谷の法難」である。『立正安国論』上奏の、わずか四十日後の文応元年八月二十七日のことであった。
九死に一生を得た日蓮は、下総に逃れた。八幡庄若宮(千葉県市川市)には、最初の檀越で生涯の外護者となる富木常忍がいた。日蓮は、この地にあって下総一円の布教につとめた。守護職千葉氏に仕官する大田乗明、曽谷教信は、この時の入信者である。
3
「文応」という年も、わずか一年に終わり、翌「弘長」元年、日蓮は再び鎌倉に帰った。死んでいるはずの日蓮が帰還したことに人々は驚いた。だが襲撃した側に咎めはなく、日蓮は捕らえられ伊豆伊東へ流罪となった。松葉谷の法難の翌年・弘長元年五月十二日のことである。貞永式目に定められた政道を、為政者である幕府が自ら破る結果となったのである。「伊豆法難」は最初の王難(国家権力による弾圧)であった。
日蓮去五月【いぬるさつき】十二日流罪の時、その津につき候しに、いまだ名をもきゝをよびまいらせず候ところに、船よりあがりくるしみ候ひきところに、ねんごろにあたらせ給候し事はいかなる宿習【しゅくしふ】なるらん。過去に法華経の行者にてわたらせ給へるが、今末法にふなもりの弥三郎と生まれかわりて日蓮をあわれみ給ふか。(「舟守弥三郎許御書」弘長元年 四十歳)
伊東の磯辺に置き捨てられた日蓮を救ったのは、船守弥三郎と名告る貧しい漁民であった。配流の地より日蓮は切々とした手紙を書き送った。
法華経「法師品」には、
若我滅度後 能説此経者 我遣化四衆 比丘比丘尼 及清信士女 供養於法師 引導諸衆生 集之令聴法 若人欲加悪 刀杖及瓦石 則遣変化 人為之作衛護(若【もし】我が滅度の後に 能【よ】く此の経を説かん者には 我化【われけ】の四衆 比丘比丘尼【びくびくに】 及び清信【しょうしん】の士女【しにょ】を遣【つかは】して 法師を供養せしめ 諸【もろもろ】の衆生を引導して 之【これ】を集めて法を聴かしめん 若【もし】人悪【みだ】りに 刀杖【とうじょう】及び瓦石【がしゃく】を加へんと欲せば 則【すなは】ち変化【へんげ】の人を遣【つかは】して之【これ】が為に衛護となさん)
とある。法華経を行じる者を、諸天善神は、男となり女となって(形を変え)、さまざまに供養したすけるべし、という経文である。
船守弥三郎よ、あなたは過去世に法華経の行者として修行をつまれ、今悪世末法の直中に、船守弥三郎として生まれ変わり、この日蓮をたすけ給うか、とその感謝の想いを新たにしているのである。
かゝる地頭・万民、日蓮をにくみねたむ事鎌倉よりもすぎたり。みるものは目をひき、きく人はあだ(怨)む。ことに五月【さつき】のころなれば米もとぼしかるらんに、日蓮を内内にてはぐくみ給しことは、日蓮が父母の伊豆と伊東かわな(川奈)と云ふところに生れかわり給ふか。
日蓮は、船守弥三郎夫妻に父母をみた。そして文末に至って、こう記すのである。「しからば夫婦二人は教主大覚世尊の生まれかわり給て日蓮をたすけ給か」。「法華経」の教主である釈迦牟尼世尊が、船守弥三郎夫妻に生まれ変わって、この日蓮を衛護したのかという一節に、王難に遭遇することによって得た「法華経の行者日蓮」たる、新たな自覚が秘められている。
この「船守弥三郎許御書」は、『昭和定本日蓮聖人遺文』(立正大学日蓮教学研究所編纂 昭和二十八年初版・六三年改訂増補)第一、第二巻に収録されている二百三十編の消息(書簡、手紙)中、最初の消息である。
翌弘長二(一二六二)年一月、日蓮は、配所から、故郷安房国は天津の領主工藤吉隆に、後に『四恩抄』と呼ばれる書簡をしたためた。──二年後の十一月十一日、吉隆は帰郷した日蓮を護るために壮絶な最期を遂げた(小松原法難)。
是程の卑賤無智無戒の者の、二千余年已前に説れて候法華経の文にのせられて、留難に値【あふ】べしと仏記しをかれまいらせて候事のうれしさ申し尽難く候。 (四十一歳)
法華経に説かれるままに信心し、生まれながらに賤しく無智無戒である私のような者が、流罪になったこのことは、二千年以上も前の昔に私の現在が、既に書かれているということではないか。ならば過去は現在にほかならず、未来もまたこの現在に熱くこめられているのである。
法華経「勧持品」には、「有諸無智人 悪口罵詈等 及加刀杖者 我等皆當忍(諸【もろもろ】の無智の人の 悪口罵詈等し 及び刀杖を加ふる者有らん 我等皆當【まさ】に忍ぶべし)」と説かれ、「数数見擯出【さくさッけんひんずゐ】 遠離於塔寺【をんりおたあふじ】(数数【しばしば】)擯出せられ 塔寺を遠離せん)」と述べられているではないか。法華経を弘めようとすると、無智の人々(三類の怨敵)が現れ、悪口を浴びせられるばかりか刀杖の危害を加えられ、さらには讒言によりしばしば排斥(流罪)され、塔寺を遠く離されてしまうというのだ。それはまさに日蓮の現在そのものを言い当てているのではないか。
また、こうも記した。自身は法華経を信じてはきた。しかし、弘経の日々を「学文」や「世間の事」に時間を費やし法華経のみにこの身を捧げることができなかった。しかし、昼夜にわたって「法華経を修行」することができるようになったのは配流のお蔭である、と。私は、大杉栄の「一犯一語」を思い起こしていた。投獄(一犯)のたびに「一語の(外国語一カ国語)」 をマスターしてしまうことをモットーとした。インターナショナルへのつよい指向だ。吃り癖のつよい大杉は、十カ国語を自在に吃ってやる、と豪語した。
とまれ配流の日々にあって日蓮は、法華経色読【しきどく】(身読)の時を迎え、「法華経の行者」として仏国土建設への使命感をふかめてゆくのである。
伊豆流罪赦免の翌文永元(一二六四)年十月、日蓮は十一年ぶりに故郷安房国東条郷片海に帰った。胸中、さまざまの想いが去来したことであろう。石をもて故郷を追われた日蓮は、父の死に目に会うこともできなかった。父の墓参、母との再会を夢見ての帰郷であった。しかし母は、病に伏し、息絶えんとしていた。
日蓮は、法華経「薬王菩薩本事品」の経文「此経則為 閻浮提人 病之良薬 若人有病 得聞是経 病即消滅 不老不死 (此【こ】の経は則ち為【これ】、閻浮提【えんぶだい】の人の病【やまひ】の良薬なり。若人病有らんに、是の経を聞くことを得ば、病即ち消滅して不老不死ならん)」を浄書し、これを焼いて灰となし、浄水とともに母の口に流した。
すると「時をかへさずいきかへらせ給いて候」(「伯耆公御房消息」)と、鎌倉より随行した日朗は、師の祈祷のありさまを驚異をもって書き記した。日蓮自らもこの時のありさまを、「されば日蓮母をいのりて候しかば、現身に病をいやすのみならず、四箇年の壽命をのべたり」(「可延定業御書」文永十二年二月、五十四歳)と述懐した。
日蓮はその波瀾の生涯において、母への重恩を繰り返し述べている。母を亡くし悲しむ子には「我が頭【こうべ】は父母の頭、我が足は父母の足、我が十指は父母の十指、我が口は父母の口なり」(「忘持経事」建治二年三月、五十五歳)と語り、子を亡くし嘆き苦しむ母には、「子と倶に霊山浄土へ参り合はせ給はん事、疑ひなかるべし。」と説き、「其故は子の肉は母の肉、母の骨は子の骨也」(「光日上人御返事」弘安四年八月、六十歳)とこれを慰めた。
4
めらめらと母が燃えゆく姿を瞼に留めた大杉は、父、弟妹たちと別れて東京へ帰って行く。夏が過ぎ、秋に入った。十月(明治三十五年)、神田区猿楽町にある私立順天中学校五年編入入学。下宿の息子の友人に頼んだ替え玉受験による合格であった。
下宿を牛込区矢来町から、本郷区壱岐坂下の甲武館に移り、同じく幼年学校を退学させられた友人登坂高三と同宿する。大杉栄十七歳、赫々たる烈日のような青春が始まろうとしていた。
*
「順天中学」という校名には、思い出がある。私の父が順天中学校に入学したのは、大正十二年四月 晩酌の折などに私はよく父から聴かされた話がある。
その日、父は順天中学校の第二学期始業式を終えて十時頃に帰宅した。浅草十二階(凌雲閣)にのぼる約束に胸をふくらませていたのだ。十二階は父の生まれた寺(下谷区入谷)からは十七八分の距離にあった。十一時になって友人が迎えに来た。母(私からは祖母)が、「お昼御飯を食べてから行きなさい」とたしなめた。関東大震災の発生が午前十一時五十八分。行っていたら、ちょうど父と友人は、最上階の展望台にいたことてあろう。
さて、私の父が順天中学校に入学した大正十二年春、日本を脱出した大杉栄は、ベルリンで開催される「国際アナキスト大会」出席のためフランスの南東部の古都リヨンに滞在していた。だが、大会は延期となりパリ郊外でのメーデー集会の壇上で演説、逮捕されパリの牢獄を味わい国外追放となる。
六月三日朝、日本郵船の箱根丸でマルセイユを出港、ポートサイド、コロンボ、上海、七月十一日午前十時過ぎ神戸港に入港。船中で、同志高尾平兵衛射殺、有島武郎心中の報を聴く。
九月一日、府下淀橋町柏木の自宅で被災。九月十六日午後、大杉栄、伊藤野枝夫妻、甥の橘宗一は、自宅前に張り込んでいた東京憲兵隊大尉甘粕正彦他数人によって、憲兵隊本部(麹町区大手町)に連行され、憲兵隊本部で暴行の上扼殺され、三人の全裸体は菰【こも】で包み廃井戸に投げ棄てられた。
橘宗一いまだ六歳 憲兵隊本部の庭に絶えし蜩【ひぐらし】
明治四十四年一月、「大逆」の罪名の下、幸徳秋水他十三名の主義者が、絞首台の露と消えてから十二年。赤旗事件で逮捕され二年六ヶ月を牢獄にあって連座をまぬがれた大杉栄は、かつて幸徳らが書いた寄せ書きに、丁寧な書体で小さく「春三月縊り残され花に舞ふ」と加筆した。デカダンの心情に身を委ねた決意表明である。以後「縊り残され」十有余年の春秋を、蹶然として優美に「舞ひ」続けてきたのである。
アンナ・バヴロワ「瀕死の白鳥」真似て舞う大杉魔子や六歳の秋

アンナ・パヴロワ
Profile
 1943年東京下谷に生まれる。早稲田大学文学部卒。69年、歌集『バリケード・一九六六年二月』でデビュー。肉声の回復を求めて「短歌絶叫コンサート」を創出。以後、全国1500ステージをこなす。『福島泰樹全歌集』(河出書房新社)、『弔い―死に臨むこころ』(ちくま新書)、『中原中也 帝都慕情』(NHK出版)、『寺山修司 死と生の履歴書』(彩流社)、『追憶の風景』(晶文社)、歌集『哀悼』(皓星社)等著作多数。毎月10日、東京吉祥寺「曼荼羅」での月例絶叫コンサートも32年目を迎えた。
1943年東京下谷に生まれる。早稲田大学文学部卒。69年、歌集『バリケード・一九六六年二月』でデビュー。肉声の回復を求めて「短歌絶叫コンサート」を創出。以後、全国1500ステージをこなす。『福島泰樹全歌集』(河出書房新社)、『弔い―死に臨むこころ』(ちくま新書)、『中原中也 帝都慕情』(NHK出版)、『寺山修司 死と生の履歴書』(彩流社)、『追憶の風景』(晶文社)、歌集『哀悼』(皓星社)等著作多数。毎月10日、東京吉祥寺「曼荼羅」での月例絶叫コンサートも32年目を迎えた。