ロックとはなんだったのか? 情熱的に語られがちなロックを、冷静に、理性的に、「縁側で渋茶をすするお爺さんのように」語る連作エッセイ。ロックの時代が終わったいま、ロックの正体が明かされる!?
「ロックの正体」とは我ながら大きく出たもので、何か大層な話をするのかと思われそうだが実のところさほど大した話はできない。ロックという音楽文化が誕生したのは20世紀の中頃、1950年代の話で、人間にたとえたら還暦をとうに過ぎておりあと数年で古希を迎える。ロックというのはその折々の時代において熱く語られてきた過去があるので、ロックに関する書籍、文章の類は星の数ほどあってもしかしたらレコードやCDよりも多いのではないか。音楽でありながら活字文化との結びつきが異常に強いのである。
ただ、ロックにまつわる文章というのはどれもやたらと情熱的で、異様な熱を帯びたものが多かった。これに対しては随分と前から、もう少し落ち着いてロックを語れないものかと考えていた。なぜかというとですね、熱く語ると、論理的な冷静さを欠いてしまうのではないかという懸念があるからなのです。
ロックを聞いて熱くなる。それはわかる。大抵のロックはそのようにデザインされているからである。しかしながら、熱くなるということは感情的で情動に流されてしまうということであって、論理的な思考から縁遠い行為ではないのか。これはなんというか一種のバグのようなもので、説明しだすとややこしい話になる。
人間の意思決定のシステムには、直感的なものと、落ち着いて熟慮の末に答えを出すのと、二通りのやり方があって、直感的なものをシステム1、じっくり考えるのをシステム2と呼ぶ。文化としてのロックについて考えるのであれば、システム2をたっぷりと使う必要があるはずなので、とにかく直感に走ることを避けなければならないし、それには熱くならない方が好ましい。
近年は認知科学や神経科学、心の哲学などがたいそう進歩していろんなことがわかってきた。ヒトの思考と感情、情動は深く結びついており、情動無しでは論理的な思考もできないというようなこともわかってきた。厄介である。しかし、だからこそ情動と論理的な思考の間で上手く折り合いをつけたいとも思う。より一層情動を落ち着かせて、決して情熱的になることなく、縁側で渋茶をすするお爺さんのような姿勢でロックという文化について語ろうと思う。
ロックは今もなお続いている文化だが、それが誕生した50年代から60年代、経済的に躍進した70年代あたりとはかなり違う様相を呈している。60年代の後半には50年代のロックは終わっており、60年代のロックも70年代には終わっていたわけで、おそらくその70年代のロックも80年代には終わっていたのだ。そして、ロックが重要な文化であると多くの人々から認識されるようになったのは主に60年代と70年代のロックが産業として、はたまた芸術として高く評価されたからである。
昔、ロックという巨大な音楽文化があり、色々な出来事があった。こう考えると、一旦は過去に終わってしまった文化としての視点が獲得できるので、なかなかに都合が良い。まあ、今ある現代のロックを鳥だとすると、60年代や70年代のロックは恐竜のようなものだろう。
というわけで、できれば古生物学のようなスタンスで行きましょうか。
「ロックの正体」というからには「ロック」には何らかの主体があると筆者は考えているわけで、それは何かというと巨大な成功を収めたロックバンド、ミュージシャンではなくて彼らの音楽に魅了され、レコードを買ったりコンサートのチケットを買った有象無象の消費者群である。
巨大なスタジアムを満員にするミュージシャンは輝いて見えるが、その輝きはスタジアムに詰めかけた消費者が自分の財布からお金を出してチケットを買ったからこそ成立している。文化というのは消費者が築くのである、というスタンスをここでは採用する。
彼らは、それぞれいつ頃、どのようにロックと接触し、その消費者になったのだろう。
今はさておき、昔は子供の頃からロックを聴いていた人はいなかった。20世紀の中頃まではまだロックがなかったからである。今でこそ、親がロック好きだったから幼い頃からロックを聞いていたという若者がいるけれども、そういう層が誕生するまでにはロックが誕生してから30年くらいの月日が必要だった。
つまり前世紀においては、ロックに魅せられる人は人生のどこかの地点で何らかのロックに触れて、好きになったのだ。親は演歌を聴いていたが、自分はロックを聴いていたのだ。という人は多い。親の影響ではなく、自分の意思で選択してロックを聴くようになったのだというのが若人にとっては大切な思い出になる。これが、ロックが持つ魔法の一つだ。
ロックを好んだ往年の若者の多くは、10代の前半から中頃、後半にかけて何らかの形でロックと出会い積極的な態度でその消費者となった。10代の前半から後半といえば二次性徴の季節だ。脇の下や隠部に毛が生え、女の子の胸はふくらみ男の子はペニスが大きくなる。これ即ち、動物でいうところの交尾が可能になるわけですから、異性への興味が高まるお年頃ではある。
20世紀においてロックという音楽を愛した人びとの大半は、脇の下と隠部に毛が生えて、胸が膨らみ始めたり、おちんちんが大きくなりだした頃にロックにハマったと考えて良いだろう。10代の中頃、二次性徴を迎えると男の子も女の子もセックスという現実と向かい合うことになる。大半の男子は10代の前半から中盤にかけて、エロティックなことを考えているわけでもないのに勃起してしまう。という経験をする。これは子孫を残したいという本能が、本人の意思を無視して暴走しているわけです。男の子も女の子も、彼氏や彼女が欲しくなる。
これはロックを演奏するミュージシャンの方も同じで、それくらいの年頃でエレキギターと出会った人が多い。小さな頃から音楽教育を受けていた子であってもエレキギターやエレキベースに手を出すのはティーンになってからだ。
もちろん、現代は生まれた時から親の影響でブリティッシュロックなどを聴いていた子供がいるので、YouTubeなどを見るとあどけない子供が凄いギターソロを決めたりしているわけだが、20世紀にはそんな子供は滅多にいなかった。いたとすれば、それはジェイソン・ボーナムのようにお父さんがレッド・ツェッペリンでドラムを叩いていた、というような特殊な環境の人である。
ともあれ、ロックという音楽は二次性徴と共に中学生から高校生くらいの年頃のハートをわしづかみにする音楽で、必然的に他のジャンルの音楽よりもセックスとの親和性が高くなった。
小学生の男子で1番モテるのは足の速い子だ。進化心理学的なことは色々とややこしいので、おいおい説明する予定ですがチンパンジーの仲間であるヒトのオスは、できるだけ大勢のメスに自分の精子を与えて自分の遺伝子の複製を残したい。そういう風にデザインされている。これが20代の半ば過ぎくらいになると、実際にたくさんの女性に精子を与えてその女性たちが全員妊娠した場合にはとんでもない責任がのしかかってくるという事実を理解できるので、たくさんの女性とセックスしたいという欲求は残したまま、現実と折り合いをつけるようになる。
二次性徴を迎えたばかりの少年少女が性行為に興味を示すのは、ある意味当たり前な話だ。小学生の頃から考えると、ほんの数年で大きく変化してしまった自分の肉体と向き合わねばならないのだから。
男性と女性では性的な戦略が違うので、特に10代の恋愛においては、すぐにセックスをしたがる男子と、なかなかセックスをしたがらない女子という構図はある。とはいえ、どちらも思春期を迎えると恋人がほしくなるのにかわりはない。
20世紀にロックという音楽が非常な盛り上がりをしめしたのは、ひとえに恋人が欲しいという若者の欲望に即した文化だったからだ。たとえば政治的なメッセージの強い歌であっても、「あ、君もこの歌が好きなの? 僕も好きなんだ」という形で出会いが生まれたりもする。
セックス、ドラッグ、ロックンロールなどという言葉があって、ロックはセックスとドラッグ、つまり麻薬と並んで讃えられる文化だった。
今聴き返しても天才としか思えないギタリストのジミ・ヘンドリックスは、色んな国でおそらく何百人もの女性とセックスを行い、アメリカ、ドイツ、スウェーデンで少なくとも3人の子供を作って(もっといるかもしれない)子孫と自分の遺伝子を残すことには成功したが、本人は27歳で死んでしまった。
進化心理学にはロビン・ダンバーが提唱したダンバー数というのがあって、これはヒトが安定した社会関係を維持できる知り合いの人数である。ダンバーによると約150人前後だ。成功したロックスターが生涯でセックスする相手の人数は150人どころではなかった。つまり70年代までに成功したロックスターの多くは自分がセックスをした相手の顔とか名前とか肉体とかを、おそらくはちゃんと覚えていない。まあ、ロックスターとセックスをした女の子の方は一生忘れない思い出になるだろうから、それはそれでウィンウィンというか、ナッシュ均衡めいた状態ではある。その女の子に片想いをしている男の子がいたとしたら、その男子にとっては悲劇かもしれないが、そういう男の子たちもロックにお金を使ったから、この文化は一大産業になったのである。
ロックスターになった男の子はたくさんの女性とセックスすることが可能になるのだけれども、若くして死んでしまうリスクもあった。僕はこれをロックのジレンマと呼んでいる。人間、長生きした方が良いわけで、ヘンドリックスがもしも長生きしていたら、彼はもっと素晴らしい作品をたくさん残していただろう。
人類が築き上げた文明は基本的にどれもトライ&エラーの繰り返しだ。19世紀に産業革命が起きて工業化社会が到来し、人々の生活が豊かになった。これがトライだとすると、工業化社会が原因で公害が起きるのがエラーだ。要はトライの段階でどこまでアクセルを踏めば良いのかわからないから、アクセルを強めに踏んでしまう。ホモ・サピエンスにはそういう癖がある。そして公害の規模は拡大してゆく……。
この大きなエラーに対しては軌道修正をほどこすしかない。ロックが大きな産業に発展した1970年代というのは公害問題がピークに達した時代で、東京や大阪といった日本の都市部の空や河川、そして海はかなり悲惨な状態だった。その後、さまざまな形で軌道修正が行われ、80年代から90年代にかけて、海、空、河川はかなり綺麗になった。そして人類は、今も環境問題に対する取り組みを継続している。
このトライ&エラーと、それに伴う軌道修正をルース・ドフリースはその著作『食糧と人類』の中でラチェット=歯車、ハチェット=手斧、ピボット=方向転換と呼んだ。ラチェットというのは一方向に歯車を回す仕組みで、ボルトやナットを締めるために使うラチェットレンチという道具が有名だ。この例えが秀逸なのはラチェットが一方向にしか回らない点である。そう、ラチェットを回すと元には戻れないのだ。ホームセンターで売っているラチェットレンチには切り替えスイッチがあるのだが、人類の文化と歴史にそういう便利な機能はない。
ロックという文化も60年代から70年代にかけて、明らかにラチェットを回しすぎたのだ。主にドラッグやセックスに関して、色んな人たちが勢いよくラチェットを回した。
後に、ロックスターの中から意識改革を行うアーティストらが現れて、悲惨なロックのジレンマはある程度は解消される。健康に気をつけるロックスターや、愛妻家なロックスターが出現したのだ。これがトライ&エラーを軌道修正する人類の叡智、ドフリースのいうピボットだ。
率先して健康的な生活を心がけたロックスターこそが、ロックに真の革命をもたらしたのである。しかしながら、ロックの誕生から最初の20年ほどは、性的に放埒で麻薬に浸るようなライフスタイルが賞賛を受けた。そしてそれで大勢死んだ。
ロックの誕生は1950年代である。二度に渡る世界大戦が終わり平和が訪れたわけだ。実際、60年代のロックは愛と平和を標榜していた。だがしかし、それにしては文化としてのロックに伴う死者はかなりいるし、暴力的で剣呑な表現も多かった。
有名なモンタレー・ポップ・フェスティバルの記録映像において、ヘンドリックスは演奏が盛り上がる中で自分が弾いていたギターを破壊し、油をかけて火をつける。これを今日の目で見ると、ヘンドリックスが何故ギターを壊したのか全く理解できないのではないか。たとえば、タクシーの運転手やダンプカーの運転手が自分の愛車に火を放ったら、大工さんがハンマーやノコギリを破壊したら、誰もが彼は頭がおかしくなったと思うだろう。ヘンドリックスがやったのはそういう行為であったわけだが、当時の観客は彼の精神状態を心配することもなくギターの破壊に熱狂した。
更に驚くべきことには、ヘンドリックスによるギター破壊を観客が歓迎したという事象について、客観的に説明した文章を読んだ記憶がないのだ。つまり当時の人々にとってギターの破壊は衝撃的ではあったけれども、それを歓迎して熱狂するための土壌があり、それがわかっていたから本人も勢いよく破壊したのである。これは時代の空気としか言いようがないだろう。カウンターカルチャーの時代だったから、と言う説明でそれを理解できるのは当時のカウンターカルチャーに関してある程度の知識がある人だけだ。
ヘンドリックスの楽器破壊は、一種の秩序を破壊する行為であったが、何故そういう行為が観客から支持されたのかが今の若い人にはわからないのではないか?と思うわけで、わからない話に関しては年寄りが説明する必要がある。その時代を知っている世代にとっては、ロックとは反逆だというコンセンサスがあるのだが、今の若い人たちにそういう認識が共有できるとは思えない。
ヘンドリックスがギターを破壊したモンタレー・ポップ・フェスティバルから15年ほど経った1982年、リッチー・ブラックモア率いるレインボーが来日公演を行い、その大阪公演に僕はアルバイトの警備員として参加していた。午前中から機材の搬入も行い、リハーサルも見学できた。ステージのクライマックスでブラックモアはヘンドリックスのように自分が演奏していたギターを破壊した。ただし、火はつけなかった。
客席の警備をしながら僕が考えていたのは、リッチーが破壊したギターの破片でも良いから手に入らないか? というものだった。バイト仲間も同じことを考えていたが、リッチーが破壊したギターは小さなパーツまでまとめて回収され、係の人が持って行った。
僕は全てを把握した。あれは壊す用のギターで、おそらくリッチー専属のリペアマンが次の公演までに修理してはまた破壊するのだ。なるほどね。ブラックモアがヘンドリックスから影響を受けたことは本人も公言しているが、長生きで七十歳を過ぎた今も現役だ。彼はヘンドリックスの破壊行動を継承しつつも、それを伝統芸能のような形に変容させることで若くして死ぬような生き方を回避したのだ。
〈参考文献〉
ルース・ドフリース『食糧と人類――飢餓を克服した大増産の文明史』小川敏子訳、日経ビジネス人文庫、2021
ロビン・ダンバー『友達の数は何人?──ダンバー数とつながりの進化心理学』藤井留美訳、インターシフト、2011
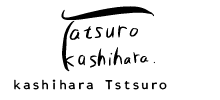 映画監督・脚本家・文筆家。一九六四大阪生まれ。大阪芸大在学中に海洋堂に関わり、完成見本の組立や宣伝などを手がけた後、脚本家から映画監督に。監督作に『美女濡れ酒場』、脚本作に『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説』など。著作に『海洋堂創世記』『「痴人の愛」を歩く』(白水社)、『帝都公園物語』(幻戯書房)がある。
映画監督・脚本家・文筆家。一九六四大阪生まれ。大阪芸大在学中に海洋堂に関わり、完成見本の組立や宣伝などを手がけた後、脚本家から映画監督に。監督作に『美女濡れ酒場』、脚本作に『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説』など。著作に『海洋堂創世記』『「痴人の愛」を歩く』(白水社)、『帝都公園物語』(幻戯書房)がある。
twitter

