ロックとはなんだったのか? 情熱的に語られがちなロックを、冷静に、理性的に、「縁側で渋茶をすするお爺さんのように」語る連作エッセイ。ロックの時代が終わったいま、ロックの正体が明かされる!?
ボブ・ディランやビートルズ、ローリング・ストーンズらが文学的な表現を行うようになったのは、人類の歴史の上でかなり重要なことだった。ジョン・レノンやミック・ジャガーは言ってみればアイドルとして世に出たわけだが、彼らはあっという間に文学者に変貌した。ディランだって、デビューアルバムにはオリジナルの歌は2曲しかなく他はトラディショナルのカバーだ。しかしディランはセカンドアルバム以降、オリジナル曲を大量に作り始めた。彼がノーベル文学賞を受賞した今の視点で見ると、ディランがウォルト・ホイットマンやヘンリー・D・ソローといったアメリカ文学の精神を受け継いでいることは明らかである。ディランとは直接、交友のあった詩人アレン・ギンズバーグを、ディランとホイットマン、ソローの間に置くとかなり見通しの良いアメリカ文学史になるのではないか。個々のアーティストたちは一見、革新的に見えはするのだが、実はそれぞれに良い形で先人の仕事を継承しているのがわかる。文化の伝達、継承には縦横斜めと3つのパターンがあるわけだが、ディランの文学性は同時代の若者へと横の伝達で広まった。なのでレノンもジャガーも、そしてジミ・ヘンドリックスもディランから強い影響を受けた。そう、ロックの基本である「我流の物真似」が彼らの表現を深化させたのだ。同時代の若者同士だから、ディランへの尊敬の念はあっただろうが、同時に負けるもんかという競争意識もあったろう。ヒトはリスペクトと負けるもんか!を同じアプリケーションで行える動物である。バイオロジカルなマーケットの中で、ディランを高く評価したからこそのリスペクトであり、同時に自分も文学的な詩を書こうではないかとモチベーションが上がるわけだ。要するに、自分もディランのように文学的な歌詞を書いた方が、今という時代において、今以上に輝けるのではないかと、当時既に有名人であったレノンやジャガーは考えたわけである。甘いラブソングだけを歌い続けていたら時代遅れになってしまうかもしれない、という危惧もあったかもしれない。彼らの目の前には、文学的な修辞を駆使したロックという新たな地平が開けていた。その頃に同じような思いを抱いた若者が大勢いたであろうことは間違いなくて、彼らの後から登場したミュージシャンたちの多くは最初から文学的な表現を使っていた。こう考えると、ある種の芸術的な表現に対する評価、批評精神というものが生物学的かつ経済学的な行動であることがよくわかる。現代社会においては、芸術として高く評価されると収入が増えるのだ。だとしたら、己がやっている表現を芸術として認知させたいと思うのは人情である。たとえばだ、色んな人がパブロ・ピカソや谷崎潤一郎を各々の分野において高く評価したので彼らの懐にたっぷりとお金が入り、元から浪費家であったピカソや谷崎は主に自分の身の回りにいた女性たちのために篦棒にお金を使った、わけである。その結果、どちらも売れっ子なのに経済はいつも火の車というはたから見たら面白いことになったのだが、彼らが浪費したお金は経済を回し、どこかの誰かを少しばかり助けた。
とはいえ、生物学と経済学が極めて近しい親戚だということが判明したのは、かなり最近のことである。当時は誰もがその辺のことがよくわからないままに、ある種の情熱を持って衝動的に市場に参加していったのだ。そう、社会運動に身を投じるという行為もまた、バイオロジカルなマーケットへの参入なのだ。街頭でデモを行うのも、大勢の他人に見せる行動である。見てもらわないと効果がないですからね。
そもそも社会的な運動、ムーブメントの類において渦中にある人間には、確固たる意図や目的、理想などはあるかもしれないが、現在進行形で自分が行なっていることが客観的に見てどのようなことなのかを理解することができない。ヒトは誰しも目の前のプロジェクトに対して、近視眼的にならないと集中できないわけだが、近視眼的になるということは客観視という理性的で便利なツールから距離を置くことにつながる。生きている限り、人には近視眼的にならなければならない時が必ず訪れる、のである。自分を客観視することはヒトにとってとても良いことである。客観視は冷静で理知的な思考とつながっているので、事あるごとに自分を客観視しようとする姿勢でいると人生において大きなミスをしでかす可能性がかなり低くなる。しかしながら、たとえば外出中に激しい便意に襲われた時に、近視眼的になるなと言われても無理である。
カウンターカルチャーの時代には公害、ベトナム戦争に公民権運動など様々な解決すべき問題が山のようにあったので、人々は近視眼的に興奮し世情は揺れに揺れた。ヒトはとにかく喫緊の問題に対しては感情的になりやすい動物である。喫緊の問題とは、どのようなものかというと、たとえば目の前で自分の家が火事で燃えているとか、帰宅したら自分の奥さんが自分の親しい友人と裸で抱き合っていたとか、そういう事態に直面することである。感情的になるなというのは無理な話だ。この、喫緊の問題に直面した際に燃え上がる我々の感情とは、おそらく我々の遥かな祖先が、ライオンの祖先に食べられそうになった時、はたまた自分の子供や親しい仲間が食べられそうになっているのを発見した時の感情なのだろう。そういう時に対策を深く考えている暇はないから脊髄反応で動くしかない。しかしながら、環境問題というのは脊髄反応で解決できる類の問題ではないし、反戦運動や公民権運動もまた持続的にやるしかない。特に環境問題や反戦運動には基本的にゴールがない。永遠にも近いようなスケールで、気長に計画的かつ継続的に取り組む類の問題である。実のところ、人類は気長に取り組むことで環境問題や反戦運動に関してはそれなりに良い結果を出しているのだが、当時の人々には汚染された海や空がそれなりに綺麗になる未来がとても予想できなかった。カウンターカルチャーの時代には、色んな本が書かれ多くの読者を獲得したが、どれもハーバート・A・サイモンがいうところの熱い言葉で書かれており、冷静かつ客観的に自分たちの行動を分析したような文章はあまりない。彼らは自分たちが何を行っているのか客観的に理解していなかった、とも言えるし、哲学者ダニエル・C・デネットがいうところの「理解力なき有用性」が作動していたとも言える。理解力なき有用性を理解してもらおうとすると、やたらと長い話になるのだが、かなり端折って説明するとこうなる。たとえばアリやハチはガウディの建築なみに凄い巣を作るけど、個々のアリやハチは自分が何をやってるのか理解してないよね、てなことである。それと同じようにヒトも自分が何をやっているのか、客観的なことはわからないままに凄いことをやってしまう場合があるのだ。
たとえばカール・マルクスという人がいる。マルクスの考え方は実はキリスト教の影響を凄く受けているのだが、マルクス自身は自分がキリスト教の影響下にあることを自覚出来なかった。それは無理もないのだ。マルクスは言ってみればマルティン・ルターが考えたビジョンの、神様が存在しないバージョンを思いついたのである。画期的なのは間違いない。とはいえ、彼がキリスト教から大きな影響を受けていることは現代のマルクス研究者も認めている。ヒトというのは実はそんなには革新的な、クリエイティブな動物ではないのである。たとえばスマホは我々の生活を大幅に変化させた大発明であるが、パソコンの歴史や携帯電話の歴史、その前には電話の歴史などが積み重なり、いくつかの文化の流れが合流して誕生したものである。天才ジョブズが何かを生み出したわけではない、彼はただApple社のトップにいて企業の舵取りをしただけだ。極端なことを言うと、我々の遥かな祖先が石斧を道具として使い始めることがなかったら、我々の文化はiPhoneを生み出すことはなかったろう。ヒトは多くの先人たちから、はたまた同時代の人たちから受け継いだ文化の積み重ねに、ほんの少しオリジナルな何かを上乗せすることしかできないのだが、時にはそのほんの少しの上乗せが大きなブレイクスルーに繋がることがある。そこだけを見れば何か爆発的なことが起きたような印象を与えるのだが、その背後にあるのは文化の継承による積み重ねである。
それにしても、ブリティッシュインヴェイジョンの波には最初から文才のある人たちが集まっていた。レノンはルイス・キャロルのフォロワーであることを隠そうとしなかったし、ミック・ジャガーはミハイル・ブルガーコフが書いた小説『巨匠とマルガリータ』にインスパイアされて「悪魔を憐れむ歌」を書いた。ブルガーコフはドストエフスキーやトルストイ以降では最大のロシア作家だが、ソ連の体制から抑圧された不運な人である。彼はドストエフスキーから非常に重要な要素を継承していた。『巨匠とマルガリータ』の終盤では、民衆がある種の熱狂に駆り立てられて祝祭状態になるわけですが、ドストエフスキーの作品もクライマックスで民衆がゴリラのパントフート的に盛り上がった挙句に悲劇が起こる場面がけっこうある。『罪と罰』ではマルメラードフが死ぬ場面やその妻、カテリーナが死ぬ場面。『悪霊』ではクライマックスの場面において、無責任な群衆がその場のノリで熱狂する様が描かれる。ドストエフスキーはヒトという動物が集団で興奮、熱狂した時の危険性をよくわかっていたのだ。かてて加えて『罪と罰』も『悪霊』も今で言う厨二病による若気の至りを描いた作品で、だからこそ世界中からの支持を得たわけだ。苦悩する若者を描いた実存主義的な文芸作品というのは割と近代の産物で、ゲーテの『若きウェルテルの悩み』が18世紀の後半だ。ゲーテには『ファウスト』という、これまた苦悩する個人を描いた超大作があって、読んだ方ならご存知だろうけれども『ファウスト』は2部構成で第2部はなぜか祝祭劇になるのである。もっとわかりやすく言うと『ファウスト』の第2部は延々とミュージカルな場面が続くのだ。個人の苦悩から始まって、第2部で意味がよくわからないミュージカルになるから『ファウスト』は後半が難解だとよく言われてきたのである。実際、『ファウスト』第2部は難解であるが、とにかく祝祭にしてしまえという作者の強い意志は感じられる。
ところで何故『ファウスト』の話を持ち出したかというと、『巨匠とマルガリータ』にインスパイアされたと言われる「悪魔を憐れむ歌」の歌詞の内容が、『ファウスト』の影響をも受けているように見えるからだ。この曲は、人類の愚行の歴史を悪魔の視点から描いたものだが、その道化師じみた語り口調はどこか『ファウスト』に登場する悪魔メフィストのようではないか。もちろんブルガーコフも『巨匠とマルガリータ』を書くにあたっては『ファウスト』を意識しているのだし、作詞の大半を行ったミック・ジャガーはおそらく両方とも読んでいるのだが、驚くべきは、他のメンバーたちとのスタジオでの試行錯誤の末に完成した「悪魔を憐れむ歌」のリズムが、サンバというきわめて祝祭的なダンスミュージックだったことである。個人を誘惑する悪魔という文学的なテーマを、ゲーテ、ブルガーコフから継承したのはミック・ジャガーであったが、それにふさわしい呪術的かつ祝祭的なリズムを発見したのはキース・リチャーズであった。
ゲーテの『ファウスト』が18世紀、ドストエフスキーの『罪と罰』が19世紀、そしてブルガーコフの『巨匠とマルガリータ』が20世紀で、これらの作品は個人の苦悩を描きつつ、後半で集団的な祝祭劇になるという点で通底している。個人VS集団というのは、人類にとっては普遍的な問題である。個人は尊重されなければいけない、そうでないと我々の傷つきやすい自我は日常生活のさまざまな場面において立ち直れないほどのダメージを受けてしまう可能性がある。その反面、我々は単独で生きる術を持たない。社会的インフラに依存して生きている動物である。だからこそ葛藤が生まれ、個人は苦悩する。実存主義が生まれるわけだ。実存主義といえばフランスのジャン=ポール・サルトルだが、彼が広く注目されて人気を集め、英語圏でも認知されたのがまさに戦後すぐの時期である。サルトルがある種のポップスターであったことは間違いない。フランスは知性の商品化に長けた国であった。サルトルが出てきた背景にはパリのセーヌ川の左岸、サン・ジェルマン・デ・プレ界隈にたむろして「実存主義者」と呼ばれていた若者たちの風俗があった。彼らはアメリカのビートニクスに似て、自由を愛し古臭い社会に縛られることを嫌った、わけであるが大正時代の日本ではモガ、モボというクラスタが発生し好き勝手なことをやった。似たような現象でありますね。モガと呼ばれたモダンガールが誕生したのは都市部での若い女性の職業的な選択肢が増えたからだ。これら若い世代による、我々は年長者とは違う存在なのだという主張が大きな運動となり得たのは文化的な資産と、それを支える経済的な資産が交差して文化的な場が形成されたからだ。たとえばフランスの場合、1686年にル・プロコップというカフェが誕生し、ここにラ・フォンテーヌやアナトール・フランスのような作家たち、ヴォルテールやルソー、ディドロといった文化人が集まり、啓蒙思想や社会変革について語り合った。これがフランス革命につながったのである。革命期には大勢の人をギロチン台に送り込んだ挙句、自分もギロチンで処刑されたロペスピエールや、彼のせいでギロチン台に送られ「次はお前の番だからな」と言ったジョルジュ・ダントンといった政治家もやってきた。フランス革命後の悲惨な時代が過ぎても、芸術家や文化人がカフェをサロンとして文化人たちが語り合う文化は続いていた。明治維新以降、日本は脱亜入欧を掲げていたので藤田嗣治のようにフランスに留学する芸術家が大勢いた。それでカフェのサロン文化は日本にも入ってきたのである。大正時代のカフェには、大杉栄のような政治活動家、高見順のような文学者が出入りして社会や文化を語りつつ、酔っ払って暴れたりしていたのである。なんとなく、後世のロックスターのようであるが、そういった文化が入ってきたからこそ大正時代にモダンガールが生まれたわけだ。明治天皇が国民に向けて脱亜入欧を煽り、海外の文化を何でもかんでも取り入れたので、社会主義まで入ってきて大杉栄みたいな人が現れたのだ。文化の系統樹で考えると、大杉栄もサルトルたちサンジェルマン・デ・プレに集っていた当時の「実存主義者」たちも、ルソーやロペスピエールから何がしかの文化を継承しているわけだ。第二次世界大戦の後、やってきたのは情報化社会でありどの国でも出版はより盛んになったから英米の若者たちはサルトルを読んでいたし1946年のノーベル文学賞を受賞したドイツ語の作家ヘルマン・ヘッセも読んでいた。1968年にデビューし映画『イージーライダー』で使われた大ヒット曲「Born to be wild(ワイルドでいこう!)」で知られるステッペンウルフは、そのバンド名をヘッセの『荒野のおおかみ』からいただいている。サンタナのセカンドアルバム『天の守護神』の原題は「Abraxas」で、ヘッセの小説『デミアン』の中で語られる神の名前だ。ずっと後の世代ではブラーのデーモン・アルバーンがヘッセの熱心な読者である。ボブ・ディランを別にすれば、ヘッセは最もロックに影響を残したノーベル賞作家かもしれない。
ザ ・フーのピート・タウンゼントも、ヘッセに影響を受けてロックオペラ『トミー』の構想を得たとインタビューで語っている。そして英国にはキンクスのレイ・デイヴィスがいた。彼は英国文学の伝統であるブラックユーモア、諧謔的な表現の正統な継承者である。諧謔的であることに秀でていたが故に、商業的成功においては他の3人に及ばないが、歴史上最も成功したアーティストの1人であることは間違いない。ちなみにタウンゼントはかなり早い段階からデイヴィスの文学性を称賛していたわけだが、デイヴィスの方は諧謔の人なのでタウンゼントからのリスペクトに対しては皮肉で返すという微笑ましい関係が半世紀ほど続いている。後に旧世代のロックに対して批判的なロンドンパンクが勃興した際、ザ・フーとキンクスは他の旧世代のバンドと違って元祖パンクスとして称賛されたが、これは音楽的な影響もさることながらロンドンパンクが皮肉と諧謔の継承者であったからだ。キンクスを有名にした名曲「ユー・リアリー・ガット・ミー」は男女関係を何やら意味深な比喩で歌っている。男女の関係を比喩的に表現するのはアメリカ黒人のブルースで多く使われていたもので、その点ではブルースを継承しているのだがデイヴィスの歌詞には具体性が少なく抽象的である。直訳すると、二人称で「貴女は僕を魅了した」みたいな感じになるのだが、抽象的な言葉で書かれているので形而上学的に読めないこともない。その上、曲調は後のヘヴィメタルに影響を与えたと言われるほどに激しいのに、熱いボーカルにはどこか物憂げなところがある。この曲が発表されたのは1964年である。この後のブリティッシュロックからは文学的、形而上学的、実存主義的な歌詞を伴った名曲が山ほど生まれるわけだが、レイ・デイヴィスはその先駆者だった。もともとアメリカ黒人のブルースには、男女の機微をシンプルな言葉で表現しながら、人生の深淵を垣間見るような文脈があったのだがデイヴィスはそれを継承しつつ更に掘り下げたと言える。
ここで顧みるべきは、戦前から伝わる黒人ブルースの、口承文学としての重要性だ。アフリカからアメリカに奴隷として連れて来られた人たちは、母国の言語や音楽といった文化を剥奪された状態で自分たちの文化を紡いだ。かろうじて録音が残された戦前のブルースで歌われる歌詞は俗っぽい表現で描かれた生々しいアメリカ文学だったのである。それを、かつての宗主国たるイギリスの若者たちが、文化的な表現手段として継承したのである。宗教音楽である黒人霊歌は、割合に早い段階から文化的かつ文学的な意義を認められて歌詞が記録されたが、世俗の歌であるブルースは悪魔の音楽といわれた。だがしかし、黒人霊歌とブルースはどちらも貴重であり重要なのだ。歴史を奪われた状態で派生した近代的な民族音楽であり口承文芸であるマイノリティの音楽文化が、ここまでの影響力を伴って世界的に波及したというのは、おそらく世界史的にも前例がないのである。そもそも大英帝国の植民地政策がなかったら、こんな文化は生まれていないのだ。大英帝国は、植民地に領土を広げてお金を儲けるために奴隷貿易を行っただけなのだが、それは誰も予想しなかった社会実験の始まりだったのである。アフリカ人から母国語と母国の音楽、楽器などを奪った状態から彼らはどのような音楽、文化を生み出すだろう? という壮大な規模の実験だ。当たり前の話だが、誰もそんな実験をやってみようと思って奴隷を売り買いしたわけではない。結果的に、奴隷貿易が行ったのは壮大な実験だった、という話である。人道的な面から見ると、今では絶対に成立してはいけない類の、それこそ悪魔の実験である。その結果、何が起こったかというと宗主国イギリスの若者たちが、黒人奴隷の子孫が生み出した新たな音楽に魅了され、あからさまに影響を受けた音楽を奏でるようになったのである。イギリスには固有の民族音楽があり、ややこしいことにイギリスとは微妙に異なるアイルランドの民族音楽があった。大英帝国イギリスとアイルランドのややこしい歴史を説明しようとしたら、それだけで一冊の本になってしまうのであるが、ともあれイギリスとアイルランドというのは文化的な葛藤のある関係だ。そしてイギリスは文化的な豊かさを重要視する国であるが、アイルランドは文学と音楽、そして酒といった文化がまことに豊穣なのである。個人的な話であるが、その昔、大阪のパブでアイルランドから来たという三人組の若者と意気投合して「私が思うに、アイルランドの文学とウイスキーはbetter than イングランドである」というような意見を述べたら、彼らはそれこそロックコンサートのようにイェーッ!と叫んで盛り上がり、お前はわかっとるな! お前は正しい! と同意してくれたものだ。アイルランドとイングランドの問題の根深さを実感すると共に、アイルランド人が大酒飲みだというのは事実であることを体感した瞬間であった。翌日の二日酔いは本当につらかった、のである。
広義の英国文化というのは、イングランド、スコットランド、ウェールズ、アイルランドの複合文化である。全くもってややこしく面倒くさい話であるが、アイルランドは12世紀のノルマン人による進攻から始まるイングランドの植民地化政策によってえらい苦労をしてきた。アイルランドの人たちは元々はゲール語で会話していたが、今現在ゲール語を話すアイルランド人は全人口の1パーセントくらいだという。イギリスお得意の植民地政策がゲール語を侵略し尽くしたわけである。異なる言語と言語が出会うと、強い方の言語が相手の言語を滅ぼすのだ。言語こそはヒトが発明した最強のツールなのだが、最強であるが故に危険なのだ。アイルランドのゲール語問題は、奴隷にされてアメリカに送られたアフリカの黒人が母語を奪われたのと良く似ている。言語とか音楽というのは、その集団にとっての存在意義である。それを侵略者の手によって奪われた場合には、侵略者側のメンタリティと同化するか、新たに自分たちの文化を作るしかないだろう。アメリカの黒人音楽はモロにオリジナルの自分たちの文化を創造する行為であったが、アイルランドにおいても似たような事例が起きた。ゲール語を奪われて久しい20世紀のアイルランドの文学者は、侵略者たるイギリス人の英語を使って、イギリス人には到底できないような英語文学を構築しようとした。具体的にいうとジェイムズ・ジョイスである。ジョイスは20世紀の前半に英語を使って誰よりも前衛的な作品を書き成功した。その結果、ヘミングウェイやフィッツジェラルドといったアメリカの作家から大層尊敬されたし、フォークナーはジョイスの手法を踏襲しつつ更に前に進めようとした。アメリカの文学は歴史が浅いにもかかわらず相当に豊穣なものだが、それもこれも白人と黒人奴隷との分断を前提とした社会があったからだろう。黒人の多かった南部の田舎にいたフォークナーのような人が、都会にいたフィッツジェラルドのような人よりも前衛的(プログレッシヴ)な手法で世界を震撼させたのだ。話がいささかややこしくなってきましたが、何が言いたいかというとですね、大英帝国の植民地主義政策は現代の視点で見ると人道的にかなり問題のある国際的犯罪行為に見えるわけだが、音楽や文学においては大英帝国様が行った植民地主義政策によって(他にも色々あるだろう)異様に豊かな文化が生み出されてしまったわけだ。因果である。人類の歴史はどこを切り取っても因果な事実に満ちている。イギリスはアイルランドに対して、アフリカに対して、新大陸アメリカに対して、植民地主義というツールを使って壮大かつ無責任な社会実験を行ったわけである。もちろん誰も、そんな実験をするつもりはなかったのだが、結果的に凄い実験が行われて、現代に生きる我々はその恩恵を受けているのですね。ロック好きですし、そのルーツであるブルースやR&Bも大好きですし、ジョイスもフォークナーも好きなわけですが、それらを生み出すきっかけとなったのは植民地主義で、それは現代人の目から見るととても悪いことに思えるわけです。面倒くさいな人類。だからこそ我々は実存主義を発明して、あれやこれやと具体的な方法では解決できないような悩みを抱えるようになったのかもしれない。忘れてはいけないのは、植民地主義自体は人類にとって罪の歴史であること、その罪の歴史が我々にとってとても素敵な文化をたくさん生み出したことである。
というわけで、20世紀の後半に誕生したロックは、植民地時代以降にしか成立し得ない最先端の音楽と文学が出会う場となった。ロックは常に最先端であることを自慢する文化であったが、実際に最先端だったのだ。ボブ・ディランがエレキギターを持った時、ブーイングした人たちは、エレキギターを使う音楽というのは通俗的で下品なものだと思っていたわけである。21世紀の視点で見ると、通俗的なブルースやロックンロールの歌詞も口承文学として重要な文化だといえるわけだが、60年代にはそういう視点がなかった。高尚で文学的なフォークソングのディランが、金儲けのために低俗なロックンロールを始めたのか?と思ったから憤りを感じたわけだ。
思えばアメリカのフォークソングというのも不思議な存在である。アメリカのように歴史のない国で、フォークたる民衆の民族音楽というのは成立するのだろうか。実際のアメリカンフォークは移民たちの音楽が交わったものだった。アイルランド、スコットランドなど、当時の英語圏の民族音楽のエッセンスが混じり合ってアメリカのフォークソングになった。白人の移民たちは、黒人奴隷よりも教養があったので、黒人音楽よりも文学的に見えたのである。構造主義的な視点で見ると、黒人のブルースも立派な口承文学なのだけれども、当時のディランのリスナーはたぶん構造主義を知らなかった。その時のディランが何を考えていたのかはさておき、彼がエレキギターを弾いたことでアメリカの文学を継承していたフォークソングと、黒人が踊る音楽、更には黒人音楽を聴いて踊る白人の若者たちの文化が合流したわけだ。確かにこれはダイナマイトを発明したアルフレッド・ノーベルの賞に値する功績ではないか。
ディランに刺激されたイギリスのジョン・レノンやミック・ジャガーたちが、ポップなラブソングを歌うアイドルから、文学的で実存主義的なロックスターに変貌したので、アメリカでロックバンドを組む若者たちも文学的な表現を使うようになった。元から文学者気質の人もロックを歌いはじめる。ザ・ドアーズのジム・モリソンは子供の頃から絵に描いたような文学少年だったが、進学先のUCLAの映画学科でキーボードのレイ・マンザレクと知り合い、ロックバンドという表現を選ぶことになる。問題は、モリソンのようなインテリがドラッグにハマってしまったことである。
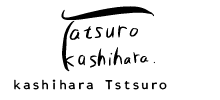 映画監督・脚本家・文筆家。一九六四大阪生まれ。大阪芸大在学中に海洋堂に関わり、完成見本の組立や宣伝などを手がけた後、脚本家から映画監督に。監督作に『美女濡れ酒場』、脚本作に『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説』など。著作に『海洋堂創世記』『「痴人の愛」を歩く』(白水社)、『帝都公園物語』(幻戯書房)がある。
映画監督・脚本家・文筆家。一九六四大阪生まれ。大阪芸大在学中に海洋堂に関わり、完成見本の組立や宣伝などを手がけた後、脚本家から映画監督に。監督作に『美女濡れ酒場』、脚本作に『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説』など。著作に『海洋堂創世記』『「痴人の愛」を歩く』(白水社)、『帝都公園物語』(幻戯書房)がある。
twitter

