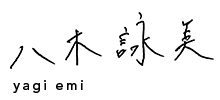『空芯手帳』『休館日の彼女たち』、ユニークな小説2作を発表し、国内外で注目を集める作家・八木詠美。本書は著者初のエッセイ連載。現実と空想が入り混じる、奇妙で自由な(隠れ)レジスタンス・エッセイ。
「子ども好き?」と最初に聞かれたのは確か20代前半くらいだったと思う。当時付き合っていた男性から聞かれた。自分が何と答えたかは覚えてないけれど、「よかった。俺も好きだから」と言われたのは覚えている。よかったってなんだろうと思ったことも。そして決めた。もう、こんな文脈読んであげない、と。
同様の質問はその後も繰り返された。主に付き合っていた男性から。その質問を受けるたびに、わたしは「子どもによるだろうね」「大人が嫌いなの?」と返した。相手が戸惑ったような顔をしていても放っておいた。ちょっと悪いな、とは自分でも思っていた。けれどこの質問が出てくる時点で、またわたしがこの質問を快く思っていない時点で、きっと一緒にいても言葉に対する温度が違い過ぎてあまりうまくいかないだろうなと考えていた。実際、うまくいかなかった。
彼らが聞きたいことが「将来自分との子どもを産んで育てるつもりがあるか」であることはなんとなくわかっていた。わかっていたけれど、わたしは質問の意図を汲みたくなかった。婚活中の友人もよく同じ質問をされるという。
思えば「子ども好き?」って質問は結構雑だ。遊びに行った家に犬がいて「犬好き?」と聞かれれば「好き」と答えてその場で犬と遊ぶし、どこかに食事に行こうという話をしていて「カレー好き?」と聞かれれば「好き」と答えてカレーを食べに行こうと思う。
しかし、脈絡なく「子ども好き?」と聞かれ、こちらが黙っている間に「僕は2人欲しい」などと希望まで言われるとなんだかなという気がする。子どもと呼ばれる人たちに好感を持っているかと、実際に子どもを生み育てるかはあまりに別の話だ。ぼんやりとした一般論の顔をした質問で、将来の個別の選択についての答えを得られると思わないでほしい。
そもそも質問の形でなくても、ときおり耳にする「子どもが好き」というフレーズは少し不思議だ。わざわざ自分から「犬が好き」「カレーが好き」と表明する場合は動物の中でも特に犬が好き、多くの食べ物の中でも特にカレーが好き、ということで「猫が好き」「パスタが好き」と同じくらいの抽象度だと思うけれど、「子どもが好き」と同じレベルの「大人が好き」はあまり聞かない。大人はあまり好きでなくて子どもが好きなのだろうか。0歳から17歳の人間を見ると好感をもち、18歳以上の人間となると途端に興味が薄れるのだろうか。
「年齢の問題ではない。自分は子どもらしい純粋さが好きなんだ」という人もいるのかもしれない。純粋さは明るさ、かわいらしさといった言葉にも置き換えられるだろう。けれどその場合、無邪気でも明るくない子どもは対象外なのだろうか。そうだとしたら、それは割とシビアな態度のような気もしてくる。
大人と呼ばれる存在の中にいろいろな人がいるように、子どもと呼ばれる存在にもいろいろな人がいるだろう。「子どもが好き」というフレーズの、子どもを一括りにしている感じがわたしは苦手なのかもしれない。
もっとも、わたしは「子どもが好き」と自分から口にしないが、付き合っていた男性以外に「子ども好き?」と聞かれたら「好き」と答えると思う。ただ、その「好き」は「嫌いではない」という意味に近く(ある年齢の人間を一律で憎む理由がないから)、「好き」という感情の対象よりも無条件で守るべき対象なのだと感じるようになった。
いつのまにかふるさと納税を申し込んで金額の使い道を選ぶときは、子どもの福祉を選択していることに気づく。友人たちの子どもに会うと「かわいい」というより、どうかこの小さな人が健やかに育ちますように、悲しみを経験することはあっても不条理に苦しむことがありませんように、と架空の叔母ポジションで祈ってしまう。大人よりも弱い立場に置かれやすい彼ら全員が守られ、尊重されてほしい。
だから児童虐待のニュースを見ると、とても悲しい。少なくとも自分の子どもという個別の存在を求め(求めていなかった可能性もあるけれど)、子どもを発生させた人が必ずしも子どもの心身を慮るわけではないと知る。子供が好きであることと、大切にすることはちがう。
わたしは子どもと呼ばれる人たちが一律に嫌いなわけではないが、問答無用で好きなわけでもなくて、でもやっぱりどの子どもも尊重されていてほしい。
「子ども好き?」と同じくらい苦手な質問の一つに「得意料理は?」がある。結婚した当初、年上の方々に何度か質問された。どれどれ、結婚生活についてひとつ話でも聞いてやろうという祝福の形の一つなのかもしれないが、知ってどうする、とつい思ってしまう。実際に答えても、会話は大概尻すぼみになる。
もしかしたらこの質問をする人はすごく料理上手で、例えばわたしが「餃子です」と答えれば皮に包むときのワンポイントアドバイスをしてくれるかもしれない、それとも持ち寄りパーティーのときに料理がかぶらないように配慮してくれるのかもしれない、と好意的にとらえようとしたこともあるけれど、いまだに画期的なワンポイントアドバイスをもらったことも一緒に持ち寄りパーティーに参加したことがないのでよくわからない。