ロックとはなんだったのか? 情熱的に語られがちなロックを、冷静に、理性的に、「縁側で渋茶をすするお爺さんのように」語る連作エッセイ。ロックの時代が終わったいま、ロックの正体が明かされる!?
1960年代後半のロックとカウンターカルチャーの歴史において重要な出来事を二つあげるとしたら、67年のローリング・ストーン誌の創刊と、翌68年の野外フェス、ウッドストックの成功だろう。どちらも当時の若者たちの文化が、何らかの大きなことを成し遂げた証として記憶されている。ヤン・サイモン・ウェナーは当時21歳だった。カリフォルニア大学バークレー校を中退した彼は、家族や友達から借りたお金をかき集めてローリング・ストーン誌を創刊した。ウェナーの動機は非常にシンプルなもので、要するに彼はボブ・ディランやジョン・レノン、ミック・ジャガーに会いたかったから雑誌を作ったのである。ローリング・ストーンという誌名はもちろんローリング・ストーンズと同じくマディ・ウォーターズの名曲「ローリング・ストーン」からいただいたものだ。なんというか、勢いとかノリだけで雑誌を作ってしまったように見えるのだがローリング・ストーン誌はかなり大きな成功をおさめた。1967年の時点で既にロックは文学的なメディアになっており、なおかつ音楽と時事的な問題を交えて語れるメディアになっていた。ロックについて語ることで、世相を語ることもできるし、哲学的な話をも語ることができる文脈が生まれたのである。ビートルズがキャリアの初期に主演した映画『ビートルズがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ!』を観るとわかるように、ロックという文化の基本はロックスターと、それに対してきゃあきゃあする女の子の大群で構成されている。ごく少数の男子ロックスターと、大量の女の子という図式があるので、運良くロックスターになれた男の子は何百人という単位の女性とセックスをすることができたわけである。その反面、ロックスターになれなかった男の子には、複数の異性と交配するような機会が与えられない。ロックというゲームに参加できないのである。しかし、ローリング・ストーン誌は、そこにロックを熱く語るという方法を導入したわけだ。誰よりもロックを熱く語るオレこそがロックという文化の理解者なのだ。WOW。これは本当に熱かった。ウェナー自身は単純に憧れの、ディランやレノンやジャガーに会いたかっただけなのかもしれないが、彼がやったことは新大陸の発見にも似たイノベーションであった。ウェナーは小柄で童顔で、ロックスターになるような人材には見えなかった。ロックスターになれない男の子が時めくためには、ロックを熱く論じれば良いのだ。かてて加えて、当時の社会は数々の問題を抱えており、ロックはそれらの問題にも深くコミットしていたから語るべきことは山ほどあったのである。1965年にはグレイトフル・デッドも結成され、新しい時代のロックバンドが登場していた。1967年にはサマー・オブ・ラブといわれるヒッピーたちのムーブメントが始まる。盛り上がって参りました、という空気が漂っていたのであろう。ヘイト・アシュベリーという土地に、自然発生的にヒッピーと呼ばれるような人たちが集まってきたという。自由を愛し、反権威的で当時としては非常識なファッションを身に纏った若者たちだ。ウェナーには同志であり導師ともいえる存在がいた。サンフランシスコ・クロニクル誌で長くコラムを書いていたラルフ・J・グリーソンである。グリーソンはジャズ世代のライター、コラムニストで、それ以前からジャズについての熱い文章を書いていたが、自分よりも若い世代の表現にも理解のある人で、ディランやビートルズ、ローリング・ストーンズの台頭に好意的だった。彼の読者だったウェナーは自分からグリーソンに近づいたのだが、30歳ほども年長のグリーソンとウェナーは意気投合し、仕事のなかったウェナーのためにグリーソンは物書きの仕事を与え、彼がローリング・ストーン誌を創刊する際には出資者の一人となった。グリーソンの先見の明は大したもので、基本的にはジャズ評論家でありながらボブ・ディランやビートルズ、ローリング・ストーンズが登場すると彼らをいち早く評価したのである。ロックの評論は「我々」の時代の音楽を熱い言葉で語ることが多いが、その先駆としてジャズ評論があったわけだ。1922年に刊行されたフランシス・スコット・フィッツジェラルドの短編集『ジャズ・エイジの物語』は1920年代の風俗を描くものであった。ジャズという音楽がエイジ、つまり時代と紐付けされている。そこにあるのは、今という時代を謳歌するのは自分たちの世代だという当事者の意識だ。そう、フィッツジェラルドは音楽と世代を紐付けたのである。ちなみに『ジャズ・エイジの物語』が出版された時、グリーソンは5歳くらいだったわけだが、彼と同い年でイギリスの歴史家にしてマルクス主義研究の大家エリック・ホブズボームはフランシス・ニュートンというペンネームで『ジャズシーン』という分厚いジャズ評論の本を書いている。これがなかなかに凄い本で、終盤の「抗議としてのジャズ」という章でホブズボームは、ジャズは抗議(プロテスト)と反抗の音楽であると語っている。思わぬところにカウンターカルチャーの先祖がいたわけだ。ホブズボームの処女作が『素朴な反逆者たち』という、反体制運動の源流を探る著作であったことと、彼やグリーソンがアラン・シリトーたちのように「怒れる若者たち」と呼ばれた作家たちより一回りほど歳上であったことは繋がっている。音楽を自分たちの時代と、つまりは世代感覚と紐付けして語る行為は少なくともフィッツジェラルドの時代にまでは遡れるわけだが、コラムや評論という形でスタンダード化させたのはグリーソンやホブズボームの世代だろう。また、フランスではサルトルの友人で作家にして音楽家でもあったボリス・ヴィアンが、ジャズに関してライナーノーツを含む文章をかなり残している。ヴィアンといえば、偽名で書いたアメリカ風の偽ハードボイルド小説から、ポップでシュールでどこか悲しい不思議な小説を書いた鬼才である。詩人でもあった彼の書くジャズ評には当然のごとくポップな表現が使われていた。ウェナーが創刊したローリング・ストーン誌の音楽と世情をポップでかつ熱く語るスタイルは、知ってか知らずか、ジャズの文化を継承していたのである。ホブズボームもグリーソンと同じく詩人としてのディランを評価し、ビートルズは大したものだと語る。とはいえ本人はジャズ贔屓なので、ジャズは後世に残るだろうがロックは後世に残るだろうか? みたいな話を別の著作で書いている。ちょっと可愛いお爺さんである。『ジャズ・シーン』は本職の歴史家が書いた本なので、ジャズを熱く語るのと歴史的な背景などをクールに分析する視線が両立されている点において立派な本である。それより後の時代のロックの評論においても、熱く語るアジテーター的な側面と、冷静な分析の両立が出来れば非常に好ましかったわけだが、雑誌メディアはコンサートのレポートや発売されたばかりの新譜を取り上げるから、どうしても喫緊の問題として熱く語る側面が勝ってしまう。難しいものでありますね。これは全てのジャンルにおける評論において共通する問題で、発表されてから何十年も経った作品に関しては割と冷静な評価ができる反面、出たばかりの新作を冷静に分析するのはかなり難しい。とはいえ、リアルタイムで発表された全くもって冷静ではない評論というのは、同時代の反応を後から知るための資料としてはかなり重要なものである。名作と呼ばれる作品が発表されたオンタイムで、これは失敗作だ! と語った人は星の数ほどいて、ある面から見るとその人たちは後の世において恥をかくことになるのだが、その人たちのオンタイムでの反応は歴史的に見ると資料としての価値が高い。ボブ・ディランがエレキギターを使った時に批判した人たちの反応が記録されたことは、歴史学的には価値があったわけだ。
グリーソンとウェナーの親族、友人などからかき集めた資金で創刊されたローリング・ストーン誌は、ほぼほぼ同人誌のような体でスタートした。ローリング・ストーン誌創刊時代のエピソードはまるでウェナーをリーダーとしたバンドを結成する物語のようだ。彼はいつもエネルギッシュで周囲の人たちを巻き込みながら前進した。いつ潰れてもおかしくなかったが、創刊1周年を迎える直前にジョン・レノンとオノ・ヨーコが全裸になった、誰も積極的に見たいとは思わないのにも関わらず全世界規模で流通した二人の写真を表紙に使用したことでローリング・ストーン誌は篦棒に売れた。この時点でレノンはおそらくアメリカの大統領よりも有名な存在であった。それが全裸である。この写真を表紙に使うことをウェナーに指示したのはグリーソンだったらしい。長らくメディアの業界人として生きてきた嗅覚のなせる技だろう。ローリング・ストーン誌はこの一件で、世間から広く認知され、編集長であるウェナーは有名人の仲間入りをした。キモオタがバズったのでパリピなセレブになったのだ。ともあれローリング・ストーン誌は広く認知され、ロックジャーナリズムが確立された。それは政治的なアジテーション、プロパガンダとコマーシャリズムの合体でもあった。ロックジャーナリズムの言説は、時に商業主義を激しく批判しながら、お金を儲けることになった。ウェナーは高価なスーツに身を包み、高級車を運転しながら商業主義的だと思われるミュージシャンを批判した。こういった、カウンターカルチャーの商業主義に対する煮え切らない姿勢は、当時のヒッピーたちが資本主義を否定も肯定もすることなく、小さなコミュニティを大切にしたのと繋がっている。資本主義が正しいのか、それとも正しくないのか、当時の人たちは答を出せなかったのである。
とはいえ、ローリング・ストーンは時代精神の象徴として認知された。当たり前の話だけれども勢いのある雑誌には有能な書き手が集まってくる。ウェナーより年配のハンター・S・トンプソンやトム・ウルフといった、これからの時代を牽引する書き手がローリング・ストーン誌で書くようになった。トンプソンにウルフといえば、ニュー・ジャーナリズム、ゴンゾー・ジャーナリズムの旗手である。長老的な存在であったグリーソンを筆頭にウェナーよりキャリアのあるライターが集結したのは、おそらく既成のメディアでは書けないようなことがローリング・ストーン誌でなら書けたからだろう。アメリカは新しい国であるが、歴史のない国家であるが故に保守層がそれなりに強い。この時期の大統領は民主党のリンドン・ジョンソンだったが、彼が大統領になったのは彼よりもずっと若くリベラルで希望に満ちた大統領と見られていたジョン・F・ケネディが暗殺されたからだ。そして選挙戦で一度はケネディに敗れたリチャード・ニクソンが再び権力の座に就こうとしていた。だからこそ彼らには書くべきことが山ほどあったのである。現代の視点から見れば、トンプソンやウルフは自分たちよりも若いヤン・ウェナーが巻き起こしたローリング・ストーン誌の波に乗ったわけだ。トンプソンやウルフの前にいたのはノンフィクション・ノベルと称されるルポタージュ的な小説『冷血』を書いたトルーマン・カポーティであり、戦後のベストセラー『裸者と死者』を書いたノーマン・メイラーである。二人とも物議を醸すタイプの作家であり、ヒップスターとしての文化人という側面があった。奇抜な言動で物議を醸すという点で、彼らは後のロックスター、たとえばレノンとライドンという二人のジョンのプロトタイプのようなところがある。あのような死に方をしてしまったがために、愛と平和の詩人というイメージが強いジョン・レノンであるが、存命中は奇矯な発言と行動で周りを振り回した人である。
ニュー・ジャーナリズムもしくはゴンゾー・ジャーナリズムの特徴は、報道においては本来必要とされる客観性よりも主観的な視点を重視することである。筆者による一人称が多用され、ノリの良い熱い文章で本人の感情が語られた。感情的な文章は熱意が伝染する、言わば時代を語るための口語体である。だからこそローリング・ストーン誌は若者たちから支持されて部数を伸ばしたわけだ。これはフランスにおけるジャン=ポール・サルトルのアンガージュマンに通じるものがある。アンガージュマンとは政治や社会問題への積極的な参加を意味する言葉で、当時のフランスの若者たちは「レイモン・アロンと共に正しくあるよりも、サルトルと共に間違おう!」というスローガンを好んで使ったと言われる。政治、社会運動に参加するぞ、そのためには間違っていても良いのだというロジックは現代の我々にはかなりわかりにくいものだから、何故そういう風潮が流行ったのかを説明する必要がある。社会学者、哲学者であるアロンはサルトルとは古い友人だが、フランスの大統領であったド・ゴールと親しかったこともあり、保守的で反動的な人物だと目されたのである。若者たちの間で、革新的で反体制的なサルトルと保守的なアランという対立軸があると認識され、サルトルの方が人気があったわけだが、どちらが正しいかではなくサルトルと一緒に間違えることが推奨されているのが肝要である。客観性よりも主観性を重視するとはどういうことか? 正しくあるよりも、共に間違えよう、とは如何なる考え方なのだろうか。
西欧における知性というのは、それこそアリストテレス辺りからずっと理性、合理性、論理性を重視してきたわけである。ところが、その西欧文明は20世紀には大きな戦争を起こし、公害で母なる地球を汚している。もしかしたら西欧的な知性には問題があるのではないか? という懐疑の念を抱き多くの人々が共有するのも不思議なことではない。この時代、数多くのロックフェスが行われる、路上ではデモ活動が頻繁に行われた。マイケル・S-Y・チウェの『儀式は何の役に立つか』によれば革命の祝祭からスーパーボウルのような大規模スポーツイベントなどの広義の儀式は、公共の空間において多くの人たちが共通の知識を共有するためにある。カウンターカルチャーと一口に言っても、フラワームーブメントのヒッピーから戦闘的な極左の政治集団まで様々な人たちがその波にのったわけだが、多くの人たちが西欧的な理性、合理性への懐疑を抱いていたのは確かである。だからこそ、東洋的な思想が人気を得た。ジョージ・ハリスンはインドのラビ・シャンカールに魅せられて彼の弟子となった。(この件に関してはインドがイギリスの植民地であったことも忘れてはいけないだろう。)日本の禅は、実は明治時代からアメリカに紹介されていた。1960年代の時点で既に歴史のある東洋思想だったのが、カウンターカルチャーの時代を迎えて若い層から注目されたのだ。禅のルーツはもちろん中国にあるが、この時アメリカで人気を得たZENは日本の、主に鈴木大拙と鈴木俊隆が広めたものだ。ジョブズが師事した乙川弘文をアメリカに招いたのは鈴木俊隆である。乙川はLSDなどもガンガンやっていたというから、まさにケルアックの『禅ヒッピー』だ。海外で日本の忍者のイメージが有名になるのが1960年代の半ばからである。なので、この時代の日本を海外の視点から見ると禅と忍者とSONYやHONDAのテクノロジーの国ということになる。なかなかにアメイジングでしょう。ウィリアム・ギブソンのサイバーパンクSF『ニューロマンサー』にサイバー千葉が登場するのは、こういった文脈を継承しているからである。そして毛沢東がいた。この時代、既にスターリン体制のソ連は恐ろしい独裁国家であったことが知られていたので、共産主義国家に対する懐疑の念はかなり広まっていたのだが、物書きとしての才能に長けた毛沢東は西欧の文化人たちに対して当時の中国はパラダイスであるかのようなプレゼンテーションを展開した。毛沢東が凄かったのは一重にこの点である。プロパガンダとプレゼンテーションではかなり違うように思えるが、彼はプロパガンダをプレゼンテーションのように行ったのである。その結果、西欧の文化人たちはこぞって毛沢東を讃えた。実際の毛沢東がヒトラーよりも恐ろしい怪物であったことが判明したのはずっと後である。
色々と錯綜してはいるが、この時代に西欧的な理性、論理性に対する懐疑の念が持たれたのは歴史的に見ればかなり価値のあることだった。何故かというと、従来の西欧的な知性においては、理性や合理性、論理性は感情、情動とは対立するものだと見られることが多かったわけだが、実はそう簡単な話でもないことが最近になってようやくわかってきたからである。21世紀においては医学を筆頭とする科学と、社会学のような人文学が交差して、新たな知見を生み出している。たとえば近年の状況をよく知らない人は、経済学と脳神経科学とはあまり関係がないように思っているのではないか。21世紀の前半を生きるホモ・サピエンスの大半が、それなりに教養のある人であっても、たとえば経済学と進化論の間には何の関係性もないと思っているのではないか。20世紀においては、たとえば感情と経済学の間に深い関係性があると考える人は滅多にいなかった。あったとすれば「オレの生活が苦しいのは国家の経済政策が間違っているからだ」というような視点である。この視点に関しては19世紀のマルクスがかなり深く考えてくれた。しかし実は、もっと根源的なレベルで感情、情動と経済学は深く関わっていた、のである。とりあえず、情動の評価説というのを紹介する。たとえば、怒っている人は何故に怒っているのだろうか? 目の前にある出来事が、怒るに値すると評価したから怒っているのである。スーパーのレジに並んでいたら、横入りする人がいて、貴方が怒りを覚えたとする。この時、貴方は横入りした人の行為を「怒るに値する」と値踏み、価値評価しているわけだ。これは、なかなかに経済学的な行動でしょう。たとえば自分の配偶者と自分の親友が、自分に内緒でセックスをしていたとする。それを知った時、貴方はどのような感情を抱くだろうか? 大抵の人は怒りと悲しみを抱くだろう。そして、怒りと悲しみが占める割合は人によってかなり違ってくるのではないか。さらに言うと、それを知ったことで喜びを感じる人もいるだろう。その場合、怒りや悲しみがカクテルされた状態を、甘露なものとして評価し、味わっているわけだ。この時、マゾヒストの脳内では怒りと悲しみが合体して更に別の感情が生まれていることに注目してほしい。情動は別の情動と合体して、新たな情動に変化したりするのである。この辺のことを考え始めると、ヒトの感情というのが途轍もなくややこしい代物であることが見えてくる。怒り、悲しみ、喜び、恐怖といったものを、我々は感情ないし情動としてひとまとめに捉えているわけだが、それぞれの機能、働き、仕組みには違いがある。ということは、脳の中で起きていることも、それぞれに違いがあるわけだ。
たとえば蛇を見た瞬間に恐怖や嫌悪感を感じる人がいるのは、おそらく本能と結びついている。なぜかと言うと霊長類の多くは、蛇を見ると怯えるからです。蛇の中には毒のある種類がいて、それを知っているからだ。毒のある蛇は、長さ数十センチくらいしかなくてもヒトを殺せるくらいの毒を持っていたりする。蛇を飼ったことのある人ならわかると思うけれども、たとえば長さ1メートルのヘビはまとまるとヒトの手のひらにちょこんと乗るくらい小さな動物だ。数メートルにまで成長する種類の蛇であっても、長さ1メートルの時点だと体感的には家猫より遥かに小さな可愛い小動物である。ヒトから見た場合、長さ30センチの蛇は、体感的には猫より小さな小動物だがヒトを死に至らしめるポテンシャルがある。逆に、毒のない蛇であっても体長が2メートルを超えると今度は飼い主を頭から食べてしまうポテンシャルがある。そして、ヒトの先祖は蛇がたくさんいる環境で生きてきた。霊長類を観察すると、仲間の猿が蛇を見て怯えるのを見た猿が、自分も蛇を恐るようになるといった例が見受けられる。これは文化的な学習だ。どうやら、ヒトを含めた霊長類が蛇を恐れるのは、本能に刻まれた側面と文化的に学習した結果が合体しているらしい、のである。その一方で、女王様に鞭打たれたマゾヒストが感じる喜びは、かなり高度に発達した文化がなければ生まれてこなかった感情ではないだろうか。そして我々は、蛇に対する恐怖も、マゾヒストの喜びも、感情、情動といった枠組の中に入れている。だから、感情とは何か? と考え始めた途端にややこしいことになるのだ。
たとえば、子供を叱る親のことを考えてみよう。小さな子供が、市販のコップやお皿を落として割ってしまった場合に、烈火の如く怒る親はまずいないだろう。軽く注意するか、怪我はなかったかと心配するのではないだろうか。ところが、子供の手によって破壊されたものが、お父さんが大切にしていたガンプラやプリキュアのフィギュアだった場合、お父さんはどのような反応をとるだろう。烈火の如く怒るかもしれないし、そんなには怒らないかもしれない。何故かというと、子供を激しく叱りつけた原因がプリキュアのフィギュアだった場合、それを知ったお母さんがお父さんを激しく叱る可能性があるからだ。激しく叱ってしまった後で、自分がお母さんから叱られる可能性に気がついて、子供に柔和な顔を見せるお父さんもいるだろう。この時、お父さんの脳内では激しい悲しみの感情と、冷静で経済的な損得計算が同時に進行している。これがたとえば、生まれて初めて立ち上がった赤ちゃんが、よちよち歩きで少し歩いた後に倒れ込み、お父さんの大切なコレクションを並べた棚に激突したとする。大切なガンプラや美少女フィギュアは倒れ、そのうちいくつかは破損する。無事なのは安定性の高いゴジラのフィギュアだけだ。この時、お父さんの脳内では、子供が初めて歩いた喜び、その子供が棚にぶつかったので怪我はしていないか? という心配、フィギュアが壊れた悲しみ、今の動きをスマホで動画撮影しておけば良かったという軽めの後悔、など複数の感情が同時に起きている。これが、わんぱく盛りな五歳児によって同じ行動が行われた場合、子供が初めて歩いた喜びはゼロだろう。そして、赤ちゃんに対してはあまり感じなかったであろう大切なものを破壊した子供への怒りがかなりプラスされるのではないだろうか。ご存じのように怒りと悲しみには相乗効果がある。同じガンプラを壊されるとしても、その犯人が赤ちゃんである場合と、やんちゃな五歳児である場合とでは反応が全く違ってくるのではないか。これはどういうことが起きているのかというと、我々の脳内に複数の感情を採点するレフェリーがいてですね、赤ちゃんが初めて歩いたから喜びポイント100点! とか、絶対に再販されないフィギュアが壊れたから悲しみポイントマイナス60点! という風に細かく採点しているわけだ。これが五歳児の場合には、初めて歩いた喜びポイントがゼロなので、子供が悪さをしたお怒りポイントが加算されて悲しみポイントも赤ちゃんが同じ行動をした時よりも大きくなる。人間ってややこしい生き物だと思いませんか? ここで重要なのは、感情の評価、ポイント計算そのものは割とクールに行われている点である。しかし、そのポイント計算が行われた途端に我々は冷静でいられなくなってしまう。感情が、ある一定のラインを超えると我々は怒りで物をぶっ壊したり、喜びで踊り出したりする。ノルウェーの社会学者ヤン・エルスターは『合理性を圧倒する感情』という著作の中で、それをストロング・フィーリングと呼んでいる。
アリストテレス以降、感情とか情動といったものは、理性や合理性、論理性と相反するものだという考えが西欧では主流であったわけだが、最近になってヒトの合理性や論理性は感情、情動がなければ作動しないらしいことがようやくわかってきた。我々はどうやら情動という燃料を使って、論理性というエンジンを駆動させるのである。この辺の事情については心理学と倫理の哲学者ジェシー・プリンツの『はらわたが煮えくりかえる』が詳しいのだが、耳から脳味噌が溢れるほど読むのが大変な本なので、先に同書の翻訳家による『感情の哲学入門講義』をお薦めする。
たとえば数学と科学は、ヒトの感情には左右されないわけです。17世紀から19世紀にかけて西欧では科学が非常に発達したので、産業革命に至るまでのブレイクスルーが起きた。イスラム社会や中国、インドにも古くから数学はあり科学もあったわけだが、いわゆる現代のテクノロジーと直結しているのは西欧の文化である。つまり19世紀の段階でテクノロジーによる文明社会の覇権を握ったのは西欧だったわけだ。西欧の人たちは論理性、合理性でもって数学や科学にアクセスし、成功を収めた。その結果が西欧の近代文明だ。ところが、そのテクノロジーの発達した西欧文明が何をやったかというと、先端のテクノロジーを使った世界大戦である。それに西欧的な文明は母なる地球を公害で酷く汚してしまった。西欧のインテリの中から、もしかして我々の西欧文明って、実はタチが悪いのではないか? と思う人たちが出てきたのも不思議な話ではない。だからサルトルやアメリカのカウンターカルチャー勢が、西欧的な知性、論理性に懐疑的な態度をとったことの意義は大きかったわけだ。これは、ロシア革命による共産主義国家の設立と並ぶような壮太なスケールで行われた一種の社会実験だったとも言える。もちろん実験には何らかの結果が伴い、研究室が爆発したりすることもある。ソ連という国家がスターリンという独裁者を産んだのはご存じの通り。ソ連の設立から崩壊までが壮大な社会実験であったという視点からすると、二度にわたる世界大戦もまた壮大な社会実験であったと言えましょう。世界大戦の被害は甚大ではあったが、人類はそこから戦争は良くないという学びを得た。我々は過去の事例から学ぶことで文明を発展させる動物である。だからこそ1960年代のカウンターカルチャーからも、なにがしかの学びを得ることができる。スティーヴン・ピンカーは『暴力の人類史』の中で「一九六〇年代における非文明化」について触れている。この本の主旨を一言で説明すると「人類は常に平和な方向に向かっており、今という時代は昔よりずっと平和なんですよ。ただし人類は時々バグる動物なので戦争や暴力事件が一時的に増えることもあるんですよ」てな感じである。同じような主旨を持つ本としてはマット・リドレーの『繁栄』、ヨハン・ノルベリの『進歩』などがある。ピンカーが本書の中で紹介しているのは、60年代に暴力事件が増加したというデータだ。ラブ&ピースが謳われた時代であるにも関わらず、である。一体、何が起きていたのだろうか? そう、サルトルと共にあったフランスの若者たちと同じように、何らかの間違いがあったのだ。
〈参考文献〉
マイケル・S-Y・チウェ『儀式は何の役に立つか――ゲーム理論のレッスン』安田雪訳、新曜社、2003
ヤン・エルスターは『合理性を圧倒する感情』染谷昌義訳、勁草書房、2008
ジェシー・プリンツ『はらわたが煮えくりかえる――情動の身体知覚説』源河亨訳、勁草書房、2016
源河亨『感情の哲学入門講義』慶應義塾大学出版会、2021
スティーヴン・ピンカー『暴力の人類史』上下、幾島幸子、塩原通緒訳、青土社、2015
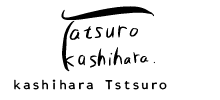 映画監督・脚本家・文筆家。一九六四大阪生まれ。大阪芸大在学中に海洋堂に関わり、完成見本の組立や宣伝などを手がけた後、脚本家から映画監督に。監督作に『美女濡れ酒場』、脚本作に『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説』など。著作に『海洋堂創世記』『「痴人の愛」を歩く』(白水社)、『帝都公園物語』(幻戯書房)がある。
映画監督・脚本家・文筆家。一九六四大阪生まれ。大阪芸大在学中に海洋堂に関わり、完成見本の組立や宣伝などを手がけた後、脚本家から映画監督に。監督作に『美女濡れ酒場』、脚本作に『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説』など。著作に『海洋堂創世記』『「痴人の愛」を歩く』(白水社)、『帝都公園物語』(幻戯書房)がある。
twitter

