ロックとはなんだったのか? 情熱的に語られがちなロックを、冷静に、理性的に、「縁側で渋茶をすするお爺さんのように」語る連作エッセイ。ロックの時代が終わったいま、ロックの正体が明かされる!?
ロックが黒人音楽と白人音楽の融合の産物であることはよく知られている。その頃のアメリカにいた黒人といえば、ほとんどがアフリカから奴隷として連れてこられた人たちの子孫だった。奴隷制度の歴史は古いが、アメリカ大陸が発見されたことから新しい局面を迎える。ヨーロッパとアフリカ、そしてアメリカ大陸を行き来して人と物資を運んだ、いわゆる三角貿易が始まったのだ。イギリスに於いて奴隷貿易の拠点となったのが、ビートルズを生んだリヴァプールという港町であったことはかなり重要ではないか。リヴァプールは港町であったが故に、20世紀に入ってからも、いち早くアメリカのレコードが入ってきたのである。ビートルズ以降のロックが、基本的に英語の音楽であり、アメリカとイギリスが互いに影響を与え合い、更にアフリカのリズムを取り入れたりもして進歩を続けたことを考えると、ロックの歴史は三角貿易を微妙に踏襲しているし、好意的な見方をすれば奴隷貿易でさんざん使われた航路の平和利用だったとも言える。
そもそも奴隷というのは、人としての尊厳や自由を奪われた人たちである。彼らはいろんなものを奪われた。まず、アフリカで使っていた言葉を禁止された。宗教も奪われた。そして音楽も奪われたのだ。多くの白人奴隷主は、奴隷たちが太鼓を使うことを禁止した。アフリカにはトーキングドラムという文化があって、太鼓の音で通信ができる。奴隷主は、奴隷たちがドラムで連絡しあって反乱を起こすのを恐れたのである。アメリカにおいては奴隷を使役した白人たちもアメリカ大陸にやってきて間もない移民だったから、奴隷の反乱が怖かったのだ。
こういった過酷な状況下でアメリカの黒人たちは、おそらくは自然発生的に自分たちの音楽を生み出した。これはかなり画期的なことだったのではないか。どんな民族であっても、音楽というのは過去の文化を継承し、伝承することで成立している。ところがアメリカの黒人においてはアフリカ音楽の伝統をぶった斬られ、なおかつ英語で新しい音楽を生み出す羽目になってしまったのだ。だからアメリカの黒人音楽は民族音楽の一種ではあるけれども、一旦はその歴史を切断された民族音楽なのだ。歴史を切断されたことは確かに悲劇なのだが、そういった状況下においては、ずっと続いてきた伝統的な音楽においてはなかなか起きないような新しい表現が生まれることもある。というのも、アメリカ黒人音楽に影響を受けたジャズやロックといった音楽においては歴史の切断が頻繁に見受けられるのだ。ロンドンパンクがそうですけれども、過去の大物ロックバンドを否定するわけです。そして、我々がやっているのは新しい、現代の文化を反映した音楽である、というような宣言・マニュフェストが行われる。
アフリカから連れて来られた黒人たちは、奴隷商人によって強制的に歴史を切断されたのだけれども、その黒人たちの末裔の音楽に影響を受けた白人の音楽においては、自主的に過去の音楽を否定して歴史を切断しようという動きが生まれた。これは白人の文化にレヴォリューションという概念があったからで、要するに歴史を意図的に切断することで新しい文化を生み出すという発想が白人の文化には存在していたのだ。たとえばマルティン・ルターによる宗教改革なんてのも歴史の切断によるレヴォリューションだろう。奴隷たちの歴史が切断されたのは理不尽な暴力でしかなかったが、その黒人音楽に影響を受けた白人のロックは意図的に歴史の切断を行うのだ。
ロックは音楽である以上、聴くだけで人から人へと伝搬するのだが、それ以外に音楽ではない話し言葉や活字といった言語によっても伝播する。ジャズ評論家やロック評論家といった職業が成立して、彼らの言葉がレコード、CDの売り上げを左右するのはジャズやロックが音楽そのものの魅力だけではなく、「それについて語る文化」と深くリンクしている証拠である。
人類の歴史において言語は非常に重要なツールであるが、言語には恐ろしい側面もある。異なった言語が出会うと、どちらかが勝ってしまい、負けた方の言語は消滅することがあるのだ。歴史上、宗教がらみのトラブルにおいては異教徒の書物を焼いたりすることはよく知られている。言語には、他の言語を侵略、征服してしまうような恐ろしい性質があるようなのだ。実際、アフリカから連れて来られた黒人たちも生まれ故郷の言葉を奪われてしまったから、19世紀にはアメリカの黒人音楽は英語で歌われていた。
ところが言語とは違って、音楽においては異文化が遭遇すると両者が混じり合うのである。フランスの人類学者ダン・スペルベルに『表象は感染する』という本があって、文化は感染するという説が論じられている。まさにウイルスが感染するように、文化も感染するというのだが、その代表が音楽だろう。ラジオから流れてきた流行歌が頭の中に残り、ふとした時に口ずさんだりしてしまうという経験は誰もがあるだろう。あれは感染しているのです。ロックやジャズは黒人音楽に感染した白人の音楽だと言って良いのだが、黒人の方も白人の音楽から何がしかの影響は受けており、相互で感染は起きていると考えるのが妥当だろう。言語と音楽は、ヒトが進化してきた上でかなり近い位置にあるのだが、異文化が遭遇した時に起きる出来事は真逆なのだ。
これは、どういうことかというと、たとえば我々は自分の知らない言語を話す人と遭遇すると、ちんぷんかんになりますね。この相手と意思の疎通をするのは困難だと思ってしまうし、実際に困難である。しかし、その人が歌を唄ったり、楽器を演奏したら、我々はどういう反応をするだろうか? 歌詞の内容が理解できなくても、歌が上手ければ拍手をするし、見たこともない民族楽器の演奏であっても、その演奏が見事であれば我々は拍手をする。つまり、その音楽の背後にある文化的なコードが全く理解できない状態であっても、これは良い音楽だ! と判断する能力を、どうやら人類は普遍的に持っているのだ。あと、子供の無邪気な歌声なんかにも我々の魂は敏感に反応する。幼児の歌声とお遊戯の仕草に、思わずニコニコしてしまわないホモ・サピエンスはあまりいないだろう。我々ヒトの脳は、そういう風にデザインされているのだ。もしも我々が音楽という文化を持たず、言語でしかコミュニケーションできない動物だったとしたら、世界は今よりもトラブルが多く、あちこちで無駄な争いが起きていたのではないか。
17世紀に始まった奴隷貿易の歴史の中で、白人の文化と奴隷である黒人の文化が分断されていたのは確かだ。しかし、その分断はいつまでも続くものではなかった。奴隷である黒人たちの音楽が、あまりにも魅力的だったからだ。19世紀にはミンストレルショーという舞台芸が生まれた。これは顔を黒く塗った白人の芸人が黒人を演じるもので、そこで演じられる黒人はコミカルに描かれていた。黒人を笑い物にしていたわけで、現在ではポリコレ的に再現不可能な文化だが、白人は白人なりに黒人の文化を理解しようとしていたのだ。後には黒人が自らミンストレルの黒人役を演じるようにもなった。白人の奴隷主と黒人の奴隷とは、文化的に分断されていたわけではあるが、お互いに歩み寄ろうとする動きは常にあった。なぜならば、同じ土地で生きている以上、セックスをして子供が産まれてしまう。往時のアメリカでは、黒人の血が流れていれば黒人として扱われたが、世代が後になるほどに色んな肌の色を持つアメリカ人が増えてゆくわけだから、線引きは難しくなる。それに加えて黒人奴隷は白人の奴隷主の子守の仕事を任されることも多かった。映画『風と共に去りぬ』で描かれているように、黒人の乳母に育てられた白人が、黒人に親しみを感じるのは当然だろう。アメリカにおける白人文化と黒人文化は、いずれ融合する運命にあったのだ。
黒人は黒人で、白人の文化の中で生き延び、豊かな生活を送るために芸能の技術を磨いた。白人主体の社会の中であっても、卓越した芸能人になれば並の白人よりも社会的強者になれるのだ。『風と共に去りぬ』でヒロインの乳母を演じたハティ・マクダニエルは黒人で初めてアカデミー賞を受賞したが、元々は牧師の父と歌手の母の間に生まれ、彼女自身も歌手として頭角を表した。黒人の音楽が多くの白人にとって魅力的であったが故に、貧しい生まれの黒人がミュージシャンとして認められることで、社会的地位と資産を手に入れるというロールモデルが成立したのだ。白人のジャズマン、レッド・ニコルズの半生を描いた映画『五つの銅貨』でニコルズを演じたのはダニー・ケイ。いわば白人による白人の音楽映画なのだが、クライマックスでクローズアップされるのはサッチモことルイ・アームストロングのダミ声である。この映画が作られた時点で既にサッチモは別格なポジションを確立していたのだ。それくらい白人は、黒人の奏でる音楽に魅了されていた。だから、ロックやジャズといった黒人音楽をベースとする文化そのものが、白人による黒人文化の簒奪であり、搾取であるという視点は昔からあるのだが、音楽というのはヒトが生み出した文化の中で最も伝染性が強いものである以上、一概に黒人に影響を受けた白人を泥棒扱いするわけにもいかない。黒人音楽が白人文化から影響を受けた面もあるのだし、音楽こそが白人中心の文化の中で黒人たちの地位を向上させるのに貢献してきたのだ。
黒人の奴隷による音楽に関する最初の記録は南北戦争の時期に遡る。トーマス・ウェントワース・ヒギンソンという、奴隷解放運動に熱心だった牧師は南北戦争で初めて黒人ばかりで編成された部隊の大佐となった。つまりヒギンソンは牧師にして軍人で、なおかつ文芸評論家でもあった。彼は部隊の黒人たちと接する中で、その音楽に魅入られ「黒人霊歌(二グロスピリチュアル)」という記事を書き、できる範囲で歌詞を記録した。これらの黒人霊歌はアカペラで手拍子、足拍子だけで歌われたらしい。興味深いのは黒人霊歌の歌詞がキリスト教から大きな影響を受けていることだ。ヨルダン川、モーゼといった旧約聖書に出てくる固有名詞がしばしば歌詞の中で歌われている。アフリカからアメリカに連れてこられた人たちと、その子孫がヨルダン川を直接知っていたとは思えない。奴隷たちの日常は過酷だったので、旧約聖書の言葉が一緒のファンタジーとして機能したのだろう。
奴隷たちは支配者の目を逃れるように夜中に集会を開き、我を忘れて歌い踊ったと伝えられている。おそらくはゴリラのパントフートにも似た、集団で忘我となる集会だ。日々の仕事が辛いからこそ、我を忘れて踊りたくなるわけです。そこから黒人霊歌(スピリチュアル)が生まれた。これがいわゆる現代のゴスペルのルーツである。ゴスペルはおそらく、世界で最もポピュラー音楽化した宗教音楽である。
奴隷たちは、綿花の畑で仕事をしながら歌を唄った。これがフィールド・ハラーと呼ばれるワーク・ソング、労働歌である。そして黒人霊歌やフィールド・ハラーから、ブルースが生まれる。
忘れてはいけないのは、アメリカは奴隷の労働力を搾取して経済力をつけ独立した国であると同時に、奴隷解放運動がアイデンティティともなっている国だという点である。アメリカの世論調査で歴代大統領の人気投票を行うと1位になるのはだいたいエイブラハム・リンカーンになる。奴隷解放で知られるリンカーンがオールタイムベストなのだ。ちなみに2位が初代大統領ジョージ・ワシントンだ。リンカーンがワシントンより人気があるということは、多くのアメリカ人にとって独立戦争以上に黒人解放と南北戦争の方が重要視されているということではないか。
ところで、17世紀には積極的にアフリカの黒人を商品としてアメリカ大陸に送っていた白人たちが、19世紀から20世紀にかけては、自分たちが散々行ってきた奴隷制度に反対するようになった。その頃、アメリカに住んでいた裕福な白人の多くは、お父さんやそのまたお父さんが黒人奴隷を働かせて、たくさん利益を得たから裕福になったわけだ。ところが、奴隷を使役してお金を儲けた白人の子孫の中から、奴隷制度に反対する声が出てくるというのは、何らかのシフトチェンジがあったのではないか? これはどういうことかというと人々の道徳心が進化したのである。17世紀の白人は、黒人を奴隷として売り買いしても、あまり心が痛まなかったのだ。みんなやってることなので、それが悪いことだとは思えないのである。ところがだ、それから二百年も経つと、自分と同じ人間を商品として売買するなんてあり得ない! 無理! という道徳心を獲得してしまうのだ。たとえば20世紀の初め頃の人類と、第二次世界大戦以降の人類では戦争に対する考え方がかなり違う。第二次世界大戦は敗戦国だけではなく戦勝国にとっても大きなダメージがあったので、人類全体が大きな戦争を忌避するようになった。前に、文化もまた進化すると書いたけれども、倫理、道徳というのも我々ヒトの文化で、常に進化を続けている。人類の平均寿命が常に少しずつ伸びているのは、複数の要因が積み重なった結果なのだが、道徳心の進化と医療技術の進化が両輪となって稼働しているからだと考えて良いだろう。雑な言い方をあえてすると、道徳心が進化すると、ミクロでは殺人事件が減少して、マクロでは大きな戦争が減少する。これを文明化と呼ぶ。ヒトは累積的な文化を有効に活用するので、常に新たな規範・法律を作る。日本でも昔は仇討ちというシステムが認められていたが、現在は廃止されている。これはどういうことかというと、個人的な復讐は良くない因果につながるので、あくまで公的な法律で裁きましょう、という話だ。たとえば家族を殺されたら、その相手を殺してやりたいと思うのは人情である。だがしかし、全ての復讐を認めてしまうと社会のルールが揺らいでしまうから、公正な裁判に任せて個人的な復讐はやめましょう、という話になった。大昔のヒトが考えた法律の一つであるハムラビ法典には、目には目をと書いてある。その時代と比べたら、道徳が進化して文明化が進んだので、犯罪者に対する罰則を、個人の復讐心から切り離すことになったのである。
こういった道徳心の進化に関して霊長類学者のリチャード・ランガムは『善と悪のパラドックス』の中で人類の自己家畜化という視点を導入した。我々は凶暴な野獣から大人しい家畜へと進化したわけである。家畜というと、あまり良くない印象があるかも知れないが、さしあたっては可愛い猫や犬をイメージしていただきたい。ヒトは分業と協力で激しい文化の進化を遂げたわけだが、お互いがお互いを飼い慣らすことで揉め事を減らしてきた。この、人類の自己家畜化は非常に重要なキーワードである。我々は、赤の他人から道を尋ねられると親切に対応する。ここで重要なのは、道を聞かれた時の我々が見返りを期待していない点である。なんと親切な動物なのだろう。見ず知らずの他人に対して道筋を説明するのは、我々がお互いに親切にしあって自己家畜化を成し遂げたからなのだ。
黒人たちの音楽は、宗教的な方向と世俗の歌に一旦は別れた。古いブルースを聴くと、そこで歌われているのは女性とのトラブルや労働の辛さなど、日常的なことがよく描かれる。神の国やモーゼを歌う黒人霊歌とは対照的なわけだが、ブルースは悪魔の音楽とも呼ばれた。実際、歌詞の中で悪魔が登場するブルースがあるし、ロバート・ジョンソンには十字路で悪魔と契約したから凄まじいギターテクニックを手に入れた、というフォークロアがある。ジョンソンは27歳で死んだので十字路・クロスロードでの悪魔との契約は伝説になった。彼の死因はよくわからない、それもまた伝説化、神話化に寄与した。後に若くして名を成したロックミュージシャンであるジミ・ヘンドリックス、ドアーズのジム・モリソン、ジャニス・ジョプリンなどの享年が軒並み27歳であったために、優れたミュージシャンは27歳で死ぬという27クラブの伝説が生まれたが、ヘンドリックス、モリソン、ジョプリンらは端的にいうとドラッグ禍の被害者でしかない。交通ルールが確立していない状態で、自動車の数が増えれば交通事故の件数も増えるだろう。彼らが27歳で死んだのは単なる偶然でしかないが、因果関係のないところに因果を見出すのがヒトという動物である。ロックという文化においては、現代の出来事なのに神話とか伝説とかが簡単に生まれてしまうのである。これは、ロックのという音楽の魅力がどのような過程を経て伝搬されるかという話とリンクしている。ロックは主にラジオと、ティーンの口コミ、フォークロアによって広まった音楽である。なのでロックにまつわる神話、伝説の類は都市伝説と同じようなプロセスを経て広まる。有名なミュージシャンがドラッグに酩酊してホテルの窓からテレビを投げたとかいう武勇伝はいくらでもあり、ミュージシャン自身も率先して無茶をしたからロックスターに憧れるティーンたちの間でそれらの出来事は神話のように語られたし、音楽雑誌もそういったスターの武勇伝を無邪気に書き立てた。
しかし、ロックというのは革新を謳いながら、実は割と保守的な文化である。多くのミュージシャンは自分に影響を与えたレジェンドに対してはかなり素直に尊敬の意を表する。二十歳そこそこのエルヴィス・プレスリーが三十路のB・B・キングと初めて出会った時、プレスリーはBBへ尊敬のを込め、貴方の音楽を聴いて育ったと語ったという。プレスリーは裕福ではない白人家庭の生まれで、黒人音楽が盛んなメンフィスで育った。10代で黒人音楽に感染していたのだ。BBもプレスリーの音楽を認めている。プレスリーは彼なりの方法で黒人音楽を継承したわけだが、それはアカデミックなものではない。アカデミックな伝統の継承というのは、茶道とか華道をイメージするとわかりやすい。宗家から宗家へと受け継がれるような文化だ。『文化進化論』を書いたアレックス・メスーディによると文化の継承には3つのパターンがある。まず重要なのは親から子へと受け継がれる縦の継承だ。これは変化する速度が遅い。黒人ブルースマンから、次世代の黒人ブルースマンに継承されるのはこのパターンだろう。それとは対照的に、変化する速度が速いのが友達から友達に伝達、感染するような継承のパターンで、メスーディはこれを横の継承と呼んでいる。もう一つのパターンは師匠から弟子に伝達する斜めの継承だ。BBキングからプレスリーへと継承されたのは斜めのパターンだと思われるが、黒人文化から白人文化へという越境が行われている。越境はイノベーションを生みやすい。たとえば、明治時代に日本の柔道を身につけた前田光世という人がいた。この人は世界各国を渡って柔道を普及させたのだが、ブラジルに滞在した時に地元の人たちに柔道を教えたら、教わった人たちは前田の技術を吸収してブラジリアン柔術という新たな競技体系を作ってしまった。BBの音楽が講道館で鍛えた前田の柔術だとしたら、プレスリーの音楽はブラジリアン柔術(akaグレイシー柔術)だったわけだ。
ロックンロールの始まりはというと、1951年にアラン・フリードというラジオのDJが「レコード・ランデブー」という番組の題名を「ムーンドッグズ・ロックンロール・パーティ」に変更したことがきっかけだ。フリードはこの番組でチャック・ベリーやリトル・リチャードといった黒人のR&Bをかけまくった。フリード自身は白人で、彼の番組も白人向けのものであった。日本人にはにわかに理解しがたいものがあるけれども、人種の坩堝と呼ばれたアメリカでは、白人向けの音楽、黒人向けの音楽というように市場が分離していたのだ。ある時、白人のティーンエイジャーたちが、黒人が演奏するR&Bで踊るのを見たフリードは、白人の若者に黒人音楽を広く聴かせようではないかと思い立ったわけだ。彼の思惑は的中した、彼の番組を聴いて黒人音楽で踊る白人のティーンエイジャーが大勢出現したのだ。これは人類の歴史の中ではなかなかに画期的なことである。何故ならば、チャック・ベリーの音楽に合わせて踊る白人の若者たちは、彼らの親の世代よりも黒人への偏見が少なかっただろうからだ。リンカーンの時代から幾星霜、文明化が進んでいた証拠である。黒人解放運動で有名なキング牧師は、有名な演説の中でリンカーンの演説を引用した。19世紀に生まれて19世紀のうちに死んだリンカーンと、20世紀に生まれたキング牧師の間に直接的な面識があったとは思えないが、リンカーンの演説はアメリカという国の文化資産として残されていたから、キング牧師はそれを有効活用したわけだ。リンカーンの演説は一回こっきりのライブであったが、19世紀のアメリカには活字メディアがあったので色んなメディアで印刷され、永久保存されることになった。文化の要は保存することだ。リンカーンが生きているうちにエジソンを筆頭とする発明家たちが音声を録音するメディアを発明していたら、彼の演説はレコーディングされていただろう。残念なことにエジソンが蓄音機を発明するのはリンカーンが暗殺された12年後である。惜しかった。とはいえ20世紀の前半には録音技術が発達したから、戦前の黒人ブルースマンの演奏がレコーディングされ、現代の我々がそれを聴いて楽しむことができる。今では、戦前のアメリカのブルースをYouTubeで聴いた、どこかの国の21世紀の若者がそれに影響を受けて、自分なりの音楽を発信したりできる。
フリードは一体何を発見したのだろうか。それは、消費者としての10代の若者たちである。第二次世界大戦が終わって何が起きたかというと大がかりな経済成長だ。それによってティーンのお小遣いが少しばかり増えたのである。ロックに先立って黒人音楽から生まれたのがジャズなのはよく知られているが、ロックンロールの消費者はジャズよりも低年齢層だった。10代の少年少女がロックンロールにお金を使えるようになったからこそ、ロックは70年代に世界を制したのだ。70年代から80年代にかけては、全世界で販売されるレコード・CDの大半はロックとディスコミュージックだった。世界で最も売れたレコードアルバムはマイケル・ジャクソンの『スリラー』で、『イーグルス・グレイテスト・ヒッツ』とAC/DCの『バック・イン・ブラック』がそれに次ぐ。音楽産業を支えていたのはまさにこの面子である。『スリラー』に収録された楽曲に、ポール・マッカートニーやエドワード・ヴァン・ヘイレンといった白人ミュージシャンが参加していることは注目に値する。まさに黒人文化と白人文化が交差する場となったからこそ、『スリラー』は世界で最もポピュラーなアルバムになった。異文化が交差した時には、両方の文化が前に進む。20世紀のアメリカで勃興したジャズやロックンロールは、まさに文化の交差だった。
ロックンロールはティーンの間で急激に広まった。広めるためのブースター的な役割を担ったのは何かというと、日本製のポータブルなトランジスタラジオだった。先駆的なメディアとして登場したラジオは、テレビの出現によって衰退するかと思われたが、ポータブルなトランジスタラジオの出現によって息を吹き返した。テレビは一家に一台だったけれども、ラジオは1人に1台というのが可能になったのだ。戦後の経済成長によってティーンの購買力が上がったとはいえ、レコードを何枚も買うにはお小遣いがいくらあっても足りない。しかし、ラジオがあれば、ヒット曲を何度も聴けるのだ。ポータブルなラジオはウェアラブルで、自分の部屋でラジオを聴くと自分1人の空間になる。戦後の日本の松下電器という企業が、それを可能にしたのだ。ポータブルなラジオと電卓は紛れもなく戦後の日本が生み出した革命だ。液晶の技術を大幅に推進したのは日本の電卓で、これがなかったら現代のスマホ文化はない。CASIOやSONYは確実に、一度は世界を変えたのである。そして60年代にはコンパクトなカセットテープが登場する。大きなオープンリール式のテープレコーダーをコンパクトな規格にしたのはオランダのフィリップス社だったが、フィリップス社はこの企画を今で言うオープンソースソフトウェアのようなやり方で解放し、日本の企業にも働きかけた。この頃、既にSONYはオープンリールのテープレコーダーでは大きなシェアを占めていたのだ。ちなみに日本の企業はオランダ人がカセットテープを発明する前から、ラジオ付きのテープレコーダーを作り始めていた。敗戦からまだ10数年、日本という国は戦前とはまた違う個性的な工業国家として欧米から注目されるようになっていた。1967年に後のPanasonicである松下電器が、翌年にはアイワがラジカセを発売する。日本は、ポータブルなトランジスタラジオ、ポータブルなテープレコーダー、その二つが合体したポータブルなラジカセというカテゴリーにおいて最先端だったわけだが、1979年にはウォークマンという怪物的なデバイスを発明してしまう。来日公演で日本にやってきたロックミュージシャンがウォークマンをお土産に買って帰り、これは凄いぞ! と友達に自慢することでウォークマンの存在は世界中に知られることとなった。基本的に英語圏の文化であるロックが世界中に流通したのは、戦後の日本という工業先進国がハブとして機能したからだ。そして、ウォークマンに衝撃を受けたアメリカ人はiPodを発明する。iPodは更に進化してiPhoneとなり、我々の生活を根本から変えてしまった。
ロックが英語圏の文化であることは言うまでもないが、日本とドイツは英語圏ではないにもかかわらず割と早い段階から自国のロックが生まれた国である。ドイツにはスコーピオンズのようなハードロックバンドから、カンやファウストといった特異なプログレバンドがいたし、日本のグループ・サウンズにはモップスもいればジャックスもいた。言うまでもなく、この2国は第二次世界大戦の敗戦国である。日本にもドイツにも米軍基地があったので、アメリカの最新の音楽が入ってきたのだ。それは、奴隷貿易で栄えたリヴァプールという港町に、いち早くアメリカのレコードが入ってきた構図と似ている。奴隷貿易も戦争も人類にとっては負の歴史なのだが、そこに人の行き来があり流通が派生すると思わぬ副産物が生まれる。文化というのは罪の歴史を背負いながらも前に進むのである。
〈参考文献〉
ダン・スペルベル『表象は感染する──文化への自然主義的アプローチ』菅野盾樹訳、新曜社、2001
リチャード・ランガム『善と悪のパラドックス──ヒトの進化と〈自己家畜化〉の歴史』依田卓巳訳、NTT出版、2020
アレックス・メスーディ『文化進化論──ダーウィン進化論は文化を説明できるか』野中香方子訳、NTT出版、2016
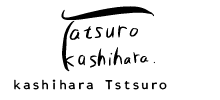 映画監督・脚本家・文筆家。一九六四大阪生まれ。大阪芸大在学中に海洋堂に関わり、完成見本の組立や宣伝などを手がけた後、脚本家から映画監督に。監督作に『美女濡れ酒場』、脚本作に『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説』など。著作に『海洋堂創世記』『「痴人の愛」を歩く』(白水社)、『帝都公園物語』(幻戯書房)がある。
映画監督・脚本家・文筆家。一九六四大阪生まれ。大阪芸大在学中に海洋堂に関わり、完成見本の組立や宣伝などを手がけた後、脚本家から映画監督に。監督作に『美女濡れ酒場』、脚本作に『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説』など。著作に『海洋堂創世記』『「痴人の愛」を歩く』(白水社)、『帝都公園物語』(幻戯書房)がある。
twitter

