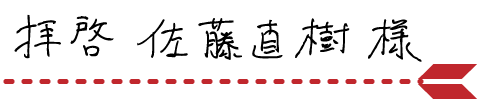2017年04月30日から2017年06月11日まで、千代田区の、「アーツ千代田 333メインギャラリー」で、「佐藤直樹個展『秘境の東京、そこで生えている』」が開催されました。板に木炭で植物を描いた作品はおよそ100メートルに及び、展示の方法も類を見ないものでした。そして、今も佐藤さんはこの続きをたんたんと描き続けています。展覧会を一区切りとしたわけではなく、展覧会から何かが始まってしまったということです。本連載は、佐藤さんの展覧会を起点に、文化人類学者の中村寛さんに疑問を投げかけていただき、「絵を描くこと」や「絵を見ること」「人はどうして芸術的なものを欲してしまうのか」など、世界についての様々な疑問について、語っていただく場といたします。
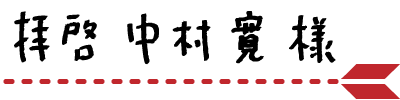
個展にお運びいただき、ありがとうございました。
展示会場でまず眼に飛び込んできたのが、黒とグレーの塊だったとのこと。その言葉に安堵しています。あの絵は、たしかにそのようなものとして描かれていました。
「そこに描かれているのが、木々であり草花であると認識できるまでに、しばらく時間があった」というところ、とても興味深いです。わたしは描いた本人なので順序が逆です。さきに木々や草花を見ている。そして描きながら「実際に見たものとはずいぶん違ってしまうものだな」と思います。絵が進むにつれて「現実に存在しているものと同じにならないのは仕方ないものの、それにしても違うな」と。そうして、時間とともにそのような認識自体が散けていき、最後には完全なる黒とグレーの塊のようなものになっていくのかもしれないのですが、つまるところその途上のような状態を晒しているわけです。
わたしは絵の個展というもの自体に強い抵抗を感じ続けてきました。それは匂いや音にも関わる問題でもあり、この機会にお話しておきたいことがたくさんあります。絵の個展というのは、それ自体かなり特殊な投げかけというか、設定な気がしているのです。今後も個展のような発表の機会がまた訪れるかもしれませんが、つねにそのこと自体を深く問うようにしなければと思います。「絵なら個展をしてあたりまえでしょう」という態度にはどうしても納得がいきません。
画集に掲載した対談で原田マハさんに最初の個展について教えてもらいましたが、わたしがやっていることのもとにあるのはどちらかというと見世物のようなものではないかと思うのです。池間由布子さんの歌が流れていた奥の部屋はそのようなイメージにかなり近いものだったかもしれません。「美術関係者」にはあまり評判がよくなかったようなのですが、そのことにはなるほどと納得できました。
さて、一つ目の問いですが、わたし自身はいま生きている他の人の絵をあまり見ないようになりました。とくに「個展」のようなものは。もちろんまったく見ないわけではありません。けれど意識的に見ることは以前に比べて少なくなりました。逆に、死んでしまった人の絵の展示はよく見ます。それは本質的な意味で「わからないもの」だからです。そう簡単にわかられたくないという意図を強く持った現代の作画者も数多く存在しますが、そのことと絵の本質的なわからなさは異なるので、そこを混同したくないという気持ちが強くなっているのかもしれません。
このような態度は現存する作家に対してひどく厳しいものになりますし、いずれ自分の首を絞めることにもなるのかもしれないのですが。
わたしがいま描いている最中の絵に人は登場しません。植物や鉱石がほとんどで、動いていると言えば水くらい。海だと思って見ている人も多いのですけれど、川を見て描いたのです。海や川の水はとてもよく動いています。意識的にそうしているわけではなく、いまのところそんな状態であるというだけです。
直接的には今現在そこで生えている身近なもので印象に残っているものをそのまま描いているつもりではいるのですが、その行動を促しているものは自分で意識できない層にあるのだと思います。それだから描いているのでしょうし。
深い森の中を歩いている時の足下の像、その時に同時に体中に伝わって来ている、音、空気感、疲労、そういったものがふと思い浮かぶのは眠りに着く時です。しかし、その様子を描くことは不可能ですし、描こうと思うこともありません。
子供の頃、父親によく山に連れて行かれていたことや、学生時代にも山に登っていたことも、もしかしたら関係しているのかもしれません。とはいえそれは今はじめて思い当ったことです。
二つ目の問いについて、「そこで生えている」植物たちは、「見た」ものがもとになっています。なにを見ているかと言えば外観です。内面のことはわかりません。科学的な方法によって植物の内面を知ろうとすることは今後かなり進むだろうと思います。けれどもわたしはそのような意味での方法論を持ち合わせませんし、今後も持たないでしょう。ですから、外観を眺めて、見たまんまのつもりでただ描いてみているだけで、それがすべてということになります。とはいえ、そもそも見たまんまに描くことなんかできないわけですが。
日本に西洋画が入って来て、もっと人間を正確に描けるようにならなければと、芸術大学には解剖学の研究室までできました。しかし解剖して描くというのは、いったいどういう種類の理解の仕方なのでしょう。そのことと人間の内面の問題が浮上していた時期が重なっているのは興味深いところです。それが近代ということなのでしょうか。
植物の外観を正確に描こうとする流れは、洋の東西を問わずあります。博物学であったり、花鳥風月であったり。でもわたしが今やっていることはそうしたものの流れとあまり関係していないと思います。もっと近視眼的というか、表面を撫でるように見ているだけなのです。かと言って、イームズ夫妻によるパワーズ・オブ・テンのように細部の細部にまで迫る意志もありません。引いて引いて宇宙を描き切るような意志も。
木を見て森を見ずというか、木から木へ、草から草へ、とただ彷徨っているだけとも言えます。最近は地面も多く描いているので、ミミズくらい出て来てもよさそうなものですが、まだ木や草、岩や地面、水面に留まっています。わたしが植物をわかりたい気持ちというのは、何て言うんでしょう、優しい気持ちとかではないのです。動物であることから逃げ出したいような。動物以外の生態に属したいというか、植物でもなくなって、鉱物になって、物質ですらなくなったらいい。その途上のような感じなのです。
そんなことは求めなくとも、あるがままの存在としてはすでにそうであるに違いないのですが。
宮沢賢治の世界観は凄いとわたしも思います。「人間でない存在、眼に見えない存在を、言語表現のうちにエージェントとして立ち上げなおすことに成功した」というのは、まったくそのとおりじゃないでしょうか。「あとはしんとした青い羊歯ばかり/そしてそれが人間の石炭紀であったと/どこかの透明な地質学者が記録するであらう」(「詩ノート『政治家』」)といった情景描写にはひどく魅かれるものがあります。
三つ目の問い、「そこで生えている」というタイトルについて。2014年の「トランスアーツ東京」というアートイベントに参加することになり、校舎ビルが取り壊されて地下空間だけ残った東京電機大学の跡地が会場だったのですが、そこでなにをするかという話になったときに、いつものことでまずは周囲をうろうろとしてみたのです。そこで出会ったというか、目に入ってきた植物を壁に描き始めた。それを見た人から「なにを描いているんですか?」と訊かれて思わず出た言葉です。
「止まることなく、止められぬまま、生い茂り、増殖し、生成変化をつづける植物」の姿は絵に描いたりしなくとも、そのようなものとしてあるわけです。しかし「そのようなものとしてある」という認識の重要さは、意味や情報としてあるわけではないように思うのです。
わたしのなかで、描く行為はまだ「反応」のレベルです。いまはこの「反応」を信じるしかありません。「なにになりたがっているか」はいまのわたしにはまだなんとも言えませんが、おそらくはこれから、新たな問いとして跳ね返ってくることになるんじゃないでしょうか。「そのようなものとしてあることをほんとうにわかっているのかな?」と。
そんなわけで、いまは少し苦しい時期に入っています。無心になって、身体が反応するまま描いているうちに数年が経ち、身体的な喜びに浸り切ることも難しくなっています。長く封印してきた「描く」行為が頭をもたげるようになったのは2011年よりもまえでしたが、地の底からやってきた揺さぶりは、ここ数年の行為のすべてに関係していると思います。そのことが強い「反応」を促していたのでしょう。けれども、あっという間に、何もなかったかのような日常がやってくることになりました。
わたしたち自身、一種の自然物であるはずです。と同時に、そこから疎外された存在であることもたしかです。その媒介というのか、往復というのか、そういうところに、ある手応えを感じます。このあと自分がどうなるのか、正直まだわからないのです。描き続けるであろうということ以外。
長谷川等伯の松林図であれ、横山大観の生々流転であれ、何らかの要請があったのだと考えていいと思います。安土桃山時代でも明治時代でもない現在、絵は「自己表現」として描かれるものであるということになっています。しかし「自己表現」とはそもそも何のことを言っているのでしょう。
今という時代に、「自己表現」としてではなく、またビジネスとしてでもなく、なお描くことを止めないとするならば、それはどのような行為として継続できるのか。腕を組んで考えていても仕方ありませんから、描き続けるなかで探るしかありません。
こちらも好き勝手に、とりとめなく書きました。自由に論を進めていただければと思います。
敬具
2018年2月14日
佐藤直樹拝
Profile
 1961年東京都生まれ。北海道教育大学卒業後、信州大学で教育社会学・言語社会学を学ぶ。美学校菊畑茂久馬絵画教場修了。1994年、『WIRED』日本版創刊にあたりアートディレクターに就任。1998年、アジール・デザイン(現アジール)設立。その後、数多くの雑誌、広告、書籍等を手掛ける。2003~2010年「CENTRAL EAST TOKYO」プロデューサーを経て、2010年よりアートセンター「3331 Arts Chiyoda」デザインディレクター。現在は美学校講師、多摩美術大学教授を務める。画集に『秘境の東京、そこで生えている』(東京キララ社)、著書に『レイアウト、基本の「き」』(グラフィック社)、『無くならない――アートとデザインの間』(晶文社)などがある。 web
1961年東京都生まれ。北海道教育大学卒業後、信州大学で教育社会学・言語社会学を学ぶ。美学校菊畑茂久馬絵画教場修了。1994年、『WIRED』日本版創刊にあたりアートディレクターに就任。1998年、アジール・デザイン(現アジール)設立。その後、数多くの雑誌、広告、書籍等を手掛ける。2003~2010年「CENTRAL EAST TOKYO」プロデューサーを経て、2010年よりアートセンター「3331 Arts Chiyoda」デザインディレクター。現在は美学校講師、多摩美術大学教授を務める。画集に『秘境の東京、そこで生えている』(東京キララ社)、著書に『レイアウト、基本の「き」』(グラフィック社)、『無くならない――アートとデザインの間』(晶文社)などがある。 web

文化人類学者/多摩美術大学准教授/人間学工房代表。一橋大学大学院社会学研究科地球社会研究専攻博士課程修了・博士(社会学)取得。専門領域は文化人類学。アメリカおよび日本を当面のフィールドとして、「周縁」における暴力や社会的痛苦とそれに向き合う文化表現、差別と同化のメカニズム、象徴暴力や権力の問題と非暴力コミュニケーションやメディエーションなどの反暴力の試みのあり方、といったテーマに取り組む。その一方で、《人間学工房》を通じて、さまざまなつくり手たちと文化運動を展開する。著書に『残響のハーレム――ストリートに生きるムスリムたちの声』(共和国、2015年)、編著に『芸術の授業――Behind Creativity』(弘文堂、2016年)、訳書に『アップタウン・キッズ――ニューヨーク・ハーレムの公営団地とストリート文化』(大月書店、2010年)がある。『世界』(岩波書店)の2017年10月号から、連載「〈周縁〉の『小さなアメリカ』」がスタートした。 web