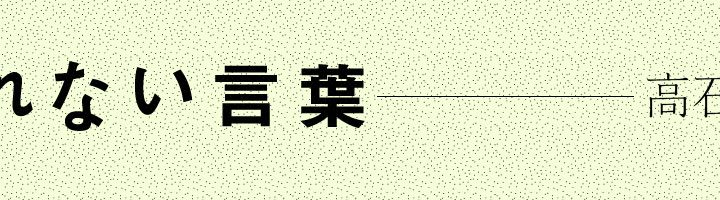数年前、美味しいということについて感覚がひらかれたことがあった。
ある料理を口に運んだとき、そこにはなにも残らなかった。
そんなはずはない。再び口に運んでみると、すっと消えていく幽かなものがあった。
その消えていく様子は、小さな光が暗闇の奥へと進んでいくようだった。
今の感覚は気のせいだろうか。
もう一口、新たに味わうと、それはまた起こった。
か細い尾を引きながら、光は暗闇の奥へと進んでいく。
それを追いかけた。
目を閉じ、残っている余韻を頼りに、味が向かった先を見つけようとしたが、それはもうすでに遠くに行ってしまったあとで見つからなかった。
そして、もう一口。
光が生まれる。
確かめようとしてはいけないのだ。無心になって、その料理がもたらすものを味わった。
そのときすっと、進んでいくそれに手をとられて、引っ張られた。
「こっちだよ」というように。
幽かに続いていく味は僕を見知らぬ暗闇の奥へと連れていく。
でも、あぁ、もう集中が切れそうだ。それ以上ついていけそうにない。
それはすっと遠くへと消え去っていった。
我に返ると、店主が目の前で次の一品を作っていた。
座っていたのは木のカウンターが仄かに照らされた、薄暗い店内だった。店主が茄子に入れている包丁の音だけが小さく響いていた。
その音は呼吸の隙間にそっと優しく入り込んでくる。
店主は僕がさっきまで旅をしていたことを知っているに違いなかった。
Profile

1980年生まれ。慶応義塾大学文学部仏文学専攻中退。初の著書『あなたは、なぜ、つながれないのか―ラポールと身体知』(春秋社)がロングセラーとなる。他に宮台真司らとの共著『「絶望の時代」の希望の恋愛学』(KADOKAWA/中経出版)がある。