選挙で正しい選択ができるほど、多くの有権者は政治的な知識を持っていない。このように指摘するのは、法学者のイリヤ・ソミンである。ソミンによれば、大学進学率の上昇など教育水準が上がり、インターネットなどで情報の入手も簡単になったのに、ここ数十年間ひとびとの政治的知識のレベルはおおむね低いままにとどまっているという[1]。
たとえば、2010年11月のアメリカ中間選挙では「経済」が最大の争点であったが、有権者の3分の2が、前年に経済成長したのかどうか、を知らなかったという[2]。また、2014年3月にロシアがクリミアに侵攻した際、アメリカによるウクライナへの軍事介入を最も強く支持したのは、ウクライナの位置を世界地図で示せないひとびとだった[3]。つまり、「ウクライナへの軍事介入を支持するぞ、ウクライナがどこにあるのか知らんけど」という状態だったわけである。政治について何も知らない有権者ばかりがいる状況では、「熟義民主主義」なんてとんでもない話で、現政権を信任するかどうか、といった投票さえも難しい。「選挙に行こう」と呼びかけてみても、正しい判断など期待できない……。これがソミンの見立てである。
このような政治的な無知の蔓延は、アメリカにかぎった話ではないだろう。参議院選挙を控えた日本でも安倍政権を支持・反対する言説があふれているが、どれぐらいのひとが安倍政権の政策を知っているのだろうか。たとえば、2015年には安保法制への反対運動が盛り上がったが、支持・反対したひとのうちの何人がその条文を読んだのだろうか(かつての60年安保でも日米安保条約の条文をだれも読んでなかったと評論家の西部邁はよく言っていた)。有権者の大半は「安倍政権に支持・反対するぞ、なにをやったか知らんけど」なのではないか。しかし、TwitterをはじめとしたSNSには、「選挙へ行こう」と投票を呼びかけ、政治的な話題をRTするひとびとにあふれている。だが、ソミンによれば、そのようなひとびとが持つ政治的な知識もバイアスがかかったもので、期待できないという。
ソミンによれば、「政治的無知」は、ひとびとの「愚かさ」からくるのではなく、「合理的行動」の結果である[4]。そのうえで、ソミンは政治的無知をふたつのタイプに区別している。ひとつは「合理的無知」と呼ばれるタイプだ。自分の一票が選挙結果を左右することはほぼないために、おおかたの有権者にとって「政治的知識獲得のためにほとんど努力をしないことが合理的である」[5]とされる。仕事、趣味、勉強といった日々の生活に忙しく、政治なんぞにかまっていられないというわけだ。
もうひとつは、「合理的非合理性」と呼ばれるタイプである。ひとびとが政治的知識を得るのは、よりよい政策を選択するためではなく、「政治ファン」であるためというのだ。つまり、自分のひいきする政党に結びつき、反対者をあざけることに喜びを感じたり、自分が所属する集団やコミュニティから承認されるために、政治的知識を獲得する。もちろん、そのような知識の多くはバイアスがかかり、偏ったものになりやすい。実際に「人々は政治的争点についてすでに持っている見解を強化するために新しい情報を利用する傾向があるが、反対の情報は割り引く」[6]ことが研究結果で示されている。しかし、これらの行動もまた「合理的」である。「彼らの目標が、よりよい投票をするために特定の争点に関する「真理」に到達することではなく、政治的「ファン」であることの心理的利益を得ること」[7]であれば、十分に合理的だといえるからである。
「合理的無知」と「合理的非合理性」――ふたつの政治的無知が組み合わさると、ひとびとは根拠の乏しいフェイクニュースにあっさりとだまされてしまう[8]。保守やリベラルといった立場に関係なく、多くのひとが陰謀論を信じているようだ。たとえば、アメリカの共和党支持者の45パーセントが「バラク・オバマは合衆国で生まれたのでないから、大統領になる資格がない」と信じていたし、民主党支持者の35パーセントが「ジョージ・ブッシュ大統領が9・11同時多発テロの攻撃を事前に知っていた」と信じていた[9]。
しかし、このような論点は『選挙の経済学』(ブライアン・カプラン、日経BP社、2009年)などでよく知られているところである。ソミンのオリジナリティは、政治的無知の解決策として「小さな政府」と「足による投票」を示したことにある。つまり、政府がその機能を縮小すれば、政治判断に必要な情報が少なくなり、有権者の理解も可能になるだろう。従来の「紙による投票」ではなく、「足による投票」=自分が支持する州に移住することをもって投票に代えることで、有権者はもう少し真面目に勉強するだろう、というわけだ。
ここで注意が必要なのは、「足による投票」もまたリバタリアン的な「脱出 Exit」であるということだ。ソミンの提案は、各人がそれぞれ理想のユートピアを追求し、複数のユートピア同士が競争するというロバート・ノージックの「メタユートピア」論や、すでに紹介したCEO的な君主が統治する国家を、有権者が株主のように選択できるという「新反動主義」に共通する、リバタリアン的な発想である。しかし、「足による投票」は、各州の独立性を重視する連邦制を敷くアメリカにおいて、自由と民主主義の両立をギリギリのところで目指した提案だといえる。
だが、ひとびとの「無知」が合理的な行動の結果ではなく、逃れがたい人間本性から由来するとすれば、どうだろうか。認知科学者のスティーブン・スローマンとフィリップ・ファーンバックによれば、ひとびとは「自分がものを知っている」としばしば錯覚する。
たとえば、ほとんどのひとは「水洗トイレ」を知っているが、どのような仕組みでトイレに水が流れるか、説明できるひとはほとんどいない。記憶力や認知能力には限界がある人間は、身体、他者、技術といった「外部環境」を「記憶装置」や「情報処理装置」として利用する。自分の脳に入っている情報と外部環境に存在する情報を、シームレスに扱う設計となっている。だが、そのためにいざ物事を説明しようとしたら、知っているつもりなのに答えられなくなってしまう。「人間は自分が思っているより無知である」[10]のだ。
しかし、「生兵法は大怪我のもと」といった人生訓だけが、ここから引き出されるべきではない。重要なのは、人間の知は協働するコミュニティや集団のなかで生まれる、ということだ。「人は集団意識のなかで、他者や環境に蓄積された知識に依存しながら生きているので、個人の頭の中にある知識の大部分はきわめて表層的である」。しかし、「それでも生きていけるのは、知識のさまざまな部分の責任をコミュニティ全体に割り振るような認知的分業が存在するからである」[11]。スローマンとファーンバックは、人間が集団やコミュニティで知識を共有したことが、人類が高い知能を獲得した進化的な要因となり、高度な文化を形成した理由であるとしている。
だが、スローマンとファーンバックが指摘するように、このような人間の「認知の特徴」は「バグ」でもある。スローマンとファーンバックはリベラルと保守の二極化に言及し、ひとびとは知をコミュニティで共有するために、自分では何も考えなくなると指摘する。
複雑さを受け入れる代わりに、特定の社会的ドグマに染まってしまう人が多い。私たちの知識は他の人々のそれと一体化しているため、信念やモノの考え方はコミュニティが形づくる。仲間内で共有されている意見を拒絶するのは難しいので、その妥当性を評価しようとすらしないことも多い。自分に変わって所属集団にモノを考えてもらおうとする[12]。
そして、コミュニティで共有された知は強固になり、増幅し、先鋭化してく。たとえ、それが間違いであったり、根拠がなかったりしても。
あなたが話す相手はあなたに影響され、そして実はあなたも相手から影響を受ける。コミュニティのメンバーはそれぞれあまり知識はないのに特定の立場をとり、互いにわかっているという感覚を助長する。その結果、実際には強固な支持を表明するような専門知識がないにもかかわらず、誰もが自分の立場は正当で、進むべき道は明確だと考える。誰もが他のみんなも自分の意見が正しいことを証明していると考える。こうして蜃気楼のような意見ができあがる。コミュニティのメンバーは互いに心理的に支え合うが、コミュニティ自体を支えるものは何もない[13]。
つまり、スローマンとファーンバックによれば、「合理的非合理性」が生じるのは、知を集団やコミュニティで共有するという人間の「認知の特徴」から生まれる[14]。そして、それがフェイクニュースやデマの温床となる。反ワクチン運動や脱原発運動、エコロジー運動には、しばしば科学的な根拠のない、フェイクと呼べるような言説が見られる。しかし、その支持者に客観的な情報を提示してもほとんど効果が見られないのは、知が「信念」と一体となっており、「共有された文化的価値観、アイデンティティ」と深く関わっているからである。
特定の信念を捨てるということは、他のさまざまな信念も一緒に捨てること、コミュニティと決別すること、信頼する者や愛する者に背くこと、要するに自らのアイデンティティを揺るがすことに等しい。こうした視点に立てば、遺伝子組み換え技術やワクチン、進化論、あるいは地球温暖化について少しばかり情報を提供したところで、人々の信念や意識がほとんど変わらなかったのも不思議ではない。文化がわれわれに及ぼす影響力は、啓蒙の努力によって覆せるものではない[15]。
近年、ジョナサン・ハイトやジョシュア・グリーンは、人間の道徳的判断が、熟慮された論理的なものではなく、直観的・情動的なものであり、その直観的な判断のちがいがリベラルや保守といった政治的対立に結びつくことを明らかにした。ジョシュア・グリーンは、私たちが「利己的な理由から、ある道徳的価値観を他の価値観より支持する場合がある」[16]という「道徳部族」であると指摘したが、スローマンとファーンバックが指摘するのは、私たちは知識にかんしても「部族」的かもしれない、ということだ。ワクチンは人体に悪影響を及ぼすという「部族」があり、地球温暖化はウソだという「部族」があり、アウシュヴィッツはなかったという「部族」があるわけだ。しかし、彼らは間違った知識や信念を抱いているから「部族」的なのだ、と言いたいのではない。賢いエリートと愚かな大衆がいる、といった愚民思想ではないのだ。私たちは多かれ少なかれ「部族」的なのである。スローマンとファーンバックは、科学における「立証の力」を重視しつつも、科学者も「コミュニティに頼っている」と指摘するように、専門知もまた「部族」的なのである[17]。
TwitterやFacebookでは、反ワクチンや放射能、歴史修正主義などをめぐって、専門家や素人が入り混じって論戦がおこなわれるも、平行線をたどったまま終わるのは、人間の「部族」的な特徴からして当然だといえる。対立意見を「論破」することはコミュニティからの承認欲求を満たし、「部族」の結束感を高めるばかりだろうし、見たいものしか見ないというネットは「部族」的な知や信念をさらに極端なものにしていくだろう。さて、私たちはみずからが「部族」的であることと、どううまく付き合えばよいのか。もちろん、その部族制を考慮に入れなければ、私たちは知に基づいた正しい判断などできっこないのである。
ところで、今回の選挙の結果はあなたにとって正しい判断でしたか?
[1] イリヤ・ソミン『民主主義と政治的無知』森村進訳、信山社、2016年、p.68
[2] ソミン、前掲書、p.1
[3] スティーブン・スローマン+フィリップ・ファーンバック『知ってるつもりーー無知の科学』土方奈美訳、早川書房、2018年(電子書籍版参照のため、以下頁数は割愛。書籍化の際に明記)
[4] ソミン、前掲書、p.4
[5] ソミン、前掲書、p.4
[6] ソミン、前掲書、p.82
[7] ソミン、前掲書、p.82
[8] ソミン、前掲書、p.87
[9] ソミン、前掲書、p.87
[10] スローマン+ファーンバック、前掲書
[11] スローマン+ファーンバック、前掲書
[12] スローマン+ファーンバック、前掲書
[13] スローマン+ファーンバック、前掲書
[14] スローマン+ファーンバック、前掲書
[15] スローマン+ファーンバック、前掲書
[16] ジョシュア・グリーン『モラル・トライブズーー共存の道徳哲学へ(上)』岩波書店、2015年、p.88
[17] スローマン+ファーンバック、前掲書
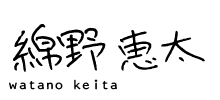 批評家。1988年生まれ。元出版社勤務。詩と批評『子午線』同人。論考に「谷川雁の原子力」(『現代詩手帖』2014年8-10月)「原子力の神―吉本隆明の宮沢賢治」(『メタポゾン』11)など。その他、『週刊読書人』や『現代ビジネス』などに寄稿。新刊『「差別はいけない」とみんないうけれど。』(平凡社)が発売中。twitter
批評家。1988年生まれ。元出版社勤務。詩と批評『子午線』同人。論考に「谷川雁の原子力」(『現代詩手帖』2014年8-10月)「原子力の神―吉本隆明の宮沢賢治」(『メタポゾン』11)など。その他、『週刊読書人』や『現代ビジネス』などに寄稿。新刊『「差別はいけない」とみんないうけれど。』(平凡社)が発売中。twitter

