(承前)とはいえ、吉本隆明が念頭に置いていたはずのヘーゲルの市民社会論においてすでに「深刻的な道徳的分断」が見られるのである。社会学者の稲葉振一郎が指摘するように、同じく「規範理念」としての「市民社会」の源流となったアダム・スミスに比べて、ヘーゲルの市民社会論は「労働」という「陶冶」を重視したものの、実は「道徳的に分断されている」のである。学者、法律家、軍人、官僚などの「普遍的身分」、農民や土地貴族などの「直接的身分」、商工業者などの「形式的身分」、それぞれの「身分」において「道徳」は異なるのである[1]。すでにヘーゲルの市民社会に「政治的部族主義」の萌芽があったとはいえないか。
みずからの党派に有利になる情報であれば、ひとびとはたとえフェイクニュースであっても簡単に飛びついてしまうし、陣営内部での評判を高めるために信じていない陰謀論を語ってしまう。客観的な判断よりも、みずからのアイデンティティの承認を優先させる「政治的部族主義」は、選挙といった民主主義的な制度でより顕著となる。人類の進歩を楽観的に描いた『21世紀の啓蒙』の著者スティーブン・ピンカーでさえ、選挙は「人間の最も不合理な部分をわざわざ引っ張り出すようにできている」と述べる[2]。みんな政治で馬鹿になる、というわけだ。
しかし、人間は馬鹿で救いようがない、ということがここで言われているわけではない。わたしたちには狩猟採集時代に獲得した「本能」があり、多種多様な人間が暮らす現代社会という「環境」において、その「本能」がうまく働かず、しばしば誤作動を引き起こす、ということなのだ。たとえば、46×49という計算は暗算できなくとも、紙と鉛筆、そろばんを使えば答えが出せる。寝る前に目覚ましのアラームをセットすれば、毎朝決まった時間に起きている。「道具」を使い「環境」さえ整えれば、私たちは適切に判断できるし、行動することができる。つまり、私たちは、あまり賢くない「生物学的な脳」の能力を高めるために「デザイナー環境」を構築している。「人間の思考と理性」は「物質的な脳、物質的な身体、そして複雑な文化的・技術的環境の間のループする相互作用」から生じてきた[3]。私たちは「生まれながらのサイボーグ」[4]であり、「脳・身体・テクノロジーから成るマトリックス」[5]なのである。
このような人間像は認知科学ばかりではなく、フェミニズムやケア、当事者研究といった方面からも現れている。当事者研究はソーシャルワーカーであった向谷地生良らが設立した「浦河べてるの家」で2001年に始まったとされる[6]。これまで治療・研究対象とされてきた当事者みずからが、同じような悩みや障害を持つ当事者とともに、みずからの症状について研究をおこなうものだ。
脳性麻痺の当事者研究をおこなう熊谷晋一郎はこれまで自明視されてきた自律/依存という対立を転倒させようとしている。「自律」できる人々とは従来誰にも依存せず、誰からも強制されない、意志が強いひとびとだと一般的には思われている。しかし、そのような「自律」している人々は、依存できるひとやものを多く持っており、一つ一つの依存先への負担が少ないために「自律」しているように見えるのではないか、と熊谷は指摘している[7]。
たいして、依存症の当事者は意志が弱く、自己決定できない人間だと一般的には思われている。しかし、依存症のひとびとは、幼少期に虐待を受けるなどの経験から人間不信に陥っているケースがしばしばある。結果、依存できる人間が周囲にいないために、ギャンブルやアルコールといったひとつのモノに深く依存してしまう。つまり、依存症の当事者は、他者に依存すべきではないという考えが人一倍強い「自律」的なひとびとなのであり、彼らにたいして「意志を強く持て!」といった考えを押し付けることは、治療において逆効果となる。そのため、アルコールの依存症の自助グループでは「自己決定や自己コントロールを行う能動的かつ近代的な主体を降りること」がまず目指されてきたのだという[8]。
「自己決定や自己コントロールを行う能動的かつ近代的な主体」はケアに注目したフェミニズムによっても批判されてきた。社会学者の上野千鶴子は、フェミニズムはそもそも女性が「男なみ」の「強者」になることを目指したものではなく、「弱者は弱者のまま尊重される社会」をつくる思想だと述べている[9]。近代社会が想定する市民は「自律的」な主体を理想化され、その担い手はもっぱら男性と見なされてきた。しかし、男性が自律的な「強者」だと見なされたのは、もっぱらケアの役割を女性に押し付け、自らの依存を認めてこなかったからだ。老人や子供をケアする役割を押し付けられてきた女性もまた男性に依存せざるをえない「弱者」とされてきた。しかし、人間は幼い頃は他者に育てられ、老いれば介護なしには生きられなくなる。「わたしたち全ての者が無力な存在として生まれてくることは、否定しえない人間の条件」なのである[10]。
当事者研究やフェミニズムは、新自由主義的な「自己責任」に親和的である自律的な強者にたいして、傷つきやすく他者に依存しなければ生きていけない弱者を対置するだけなのではない。傷つきやすく弱いものたちの「つながり」や「共助」を称揚することは、社会福祉の削減を掲げ、民営化を進める新自由主義にとって何ら抵抗とならない。むしろその民営化を推し進めるきっかけになってしまう。ではなく、これまで自明視されてきた「自律/依存」という対立を、「依存先の多さ/少なさ」と書き換え、価値転倒することによって、「弱者は弱者のまま尊重される社会」を生み出すことが目指されている、というべきである。
ところで、ジョセフ・ヒースは認知科学における「二重過程理論」の観点から現代人の肥満について次のように述べているが、熊谷晋一郎が依存症について述べたこととほぼ同じではないだろうか。
セルフコントロールを損なって、もっとたくさん食べさせようと、ありとあらゆる種類の認知バイアスを組織的に利用する環境に、私たちは生きている。残念ながら、与えられる伝統的な助言は、個人の意志の力をひたすら強調する傾向がある。セルフコントロールは「頭の中」のどこかにあるとの誤った考えに基づいたものだ。セルフコントロールされた人物とは、途方もない意志の力を行使する能力をもつ人だと見なされがちだが、実のところ、途方もない意志の力を行使する必要がないように生活を構成できる人のことだ。これは非常に紛らわしい。意志の力と見えるものは往々にして、実際にはその行使が求められる状況を避けることで、意志の力を節約するよう生活を整えた個人の巧みな試みの結果である。(ジョセフ・ヒース『啓蒙思想2.0』栗原百代訳、NTT出版、2014年、p.364)
ヒースは環境を整える試みとして、「認知バイアス」を利用し、正しい選択に誘導しようとする「リバタリアン・パターナリズム」(リチャード・セイラー、キャス・サスティーン)を評価している。
ところで、当事者研究が生まれた2000年代、批評は「ゼロ年代は東浩紀の一人勝ち」(佐々木敦)といわれた時代だった。その評価の当否はおくとして、2000年代にかけて東浩紀が「環境管理型権力」という概念を提起し、「アーキテクチャ」への注目を深めていったことは興味深い。というのも、熊谷晋一郎が綾屋紗月の自閉症スペクトラムの当事者研究を論じるなかで「綾屋の経験は、数多くの物のアフォーダンスに気づいてしまうということが、autonomyの感覚を失わせてしまう可能性」があり、「実際は多くに強制されているのにそれに気づかないときにautonomyを感じられるではないか」と指摘しながら、このような強制を忘れた「autonomy」として、マクドナルドといった飲食店が客の回転率を上げるために硬い椅子を設置するといった良く知られた「アーキテクチャ」のエピソードを紹介するからである[11]。もちろん、両者によってその力点は異なる。当事者研究において「身体」が、アーキテクチャ論において「テクノロジー」がその分析対象となった。しかし、「ゼロ年代」におけるアーキテクチャ論と当事者研究は「脳・身体・テクノロジーから成るマトリックス」という人間像をめぐる同時代的な現象ではないだろうか。そして、「環境管理型権力」=「セキュリティ」の語源がラテン語secura=se(なしで)+cura(care)であることを思い返すならば、フェミニズムや当事者研究は「ケア」を対置することによって、マイノリティによるヘゲモニー闘争を敢行したのかもしれない。
たとえば、自閉症スペクトラムの当事者研究をおこなう綾屋紗月は、身体の感覚や経験を事細かに記述することで、「コミュニケーション障害」と従来判断されてきた自閉症スペクトラムを「たくさんの身体感覚を次々と拾う」ために、「大量の身体感覚を絞り込み、あるひとつの〈身体の自己紹介〉をまとめ上げるまでの作業が、人よりゆっくりである」と捉え直した[12]。綾屋によれば、このような「私たちの身体特性を表す言葉」をうみだす「当事者研究」にくわえて、しばしば「暗黙の了解」とされる「多数派の身体特性をもった者同士が無自覚に作り上げている相互作用パターン」を分析する「ソーシャルマジョリティ研究」をおこなうことで、「どこまでが個人的に変化可能で責任を引き受けられる範囲で、どこからが社会の問題として変化を求めるべき課題なのか」[13]を区別し、当事者自身でさえ気づかなかった新たな対象法やニーズを発掘できる、としている。
私たちが文字を書くときは、手や指を動かす筋肉や神経をいちいち意識しないように、ペンにもほとんど意識を向けることはない。アンディ・クラークは、私たちの生活や行動にうまく適応したために「ほとんど見えなくなるような道具」のことを「透明なテクノロジー」と呼んでいる[14]。クラークが人間を「生まれながらのサイボーグ」と呼ぶ所以だが、しかし、道具、環境や身体が透明化されなかったとしたら、「物質的な脳、物質的な身体、そして複雑な文化的・技術的環境の間のループする相互作用」は十分に機能せず、しばしばそれは「障害」と意識されるだろう。アーキテクチャ論は「透明化」しがちな「文化的・技術的環境」をあらためて言語化することを目指したとすれば、当事者研究は「透明化」しなかった「物質的な身体」を言語化することで、マジョリティによって「透明化」されてしまう「文化的・技術的環境」をもあらためて問い直そうとしたものだった。
ところで、選挙への不信は当事者研究の側からも表明されていると思われる。依存症の当事者研究から着想をえた國分功一郎は、かつてのインド=ヨーロッパ語族には能動態と受動態ではなく、能動態と中動態の対立があったことを指摘している。能動と受動においては「する/される」が問題となるが、能動と中動では「主語が過程の外にあるか内にあるか」が問題となる[15]。注意すべきは、能動態と中動態の対立では「意志が前景化しない」ことである。つまり、ある行為を誰がおこなったのか、ということは重視されず、その行為の責任を問われることもない。たいして、「する/される」という能動態と受動態の対立では、行為者に意志があるとみなされ、行為の責任を問われることになる。しかし、いうまでもなく、現在の政治や法は人々に意志があり、その行為には責任があるという前提で成立している。そして、選挙もまた「自発的」な「意志」の表明とみなされている。
東京都小平市の道路建設に反対する住民運動にコミットした経験を踏まえてか、國分は「実際の投票行為ではなく、住民投票に至る過程」のほうに意義がある、と述べている[16]。住民がビラを受け取ったり、やりとりを重ねるなかで、おのずと世論が形成されることが「自発性に頼らない、能動性に頼らない、意志に頼らない、中動態的な政治のプロセス」[17]である、と。たしかに、小平市の住民運動では、建設の是非をめぐる住民投票はおこなわれたものの、既定の投票率に届かず不成立のため開票されなかったのだった。地域やつながりという「環境」であれば人々は合理的に振る舞えるが、しかし、「自発」的に「意志」することが求められる投票という「環境」においては……ということだろうか。
[1] 稲葉振一郎『「公共性」論』NTT出版、2008年、p.27
[2] スティーブン・ピンカー『21世紀の啓蒙(下)』橘明美ほか訳、草思社、2019年、p.287
[3] アンディ・クラーク『生まれながらのサイボーグ』呉羽真ほか訳、春秋社、2015年、p.17
[4] 同上p.39
[5] 同上p.40
[6] 石原浩二編『当事者研究の研究』医学書院、2013年
[7] 熊谷晋一郎「自己決定論、手足論、自立概念の行為論的検討」田島明子編『「存在を肯定する」作業療法へのまなざし』三輪書店、2014年、pp.24-27
[8]熊谷晋一郎「「当事者研究」の視点から見えてくる〈わたしらしさ〉のよりどころ」https://wired.jp/2020/03/20/hints-for-the-futurist-kumagaya/
[9] 上野千鶴子『生き延びるための思想 新版』岩波書店、2012年、p.359
[10] 岡野八代『フェミニズムの政治学』みすず書房、2012年、p.54
[11] 熊谷晋一郎「自己決定論、手足論、自立概念の行為論的検討」田島明子編『「存在を肯定する」作業療法へのまなざし』三輪書店、2014年、pp.27-32
[12] 綾屋紗月×熊谷晋一郎『発達障害当事者研究』医学書院、2008年、p.23
[13] 綾屋紗月×熊谷晋一郎『ソーシャルマジョリティ研究』金子書房、2018年、電子書籍版参照のため頁数割愛
[14] クラーク、前掲書、p.43
[15] 國分功一郎『中動態の世界』医学書院、2017年、p.97
[16] 國分功一郎『中動態の世界』医学書院、2017年、p.306
[17] 國分功一郎×千葉雅也「『中動態の世界』で考える」『幻冬舎plus』https://www.gentosha.jp/article/8414/?page=2
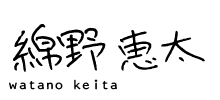 批評家。1988年生まれ。元出版社勤務。詩と批評『子午線』同人。論考に「谷川雁の原子力」(『現代詩手帖』2014年8-10月)「原子力の神―吉本隆明の宮沢賢治」(『メタポゾン』11)など。その他、『週刊読書人』や『現代ビジネス』などに寄稿。新刊『「差別はいけない」とみんないうけれど。』(平凡社)が発売中。twitter
批評家。1988年生まれ。元出版社勤務。詩と批評『子午線』同人。論考に「谷川雁の原子力」(『現代詩手帖』2014年8-10月)「原子力の神―吉本隆明の宮沢賢治」(『メタポゾン』11)など。その他、『週刊読書人』や『現代ビジネス』などに寄稿。新刊『「差別はいけない」とみんないうけれど。』(平凡社)が発売中。twitter

