ニック・ランドとその教え子であるマーク・フィッシャーは、資本主義にたいして真逆の態度を取りながらも、「世界の終わり」という終末観を共有している。そして、新反動主義者らはその終末観を受け継ぎつつ、「世界の終わり」から「脱出Exit」することを思想的な課題としていた。たとえば、PayPalの創業者として知られるピーター・ティールは、「自由と民主主義はもはや両立しない」という考えのもと、リバタリアン的な「自由」を選択し、「世界の終わり」からの「脱出」先の候補として、シーステッドといった洋上人工都市や、税制が優遇されるニュージーランドを考えているようだ。しかし、万能感と無能感がしばしば反転するように、「世界の終わり」を煽るものは「外部」を安易に見出してしまうのではないか。
フランクフルト学派の記念碑的著作である『啓蒙の弁証法』で、アドルノとホルクハイマーは「プロパガンダ」と題した草稿の末尾に次のように書いている。
もちろん、疑わしいのは現実を地獄として描くことではない。そこからの脱出を勧めるありきたりの誘いが疑わしいのである。今日語りかけることのできる誰かがいるとすれば、それはいわゆる大衆でも無力な個人でもなくて、むしろ架空の証人であり、彼にわれわれは言い遺してゆく。われわれとともにすべてが無に帰してしまわないように[1]。(下線、引用者)
「脱出」という言葉の連想だけで、この文章を引用したのではない。アドルノやホルクハイマーもまた「世界の終わり」のもとで思想を形成したからである。
ドイツ哲学研究者の細見和之は、第一次世界大戦が終結した1918年に刊行されたシュペングラーの『西洋の没落』を「フランクフルト学派が成立した時代背景を示すもの」として紹介し、「西洋の文化・文明そのものが崩壊していく危機意識」[2]があったとしている。ここで興味深いのは、著述家の木澤佐登志もまた、ピーター・ティールの思想遍歴を紹介するなかで『西洋の没落』に言及していることだ。世紀末的な雰囲気を背景に国民国家の崩壊を説いた『主権ある個人』(ジェームズ・デビッドソン、ウィリアム・リース=モッグ、1997年)はティールの「生涯の愛読書のひとつ」であるらしいが、木澤はこれを「シュペングラーの『西洋の没落』をリバタリアン好みにアレンジしたもの」[3]と評している。
「西洋の没落」という主題はなんども変奏され、反復されてきた。その背景にはリベラル・デモクラシーの機能不全があることは明らかだろう。「自由と民主主義はもはや両立しない」と「自由にとって民主主義は悪である」という新反動主義者の昨今の発言はあげるまでもないし、リベラル・デモクラシーが自由主義と民主主義という異なる政治システムの混合物であり、両者が克服できない対立関係にあることを示したカール・シュミット『現代議会主義の精神的状況』は1923年に刊行された。『啓蒙の弁証法』でもシュミットと同じ認識が示される。メディア論の観点から電話とラジオを比較し、「電話の場合には、通話者はまだ主体の役割を自由主義的に演じている」のにたいして、「ラジオの場合には、すべての人は民主主義的に一律に聴衆と化し、放送局が流す代り映えのしない番組に、有無を言わせず引き渡されることになる」[4]と述べられる。ファシズムにおいてラジオが重要なメディアであったことは知られるとおりである。
フランクフルト学派と新反動主義者のちがいが最もあらわれるのは、「西洋の没落」=「世界の終わり」から見出される「外部」の扱いである。アメリカはその一部でありながら西洋の「外部」だとしばしばみなされてきた。新反動主義者らが依拠するリバタリアニズムが、「ジョージ・ワシントンやトーマス・ジェファーソンなどの「建国の父」たちまで遡ること」もできる「最もアメリカ的なイデオロギー」[5]と言われるのは、アメリカがあらゆる権力や権威が及ばない自由な「フロンティア」としてイメージされたからである。だが、「西洋の没落」=「世界の終わり」を前にして、ピーター・ティールらがアメリカ建国以来の「フロンティア」精神にのっとって、「外部」へと「脱出」を計画するのにたいして、ユダヤ系の出自をもつアドルノらは、ナチス台頭によってアメリカに亡命=「脱出」をせざるをえなかった。もちろん、彼らの背後には、スペイン国境で服毒自殺したヴァルター・ベンヤミンをはじめ、「脱出」できないままナチスの犠牲になった多数のユダヤ人が存在したわけである。
亡命者たちにとってアメリカは西洋の「外部」ではあったが、可能性にあふれた「フロンティア」では決してなかった。アドルノは、「ヨーロッパの破局」によって「知的亡命者」という新しいタイプの知識人が誕生したと指摘する[6]。「知的亡命者」たちが見たアメリカは、「パイオニアが精神的にも開拓し、それに照らして自己自身を刷新するつもりだった荒野」ではなく、「システムとして生全体を捉える文明」[7]であった。そして、アメリカにたいする「知的亡命者」の「狼狽の堆積」と「その合理化」[8]として、オルダス・ハクスリーの小説『すばらしい新世界』(1932)をあげている。
『すばらしい新世界』はアメリカをモデルとしている。作者のハクスリーは1925年に旅行記を執筆するために、インド、ビルマ、日本などを回り、アメリカを訪れた。そのときの「新鮮な印象」によって『すばらしい新世界』が執筆されたという[9]。「西洋の没落」=「世界の終わり」から描かれたアメリカが『すばらしい新世界』なのである。アドルノもまた『すばらしい新世界』を「パロディー化されたアメリカニズム」[10]と呼び、「ベンサム流の自由主義者と同様に、ハックスリーは最大多数者の最大幸福へと向かう発展を予測する。違うのは、ただそれが彼の気に入らないことだけである」[11]と指摘している。
『すばらしい新世界』で描かれる世界では、人工授精によって人類の繁殖がおこなわれ、胎児は誕生前に「アルファ」「ベータ」「デルタ」「エプシロン」と階級に振り分けられ、その階級に見合った知性や肉体を持つように科学的な操作を受ける。そして、誕生後は集団生活を営み、プロパガンダを徹底的に刷り込まれる。当局と異なる考えをもつことは禁じられ、精神的な動揺や不安を感じたときは「ゾーマ」という精神安定剤を服用する。このような人間の生に関与するテクノロジーを構想したことで、『すばらしい新世界』は現代の管理社会を予言したディストピア小説の傑作と評されてきた。
アドルノもまた「コンディショニング」という言葉に注目し、次のように述べる。「コンディショニング」は「生物学と行動心理学からアメリカの日常語に移された翻訳しにくい言葉」であり、もともとは「環境を任意に変化させること」「「諸条件」の制御によって特定の反射ないし振る舞い方を呼び起こすこと」[12]を意味したが、「生活条件を科学的にコントロールするあらゆるやり方」を指すようになった。そして、「コンディショニング」によって、「社会的圧力と強迫を、あらゆるプロテスタント的規範をはるかに超えて内面化し、自己獲得させること」が可能となり、「人間は自分がなすべきことを愛するのを断念するが、それでいて自分が断念したことすらも知らない」[13]状態になった、と。
『すばらしい新世界』の登場人物たちは、幼少期から就寝中にプロパガンダを繰り返し聴かされたために、反射的にプロパガンタを口にしてしまう。ここで描かれるのは、「規律・訓練」(ミシェル・フーコー)の究極的なあり方である。しかし、アドルノが指摘しているのは、むしろ「管理社会」(ジル・ドゥルーズ)だ。アドルノがアメリカに見た「システムとして生全体を捉える文明」とは、「自分が断念したことすらも知らない」ように、「環境を任意に変化させ」、「特定の反射ないし振る舞い方を呼び起こ」そうとするという点で、いま私たちが「アーキテクチュア」と呼ぶ権力にほかならない。アーキテクチュアとはある意味で最も成功したプロパガンダである。なぜなら、プロパガンダがもはやプロパガンタとして認識されず、私たちの日常や生活の一部になった状態だからだ。
アメリカは西洋の願望や不安が投影される「外部」であった。あらゆる権力から自由な「ユートピア」としてイメージされるいっぽうで、周囲の権力にさえ気づくことができない不自由な「ディストピア」として描かれる。万能感と無能感。ピーター・ティールがかつて「世界の終わり」からの「脱出」先とした「サイバースペース」も、アメリカ=「外部」をめぐる言説と同じ展開をたどっている。「サイバースペース」はあらゆる権力が及ばないリバタリアン的自由が実現可能な領域としてみなされた。東浩紀が指摘するように、1996年にジョン・ペリー・バーロウが発表した「サイバースペース独立宣言」からは、「情報技術というフロンティアに挑戦し、個人の自由を肯定するその姿は、彼ら自身には、むしろ、建国以来の伝統に忠実な「アメリカ的」存在に映っている」[14]ことが読み取れる。しかし、「特定のアーキテクチャを選べば、その条件下で可能な自由や競争しか実現されない」[15]という「環境管理型権力」によって、「サイバーリバタリアン」の理想はあっけなく裏切られた。ちなみに「情報自由論」の最終回でハクスリー『すばらしい新世界』が「「環境管理型」あるいは「生権力型」と呼ばれるポストモダンの権力の特徴をすでに見通していた」と言及されている[16]。
「西洋の没落」=「世界の終わり」が変奏されるように、「外部」もまたその都度発見され、そして、ユートピア(万能感)とディストピア(無能感)のあいだで揺れ動く。実際、『すばらしい新世界』には、アメリカ以外の西洋の「外部」が投影されている。最初期の著作『アメリカの哲学』(1950)でハクスリーの神秘主義への転回を紹介し[17]、のちにハクスリー研究会にも所属した思想家の鶴見俊輔は、「『すばらしい新世界』は、第二次大戦後の高度成長下の日本によくあてはまる」[18]と述べている。注意すべきは、この指摘がバブル経済直前の1985年にされていることだ。そして、いまや『すばらしい新世界』は中国とともに言及される。中国経済学者の梶谷懐は、「芝麻信用」などの信用スコアの普及といった中国の監視社会化・管理社会化を指摘しつつ、「人々のより幸福な状態を求める欲望が、結果として監視と管理を強める方向に働いているという点では、現代中国で生じている現象と先進国で生じている現象、さらには『すばらしい新世界』のようなSF作品が暗示する未来像の間に本質的な違いはない」[19]と述べている。つまり、私たちは『すばらしき新世界』に世界資本主義の覇権国家を見出してしまうのだ。アメリカ、日本、中国といった西洋とは異なる政治体制や風俗習慣を持ちながら、西洋以上の高度な資本主義経済を達成した国家である。
資本主義にはいくつかの「外部」があるとされてきた。資本だけでは再生産できない人間や自然などである。マルクス経済学者の宇野弘蔵が「労働力商品化の無理」によって、資本主義が周期的な恐慌に陥ると定式化したことは知られている。しかし、長原豊は「労働力商品化の無理」が「通る」のが資本主義であると批判するように[20]、資本主義はみずからの危機を糧にして、その危機を乗り越えていくわけである。結局のところ、人間にしても自然にしても資本の「外部」でありながら、その内部に包摂された擬似的な「外部」にすぎないのかもしれない。左派は階級闘争やエコロジー運動などで、この「外部」に依拠するかたちで反資本主義闘争を組織してきたが、ニック・ランドはそのような擬似的な「外部」に飽きたらず、資本主義のまったきの「外部outside」をもとめたといえる。資本主義をさらに加速させることで、人間や自然をすべて食い尽くした果ての「世界の終わり」? しかし、その資本主義のまったきの「外部」が、西洋の不安と羨望を投影される「外部」へといつのまにかすり替わってしまう。
「資本主義によって世界を終わらせてしまえ」というニック・ランドが1998年に上海に移住し、すでに中国が「加速主義社会」に突入していると認識のもと、「親中国政府プロパガンダ」的な文章を発表したことは[21]、「西洋社会の不安や羨望が「中華」に投影された発想」[22]にすぎないと批判されている。これもまた「世界の終わり」の「外部」をめぐる「ユートピア」と「ディストピア」の反転のひとつだろう(ニック・ランドに影響を与えたとされる『ブレードランナー』(リドリー・スコット、1982)や『ニューロマンサー』(ウィリアム・ギブスン、1984)が異国情緒あふれる日本を舞台にしていたのは、この意味で興味深い)。もちろん、「ディストピア」としての中国を強調することでニック・ランドを批判することは簡単だが、アドルノはハクスリーを次のように批判している。
文明は文化の名の下に野蛮状態に入っている。ところが、ハックスリーはそこに敵対関係を幻視する代わりに、技術的理性の、自己の内に矛盾をもたない全体的主体のようなものを幻視し、それにふさわしく単純な全体的発展を幻視する[23]。
「外部」をディストピアとして描くこともまた、投影のひとつにほかならない。では、アドルノがいう「敵対関係」をいまどこに引くことができるのか。先の引用文で梶谷が注意深く指摘したように、『すばらしき新世界』は異国の出来事なのではなく、目の前で進行中の出来事なのである。たしかに新反動主義者らは人種や男女間の生物学的特性を「啓蒙」しながら、その実「野蛮」に突き進んでいっている。
さて、『啓蒙の弁証法』はアメリカのカリフォルニアで執筆されたが、細見和之は先の引用文に「亡命者としての暗い意志」[24]を見てとっている。そして、『啓蒙の弁証法』とは「架空の証人」に宛てた「投瓶通信」(アドルノが好んで用いた比喩)ではないか、と指摘している[25]。たしかにそう読み込むことは十分に可能だろう。しかし、注意すべきなのは、語りかけるべき対象として、民主主義的な「大衆」も、自由主義的な「個人」も、ともに否定したうえでの、「架空の証人」に宛てた「投瓶通信」である、ということである。すでに自由主義にも民主主義にも希望は見失われている。
[1] ホルクハイマー、アドルノ「プロパガンダ」『啓蒙の弁証法』徳永恂訳、岩波文庫、p.526
[2] 細見和之『フランクフルト学派』中公新書、2014年、p.9
[3] 木澤佐登志『ニック・ランドと新反動主義――現代世界を覆う〈ダーク〉な思想』星海社新書、2019年、p.35
[4] 「文化産業――大衆欺瞞としての啓蒙」『啓蒙の弁証法』徳永恂訳、岩波文庫、p.254
[5] 渡辺靖『リバタリアニズム――アメリカを揺るがす自由至上主義』中公新書、2019年、p.21
[6] アドルノ「オルダス・ハックスリーとユートピア」『プリズメン』渡辺祐邦ほか訳、ちくま学芸文庫、p.137
[7] 同上、p.138
[8] 同上、p.138
[9] 「著作解題」『オルダス・ハクスリー――橋を架ける』片桐ユズル編、人文書院、1985年、p.203
[10] アドルノ「オルダス・ハックスリーとユートピア」『プリズメン』、p.140
[11] 同上、p.168
[12] 同上、p.141
[13] 同上、p.142
[14] 東浩紀「情報自由論第5回 サイバーリバタリアニズムの限界」『情報自由論
html version index』http://www.hajou.org/infoliberalism/5.html
[15] 同上
[16] 東浩紀「情報自由論第14回 不安のインフレスパイラル(後編)」『情報自由論
html version index』http://www.hajou.org/infoliberalism/14.html
[17] 鶴見俊輔「ハクスリー――非人間主義」『アメリカの哲学』講談社学術文庫、1986年、pp.265-281
[18] 鶴見俊輔「ハクスリーの日本文化」『オルダス・ハクスリー――橋を架ける』片桐ユズル編、人文書院、1985年、p.122
[19] 梶谷懐「中国の「監視社会化」を考える(5)──道具的合理性が暴走するとき」Newsweek、 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/02/post-11750.php
[20] 長原豊『われら瑕疵ある者たち──反「資本」論のために』青土社、2008年
[21] 水嶋一憲「中国の「爆速成長」に憧れる〈中華未来主義〉という奇怪な思想」『現代ビジネス』19年3月8日https://gendai.ismedia.jp/articles/-/60262?page=2
[22] 同上
[23] 「オルダス・ハックスリーとユートピア」『プリズメン』p.168
[24] 細見、前掲書、p.109
[25] 同上
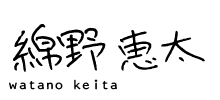 批評家。1988年生まれ。元出版社勤務。詩と批評『子午線』同人。論考に「谷川雁の原子力」(『現代詩手帖』2014年8-10月)「原子力の神―吉本隆明の宮沢賢治」(『メタポゾン』11)など。その他、『週刊読書人』や『現代ビジネス』などに寄稿。新刊『「差別はいけない」とみんないうけれど。』(平凡社)が発売中。twitter
批評家。1988年生まれ。元出版社勤務。詩と批評『子午線』同人。論考に「谷川雁の原子力」(『現代詩手帖』2014年8-10月)「原子力の神―吉本隆明の宮沢賢治」(『メタポゾン』11)など。その他、『週刊読書人』や『現代ビジネス』などに寄稿。新刊『「差別はいけない」とみんないうけれど。』(平凡社)が発売中。twitter

