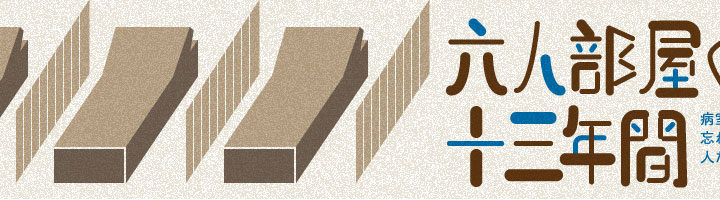「特別な人生には、ちがいないだろう」
「たしかにね、俺たち、普通の人生じゃないな、
と思うこともありますよ」
(『男たちの旅路 山田太一セレクション』里山社)
最初は個室
初めて入院したときのことから、お話ししてみよう。
最初は個室だった。
これは個室を選んだわけではなく、重症だったからだ。重症者は病院のほうで個室にする。当時、私は一日二十回以上の血便が出て、熱も高く、意識障害もあった。
しばらくして、症状が少しましになってくると、「このまま個室にいる場合には、差額ベッド代がかかる」と言われ始める。症状が重くて病院側で個室にする場合は差額ベッド代はとられないが、そこまでの症状ではなくなり当人が個室を望む場合には差額ベッド代をとられる。
そのとき、差額ベッド代がいくらだった覚えていないが、かなりの金額だったと思う。一日一万円とか二万円とかそれくらいだったのではないか。とにかく、大学三年生で二十歳の私にとってはとんでもない金額で、とても払えない。まして、いつまで入院するかもわからなかったから。
それで個室は無理ということになり、そうすると「二人部屋にするか、六人部屋にするか」と聞かれた。
二人部屋だと、個室ほどではないが、やはり差額ベッド代がかかる。六人部屋だと差額ベッド代はかからない。
二人部屋の差額ベッド代がいくらだったか、これもはっきりとは覚えていないが、一日五千円くらいだったのではないかと思う。これもかなり高額だし、ずっと払い続けられる金額ではない。
しかし、そのときの私は病気に打ちのめされていた。精神的にもまいっていたので、人と同じ部屋というのは耐え難く思われた。なので、いきなり六人部屋というのはとても無理に思え、せめてしばらくの間だけでも二人部屋にしたいと思った。
この選択が、大きな間違いだったのだが、そんなことは初めての入院の私にわかるはずもなかった……。
ふんどしと入れ墨
ある程度は元気のある場合、患者は自分で歩いて新しい病室の空きベッドに引っ越すのだが、そのときの私はまだそんな状態ではなかったので、ベッドに寝たまま、ベッドごと移動することになった。
看護師さんが廊下をズルズルとベッドを引きずっていってくれて、二人部屋の空きベッドと入れ替えてくれた。部屋や廊下の天井を見ながら、なすがままに引っぱられていくというのは、なかなか独特の体験だ。他人に身をゆだねることの、無力感と、不安と、そして安堵感のようなもの。そういえば幼いの頃、座布団の上に寝転んで、畳の上を兄にひっぱり回してもらって遊んだのを思い出した。
引っ越し先の二人部屋の、もうひとつのベッドには、四十代前半くらいに見える、頭を角刈りにした精悍な男がいた。点滴もそのときはしておらず、ベッドに座っていて、あまり具合が悪そうには見えなかった。
どういう職業の人か、見た目からはちょっと見当がつかなかった。しかし、着替えのときになってすぐにわかった。
一日一回、病院のお仕着せが配布されて、それに着替える。同室の男性は自分で着替えられるので、お仕着せが届いたら、さっさと着替えをはじめた。
それが、なぜかベッドの上に仁王立ちになって、着替えるのだ。こちらに背中を向けていた。まず全身、上も下も脱ぐ。驚いたことに、ふんどしをしていた。
しかし、さらに驚いたのは、全身に鮮やかな入れ墨があったことだ。手は手首まで、足は足首まで、びっしり入れ墨がある。ふんどしなので、両方のお尻ほっぺたも見えているが、そこにも入れ墨が入っている。
「やくざだ!」と思った。暴力団というより、やくざという感じだった。
なぜ、よりにもよって、やくざと二人部屋になってしまったのか。愕然とした。
そういう入れ墨は、映画でしか見たことがなかった。最近のタトゥーのようなものとはちがって、高倉健の映画に出てくるような、古風な入れ墨だ。今でもこういう人がいるのかと驚いた。
入れ墨は「ガマン」とも呼ばれるくらいで、ずいぶん痛いらしいし、熱も出るという。だから、背中だけでなく、全身に彫っているのは、すごい人なのだ、ということをどこかで聞いて知っていた。
私はまさに凍りついた。元気でもこんな人と同室はつらい。なのに、こんなに弱った状態でこんな目に遭うとは!
しかしもちろん、苦情は言えない。別の部屋にしてほしいなどと看護師さんに泣きつけば、それは当然、隣りに聞こえるし、それで他に空きベッドがなくて替えてもらえなかったら、悲惨なことになる。
その後、隣りの人にはたくさんのお見舞いが来た。それはまさにそういう人たちだった。
親分らしいのが、大勢を引き連れてやってきたこともある。隣の男は、ベッドの上に正座をして頭を下げて話をしていた。私は隣りで身を縮めて、いてもいない存在になるように息を殺していた。
二人のベッドの間にはカーテンがあって、それで仕切ることができるのだが、私のほうが窓側だったので、それを閉めると隣りの男は日陰になる。
だから男は、一度としてカーテンを閉めることはなかったし、もちろん私も閉めることはできなかった。
看護師さんが私の処置をするときにカーテンを閉めてくれたが、看護師さんがいなくなると、たちまち隣りの男がカーテンを開けた。
隣の男のところに、弟分らしい男がちょくちょく見舞いに来た。
そして、上着のジャンパーの中から、隠し持ってきた一升瓶の酒を取り出す。
「兄貴、これがなきゃすまないでしょ」と笑う。
「おお、気がきいているじゃねぇか」と、男の方も喜んで受け取り、すぐに栓をポンと抜き、またなぜかベッドの上に仁王立ちになり、一升瓶を片手で持って、そのままグビグビと飲む。
私はそれを見てますます恐怖を覚えた。
弟分はその一升瓶を着替えか何かで包んで、床頭台 (ベッドサイドに置いてある私物入れ)の中に隠し、「こうしておけば、わかりませんぜ」とまた嬉しそうに笑う。兄貴も「おぅ」と、嬉しそうに返事をする。
(実際のやり取りは、茨城弁で行われたが、私にはその通りには再現ができないので、映画の中のやくざ風な会話になってしまうが)
しかし、その弟分が帰ると、兄貴は暗い顔をしてぐったりする。そして、隠してあった一升瓶を取り出し、その中身を洗面台に流して捨ててしまう。そして空ビンをまた同じ場所に隠す。
翌日か翌々日には、また弟分がやってきて、同じようにジャンパーから一升瓶を取り出す。そして前の空ビンを代わりにジャンパーに隠して、持って帰る。そのとき、空になった一升瓶を見て、嬉しそうに「さすが兄貴ですね」と感嘆の声を発する。こういうやり取りが、ずっと続いていた。
どうやらこの兄貴は、肝臓が良くないようだった。アルコール中毒というわけではなさそうで、もう酒を飲むのはきつくて、まったく飲みたくなさそうだった。
にもかかわらず、弟分が一升瓶を持ってくるたびに、ベッドに仁王立ちになって、片手に一升瓶を持ってグビグビと一合か二合は飲む。そして弟分が帰ると、暗い顔をしてぐったりし、残った酒を洗面台に捨てる。
その姿を見て、私は初めて親しみを感じた。そして、弟分に対して虚勢を張らなければならない兄貴に対して同情を覚えた。
だいたいこの兄貴は、少し可愛いところがある。私は当初、大いに怯えていたが、ベッドに仁王立ちになってこちらに背を向けて着替えをするのも、私に対して入れ墨を見せつけているわけだ。どうでもいい私にまで虚勢を張っているわけだ。
ちょっと話しかけたいような気にもなった。
でもハッとしてやめた。
兄貴の酒の秘密を知っているのは、私だけなわけだ。看護師さんも知らない。もし私が弟分に話せば、兄貴の面目は丸つぶれになる。私はあくまで、一言も口を聞かない、いてもいない存在を貫いたほうが安全だ。
しかし、あらためて考えてみると、あの弟分は本当に兄貴のために酒を持ってきているのだろうか?
兄貴が肝臓で入院していることは、わかっているはずだ。だから酒が毒になることも、承知してるだろう。
それでも嬉々として一升瓶を持ち運び、兄貴がグビグビとやるさまを見て、「さすが兄貴」などとおだてているのは、もしかして兄貴を殺そうとしてるのではないか?
どうにもそんな気がしてきて、ますます兄貴に親近感がわいた。
兄貴の病状がどうなっていくのか心配をしていたが、その後、兄貴は病室を移動になった。理由はわからない。私から看護師さんに頼んだわけではない。私を可哀想と思ってくれたのか、あるいは弟分の目論見通りのことが起きてしまったのかもしれない。兄貴が個室行きになっていなかったことを祈るばかりだ。
元気に全快して、弟分を口惜しがらせた、と思いたい。
納豆おじさん
次にやってきたのは、おそらく六十歳前後くらいのおじさんだった。私と同じようにベッドに横になったまま運ばれてきて、かなり寝たきりの状態だった。
穏やかでおとなしく、人がよさそうな人だった。ただ、茨城弁が非常に強くて、話しかけられても何を言っているのか、私にはまったくわからなかった。それをいいことに私は、このおじさんを無視し、カーテンを今度はずっと閉め切っていた。おじさんはずっと日陰になっていたわけである。
私はやくざとの日々にすっかり疲れていて、一人になりたかった。
しかしこれは、おじさんが優しそうで弱そうだから、強い態度に出たわけで、強いやくざから受けた圧迫を、弱いおじさんで晴らしたわけで、非常によくなかったと反省している。
強いものから受けた鬱憤を、その強い者に対して復讐するのではなく、別のまったく関係ない弱い者にぶつけるという最低の行ないだった……。
それと、今回は私のほうが先に部屋にいて、後からおじさんが来たので、なんとなく部屋の主導権を私が握ってしまったということもある。
病室ではこういうこともよくありがちだ。芸人で入門が早いほうが年下でも先輩面をするのと同じようなものかもしれない。
このおじさんの病気が何だったかは知らない。しかし、このおじさんは看護師さんが来るたびに「納豆が食べたい」とこぼし、そのたびに「納豆はダメと先生から言われているでしょ」と注意されていた。
茨城は納豆が名物のひとつで、それだけに好きな人も多いのだろう。それにしても、おじさんのこだわりは激しかった。食べ物を禁止されるとひどく執着してしまうということを、私はまだ知らなかったから、不思議に思った。
ちなみに、私はその頃、完全絶食中だったので、「納豆ぐらいでガタガタ言うな」と内心思っていた。また、納豆が禁止される病気があるのかと、「へー」とも思っていた。健康食品だと思っていたからだ。
このおじさんとの生活は、私のほうが一方的に感じが悪かった。おじさんから私が嫌な目にあわされることはまったくなかった。ただ、人を日陰に置いてしまっていることが、勝手ながら私自身への圧迫にも少しずつなってきていた。態度を改めなければと思いながら、なかなかできずにいた。
そんなある晩、夜中にふと目を覚ました。
点滴はつながっているし、病院内ではいろんな音が夜中でもするから、目を覚ますことはしょっちゅうある。
おじさんの側に寝返りをうって、ふと視線が下のほうにいくと、閉め切ったカーテンの下の床の色がなんだかおかしい。明かりが消してあって暗いのだが、そこの床がより深く暗い。黒いと言ってもいい。
ん? と思って首を伸ばすと、黒い水たまりのようなものが向こうからこちらに迫ってきている。なんだこれはと思って、よくよく目をこらすと、黒いのではなく赤い。
血だ!と思った。でもまさかと思った。血だとしたらこんなに大量に!とびっくりした。隣りのおじさんはそんなに出血をしそうには見えなかった。もしかして手首でも切ったのかもと思った。それにしても量が多かった。
本当に血かどうかわからなかったが、もし血だったら大変なので、あわててとにかくナースコールをした。「なに?」という呑気な声がした。私は「血みたいなものが流れてきてるんですけど」と言った。
ブツッとナースコールが切れて、バタバタという看護師さんの足音が聞こえてきた。病室の灯りがついた。床の黒い水たまりは、明かりの中で真っ赤になった。
やはり血だった。
それから大騒ぎになった。医師や看護師が何人もで、隣のおじさんに処置をしていた。カーテンは引かれたままだったので、どういう状態になっていたのかはわからない。しかしドキドキして私もずっと起きていた。二人部屋は恐ろしすぎると思っていた。やくざの後は、今度は血が流れてくるのである。カーテンを閉めきっていても、異変はその下から床を伝わってくるのである。
おじさんは幸い、命に別状はなかった。翌朝はいつもどおりに看護師さんとしゃべっていた。
そのときに看護師さんから「納豆を食べたでしょう!」と怒られていた。
これを聞いて私はとても驚いた。昨晩の大出血は、どうやら納豆を食べたことが原因だったようだった。もちろんそのせいだけかどうかはわからないが、そのことが関係しているようだった。
しかもおじさんが納豆をこっそり食べて出血したのは、これが初めてではないようだった。つまり、出血するとわかっていて、おじさんはまた納豆を食べたのだ。
正直、そのときは、このおじさんのことを「アホか」と思った。こんな大変なことになるのに、納豆ぐらい我慢すればいいじゃないかと思った。こっちは納豆どころか、何も食べていない。水さえ飲んでいない。
おじさんが納豆を食べたせいで、こっちは一晩中寝られず、ドキドキ動揺していた。元気ならともかく、こっちも病人だ。「なんて人騒がせな!」とそのことにも腹が立った。
しかし、これはまったくの私の間違いだった。まだ病人としての経験が浅く、いろんなことがわかっていなかった。
その後、病人歴が長くなってから、このおじさんのことを思い出し、たいへん敬服するようになった。
今ではこの納豆おじさんは、私の尊敬する偉大な人物の一人である(その理由については、別の経験とともに、また先でお話ししたいと思う)。
ただ、おじさんとの交流はこの時一度きりで、その後どうなったのかは知らない。言葉がわからなかったので、ついに会話を交わすこともなかった。
そして六人部屋へ
二人部屋にすっかりこりた私は、看護師さんに「六人部屋に移りたい」と頼んだ。
表向きの理由は、差額ベッド代が大変だからということで、それもたしかに大きな理由ではあった。しかし、それよりなにより、二人きりということの濃密さにもうこりごりしていた。
六人部屋なら、肝臓のよくないやくざが一升瓶をラッパ飲みしようが、おじさんが納豆を食べて大出血をしようが、自分ひとりでドキドキしないですむ。
今のままだと、毎晩何度も床に血だまりがないか確かめてしまって、おちおち寝ていられない。
六人部屋なら少なくとも責任が分散する。自分だけで気をつけなくてすむ。
ただ、まだ二十歳だった私は、家族や友達以外と二十四時間寝食を共にするという経験がなかった。六人部屋に果たして耐えられるのか不安だった。二人部屋での厄介ごとが五倍になったらどうしようとも思っていた。
六人部屋に行ってからのことは、また次回に……。
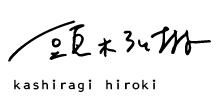 文学紹介者。筑波大学卒業。大学3年の20歳のときに潰瘍性大腸炎を患い、13年間の闘病生活を送る。そのときにカフカの言葉が救いとなった経験から、『絶望名人カフカの人生論』(新潮文庫)を出版。その後、『カフカはなぜ自殺しなかったのか?』(春秋社)、『NHKラジオ深夜便 絶望名言1・2』(飛鳥新社)、『絶望書店 夢をあきらめた9人が出会った物語』(河出書房新社)、『トラウマ文学館』(ちくま文庫)、『落語を聴いてみたけど面白くなかった人へ』(ちくま文庫)、『食べることと出すこと』(医学書院)、『自分疲れ』(創元社)などを刊行。
文学紹介者。筑波大学卒業。大学3年の20歳のときに潰瘍性大腸炎を患い、13年間の闘病生活を送る。そのときにカフカの言葉が救いとなった経験から、『絶望名人カフカの人生論』(新潮文庫)を出版。その後、『カフカはなぜ自殺しなかったのか?』(春秋社)、『NHKラジオ深夜便 絶望名言1・2』(飛鳥新社)、『絶望書店 夢をあきらめた9人が出会った物語』(河出書房新社)、『トラウマ文学館』(ちくま文庫)、『落語を聴いてみたけど面白くなかった人へ』(ちくま文庫)、『食べることと出すこと』(医学書院)、『自分疲れ』(創元社)などを刊行。