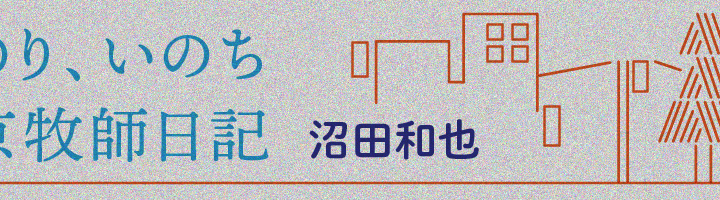教会のなかで出遭う人。教会の外で不意打ちのように出遭う人。一時は精神を病み、閉鎖病棟にも入った牧師が経験した、忘れえぬ人びととの出遭いと別れ。いま、本気で死にたいと願う、そんな人びとと対話を重ねてきた牧師が語る、人との出遭いなおしの物語。いのりは、いのちとつながっている。
帰省して済ませなければならなかった用事をどうにか済ませ、わたしは故郷の繁華街で夜行バスを待っていた。季節がら日没は遅く、もう7時はまわっているはずだが、まだまだ空は明るい。乗車までまだだいぶ時間がある。わたしは石段に腰を下ろし、鞄から本を取り出して読んでいた。目の前に人の気配がしたので目を上げると、いつの間にか、中学生くらいの少女が立っていた。首元が緩んで伸びたトレーナーは汚れており汗臭い。髪の毛も洗っていないのか、頭にぺったりくっついている。彼女はわたしの目を見て、言った。
「ねえ、ラブホいかへん?」
「わるいな。おれ、これでも牧師やねん。君、どうしたんや?」
「ええっ牧師さん!?わたし小さいとき教会行ったことあるんよ。教会学校、楽しかったなあ!クリスマス会やったよ。あと、イースター!卵探ししたなあ。」
勢いよく話しだすと、彼女はわたしにくっつくように、ぺたんと座った。どうやら育った環境それ自体は貧困家庭ではなかったらしいことが、彼女の言葉の端々から見てとれた。塾やピアノなどに通わせてもらえるていどには、経済的にも豊かであったようだ。それに、教会への抵抗のなさ。クリスマスはともかく、イースター恒例の行事まですらすら話してくれるところをみると、彼女はけっこうながいあいだ教会に通っていたようだ。なにがどうなって彼女は今、見知らぬ男をラブホテルに誘うような生活になったのだろう。
「まあ、言いたくなかったらええんやけど。家帰らんの?」
「知らんわ。あんなとこ家ちゃうし」
彼女はそういうと黙り、繁華街を歩く人々を見ている。スーツ姿で腰掛けるわたしと、そのわたしにくっついて座る彼女との組み合わせ。道行く人たちは、ちらりとこちらを見ると、わたしたちの前に来るまでに少しよけて歩き去っていく。
しばらく話していたら、彼女は「ああ、つかれたわほんま」と、いきなりわたしの膝に頭をのせた。これでは、わたしはますます不審者ではないか。とはいえ追い払うわけにもいかないし、どうしたらいいのだろう。いま警察を呼べば、とたんに彼女は逃げていなくなるだろう。わたしは彼女に膝枕を貸したまま、途方に暮れてしまった。
「なあ。ずっと家帰らんのやったら、君はどうやって生活しとるん」
わたしの膝枕から彼女が応える。
「男に金もらったり、ホテルに連れてってもらったりして。そこでご飯食べたり、風呂はいったりしとんねん」
「なあ...そのうち襲われるで。いや、セックスのことやない。殴られたり蹴られたりな、お金とられたり。それと病気うつされてまう。妊娠してしまうかもしれんぞ。誰か友だちおらんのか?」
「おるよ。いっしょに集まったりするよ」
「そいつら、君のこと心配しとるやろ?」
「さあ...してへんよ。みんな同じことしてるし。みんなで集まってな、そこからそれぞれ行くねん。男と別れたら、また集合する」
「みんな同じことしてる」という、彼女のことを心配しないらしい「みんな」。こんなふうに会話に応じる彼女はわたしを信用したのかもしれないが、やはり赤の他人だ。ほとんど無意識的、生理的なレベルで警戒を怠っていないかもしれない。それと同じように、彼女は自分と同じような境遇の友人たちを、友人ではあるがしょせんは他人でもあると、そんなふうに捉えていると感じられた。友人たちも客の男たちも、わたしも同じ。最後に頼れるのは自分だけ。そういう「みんな」。自分以外の全員を、当然わたしも含んだ「みんな」。
わたしはそっけなく話すふりをしながら、頭はフル回転させていた。落ち着け。彼女を助ける方法を考えろ。考えあぐねた結果、わたしは話が分かりそうな同僚に電話をかけてみることにした。もちろん彼女に許可はとった。
「そいつなら、君のことなんとかしてくれるかもしれへんから」
「うん、ありがとう」
彼女は素直にうなずいた。同僚もわたしからの急な電話に、あわてて着替えでもしているのか、それほど遠くはないはずなのだが、姿を現すまでの時間は長かった。待っているうちに、彼女は膝枕のうえで寝息を立て始めた。日ごろの疲れがたまっているのだろう。穏やかな寝顔がむしろ痛ましい。まだ中学生くらいの子どもが、どうしてこんな厳しい生活をしないといけないのか。
やがて遠方から同僚が歩いてきた。近づいてわたしに気づくと、こんどは駆けよってきた。「これはどういうことです!?」
どうやらわたしの膝枕状態を、変に誤解してしまったらしい。わたしは誤解を解くよりは事情を説明したほうが早いだろうと、彼にこれまでの経緯を話した。彼女も目を覚まして、彼を見上げた。
残念なことに、話はわたしの思いもよらぬ方向へ進んでいった。彼は彼女にではなく、わたしに向かって説得を始めた。
「難しいですよ、やっぱり。たしかに、この子は厳しい立場だと思います。でも今、この子を引き受けて、責任とれます?なにかあったらどうするんです?」
彼女の顔がこわばりはじめた。彼女は立ち上がり、わたしと彼との論争を、こぶしを握って聴いていた。
わたしは彼と論争しながら、ちらちら彼女のほうを見る。
「いや、だいじょうぶだから。必ずなんとかするからね」
だが、もうだめだった。彼女とわたしとのあいだには、膝枕のときには考えられなかったような、なにかとてつもないものが立ちはだかっていた。彼女はわたしの顔から眼をそらさず、少しずつ、少しずつ後ずさりし始めた。まるで野良猫が人間を警戒するように、その野生の鋭い眼をそらさず、少しずつ、少しずつ。 どうすればいいのか。彼女を引き止められないか。同僚を納得させることはできないか。
「この子を今晩だけでもいいから、とりあえず泊めてくれませんか。それで明日以降、福祉につないでもえたら。それだけでもいいんですけど。ほんとうはわたしがそうしたいんだけど、幼稚園の仕事もあるし、バスには乗らないといけないし」
「無理ですよ。それにもう夜です。未成年者を親にも警察にも言わず、勝手に教会に泊めることはできません。わたしもあなたも男性ですよ?そんなことが露見したら、教会の社会的信用に関わります。彼女に親の連絡先を尋ねてください。」
「いや、親には連絡できない。彼女は親には会いたくないと言っている。警察のことも警戒している」
「それなら警察に連れて行きましょう。警察に保護してもらうしかない」
わたしの夜行バスの時間は迫っていた。呼ぶべき同僚を誤ったのか?いや、彼が言うことももっともだ。彼女が大人だったら、彼も教会に宿泊させることに同意したかもしれない。だが中学生である。ここは近代のキリスト教世界ではない。牧師の独断で未成年を、誰にも告げずに教会に泊めることなどできない。やはり最初から警察を呼ぶべきだったのか?
そのあいだも彼女は少しずつ後ずさり続けた。やがてわたしたちが追いかけてもすぐ逃げきれるほどに遠ざかると、彼女は繁華街の雑踏へと、あっという間に姿を消した。わたしも同僚も、引き留める暇もなかった。バスは到着し、同僚に見送られながら、わたしはステップに足をかけた。
なにもできなかった─── 夜行バスに揺られながらシートの背もたれを倒し、わたしは目をつむる。まぶたのなかで少女の、幼さの残る屈託のない笑顔と、立ち去り際の野生動物のような鋭い眼光とが、交互に浮かぶ。わたしを突き刺すように見る、ふたつの野生の眼。弾むように話す声と、息を殺す沈黙。わたしの膝の上で安心して眠るまぶたと、警戒に光りつつ遠ざかる細い眼。
「なぜ、なにもできないくせに、わたしにやさしくした?」
「うらぎり、ぜつぼうさせるために、わたしをしんらいさせ、きぼうをもたせたのか?」
彼女は幼い頃教会に通ったと言っていた。それも心から懐かしそうに。今は大嫌いな親に連れられて通ったのだろう。だが、その思い出を彼女は楽しそうに語った。彼女にとって、想いでのなかの教会は楽しく、なにより安心できる場所だったのだ。だからわたしが牧師だと分かったとたんに、わたしを客の男ではなく、頼れる大人として安心したのである。彼女はわたしに、想いでの教会を見たのだ。わたしの膝の上で寝ていた彼女は中学生ではなく、まだ教会に通っていた頃の、幼い女の子だったのだ。親を憎み、家での居場所を失い、夜の街を男性客を求めてさまようようになる前の。
だがわたしは、そんな彼女にとっての教会を破壊した。わたしは彼女の目の前で、牧師と牧師が彼女を押し付けあう醜態をさらしたのだ。それだけはやってはいけないことだった。彼女が野生の眼を光らせたとき、もはや教会さえもが彼女の居場所ではなくなった。彼女は今後二度と教会には近寄らないだろう。彼女は二度と牧師を信用しないだろう。
責任もとれないのに、わたしはその場だけのいい格好をしようとした。そして責任の所在という重い問題が頭をもたげるや、保身に走ろうとした。それでも、わたしはずるずると考え続けている。「責任をとれないことはやらない」でいいのだろうかと、往生際の悪い悩みを悩み続けてもいる。もう答えは出たではないか。無責任な結果がこれである。それにもかかわらず、わたしは未だに別の答えを探し続けているのだ。彼女を目の前にしたときに、拒絶することは「責任をとれないことはやらない」という意味では正しい。ただし、「責任がとれないことはやらない」という意味でのみ正しい。言っておくが、わたしはあの少女に声をかけたことを正当化したいのではない。わたしが彼女と出遭ってしまったとき、そこには、後先を考えずに応答せずにはおれないなにかがあったのではないか。決してうまくやり過ごしてはならない、関わりの意志へとわたしを衝き動かすなにかがあったのではないか。
わたしの神学部時代の恩師が、かつてこんなことを言った。
「人との出遭いは、交通事故のようなものだよ」
交通事故は予測可能なら起こらないものだ。起こってほしくもない。それは唐突に、自分の思いなし一切を突き破って起こる。事故を起こしたら、救急車や警察を呼ぶなどしなければならない。放置して逃げたら、それは犯罪である。事故に巻き込まれること。それは、自分の意志に関わりなく、その事故に関わらざるをえないということである。わたしは彼女と交通事故を起こしたのかもしれない。その場を立ち去ることは、彼女を轢き逃げするに等しいことだった。
わたしはそのような仕方で出遭う、予想外の他人に対して、責任をとれるのだろうか。そこで語られる責任とはなんだろうか。わたしたちは、究極的には自分の人生を生きるしかない。自分の人生の責任を他人に負ってもらうことはできない。また、他人の人生における、あれこれの結果をその人の代わりにわたしが出してやることもできない。あの少女がどんな人生をその後歩んだのかは分からないが、もしもあのとき「適切に」関わったとしても、それは彼女の人生を代わりに善くしてやったことにはならない。わたしとの関りを善いか悪いか判断し、行動を起こすのは彼女自身なのだ。彼女の人生を生きるのは彼女自身だからである。もしもわたしがあのときバスをキャンセルして彼女と関わり続けたとしても、それでも、わたしは彼女の人生に現われ出るもろもろの結果について、責任を負うことなどできないのである。
しかし、他人の責任を負えないということは、他人に対して無責任であることとイコールではない。他人に対してあらゆる意味で責任をとれないということになれば、そもそも責任という言葉が無意味になってしまう。そうではない。わたしはたしかに、相手の人生の結果までは背負えないという意味において、他人の人生の結果に対しては無責任に、その他人と関わる。だが、いちど関わったら、その人のことが頭の片隅にこびりつき続けるだろう。わたしたちの業界では「~のことを覚えて祈る」というが、「〇〇さんの状態が改善しますように」と言葉に出して祈るだけが祈りではない。忘れようとしても忘れられず、いつまでも頭にこびりついており、「あの後あの人どうなったかな」と気になり続けている、そのこと自体が祈りなのである。
この少女の責任を、あなたはとれるのですか。その問いに当時のわたしはひるんだ。だが今なら、こう答えるかもしれない。
そうです、責任はとれません。でも、この人に関わってみようと思います。責任なら神がとってくれますから。
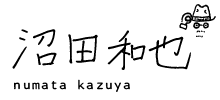 日本基督教団 牧師。1972年、兵庫県神戸市生まれ。高校を中退、引きこもる。その後、大検を経て受験浪人中、1995年、灘区にて阪神淡路大震災に遭遇。かろうじて入った大学も中退、再び引きこもるなどの紆余曲折を経た1998年、関西学院大学神学部に入学。2004年、同大学院神学研究科博士課程前期課程修了。そして伝道者の道へ。しかし2015年の初夏、職場でトラブルを起こし、精神科病院の閉鎖病棟に入院する。現在は東京都の小さな教会で再び牧師をしている。
日本基督教団 牧師。1972年、兵庫県神戸市生まれ。高校を中退、引きこもる。その後、大検を経て受験浪人中、1995年、灘区にて阪神淡路大震災に遭遇。かろうじて入った大学も中退、再び引きこもるなどの紆余曲折を経た1998年、関西学院大学神学部に入学。2004年、同大学院神学研究科博士課程前期課程修了。そして伝道者の道へ。しかし2015年の初夏、職場でトラブルを起こし、精神科病院の閉鎖病棟に入院する。現在は東京都の小さな教会で再び牧師をしている。
twitter