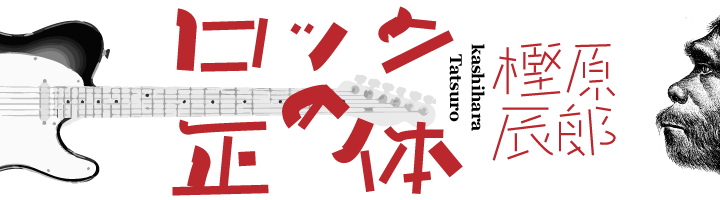ロックとはなんだったのか? 情熱的に語られがちなロックを、冷静に、理性的に、「縁側で渋茶をすするお爺さんのように」語る連作エッセイ。ロックの時代が終わったいま、ロックの正体が明かされる!?
ジョセフ・ヒースとアンドルー・ポターの共著『反逆の神話』は、60年代のカウンターカルチャーが色々と失敗をしでかしたことについて詳しく述べており、その背後に第二次世界大戦でのナチス・ドイツに対する恐怖があったことを指摘しているのは鋭い。実のところ、カウンターカルチャーがやらかした失敗とは、ヒトという動物がしばしば行う「良かれと思って始めたことが良くない結果を招いてしまう」行為の一つだからである。たとえば毛沢東は、良かれと思って文化大革命を行い、40万人が死んだ(と言われている。被害者は一億人という説もある)。スターリンだって、良かれと思って独裁を続けたわけだがソ連では78万人が犠牲になった。オーストリア出身の哲学者カール・ポパーの『歴史主義の貧困』によると歴史は決して繰り返さないのだが、世間の人々はしばしば「歴史は繰り返す」という言い回しを好む。これは何故かというと歴史の中で、似たようなことが何度でも起きるからだ。しかしながら、歴史は繰り返しているわけではない、別の時代の別の人たちが先人と似たような失敗をしてしまっただけなのである。
たとえばね、ピクニックの途中、森の中で小さな子熊を見つけたら、貴方はどうしますか? 当然のことながら子熊はめちゃくちゃ可愛い。哺乳類の子供は全部可愛いけど、熊の子供は特に可愛い、リアルちいかわだ。ヒトは小さくて可愛い奴の魅力にはあらがえない動物である。そういうふうにプログラミングされている。我々は共同体を作って生活し、時には自分の子供以外の子供の世話をすることもある動物なので、子供の哺乳類を見かけたらその可愛さにキューンとなってつい手を伸ばしたくなる。それは人情であり本能なわけだけれども、森の中の子熊には絶対に手を伸ばしてはいけない。お弁当の残りのソーセージをあげようかしら? なんてことを考えるのも良くない。子熊を見つけたら、慌てず騒がず静かにその場から離れる以外の選択肢はない。なぜなら、すぐ近くに子熊のお母さんがいて、子供に手を伸ばした貴方を見つけたら、必ず貴方を襲うだろうから。子熊に手を差し伸べて、お母さん熊に襲われた場合、悪いのは熊の親子ではなくて貴方の方なのだ。この場合、貴方は良かれと思って子熊にソーセージをあげようとしたのかもしれないが、お母さん熊はそうは判断してくれないのである。ヒトが、森の中の子熊に近寄ってエサを与えようとする度に、お母さん熊はヒトを襲うことになるだろう。このことは、今ではよく知られているので、リテラシーのある現代の登山者は子熊を見かけてもエサをあげようとはしない。しかし、今よりも熊の習性が知られていなかった時代には、子熊にエサを与えようとする人は多かったのではないだろうか。
歴史は繰り返す、という表現が使われるのは主に良くない事件が起きた時である。スターリンの失敗と毛沢東の失敗はよく似ているし、それより後に起きたポル・ポト政権の惨劇も似ている。歴史を遡ると、似たような惨劇は何度も起きているし、ヒトラーとナチス・ドイツの行ったこともやはり似ているのだ。
森の中での子熊に手を差し伸べて母熊に襲われるという惨劇はなぜ起きるのだろうか? 熊という動物の習性をよく把握していないからである。動物と接するためには、その動物の習性という情報が必要なのだが、スターリンも毛沢東もヒトという動物の習性をよく把握しておらず、必要な情報がない状態でより良い社会を築こうとしたために「良かれと思って始めたことが良くない結果を招いてしま」ったのである。何事も、必要な情報がない状態では間違った前提条件が入力されてしまう。間違った前提条件は、当然のことながら当初の目的とはかなりかけ離れた結果を招いてしまう。理想的な社会を築こうとして惨劇が起きてしまったという話は昔から山程あるから、歴史は繰り返されるように見えるわけだが、これらは全て前提条件が間違っていたのである。
スターリンも毛沢東も、ヒトという動物の習性をよく把握していないにも関わらず、人間がわかっているつもりで独裁政治を行ったわけだ。ヒトラーも同じで、おそらく彼らは自分のやっていることが歴史的にかなり悪いことだという自覚はなかっただろう。良かれと思ってやったのである。これは論理学で言うところの誤謬である。ある種の認知バイアスが彼らを狂った行動に駆り立てたのだ。認知バイアスについては、近年になって注目が高まり、ヒトが数々の認知バイアスにとらわれていることが明らかになってきたわけだが、これはつい最近の話である。行動経済学などが台頭してきた21世紀の現代になって、人類はようやくこういう話ができるようになったのだ。1978年のノーベル経済学賞を受賞したハーバート・A・サイモンは『人間活動における理性』(『意思決定と合理性』)という短かいけれどもすごい本の中で面白いことを書いている。ヒトラーが書いた『我が闘争』を分析的に読むとためになるというのである。ヒトは本を読むと、そこに書かれていること、著者の考え方などに影響を受けてしまうことがあるけれども、ヒトラーの本だったら大抵の人は最初から批判の目を持って読むので、これに影響されてユダヤ人を撲滅しよう! などと言い出す人はまずいないでしょ? という論旨である。この発想はなかった。
サイモンによると、ナチスの活動の目的はドイツ国家の安全保障とドイツ国民の福利厚生だ。これ自体は悪くない。ところが、ヒトラーが語る事実がおかしいのである。ヒトラーは欧州における経済活動が困難な原因を主にユダヤ人とマルクス主義者のせいにしている。しかも、ヒトラーはユダヤ人とマルクス主義者は見分けがつかないとも書いているのだが、これらは全部間違っている。ナチス・ドイツの行動が間違っていた理由は、前提条件が間違っていたからなのは明白だ。つまり、ヒトラーは間違った前提条件でピタゴラスイッチを動かしてしまったのだ。スターリンも毛沢東も、ポル・ポトも右に同じ。だとしたら、ソ連や中国が奉じていたマルクス主義そのものが間違っていたのだろうか? という話になるのだが、これについては資本主義という難物と並べて説明する必要があるので、後ほど詳しくやります。マルクス主義、共産主義、コミュニズムといった名称で呼ばれるイデオロギーは今でも人気があるので、その支持者の皆さんと対立してしまうような事態は避けたいし、できるだけ穏当に対立を避けるための筋道を用意している。とにかく対立が一番良くないのである。実際、ヒトラーが行ったことは「我々」と「やつら」を分断する作業である。人類にとって、分断が何よりも良くない理由はチンパンジーを見れば明らかだ。我々と同じく集団で生活するチンパンジーは、別の集団と縄張り争いを行い敵と認識した個体を襲撃して殺す。つまり「我々」と「やつら」という分断が成立した時に集団内部でのトラブルとは違ったレベルの殺戮が起きるわけだ。(ちなみに、チンパンジーの集団内部での殺し合いは、たとえばメスとの交尾をめぐるトラブルなどによって起きる。この辺もヒトとよく似ている)。我々は同じ部族の仲間を守るために道徳心を育んだ動物なので、別の部族だと認識してしまったら途端に冷淡になれるのである。(この辺のお話は心理学者のジョシュア・グリーンが書いた『モラル・トライブズ』が参考になるだろう。)
分断が良くないのだとしたら、カウンターカルチャーが起こした失敗の理由も明らかではないだろうか? そう、カウンターカルチャーは「我々」であるところの若者たちと、「やつら」であるところの大人たちを分断してしまう側面があった。当時の活動家であったジェリー・ルービンは「Don’t trust anyone over thirty(=30歳以上の奴らは信用するな)」というスローガンを唱え、これがえらくウケたわけだが、実際に社会を良くしようと思うのなら世代を超えた協力が必要なはずなのに、老人を敵に回してどうするのだ。しかし、当時の若者たちはノリノリで、30歳以上は信じるな! と叫んだようである。
ここでヒトラーの話に戻る。ヒトラーが提示した前提条件はデタラメばかりだったのに、何故それが当時のドイツで通用してしまい、なおかつ多くのドイツ人から支持を得たのだろうか? 理性溢れるサイモンは、そこに注目するのだ。ドイツと言えば哲学の盛んな国である。論理的な考え方ができる人は大勢いただろう。冷静に考えたら、当時のドイツ人だってヒトラーの間違い、嘘に気がついたはずではないか。しかし、彼らの多くはヒトラーの呼びかけに乗ってしまった。これは何故か? ヒトラーがドイツ国民たちの感情に訴えたからだ。第一次世界大戦後のドイツが経済的な苦境に直面したことはよく知られている。ドイツの国民はみんなが苦労していたのだ。そこに雄弁で情熱的なヒトラーが現れた。当時のヨーロッパではドイツ以外にも反マルクス主義や反ユダヤ主義が蔓延していたというのも彼の言動に説得力を持たせてしまった理由の一つだ。ヒトラーを支持する側に回った人たちは、たとえそれが論理的でないとしても、本人の中で納得してしまったのだ。通常の場合、納得とは理解を意味するが、こういう場合において納得はバイアスとして機能してしまう。サイモンは『我が闘争』での理由付けは「冷たい理由付け」ではなく「熱い理由付け」だったと書く。そう、人類は色んなことを言葉にして文章を書くのだが、世の中には「熱い言葉で書かれた文章」と「冷たい言葉で書かれた文章」が存在する。ヒトラーの本や演説はどれも熱い言葉で構成されていた。だから国民の心を揺さぶってしまったわけだ。熱い言葉は熱い認知から来る。熱い認知とは情熱だ。感情、情動と結びついた言葉は熱いのである。でもって、どうやらヒトは情動が高まると理性というか冷静な判断力から遠ざかってしまうようなのだ。物事を論理的に解決したいのであれば、できるだけ冷静に対策を考えるのがベストだろう。ヒトラーと当時のドイツ国民も、スターリンや毛沢東も、もっぱら熱い言葉ではなく冷たい言葉と冷たい認知でことを運ぶべきだったのだが、そうはいかないのがヒトという動物のつらいところである。何故なら、冷たい言葉で演説をすると選挙で当選する確率が低くなってしまうのである。選挙で当選したいのなら、熱い言葉で市民の感情に訴えかけた方が良いことは冷たい言葉で冷静に考えても明らかである。人間というのは個人を運営するのも国家を運営するのもかなり面倒くさい動物なのだ。実際問題としては熱い認知と冷たい認知、熱い言葉と冷たい言葉を上手く使いわける道を模索するしかないのだろう。ちなみに、当時のドイツにも冷静な判断ができた人たちはいて、その多くはアメリカに亡命した。戦前のドイツは映画の先進国だったので優秀な映画人が大勢アメリカに移動したために、アメリカの映画産業は大きく発展した。戦時中のアメリカ映画には反ナチス映画がたくさんあるが、それらの多くはドイツ人の監督や俳優が作ったものだ。彼らはヒトラーに恨みを持っていたので、監督は喜んでヒトラーの悪行を効果的に演出し、俳優は喜んで悪いドイツ兵の役柄を演じたりしたのである。その結果、『カサブランカ』や『死刑執行人もまた死す』といった映画史に残る名作が誕生した。これらは、亡命ドイツ人が異郷であるハリウッドで情動と理性を上手く使い分けた好例だろう。ヒトラー許すまじ! という情動を、的確に多くの人に伝えるために、冷静に脚本や演劇プランを練ったからこそ良い映画になったわけだ。亡命ドイツ人が、悪者であるドイツ兵を見事に演じるというのは、かなり高度な知性の産物である。『カサブランカ』でドイツの軍人を演じたコンラート・ファイトは、歴史に残る名優だが奥さんがユダヤ人だったのでイギリスに渡り、その後ハリウッドに移った。『カサブランカ』の監督であるマイケル・カーティスはオーストリア=ハンガリー帝国の出身だ。生まれ故郷では『ノアの方舟』のような超大作を撮っていたが、ドイツを経由してハリウッドに招かれた。亡命したわけではないが、ヒトラーのせいで状況が変化して帰れなくなったのだ。アメリカではリーズナブルな作品ばかり撮っていたが『カサブランカ』はハリウッドの歴史に残る名作である。悪役を演じたコンラート・ファイトとカーティスは歴史に残る良い仕事をしたと言える。
カウンターカルチャーの当事者たちは、当然のように熱い言葉で語った。ただし、変な比較になるけれども、カウンターカルチャーによる副産物的な被害はスターリンや毛沢東、ポル・ポトに比べれば可愛いものなのだ。これはやはり建前とはいえラブ&ピースがあったのと、中央集権的な運動ではなかったからだろう。カウンターカルチャーの中には急進的なマルクス主義者もいたが、ヒッピーたちの多くは資本主義を頭から否定するスタンスはとらなかった。ヒッピーは色んな面でユルかったのである。そして、ユルいことはヒッピーにとって最大の美徳であったと思う。1917年、20世紀が始まってまだ間もない頃にロシア革命が起きた。人類はそこから、共産主義にしますか? それとも資本主義を続けますか? という2択問題に悩まされるようになった。この問題は、人類にとっては深刻な問題なのだけれども、人類が物事を考えるための能力を鍛える上でドリルとしては非常に好ましい課題として機能した。革命が起きてリアルに共産主義を実現したのはロシア・ソ連だった。革命って良いよね?的なことの言い出しっぺはフランスであるが、フランス革命は副産物としての被害が甚大だった。フランスでフランス革命は起きたけれども、それはブルジョワ革命であって、フランスでロシア革命は起きなかった。変な言い方になりましたが、要するにフランスではロシア革命が行ったような、国家規模で共産主義に基いた社会形態の変革は起きなかったのだ。続いて中国が共産主義化するわけだが、革命の総本舗たるフランスが共産主義国になったりはしなかった。イギリスも同じことだ。共産主義に移行したロシア・ソ連と中国は、どちらも国土がやたら広くて人口も多い。面積と人口で見るとフランスやイギリスは小国である。しかし、歴史的な影響力はやたらと大きい。イギリスの植民地政策がなかったらアメリカという国家はなかったし、イギリスが奴隷貿易をやらなかったらジャズやブルース、ロックンロールは生まれていなかった。大英博物館のコレクションが他の国の博物館よりも凄いのは、大英帝国が侵略、略奪、文化的盗用といった現代の視点から見ると悪事に見えるような行為を、他の国々よりも上手く行ったからである。ヒトはチンパンジーやゴリラと同じように集団で生活する動物であること、そしてヒトだけがその集団の規模を拡大させて国家を作る動物であることはすでに述べた通りだ。歴史の本を読むと、神聖ローマ帝国だのモンゴル帝国だのと、昔は帝国が多かったことがわかる。どうやら初期条件でヒトが作る国家は、帝国という体裁をとりやすいようなのである。これはなんとなくわかる。要するにアルファオスたるボス猿が頂点に君臨する社会である。しかし、ヒトには利他性がある。他人を思いやる心がある。ヒトは公平さを求める動物なので、道徳心を進化させるうちに、帝国とか奴隷制度とか、あんまり良くないよね? と思うようになる。植民地主義も良くないよね? 現地の人に迷惑かけるから。植民地主義というのは基本的に帝国の産物である。帝国は、どんどん領土を広げようとしますよね。モンゴル帝国などは、ユーラシア大陸全体に広がるところまでいった。ヨーロッパの植民地というのは、海の向こうの土地にまで領土を広げようとした結果である。ところがイギリスの植民地であったアメリカが独立する。その後を追うようにフランス革命が起きる。これが18世紀の話。日本はまだ江戸時代だったから、えらく昔のことのように思えるけれども、人類の歴史を文明の誕生、農耕社会の誕生からカウントすると1万年で、200年前とか300年前というのは割と最近のことなのだ。これがホモ・サピエンスの誕生からカウントするとなると20万年前である。だから、我々が今、比較的平和に過ごしている民主主義の社会というのは、人類史のスケールで考えるとわりと最近できたものなのだ。理想的な社会とはどのようなものなのだろうか? ということに関しては昔から色んな人が考えてきたのだけれど、(ちなみに、プラトンが『国家』を書いたのが2300年くらい前です)、実際に帝国ではない、新しい形の社会を作れたのはわりと最近で、しかもそれがベストなのかどうかはまだ誰にもわからなかった。国のやり方を大きく変えるというのは、一種の社会実験なわけだが、スケールが大きすぎるのと、失敗したら目も当てられないので滅多にできない、というか滅多に起きないイベントである。ロシア革命は、この滅多に起きないイベントが起きたわけだが、その少し前から第一次世界大戦が始まっている。言い換えると、第一次世界大戦が引き金になってロシア帝国やドイツ帝国、オーストリア=ハンガリー帝国などの帝国がバタバタと倒れたとも言えるわけだ。第一次世界大戦が終わってから第二次世界大戦が始まるまでに20年の月日があるが、戦後の混乱期があり敗戦国は経済的な苦しみを味わい、小さな規模の戦乱、軍事介入はたくさんあった。そのうちに大恐慌がありファシズムが台頭する。つまり、戦間期とはいえ相対的に平和な時代は数年しかなかったのである。本当に20世紀の前半は戦争に終始した。戦争が終わって、人類全体が、戦争は良くないものだ、というコンセンサスを獲得したのはめでたいことではあった。
カウンターカルチャーが勃興した60年代の世界は、問題だらけだった。まずは環境問題。1962年にレイチェル・カーソンの『沈黙の春』が出版され、ベストセラーになった。この本は公害の恐ろしさを描いたものだが、実際に公害が酷いことになっていたからこそ、ベストセラーになった、のである。奇しくも同じ年にキューバ危機が起きている。第二次世界大戦が集結した後、アメリカとソ連が冷戦に突入したことはよく知られているが、キューバ危機は本当に世界のピンチであった。アメリカとソ連がそれぞれ所持していた核兵器を使っての全面核戦争が起きた場合、全世界規模の核爆発で人類が絶滅すると言われていたのである。キューバ危機の時は本当に、全面核戦争に突入しそうになった。つまり、60年代から70年代にかけて、世界中の人間が〈我々の文明が生み出した公害によって地球が滅びてしまうかもしれない〉恐怖と〈明日、いきなり全面核戦争が起きて人類が滅亡するかもしれない〉恐怖、この2つをずーっと抱えて暮らしていたわけだ。当然のことながら新聞や本には地球が滅びる可能性について書かれた言葉がたくさん踊っていたし、映画のようなフィクションの世界でも人類滅亡をテーマにした作品が量産された。人類は良い方向に向かって繁栄していますよ、というテーマの『繁栄』を書いたマット・リドレーが、同書の中で熱心に人類の未来は明るいのだという話を繰り返すのは、自分が子供の頃に「人類の未来はお先真っ暗だ」というニュースやフィクションが山のようにあって、そういう暗いニュースが多いこと自体が人類のために良くなかったと考えているからである。
1962年といえば、ビートルズがデビューし、翌年デビューするローリング・ストーンズが結成されて初めてのライブをやった年である。ジョン・レノンやポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスンは、生まれて初めてのレコードが発売されてわずか十日ほど後にキューバ危機のニュースを知り、せっかくデビューしたのに世界が破滅するかもしれないという恐怖を味わったことになる。
核戦争が起きるかもしれないという恐怖は、基本的にソ連が崩壊し冷戦が終わったと認識されるようになるまで続いた。その一方、公害に関しては色んな国のいろんな企業や市民団体などが、時間をかけて取り組み、海や空は徐々にきれいになっていった。日本でも60年代後半から70年代にかけての河川や空は凄まじく汚染されて本当に汚かったのだが、今の海や空しか知らない若い世代にそれを伝える術がない。最も良いのは映画『ゴジラ対ヘドラ』を観てもらうことかもしれない。今観ると奇天烈な映画だが、そこに描かれている公害の恐怖は当時はリアルなものだったのである。リドレーも、昔の空や海を自分の目で見てきたからこそ、シフトチェンジした時の人類の底力を高く評価し、未来は明るいぞと言えるわけだ。漠然とした社会的な不安が人々の行動にどのような影響を与えるかについては、なかなか計測したりできるようなものではないが、我々はまだ終結していないコロナ禍において、色んな国で暴動が起きたのをネットの動画で見たばかりである。たとえばBlack Lives Matterはコロナとは直接は関係ないが、誰もがコロナ禍におけるストレスを感じていたので騒ぎの規模が大きくなった面もあるのではないか。60年代というのは今よりも治安も悪く、社会的な恐怖は遥かに大きかった。かてて加えて、アメリカは山のような問題を抱えていた。深刻化するベトナム戦争、アフリカ系アメリカ人の公民権運動、女性解放運動。ビートルズやローリング・ストーンズ、ボブ・ディランらが世に出たのは、そういう時代だったのである。
ビートルズもローリング・ストーンズも初期のアルバムはオリジナルの曲だけではなく、彼らが影響を受けた人たちのカバーが含まれていた。どちらも、アメリカで発売されたアルバムはイギリスでのオリジナル盤とは少し曲目が違う。これは、レコード会社もアーティスト自身も、ロックのアルバム作りとはどういうことなのか、まだよくわかっていなかったのでオリジナル盤には入っていなかったヒットナンバーを加えたりしたのである。その方が売れると思ったわけですね。ところが、どちらのバンドもあっという間にオリジナルアルバムの作り方を確立させた。ロックにおけるコンセプトアルバムの先駆けはビートルズの『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』だと言われるが、映画のサントラ盤でもあった『ハード・デイズ・ナイト』あたりから既に全体に統一感のあるアルバム造りが始まっている。エリック・ドルフィーやマイルス・デイヴィスといったモダンジャズのアーティストたちは、早くからアルバム単位で統一感のある作品を作っていたわけだが、ロックミュージシャンたちもそれに倣ったのである。ロックンロールから60年代ロックへの移行で大きな変化があったのは、エルヴィス・プレスリーと彼のバックバンド、という形ではなくバンドが主体として扱われるようになったこと。そして、シングルレコードよりもアルバム単位で扱われることが多くなった点だ。アメリカの音楽評論家でボブ・ディランが初めてエレキギターを持ったニューポート・フォーク・フェスティバルの現場にもいたイライジャ・ウォルドは、ビートルズがロックンロールを破壊したと主張している。ジュークボックスでかけられるシングルレコード主体のロックンロールが、ビートルズによってもたらされたアルバム至上主義によって破壊されてしまったという論旨である。言いたいことはわかる。確かにロックは、ティーンが気楽に踊るだけの音楽ではなくなってしまった。とはいえ、時計の針を元に戻す方法はないのだ。ビートルズの歌う歌詞は、短期間でどんどん実存主義やシュルレアリズムの影響を受けたようなものになっていった。ほんの数年前まで、「愛はお金では買えない(Can't Buy Me Love)」と歌っていた人たちが「私は海象(I Am the Walrus)」など歌い始めたのだ。貴方たちの人生に、いったい何があったんですか?! と訊ねたくもなる。ビートルズのメンバーたちはドラッグカルチャーとサイケデリックカルチャーを真っ正面から受け止めた人たちでもある。何しろ彼らには有り余るほどのお金があったので高価なドラッグがたっぷり手に入った。
ローリング・ストーンズも歌詞の内容を文学的で社会派な方向にシフトしていった。ジョン・レノンやミック・ジャガーはおそらく、自分たちがどうやら単なるポップスターではなくて社会的な影響力を持つ文化人であることに気がついていたのだ。レノンもジャガーもアートスクール出身である。パンクロックの時代になってもブリティッシュロックの牽引者はアートスクール出身者が影響力を持った。日本にたとえると、美大や芸大である。ジャガーはアートスクールを経由して経済学を学んだ。ロックの時代においても学歴や教養といった文化資産は役に立つのだ。
ブリティッシュインヴェイジョンの旗手たちが、軽いラブソングから文学的な表現に移行できたのは何故だろう。イギリスでは、1950年代に「怒れる若者たち」と呼ばれる作家たちが出現していた。短編集『長距離走者の孤独』で知られるアラン・シリトー、『怒りを込めて振り返れ』で知られる劇作家ジョン・オズボーン、カウンターカルチャーに多大な影響を与えた評論『アウトサイダー』で世に出たコリン・ウィルソンたちである。そしてアメリカにはビートニクスと呼ばれる作家たちがいた。『路上』や『禅ヒッピー』で知られる放浪の作家ジャック・ケルアック、『吠える』の詩人アレン・ギンズバーグ、『裸のランチ』で知られるドラッグまみれの作家ウィリアム・S・バロウズたちだ。ロックの文学性や実存主義的なイメージはこれらの作家たちから受け継がれたものである。さらに源流をたどると、19世紀のイギリスには『阿片常習者の告白』で知られるトマス・ド・クインシーがいた。イギリスにはジョン・キーツ、ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティといった詩人がおり、彼らもまた阿片に耽溺していた。キーツもロセッティもロマン主義の詩人であることに注目。薬物による酩酊はロマン主義、デカダンスと相性が良かった。だから20世紀のロックとも当然のごとく相性が良かった。クインシーやキーツらが阿片にハマった理由は簡単で、手に入りやすかったのである。19世紀の初頭からイギリスは植民地であったインドで現地の農民にケシを栽培させて阿片を大量に生産した。これが阿片戦争に発展したのは歴史の教科書に書いてある通りだ。当時のイギリスでは町の薬屋で阿片が買えた。ジョン・レノンやルー・リードといったドラッグ体験を歌にしたアーティストたちは、ビートニクスを経由してロマン主義の文学を継承しているのだが、20世紀のドラッグは前世紀の阿片よりも洗練され、効き目が強かった。それが数々の悲劇を生む……。
〈参考文献〉
ジョセフ・ヒース、アンドルー・ポター『反逆の神話〔新版〕――「反体制」はカネになる』栗原百代訳、ハヤカワ文庫NF、2021
ハーバート・A・サイモン『人間活動における理性』山形浩生訳、2020,cruel.org/『意思決定と合理性』佐々木恒男、吉原正彦訳、ちくま学芸文庫、2016
マット・リドレー『繁栄――明日を切り拓くための人類10万年史』大田直子、鍛原多恵子、柴田裕之訳、ハヤカワ・ノンフィクション文庫、2013
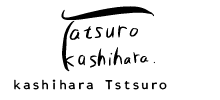 映画監督・脚本家・文筆家。一九六四大阪生まれ。大阪芸大在学中に海洋堂に関わり、完成見本の組立や宣伝などを手がけた後、脚本家から映画監督に。監督作に『美女濡れ酒場』、脚本作に『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説』など。著作に『海洋堂創世記』『「痴人の愛」を歩く』(白水社)、『帝都公園物語』(幻戯書房)がある。
映画監督・脚本家・文筆家。一九六四大阪生まれ。大阪芸大在学中に海洋堂に関わり、完成見本の組立や宣伝などを手がけた後、脚本家から映画監督に。監督作に『美女濡れ酒場』、脚本作に『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説』など。著作に『海洋堂創世記』『「痴人の愛」を歩く』(白水社)、『帝都公園物語』(幻戯書房)がある。
twitter