セクハラ被害を言語化することはむずかしい。ましてや、それが「よきことをなす人」たちの組織内で起きたときの場合は、さらに複雑な事態となる。そもそも、セクハラはなぜおきるのか。「よきことをなす」ことが、なぜときに加害につながるのか。被害を言語化するのにどうして長い時間が必要になるのか。セクハラをめぐる加害・被害対立の二極化を越え、真に当事者をサポートするための考察。
本連載のタイトルにある「セクハラ」という言葉について、第一回掲載の後、いくつかのご意見をいただいた。もっと別の言葉を使った方がいいのではないか、性暴力という言葉を用いればダイレクトに伝わるのではないか、などといった提案だった。
それを機に私自身がなぜハラスメントという言葉を使用したのか、性暴力ではなくセクハラと表現したのかについて説明したい。私がもっとも大切にしているのは、ひとつの事態をどのように呼ぶか、どのような言葉で定義するかということである。長年、ひとつの言葉は誰のためのものかという疑問を抱いてきたことも大きい。
精神医学的診断名も、臨床心理学における見立ての言葉も、いったい誰のためなのか。正確な診断は、目の前の患者さんの望ましい治療のためであったはずなのに、保険診療のために必須な行為に化していないだろうか・・カウンセラーとして、私は目の前に居る人たちを、勝手に名づけることを禁じてきた。
近年の私の言葉へのこだわりは、あまりに厳密すぎるのではないかという批判さえ受けるほどだ。時には「検閲官」みたいだと自嘲したりすることもある。たぶん、これは私がカウンセラーとして生きてきたことも大きいだろう。精神科医とは違い、診断基準にとらわれる必要はなく、病名をつける義務もないからだ。国家資格である公認心理師は、診断という医師の診療行為に近づくことは禁じられている。
そんな私だが、実はセクハラという言葉についてはそれほど考えずに使用してきた。そのことを恥じている。しかし本連載を機にはっきりしてきたことがある。それは官製の言葉としてハラスメントが広がってきたということだ。
考えても見てほしい、1990年代には問題とされなかったことが、この20年間で急速に規制されるようになったのである。それも、長年尽力してきた女性アクティビストたちの努力の成果というよりも、後述するようにグローバル資本主義の時代が要請したから生じた変化ともいえるのだ。
女性に対する2つの暴力
70年代のウーマンリブ、80年代から始まる女性学やフェミニズムの広がりを担う女性たちが、これまで自分たちに対して行われてきた「人権侵害」的な行為を、耐えるべきではなく「暴力」と呼ぶことで自らの被害を共有するようになったのである。欧米では70年代に始まる夫からの暴力から逃げてきた女性たちのシェルター設立運動だったが、日本でも80年代に民間の支援者たちによってそれは誕生した。フェミニズムのムーブメントは、DVと性暴力という他者の目が遮断された状況における女性への暴力被害への糾弾と被害者支援を抜きにはありえなかったと思う。家族という親密圏における配偶者(多くは夫)の暴力と、人間にとってもっとも個人的(プライベート)な性をターゲットにした暴力。この二つは重なる部分もあるが、ともに手に手を取るようにして被害者支援や防止を訴えながら発展してきた。人権という言葉が届かない場所として、つまり「愛情」という言葉で粉飾されがちであった家族や性的関係においても人権侵害が生じることを訴えたのである。その主体が女性たちだったことは当然だろう。
この二つに関して、日本社会はいまだに正面から対応していない。2001年のDV防止法の制定は大きかったが、いわゆる「加害者逮捕」「司法による処罰」に関しては手付かずのままである。いたずらに防止だけが叫ばれて、被害者だけがすべてを捨てて逃げるしかないという貧困な対策であることはもっと多くのひとに知ってほしい。
性暴力に関しては、明治時代の刑法のままだった「強姦罪」が改正されたが、性交同意年齢は13歳と先進国では最低のままであることも意外と知られていない。お隣の韓国では13歳から16歳に引き上げられたことは記憶に新しい。その他性犯罪に関する法律に関しては現在改正の動きがあるが、遅々として進まない。明治時代のままの法律を守りたいという国家の意志をそこに感じてしまうのは私だけだろうか。
グローバル資本主義とハラスメント防止
そこにするりと入ってきたのがハラスメントのひとつとしてのセクハラという言葉だ。
21世紀になって先進国で顕著になったのは、ハラスメントは企業にとって最大のリスクであるという認識である。人権重視がいわゆる企業の組織防衛に有効であり、そのためにハラスメント対策が必要だということになる。企業や銀行といった大きな組織にとって、今や最大のリスク管理は数々のハラスメントを防止することである。不祥事が起きた際の謝罪会見が、どれもこれも似通っているのは、このような練りに練られた対策にのっとっているからだろう。企業イメージや印象は、ハラスメント事案の表面化、それへの対応によって、一日で失墜しかねない時代なのだ。
そのような流れの中で法改正が行われた。2019年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律(いわゆる女性活躍推進法)の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正された。2020年6月にそれが施行されたことに伴い、職場におけるパワーハラスメント(セクハラを含む)防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となった。さらに、中小事業主も、2022年(令和4年) 4月1日からそれが義務化されるのである。
簡単に言えば、企業においてセクハラ相談窓口設置が義務化されたことを表している。厚労省の次のような通知を見てほしい
(事業主向け)セクハラリーフ完成版 (mhlw.go.jp)
じつは、この通達に類した内容は、2000年代の初めから外資系企業では当たり前だったし、一部の上場企業では、すでにパート社員(当時はこう呼んでいた)に対してもハラスメント相談窓口があった。
1995年に原宿カウンセリングセンターを設立してから、女性クライエントの中には職場の人間関係で不安定になった方も珍しくなかった。2000年代初頭のころから、某自動車会社にはそのような窓口が設置されていて、正社員でなくても懇切丁寧な相談がなされていた。そのことにカウンセラーとして驚いたことを覚えている。
ハラスメントという言葉が切り離したもの
日本の企業が慌てふためいているのは、欧米の企業に比してはるかに対策が遅れていたことの表れだろう。それまで当たり前になっていたいわゆる企業文化、サラリーマン文化が(マンとは男性のことだ)、多くは男性目線によるものであり、曖昧に笑って見過ごすしかなかった女性たちが実は不快だったり、ショックを受けていたということが示されたことになる。
その副産物として、多くの企業はハラスメント対策全般を請け負う団体と契約するようになった。社員のメンタルヘルス維持・増進は当たり前になっていたが、ここにきてハラスメント(中でもセクハラ)をどのように防止するかについて、社員教育や相談活動全般を請け負い、ハラスメントが生じたときに迅速なシステム的対応ができるためのスキルを提供する団体が増加しつつある。私たちのような公認心理師たちも、研修や相談活動要員として雇用されることが増えている。
さまざまな不祥事が発生した際の組織や企業の「謝罪会見」がどれも似通っているのは、そのような方法やスキルが用意されていることの表れだろう。
このように、法改正に伴って遅まきながらセクハラが企業の主要リスクのひとつと化したことによって、犯罪としての性暴力との切り離しが起きたのではないかと思う。
言葉を戦略的に用いる
本連載ではそのような切り離しに内在する問題点を無視するわけではない。性暴力は夫婦のあいだでも、見知らぬ男性とのあいだでも、顔見知りの男性との間でも起きる。そして職場や仕事関係に特化した性暴力がセクハラだと考えている。
そのうえで、あえてセクハラという言葉を使用するのは、仕事、職場、団体内で起きるそれを特化させるためである。性暴力と名指すことで漏れ落ちてしまう可能性を少しでも減らすためである。中でも、社会的正義のための活動、利益追求とは無縁と思われる活動でありながら、そこで活動する人たちの生活が支えられている団体、いわゆる「よきことをなす」団体において生じた被害を特化させるために、あえてセクハラという言葉を使用する。
それと逆のことを、モラハラとDVという呼び名の間で主張している。夫の行為をモラハラと呼ぶか、精神的DVと呼ぶかは女性たちのあいだで違いがある。ネットユーザーのあいだでは、圧倒的にモラハラが優位であり、モラ夫、モラ、という呼び名さえ流通している。私は、これまでずっとモラハラという言葉を使用してこなかった。夫のモラハラを訴えるクライエントに対しては、わざわざ「それは精神的DVではないでしょうか」と言い換えたりしてきた。
その理由は、身体的DV(殴る蹴るなど)と同じであることを強調したいからだ。いまだに殴られて痣ができなければDVではないと信じている人が多いから、よけいにそのことにこだわっている。モラハラだけどDVじゃない、などという認識は、DVに対する誤解である。それに、このようにDVを特殊化し、差異化することで生じるものは、不完全なDV防止法を固定させてしまうと思うからだ。それほどまでに、DV対策はこの20年間で打ち捨てられてきたと思う。DV被害者は骨折や痣だらけという誤解は、行動制限したり女性蔑視的な言葉を吐いたりし、正義を押し付けたり、時々キレたりする夫に対して、モラ夫と名付けるだけでスルーすることにつながる危険性がある。
その言葉によって救われる人たちの存在
セクハラに対して法改正によっていっせいに企業が対策に乗り出すという迅速さを目にするたびに、DVはなぜ防止法が制定されてから20年経っても変わらないのかという苦い感懐を抱く。どこかで「打ち捨てられた」感が私を襲う。この明快なまでの対比を前に、それほどまでに、家族で起きていることは変えたくないのか、被害者という自覚をもたせたくないのかと思ってしまう。
だから私はモラハラという言葉を回避する。いっこうに変わらない日本のDVに対する政策に対して、膨大なDV被害者の存在を訴えていく必要があり、DVの本体は精神的DVであることを周知してほしいから、あえて精神的DVと言い換えることにしている。そこにも戦略的意図がある。
これまでもひとつの言葉によって「ああ、私の経験に名前がつくんだ」と思い、救われた人が数多くいた。セクハラも同様だ。「これをどう呼べばいいのか、この経験をどのように名づければいいのか」と混乱する。それが定まらないために、精神的不調を訴え、体調まで崩す女性たちに何人もお会いしてきた。
次回はそれらについて書いてみたい。
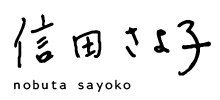 1946年生まれ。公認心理師・臨床心理士。お茶の水女子大学大学院修士課程修了。1995年に原宿カウンセリングセンター設立、現在は顧問。アルコール依存症、摂食障害、DV、子どもの虐待などに悩む本人や家族へのカウンセリングを行なってきた。『母が重くてたまらない』(春秋社)、『DVと虐待』(医学書院)、『加害者は変われるか?』(筑摩書房)、『家族と国家は共謀する』(KADOKAWA)、『アダルト・チルドレン』(学芸みらい社)、『家族と災厄』(生きのびるブックス)など、著書多数。
1946年生まれ。公認心理師・臨床心理士。お茶の水女子大学大学院修士課程修了。1995年に原宿カウンセリングセンター設立、現在は顧問。アルコール依存症、摂食障害、DV、子どもの虐待などに悩む本人や家族へのカウンセリングを行なってきた。『母が重くてたまらない』(春秋社)、『DVと虐待』(医学書院)、『加害者は変われるか?』(筑摩書房)、『家族と国家は共謀する』(KADOKAWA)、『アダルト・チルドレン』(学芸みらい社)、『家族と災厄』(生きのびるブックス)など、著書多数。

