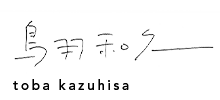いつも旅が終わらぬうちに次の旅のことを考え、隙あらば世界中の海や山に、都会や辺境に向かう著者。とは言っても、世界のどこに行っても自己変革が起こるわけではなく、それで人生が変わるわけでもない。それでも、一寸先の未来がわからないかぎり、旅はいつまでも面白い。現実の砂漠を求めて旅は続く。体験的紀行文学の世界へようこそ。
いよいよジャワ島も最終滞在日になり、空港に行く途中に僕の家があるからと、4日前からいっしょに島の東部を周ったミコの家に立ち寄ることになった。ジャワ島では治安の心配がある山岳地帯を巡ったので、日程の後半は専属ガイドをつけて行動した。ミコはいつだって私の拙い英語をウンウンとうなずきながら一生懸命に聞いて、せいいっぱい応答してくれた。僕は彼のウンウンがとても好きだった。君は興味深いことを話しているねというふうだが、でもわざとらしくない。こんなに自然でやさしい人に僕はこれまでに出会ったことがあるだろうかと思ったくらいだ。
車窓から見えるのは稲の手植えや鋤を引く水牛といった伝統的な農村風景。「この時季に田植えをするんだね」と尋ねると、ミコは「年に2回植えるんだよ」と言う。米の二期作だ。「二毛作とは違うよ。」思わず頭の中の生徒たちと授業を始めてしまう。この地域は最近、エコツーリズムで西洋人たちがさかんに訪れるようになったらしい。
「でも日本人はまず来ないよ。来るのは欧米人ばかり。そういったツアーを受け入れることで、一部の農家は経済的にすごく助かってる。」
「水牛が活躍してるけど、農業機械を導入する…とかいう話はないの?」
「もちろんあるよ。一部では実際に使われているし。でもすごく高価なんだ。だから、稲刈りのときはよそから借りたり共同購入したものを使ったりしている。一方、老人がその使い方をいまさら習得するのは難しい。使ってみたけどうまくいかなくて、結局もとのやり方に戻った人もいるよ。まあ、それぞれがやりやすいようにやればいいさ。」
そう言ってミコは車を走らせたまま目を細める。彼の視線は遠く、空のかなたをさまよう。
「ラヤンラヤン」
何かのまじないのようにミコはつぶやく。
「カイト、凧だよ。インドネシアの人たちの生活にはいつもカイトがある」
彼の視線の先に、凧が4つ、5つ空を高く舞っている様子が見える。凧の下で糸を引く、生き生きとした人たちのことを想像する。
「このあたりの棚田はほんとうに美しいね。さっきミコが「日本人はまず来ない」って言ったけど、なぜ来ないと思う?」
「日本人…というか、これはまあ韓国や中国、台湾の人たちも含まれるんだけど、そういう人たちと、ここに来る欧米やオーストラリアの人たちとでは旅に求めるものが違う。トバさんにはきっとそれがわかるよね?」
「確かにそういう傾向はあるかもしれない。大雑把に言うと、アジア人は概して買い物が好き、欧米人は自然や文化が好き。そういう感じかな?」
「そう。僕はバリ島で働いていたことがあるから、そのコントラストは目を見張るほどだった。ダイビングだけはアジア人も好きだけど。でも、バリ島で登山やトレッキングをする日本人はほとんどいないでしょ。そして、ここジャワ島まで来てわざわざ火山を登りたいって言いだす日本人も珍しいよ。」
そう言ってミコは僕のほうをみて笑う。昨日まで僕とミコのふたりは島東部の火山地帯を巡った。噴出するガスでボコボコと揺れる火山原を歩いたり、ブルーファイア(硫黄ガスが発火したもの)を見るために防毒マスクをつけて火山の縁から火口に下りたり、高さ40mから落下する滝水を浴びて身体ごと流されそうになったり。僕はいつもと全く違う世界で、今を生き生きと生きているんだ。そういう実感に溢れていた3日間。
「西洋人とアジア人では、消費についての意識が違ってるよね。西洋のツアリストたちは、日ごろから仕組まれた産業の中で自分らが消費を強いられていることに自覚的だからさ、消費行動として最もわかりやすいショッピングには興味を失っている。でも、なんだかんだそこはまだアジアの人たちは素朴だよ。いまだにショッピングが楽しみとして成立しているんだから。この国の人だってそうさ。みんな買い物が大好き。トバさんを空港に降ろしたら、僕もすぐに家族へのお土産を買いに行くさー。ふふふー。」
ミコの「ふふふー」の笑いには暗さが少しも混じっていない。純然たる明るさとしての「ふふふー」。ミコは僕より3つおじさんで、そして「ふふふー」がかわいい。こんなふうにただ明るく笑うには、どう生きたらいいんだろう。僕もミコみたいにただ明るく笑えたらいいのに。
「でも、アジアの人たちは西洋の人たちと比較して自分たちの行動を卑下しなくってもいいよね。だってさ、西洋人のエコな体験や娯楽ってのは、結局のところ消費行動をサニタイズするためにあるんだから。彼らだって自分がそれをやって何になりたいのかなんてわかっていない、僕にはそう見える。えーっと、トバさんはどうかな。うーんとね、トバさんは生きるエネルギーを余らせてるから、ここで発散してバランスを取ってるんだねー。」
ちょっと意訳だけど、ミコは隣で人なつこい笑顔のままつらつらとそんなことを話している。4日も同じ人と同じ時間を過ごすと、話す英語がスラスラと頭の中に入ってくるようになることに満足する。僕は「いまはアジアの人たちも変わってきてると思うけど…」と言いながら、ミコはどうやって「消費行動」というキーワードにたどりついたんだろうかと思う。
「ミコはガイドの仕事を楽しんでるの?」
「もちろん楽しいよ!4日もいっしょにいてなぜそんなことを聞くんだい? 実際に「体験」が始まると、動機は消えて楽しさだけが残るじゃない。だから体を動かすってことはいつでもいいことさ。そして、ゲストだけでなく、ガイドする側、つまり僕も同じこと。」
「ガイド中にイヤなことが起こったりすることはある?」
「イヤなことなんてものはないね。でも気になることはある。例えばよく「うちの国にも遊びにおいでよ!」って仲良くなった欧州の人たちに言われるけど、僕たちインドネシア人が観光で欧州に行くのがどれだけ難しいことか、きっと彼らの想像の何倍も難しいということをわかっていない。ビザの問題もあるし。でもね、そのかわりに僕はたくさんの国の人たちと話している。今日は日本のトバさんと。だから僕は彼らに言うんだ。「僕はもう何もかも見ているから、行かなくても大丈夫」って。実際のところ、移動することとものを見ることの間には直接の関係はないんだよ。」
ミコの自宅に着いた。エンジンの音を聞きつけた男の子が家の黄色いドアから飛び出してくる。目がきりりと美しいその男の子は僕と目が合って少しひるむ。ミコが「トバさんだよ、日本からのお客さん」とその子にたぶん言っている。男の子はミコさんのズボンにしがみついて何かをねだるような声を出している。ミコは「ちょっと待ってよ、プリンゴ」と言って彼を引きずりながら黄色いドアを開ける。
部屋に入るとミコによく似た顔立ちをした高齢の女性と、中学生か高校生くらいの女の子がソファーに座ってピーナッツを食べている。
「アユ、日本からのお客さんのトバさんだよ、挨拶しなさい」とミコに言われているようだが、女の子は絶賛思春期中のひきつった表情で部屋の隅に逃げて座り込んでしまう。「もう、いつもアユはこんななんだから…」とミコはお手上げのポーズ。「アユはJKT48が好きなんだから、話してみなよ…」と言ってる最中から「なんで勝手にそんなこと言うの!?」とキレられている。
「うちの畑で採れたバナナ、食べてみる?」とミコに言われて緑色のバナナが置かれたテーブルの前に座る。隣にはおばあちゃん。いつもこの席に座っているんだろう。プリンゴとアユもバナナに寄って来る。思春期の葛藤もバナナには勝てないらしい。バナナは日本のそれよりずっと小さい。包茎の半勃ちチンチンが根元から大量に生えているようだ。
「美味しいんだから~」とミコが甘い顔で言うので一気に根元まで頬張ってみると、全然甘くなくて、しかも固くて噛みきれなくて思わず吐き出しそうになる。ガリガリとした食感を楽しむ余裕もなくゴクリと吞み込む。平静を保っていたつもりなのにミコから「苦手だったかい?」と尋ねられる。「いや、慣れないだけ。これは野菜みたいに料理にも使うの?」と尋ね返すと、揚げたりご飯に混ぜたりして食べることもあるそう。
プリンゴとアユはテーブルの向かいでたまにお互いを見やりながらバナナをむしゃむしゃと食べていて、おばあちゃんに「あまり食べ過ぎないのよ」とたぶん言われている。
子どもたちにお土産を持ってきてないのがつくづく残念だと思いながらふたりを見ていると、バッグの中にお菓子が入っていたことを思い出して取り出す。南阿蘇の料理家、かるべけいこさんのローズマリークッキー。僕が世界で一番好きなクッキー。
「日本からのお土産、クッキーだよ」と言ってふたりに渡そうとすると、ミコが「ほら、日本のクッキーだって。食べてみなよ」と助太刀してくれる。ふたりは興味を示すものの、あからさまに警戒している。
結局プリンゴくんは「いらないー!」と言ったきり隣の部屋に走り去ってしまう。ひとり残ったアユに「ほら、食べてみなよ」とミコがゴリ押しするので、アユはしかたなく一口サイズのまん丸いそれを口に頬張る。途端にアユは異物が入ったような「何コレ!?」という顔をする。かるべさんのクッキーは既製品のそれとは違ってとても固いのだ。ヨックモックのやわらかいクッキーだったら喜んで食べてくれただろう。でもアユはいま、人生ハードモードみたいな表情で、人生を噛むようにクッキーを噛んでいる。僕はバナナ、アユはクッキーで、ハードな体験を交換するという結果になった。
ミコが村を案内してくれるという。ここはわずか80人くらいが住んでいる小さな集落で、隣の集落までは5㎞以上離れているとのこと。ミコは道で会う人すべてに等しく話しかける。「みんな家族みたいなものだから」と言う。途中、青い扉の家の前で凧を作っているおじさんがいる。僕の兄だよとミコ。家族みたいというか家族だった。兄は凧を作るのが上手なんだというのでその手さばきを見ていると、実際に匠に見えてきた。腰を浮かしたまましゃがんで作業をしていて、よくそんな姿勢のままずっと安定していられるなと思う。
途中からプリンゴの友達ふたりがついてきた。いっしょに石磨きのおじさんのところや洋裁店に行く。子ども3人はいつの間にか棒アイスをかじっていて、人生の辛酸を味わったアユとは違って幸せそうだ。店の中で溶けたアイスが床に落ちても、一瞥するだけで誰も気にしない。後で拭けばいい。ただそれだけのことだから、よそさまの家を汚して!なんて声を荒らげる必要はないのだ。
最後に小学校に立ち寄る。僕がこれまで人生で見たどの学校よりも小さい学校。日本の一軒家より少し小さいくらい。校舎の壁にはくまのプーサンらしきキャラクターの絵。右手と左足を同時に上げて、口角も限界まで上がっているプーさんはノリノリで少し生意気そうだ。他にもいろんなキャラクターのイラストが描かれている。
「この学校は私設の小学校。ここはほんとうに小さな集落だから、もともと小学校がなかったんだ。だから十数年前に僕ら数人がこの学校を建てて、バニュワンギから先生ができる人を連れてきて学校を始めた。でも、私設だからせっかくこの小学校で学んで卒業しても正式な資格として認められずに上級の学校に上がれない、ずっとそんな状態が続いていた。でも、昨年ようやく政府に学校として認められて、国から派遣された先生がやってきた。だからプリンゴは、僕らが行けなかった上級の学校に行ける。僕はこの集落でひとりだけ英語が喋れるけど、ジャカルタやバリでバイトしながら勉強して、本当に苦労したんだ。そういうわけで学校をつくった私たちにとって、この学校はちょっとした誇りだよ。」
自分が建てた学校が十年越しに正式な学校と認められて、息子がそこに通い始めた。こんなに誇らしいことは人生でそうはないだろう。僕は「すごいね、すごいね」と言いながらカラフルなペンキで塗られた教室のあちこちをいとおしく見ながら教室の備品をそっと触る。大人の創意工夫と愛情だけでできた空間。
僕はこの4日間、ミコの秀才さに圧倒されながら、彼のことを勝手に高等教育を受けた人だと想定していたし、そんな彼の前で日本の現代的な教育の問題について滔滔としゃべってきた。ミコはそれにひとつひとつ丁寧に自分の意見を話してくれたし、僕は理想を追いながらもどこまでも地に足をつけた彼の思考に共鳴していた。しかし、彼は小学校もない集落に生まれて、学校には通えていなかった。彼の英語も思考も、大人になって自分の生活の中で磨かれていったものだった。
「政府から派遣された先生が来るようになったでしょ。どうなったと思う? なんと勉強の質が落ちちゃったんだよ。先生たちの悪口はあまり言いたくないけどね。」
ミコによると、新しい先生は子どもたちとのコミュニケーションが上手じゃない、英語もちゃんとできないので、ミコが先生に教えたりしているとのこと。
「こんなことは子どもたちの前では話せないよ」
「そうだね、子どもたちの前で先生のことを悪く言ってはいけない」
学校裏の扉の前には、身長を測るためのメモリがついたキリンの絵が貼り付けてある。プリンゴはミコが何も言わないうちからキリンに吸い寄せられるように壁にピタリと貼りついて身長を測られるのを待つ。「107㎝、この前よりまた身長がのびたね」ミコがたぶんそう言って、プリンゴはミコを見上げてふふふーと笑う。そしてプリンゴの隣では学校で飼われている白黒模様の猫が眠そうに座っている。確かな幸せがここにあると思って、心がざわめいた。
ミコの家に戻ると畑で働いていた母親も戻ってきて家族5人でアシャールのお祈りをした。そして家族と記念撮影。アユは恥ずかしい…と言いながらも、撮影の瞬間だけはにっこり笑ってくれた。花が咲いたと思った。そして空港へ。ミコとふたり、互いに寂しい気持ちを共有していることを感じる。
最後にミコは「トバさんは公平にものを見ようと努力する人だ。これからも旅を続けるべきだと思うよ」と声をかけてくれた。「きっとまた会おうね」とハグ。飛行機の窓から見たジャワ島の山々は、にじんで揺れていつまでも焦点が定まらなかった。
校舎の裏で身長を測るプリンゴ