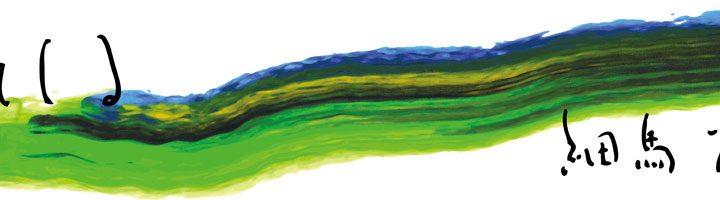いつものように学食で昼食を食べていたら、隣の学生たちがいそいそと立ち上がった。
「今日のプーさん、どこからやったっけ?」
「together?」
「あ、そうそう」
断片的にもれてくるやりとりが一瞬、詩のように聞こえる。彼らは『プーさん』という符牒で呼ばれている旅に出るところ、旅の始まりはtogetherという待ち合わせ場所か。いや、常識的に考えよう。いまはもうすぐ三時間目が始まる時刻で、彼らの手にちらと英語のリーダーらしきものが見える。おそらく彼らは英語の講読か何かの授業を受けにいくところで、その授業ではミルンの名作『クマのプーさん』をテキストにしているのだ。
彼らはただ、授業の内容を確認するためにこんなやりとりをしただけなのだろう。しかし、それを漏れ聞いたわたしは、なんだか謎をかけられたような気がした。『クマのプーさん』に「together」が出てくる箇所とはどこだろう。プーさんにはクリストファー・ロビンも子豚のピグレットもイーヨもいる。誰と誰がtogetherなのか。
数十年前なら洋書屋にわざわざ出かけていって、『クマのプーさん』のペーパーバックを手にとり、最初から丹念に読んで行くというロマンチックな展開になっただろう。しかしいまやミルンのテキストはオンラインで容易に閲覧することができる。『クマのプーさん』の原文を検索するという無粋なこともすぐにできてしまう。さっそく12件の「together」がヒットした。
クリストファー・ロビンとウィニー・ザ・プーとピグレットは一緒に話している。/ピグレットとプーはそれからいろいろ話して一緒に家に帰る時間になった。/彼らは一緒に座って考え抜いた。/ピグレットは穴の底に瓶詰めを置いて、這い出すと、一緒に家に帰った。/でもクリストファー・ロビンとプーは家に戻って一緒に朝食を食べた。/そこで彼らは一緒に話し始めた。/そして彼らは一緒に小川を少し遡った。/プーとピグレットは思案しながら、すばらしい夜の中を、長いこと何も言わず、一緒に家路に着いた……
誰かと一緒にやることは意外に種類が少ない。話すか食べるか歩くのだ。
***
「一緒に」動くというのは不思議な活動だ。たとえば今、立ち上がった彼らの動きがそうだ。相手に視線を向け、声をかけながら、テーブルに手をつき、両脚の向きを細かく動かしながら、椅子を引く。体のそれぞれの部分が異なる目的で動きながら「話しながら立ち上がる」という活動を行っている。そのまま話しながら歩き出すとき、歩く歩幅や歩速は我知らず調節されている。自分たちが横並びになっていることを確かめながら、周囲のざわめきを感じつつ自身の声をときには快活に、ときには声高に、そしてときには小さくする。食堂の重い扉を開ける。先頭の一人が扉を押すと、それが自動的に戻ってくるよりも早く二番手が扉を押さえてすり抜ける。体はすり抜けながら片手はまだ三番手のために扉を軽く支えており、三番手はあわてて歩を早めてその支えられた扉に手をあて、すり抜けざまに軽く後ろを振り返ってから誰も来ないのを確かめて扉を手放す。
「一緒に」動く活動は、多くの場合、惚れ惚れするような微妙なタイミングで調整されているのだが、わたしたちはそれをあまりに当たり前のように行っているので、自分がいかに複雑なことを成し遂げているかに気づかない。この「当たり前のすごさ」を実感してもらうために、わたしは毎年、人がドアを開けて向こうに行くという行動を何度も観察するという演習を行っている。学生に、交替でドアを開けて向こうに出てもらう。一人がドアを通過するとき、ドアに近づく歩幅がどう変化するか、ドアを押そうとするときと引こうとするときで、歩幅の変化はどのように違っているか、手はいつドアに向かって差し出されるか、ドアを開ける瞬間、脚の向き、上体の向きはどう変化するか、ドアが開いているわずかな時間の間にいかに体は巧妙に向こう側に移動するか。こうした細々とした動きをことばにするという課題を繰り返す。
一通り課題が終わったら、今度は食堂に移動して、利用者がドアを開けるところを観察する。おもしろいことに、複数の人がドアを通過するときに毎年必ず笑いが起こる。一人の人がドアを通過する運動の精妙さを何度もたどったあとでは、動作を見る観察眼は格段に解像度が上がっている。二人、あるいは三人が開けた扉を次々とリレーのように受け渡して通過していくさまは、まるでアクロバティックなグループ演技を見るようで、ふだん当たり前に見過ごしていることが、あまりに見事に見えるので、自分で自分がおかしくなってしまうのだ。
***
もし、学食で立ち上がった学生たちの用事が英語の授業だったなら、それは単に「together」の出てくる箇所というだけでなく、文が「together」で終わる箇所だろう。そしてそれは授業の区切れ目になるような箇所、今週の授業を終え、来週の授業を始めるのにふさわしい場所のはずだ。そんな区切れ目らしい区切れ目はどこだろう。
どうやらそれはここらしい。
ピグレットはまんざらでもなさそうに耳をかいてから、金曜まではやることがないし、行くのは楽しそうだ、もしそれがほんとにイターチだったら、と言いました。「もしイターチたちだったとしたら、ってことだよね」。とウィニー・ザ・プーは言って、ピグレットはなんであれ金曜まではやることがないから、と答えました。そんなわけで、彼らは一緒に出かけたのです。」(『クマのプーさん』第3章)
そこからプーとピグレットは小さな堂々巡りの旅に出る。彼らもいまごろその旅を読んでいる。
Profile
 1960年生まれ。滋賀県立大学人間文化学部教授。専門は人どうしの声の身体動作の調整の研究。日常会話、介護場面など協働のさまざまな場面で、発語とジェスチャーの微細な構造を分析している。最近ではマンガ、アニメーション、演劇へと分析の対象は広がっている。『介護するからだ』(医学書院)、『うたのしくみ』(ぴあ)、『今日の「あまちゃん」から』(河出書房新社)、『ミッキーはなぜ口笛を吹くのか』(新潮選書)、『浅草十二階(増補新版)』『絵はがきの時代』(青土社)など著書多数。ネット連載に「チェルフィッチュ再入門」、マンバ通信の「おしゃべり風船 吹き出しで考えるマンガ論」などがある。
1960年生まれ。滋賀県立大学人間文化学部教授。専門は人どうしの声の身体動作の調整の研究。日常会話、介護場面など協働のさまざまな場面で、発語とジェスチャーの微細な構造を分析している。最近ではマンガ、アニメーション、演劇へと分析の対象は広がっている。『介護するからだ』(医学書院)、『うたのしくみ』(ぴあ)、『今日の「あまちゃん」から』(河出書房新社)、『ミッキーはなぜ口笛を吹くのか』(新潮選書)、『浅草十二階(増補新版)』『絵はがきの時代』(青土社)など著書多数。ネット連載に「チェルフィッチュ再入門」、マンバ通信の「おしゃべり風船 吹き出しで考えるマンガ論」などがある。