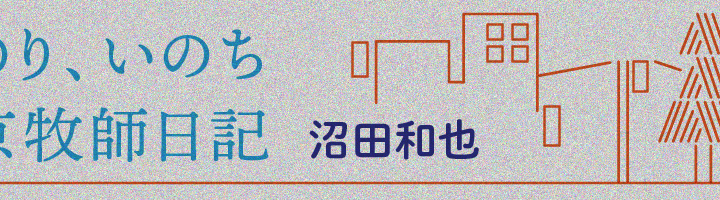教会のなかで出遭う人。教会の外で不意打ちのように出遭う人。一時は精神を病み、閉鎖病棟にも入った牧師が経験した、忘れえぬ人びととの出遭いと別れ。いま、本気で死にたいと願う、そんな人びとと対話を重ねてきた牧師が語る、人との出遭いなおしの物語。いのりは、いのちとつながっている。
わたしは2015年の6月に、精神科病院の閉鎖病棟に入院した。当時わたしは教会の牧師としてよりもむしろ幼稚園の理事長および園長として働くことが日常の大半をしめていた。サービス残業をはじめとした連日の過酷な職務内容と、幼稚園から認定こども園への登録変更の責任を負う重圧とに、わたしは次第に圧し潰されていった。ある日、そのきっかけがなんであったのかもはや思い出せないほどのささいなことで、わたしは副園長に対して怒りを制御できなくなり、瞬間的に激昂した。わたしは副園長を大声で罵ったあと、職員室から飛び出し、牧師館にひきこもった。とっさに自殺をほのめかしたわたしを、妻は泣きながら精神科病院へ入院するよう説得したのである。葛藤ののち、わたしは彼女の言葉を呑んだ。閉鎖病棟2か月、開放病棟1か月の入院。わたしはその教会と幼稚園を辞し、妻と故郷へ帰った。
それからおよそ2年後、わたしとほぼ同世代の国会議員が、激昂して秘書を怒鳴り散らしている音声がスクープされた。秘書が被害届を警察に出したことで、議員は書類送検されたという。わたしはこの出来事を他人事とは思えず、強い不安や恐怖、それに罪の意識を覚えた。話題の渦中にある議員の映像を見ながら、わたしは自身に問うていた──わたしは償ったのか?
わたしは子どもの頃から、しばしば癇癪を起した。いちど癇癪を起すと、それは自分でも分かるのだが、癇癪のきっかけとなった出来事それ自体は影をひそめてしまう。もはや怒りの感情それ自体が不愉快になってしまい、ますます癇癪がひどくなるのである。けっきょく疲れ果てるまでわたしは怒鳴り散らしたり、おもちゃを壊したりし続けた。とうぜん親に叱られたりもしたのだとは思うが、それがあまり記憶に残っていないのは、殴られることがなかったからだろう。少なくとも、叱られてすぐにおとなしくなることはなかったと思う。
牧師になってから数年経ち、ようやく仕事にも慣れた頃、わたしは妻とお見合い結婚をした。共通の知人の紹介で、両親同伴の彼女と食事をした。そのあとほんの数回、デートのまねごとをしただけで結婚した。時はすでに21世紀であったが、じつに古めかしい結婚の仕方であった。彼女は住み慣れた町から、親も友だちもいない見知らぬ土地、すなわちわたしの働く教会へと、いわば「お嫁入り」してきたのである。彼女にしてみれば人生一大決心、そうとうな覚悟をもって臨んだはずである。だが、いざやってきてみて、やはり孤独や牧師夫人としての重圧に耐えかねたのだろう。結婚早々、妻は布団から出てこなくなった。
布団にこもり続ける彼女を前に、どうしたらよいのか分からないわたしは、またしても癇癪を起した。わたしは布団のふくらみの前で、腹から大声を出した。
「起きろ! 布団から出ろ!」
彼女は追い込まれた兎のように布団から転がり出た。転げ出た彼女を見たとき、わたしは自分の持つ暴力におののいた。親や先生に対して癇癪を起していたのとはまったくちがう。彼女に与えたのは呆れではなく恐怖であった。それ以降、わたしは彼女に直接大声を上げることをやめた。だが、癇癪それ自体がおさまったわけではない。仕事で不愉快なことがあったり、彼女との言い争いに苛立ったりすると、わたしはしばしば鍋や食器を床にたたきつけた。そんな家庭で彼女が穏やかな暮らしをすることなど、とうていできようはずもなかった。
彼女の心身は不調をきたしてゆき、ある単身帰省の折、とうとうパニックの強い発作に襲われたのである。彼女は帰省先の精神科病院に、急遽入院の運びとなった。そこはわたしの勤務地から遠い病院であった。わたしは勤務地と病院とを行き来しながら、仕事を辞める決意をした。今でいう介護辞職である。のちにわたし自身が閉鎖病棟に入ることになったとき、主治医はわたしに言ったものだ。なぜ辞職を即断したのかと。ほかに方法があるかもしれないと、なぜ考えたり相談したりしなかったのかと。
退職金や教会関係者からのお見舞い金は、あっという間に底をついた。貧困への不安のなかで、わたしは郵便配達の仕事を始めた。アマゾンやゆうパックの時間指定配達に振り回される日々。配達時間が遅れたら「責任者を呼んで来い!」と怒鳴る客の前で土下座した。もちろん客は許してくれない。その場で課長代理に電話をしたら「あほか! 自分で処理してこい!」そんな日々が続くなかで、わたしは自分が叱られてばかりの、社会の役には立たない、人間のクズだと思うようになっていった。
あるとき、小康状態となった妻と、借家から電車で数駅の公園へと散策に出かけた。出かけるときにデパ地下で奮発した、ちょっと豪華な弁当を、わたしは手に提げていた。改札口で中年女性とすれちがいざま、わたしは彼女と少しぶつかった。なんでもない、ほんのちょっとした手荷物のぶつかりあいに過ぎなかった。だが、弁当の袋が揺れた瞬間、わたしは中年女性に叫んでいた。
「ころすぞおまえ!」
意識が一瞬、飛んだ。気がつくと中年女性はもういなかった。目まいがするほど頭から血が引いていた。そばにいた妻がわたしの袖を、ぎゅっとつかんだ。
「せっかくのお休みなのに、なんでそんなこと言うの」
あの議員の場合もおそらくそうだったのだと思うが、激昂して暴言を吐く際には、反射的に相手を選んでいる。わたしは卑劣にも、自分が勝てそうな相手を選んでキレていたわけである。子どもの頃からのことを想いだしても、それは当てはまる。自分が癇癪を起こせば言うことを聞いてくれそうな相手に対して、わたしは癇癪を起してきた。こうしたことの積み重ねのうえに、わたしの閉鎖病棟への入院もあったわけである。そこでの診察においても、主治医の言葉に神経を逆なでされるたび、わたしは激昂して大声を出した。彼はそんなわたしに動揺一つせず、静かにこう言ったのであった。
「あなたはそうやって、まわりの人たちに言うことをきかせてきたんですね。だだをこねれば要求を聞いてもらえたわけだ。そういう成功体験を、あなたは積み重ねてきてしまった」
わたしは精神科病院での入院生活において主治医との対話を重ね、退院後は牧師として復職し、現在に至っている。そのことは拙著『牧師、閉鎖病棟に入る。』にも書いた。だが、本の感想を受け取るたびに、わたしは読者への感謝の思いとともに、うしろめたさを覚える。成功秘話を誇っているような恥ずかしさを感じるのである。というのも、同じように職場でキレてしまい、そのまま失職した牧師が何人もいることを、わたしは知っているのだ。そう、あの議員のように。わたしだけが、ここにいていいのか? 本を出してもよかったのか?
わたしは運がよかった。そう、キレた相手がよかったのだ──読者におかれてはじつに不愉快な事実であるが、じっさいのところ、それがすべてである。わたしが大声を出した相手が70代の懐深い、大ベテランの副園長ではなかったとしたら。もしもわたしが若い保育教諭や保護者、あるいは園児に対して暴言を吐いていたとしたら、わたしも他の人々同様、パワーハラスメントや幼児虐待で書類送検されるか、民事訴訟を起こされていたはずである。そうなっていれば『牧師、閉鎖病棟に入る。』もへったくれもなかったであろう。
そう、わたしは運がよかったのだ。運がよかっただけなのだ。わたしなりに努力した、それは嘘ではない。だが、努力したから今があるとは、とても言えない。キレた相手次第では、わたしは努力以前の状態に陥っていたはずであった。副園長がわたしを赦してくれたということ。それがすべてなのであって、彼女がわたしを赦していなければ、その後からのわたしの今も存在していない。
ほんらい、わたしは赦されざる者である──身を焼かれるような焦燥を覚える。副園長に喉が枯れるほどの大声で吠えたあと、わたしは思ったのだ。
「副園長を殺してしまった」
殴ったのではなく、激昂して大声を出しただけである(もちろん、それも論外の行為ではあるが)。しかし、そのたった一度の罵声で、わたしは彼女と今まで培ってきた信頼関係のすべてを破壊してしまった──そのときはそう思い込んだ。相手との人間関係、信頼関係のすべてを一方的に破壊し尽くしたと。それはわたしにとって、殺人の手応えであった。だからなのであろう。わたしはとっさに死にたくなった。あのときほど具体的に死を企図したことはない。人を殺してしまった自分を自裁したいという、強い衝動に駆られたのである。そういうわたしを、妻は閉鎖病棟に入れてくれたのであった。
わたしは副園長から赦され、妻からも赦されて、今こうして生きている。また、駅でぶつかった女性からも──彼女にしてみればさぞかし不愉快であったはずだが──駅員を呼ばれたり、訴えられたりしなかったという意味において、わたしは赦されて今を生きている。
赦しとはなんだろうか。わたしは赦されてラッキーなので、今こうしてこんな文章を書いていられるのか。わたしと、スキャンダルを起こして業界から干されてしまう人々との、その紙一重の違いはなにか。考えれば考えるほど、その紙一重のなにかの重さに、わたしは背中を焼かれる思いがする。聖書にはこんな一言がある。
あなたを憎む者が飢えているならパンを食べさせ
渇いているなら水を飲ませよ。
こうしてあなたは彼の頭に炭火を積み
主はあなたに報いてくださる。(箴言25章21-22節 聖書協会共同訳)
頭に炭火を積まれるとはどういうことだろう。日本風の言い方をするなら、顔から火が出るほど恥ずかしいということになるだろうか。怒りに駆られたわたしが激昂する。それも一度だけではなく、繰り返し過ちを犯す。そのたびごとに相手の人々は、わたしを赦してきた。わたしにパンを食べさせ、水を飲ませてくれたのである。わたしはパンや水を、すなわちその赦しを、とうぜんのごとく受け取ってよいのか。
わたしはそれらの赦しを、顔から火が出るような恥ずかしさとともに受け取るのであり、その恥ずかしさの炭火は、じりじりと頭の上で燃え続けているのである。炭火の存在をふだんは忘れていても、記憶の風が吹きこめば熾り、わたしを焼くのである。
ペトロはイエスが逮捕された土壇場で、他人のフリをして逃げようとした。そのとき彼はイエスの、
「鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろう」
という予言を想いだし、泣き崩れた(マルコ14:72ほか)。彼は十字架に磔となったイエスを、自分だけ助かろうとしたという自責の念とともに想起したかもしれない。復活したイエス・キリストは、その件についてペトロになにも言わなかった。結果的にペトロはイエスから赦されたといえる。だが、黙って受け入れられ、赦されるということ。このことはペトロをしてラッキーと思わしめただろうか。彼はむしろ、イエスから呪われるよりも熱い炭火を、その頭に積まれたのではなかったか。
赦しの炭火はパウロにおいて、さらに熱かったと思われる。パウロは最初、キリスト教徒を迫害する側であった。彼自身が証言している。
「私はこの道を迫害し、男女を問わず縛り上げて牢に送り、殺すことさえしたのです」(使徒言行録22章4節 同訳)
パウロはキリスト教徒を殺した。しかし、彼はキリスト教徒になった。ところで、彼を受け入れる側の教会の人々は、そう簡単に彼を赦すことができただろうか。教会のなかには、他ならぬパウロによって家族を殺害された者さえいたかもしれない。殺人の被害者遺族のところに、殺人の容疑者が入ってくる。古代人はそういうことが平気だったとでもいうのだろうか。パウロは教会員たちからの刺すような視線にさらされたはずである。黙って彼を赦す、しかし決して彼のしたことを忘れない人々の、沈黙の眼差しに。
パウロはもともと、優れた師から教えを受け継いだ、生粋のファリサイ派ユダヤ教徒であることを誇りに思っていたことが想像される(使徒言行録22:3、フィリピの信徒への手紙3:4以下)。そういうプライドの高かった男が、おのれがまさに殺人者でしかなかったと思い知らされ、なおかつ相手の寛容によってのみ今自分が生かされていると自覚したとき。その被害者を前にして平然としていられただろうか。
パウロは回心体験をした。しかし、それと過去を水に流すことができたかどうかとはまったくの別問題である。パウロは自分が殺した命の重さを、焼けて炎を上げる炭として頭に積まれたのだ。その炎は、パウロが殉教するその日まで消えることはなかったであろう。神はパウロの入信に戸惑うキリスト教徒アナニアに告げる。
「私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを、彼に知らせよう」(使徒言行録9章16節 同訳)
ペトロもパウロも、殉教にいたるまで福音宣教を続けたという。彼らはキリストに赦された喜びがあったからこそ、衝き動かされるように伝道を続けたことであろう。だが一方で、その赦しの深さを繰り返し想えば想うほどに、自分が犯してしまった過ちの大きさに苦しみ続けたことだろう。彼らはその取り返しのつかない過ちを、なんとか取り返そうと足掻いたことであろう(悔い改めるμετανοέωには、「取り返しのつかないことを後悔する」という意味もある)。ペトロは赦し主キリストに、そしてパウロはキリストだけでなく自分を赦し受け入れた教会に、砂一粒ほどでも恩を返したいと思ったことであろう。その強い思いが、どんな逆境にも、ひいては死に至る危険を冒してでも、キリストを伝えたいという衝動につながったのだと思われる。
牧師の仕事をしていると、重い話を打ち明けてくださった方ご自身がわたしに気遣いをしてくださることがある。
「こんなしんどい話ばかり聞いておられるのですか。なぜ、そんないやな仕事ができるのですか」
だが、わたしはいやな仕事だとは思っていない。わたしは何人もの人々から赦されて、今ここにいる。ペトロやパウロがもはや直接、赦し主であるキリストや、自分が殺した人に償いをすることができなかったように、わたしも、わたしが激昂して暴言を吐いてしまった、しかもそれを赦し不問に付してくれた人々の多くに対して、いくら謝っても謝り足りない。ならばせめて他の人に、なにか喜びを伝えたい。直接キリスト教の話でなくてもよい。苦しんでいる人、泣いている人の話に、ただ黙って耳を傾けたい。わたしは赦しをとおして自分の頭に置かれた炭火が燃え尽きるまで、目の前の誰かとともに足掻き続けたいと思っている。
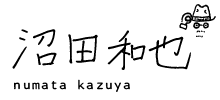 日本基督教団 牧師。1972年、兵庫県神戸市生まれ。高校を中退、引きこもる。その後、大検を経て受験浪人中、1995年、灘区にて阪神淡路大震災に遭遇。かろうじて入った大学も中退、再び引きこもるなどの紆余曲折を経た1998年、関西学院大学神学部に入学。2004年、同大学院神学研究科博士課程前期課程修了。そして伝道者の道へ。しかし2015年の初夏、職場でトラブルを起こし、精神科病院の閉鎖病棟に入院する。現在は東京都の小さな教会で再び牧師をしている。
日本基督教団 牧師。1972年、兵庫県神戸市生まれ。高校を中退、引きこもる。その後、大検を経て受験浪人中、1995年、灘区にて阪神淡路大震災に遭遇。かろうじて入った大学も中退、再び引きこもるなどの紆余曲折を経た1998年、関西学院大学神学部に入学。2004年、同大学院神学研究科博士課程前期課程修了。そして伝道者の道へ。しかし2015年の初夏、職場でトラブルを起こし、精神科病院の閉鎖病棟に入院する。現在は東京都の小さな教会で再び牧師をしている。
twitter