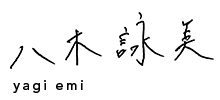『空芯手帳』『休館日の彼女たち』、ユニークな小説2作を発表し、国内外で注目を集める作家・八木詠美。本書は著者初のエッセイ連載。現実と空想が入り混じる、奇妙で自由な(隠れ)レジスタンス・エッセイ。
2月1日
この連載の編集担当の方と打ち合わせをする。もう少しで休館予定の山の上ホテルのコーヒーパーラーに行きませんか、とお誘いいただき行くものの満席。みなさん朝から並んでおられるそう。代わりにロイヤルホストに行く。パフェを食べながら打ち合わせ。
つやつやしたフルーツやクリームなども含め、パフェというのはカラフルというか悲喜こもごもという感じがする。ご褒美のパフェ、寄り道のパフェ、口実としてのパフェ、悲しみにくれるパフェ、なだめすかしのパフェ。その最初の一口へとスプーンをさし入れる人ばかり集めた写真集があったら間違いなく買う。
2月2日
会社の全社朝礼があり、各部署の状況や社長のご挨拶というものを聞く。
そういえば就職活動をしていた学生のころ、入社説明会などでもらったパンフレットにはよく冒頭に「社長の挨拶」があり、そのうちのいくつかが、時代の変化を「波」にたとえ、会社という「船」に一緒に乗ってくれる個性あふれる「船員」を募集するみたいな内容だった。船員に個性を求める前にテンプレみたいなこの文章をなんとかした方がいいのではと思いながら読んでいた。あの社長たちはまだ船に乗っているんだろうか。
2月3日
友人2人に会う。うち1人に会うのは久しぶりで、お互いの近況や共通の知り合いのこと、カルディのこの紅茶がおいしいとかなんかアメリカが報復攻撃したんでしょ怖いね、といったことのほかに芸能ニュースみたいなことを大いに話す。
子どものころは母がその友達とお茶をしながらこういうゴシップを話していると、久しぶりに会ったんだからもっと別のことを話せばいいのにと思っていたけれど、今なら少しわかる気がする。結婚している/していない、子どもがいる/いない、仕事をしている/していない、お金に余裕がある/ない、ニュースに目を通す時間がある/ない、など少し会っていない間にお互い驚くほど状況が変わり、ときにある話題が相手を傷つける可能性がある中、ゴシップはクッションのようなものなのだと思う。ある芸能人が整形をしたかどうか知らなくても恥ずかしがる必要がないし、本当に話したいことはきっと放っておいても話すだろうし。
2月4日
一日中家にいる。書き始めた小説を直す。
2月5日
昼前から雪が降る。猫がずっと窓から外を見ている。去年の10月に生まれた猫にとってはじめての雪。ほら、この白いのが雪ですよ、ともっとよく見えるように抱き上げると、指を噛まれた。
2月6日
いつからか本や映画の感想などで「救われた」という言葉をよく見かけるようになった気がする。物理的に「救われた」というより心理的に「救われた」というニュアンスで、少し前だったら「慰められた」という言葉が用いられていたように思う。何がちがうんだろう。慰められるだけではもう足りないのだろうか。ずっと気になっている。
2月7日
先週山の上ホテルのコーヒーパーラーに入れなかったことが悔しく、再び向かう。今度は夫と。いただいたプリンアラモードはどの一口もおいしくて儚くて、夢みたいな食べものだった。
お茶をした後は『哀れなるものたち』を観に行く。この映画を観るのは2回目。もともと好きな監督の作品であるということと、1回目はその映画を観た後に大好きな作家の方とお茶をする約束をしていたこともあり、ややおかしなテンションで観た。そのとき興奮しすぎたランティモス監督おなじみの変なダンスシーンや、美しく奇妙な衣装や美術をもう少し冷静に観られるかと思ったけれどそんなことはなく、やはり興奮しながら観た。
その前に2回観た映画は偶然にも『メアリーの総て』で、『フランケンシュタイン』の著者である作家・メアリー・シェリーの物語だった。今回はそのフランケンシュタインの怪物を想起させる女性、ベラ・バクスターが主人公。メアリーの父の姓「ゴドウィン」がベラに脳を移植した科学者の名前に引き継がれていたりして、たまらなくなってしまう。世界に対峙し、自由を手にしていく女性の物語が私はいつだって大好きだ。
2月8日
かつて住んでいた家の近くを通る。
その家で暮らし始めたばかりのころ、同じ通りのマンションのドアが開くと同時に、ある有名なアニメの大きなポスターが貼ってあるのが目に入った。その作品が好きな人たちがルームシェアをしているのかなと思っていた。
その後も通りかかるたびにそのマンションを目で追った。夜になると二階のベランダで煙草を吸っている人たちの姿をときどき見かけた。ルームシェアもきっと疲れるよねと思っていた。
それがエヴァンゲリオンの制作会社だと気づいたのは、NHKの「プロフェッショナル 仕事の流儀」で「庵野秀明スペシャル」の回を見たときのことだった。好きな人が集まっているどころじゃなかった。
2月9日
午後に編集者の方との打ち合わせがあるので、いつもは午前を小説の仕事、午後を会社の仕事としているのを逆にし、ついでに在宅勤務ではなく出社する。お昼過ぎに会社を出ると、空気に、ビルのガラスに、街路樹の葉の一枚一枚に、あらゆるものに光が満ちていて驚く。
小説を書くずっと前、会社の仕事が忙しかったころ、私は昼間というものがあることを忘れていた。毎朝足を引きずるようにして会社に向かい、一度そこに飲み込まれてようやくまばたきをしたときにはもう夜で、仕事を終えて裏口(表のドアは21時くらいで施錠される)から出るとあたりは等価に暗く、歩行者も車もほとんどいない交差点でまどろむような赤信号をぼんやりと眺めていた。
もしこれを読んでいる人の中にそんな方がいたら(こんな日記を読んでいるどころではないと思うのですが)どうか昼間のうちに外に出てみてください。あなたから不条理に時間を奪う人も、昼間の光まで消し去ることはできないから。
2月10日
一日中家にいる。小説を書き進める、はずが冒頭からいろいろなことが気になって直してしまい、あまり進まなかった。
2月11日
三連休らしいことをしようと夫と出かける。
途中でカフェに入る。大きな窓とそこから見える景色が美しいカフェで、本がたくさんあり、その中の一冊が飛行機の機内食に関する本だった。航空会社ごとの特色が出る機内食がおもしろい。次に旅に出るならどこがいいかな、などと考えていると「特別食」のパートで新婚旅行のときに提供される機内食を見つける。いろいろな食材でハートマークを作るというのはなんとなく想像の範囲内だったけど、茹でた2匹のエビを組み合わせて作られたハートマークを見て動揺する。このエビたちは初対面なんだろうか。たまたま調理時に隣にいたのだろうか。
捕獲され茹でられ、海の中で暮らしていたときはなんの縁もなかったエビとペアを組まされてハート形をつくり、見ず知らずの人間たちの新婚旅行を盛り上げるアイテムとして空まで飛び、一生を終えたエビたちのことを考えてなんだか落ち込む。
2月12日
電車の隣の席に座った人がパソコンで日記を書いていた。心中と思わしきものを現在進行形で書いている人が隣にいることに緊張する。あまり見ないようにと思うけれど、つい気になって横目で追ってしまう。
途中でふと、「他人の日記を盗み見て楽しいですか」と書かれたらどうしようと不安になる。冷や汗をかく。そうなったら終わりだ。破滅だ。自身を恥じながら立ち去るしかない。だからもう読むのをやめようと思うのに、一方ではその一文が現れることを心待ちにしている自分がいる。わたしは自分が狼狽するのを見たいのだろうか。日記を読みたい。いや、盗み見はよくない。けれど破滅への期待が止められない。中央線は走り続ける。葛藤もまた続く。
電車を降りるとふらふらし、ホームで少し休む。
2月13日
なかなか書き進められずにいる小説を冒頭から書き直し始める。とても楽しい。小説は冒頭を書くのが一番楽しいように思う。
ずっと冒頭だけ書き続けることができればと思うのだけど、それはもう冒頭ではないね。
2月14日
ソファで目をつむっていたら、猫が隣で眠っていた。投げ出した前脚が膝にのせられて、そこだけ温かくしめっぽい。
猫が家にやってきて約2か月。かわいい、大好き、とにかく一日でも長く元気に生きてほしい、と毎日強く思う。けれどそう思うほど猫が死んだときのことを想像してしまう。猫は生と死を詰め込んだ爆弾。