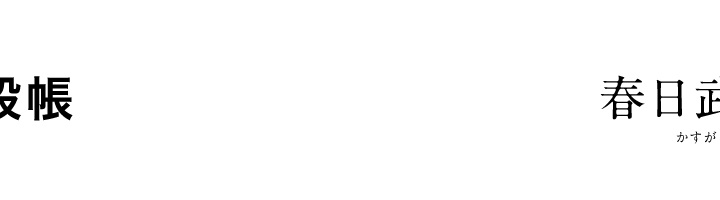精神科医、春日武彦さんによる、きわめて不謹慎な自殺をめぐる論考である。
自殺は私たちに特別な感情をいだかせる。もちろん、近親者が死を選んだならば、「なぜ、止められなかったのか」、深い後悔に苛まれることだろう。でも、どこかで、覗き見的な欲求があることを否定できない。
「自分のことが分からないのと、自殺に至る精神の動きがわからないのとは、ほぼ同じ文脈にある」というように、春日さんの筆は、自殺というものが抱える深い溝へと分け入っていく。自身の患者さんとの体験、さまざまな文学作品などを下敷きに、評論ともエッセイとも小説ともいえない独特の春日ワールドが展開していきます。
ミステリ小説ではさまざまな謎が提示される。しかし謎を支えるトリックだとか解決のプロセスよりも、謎そのものに「技あり!」と言いたくなるものがあって、たとえばE.D.ホックの短篇「長い墜落」ではビルの21階にあるオフィスのガラス窓を破って飛び降り自殺をした男が、三時間四十五分後にやっと地面に激突したという不可解な状況を扱っている。三時間四十五分をかけて墜落したという悪ふざけのような設定はまさに空前絶後で、これはもう名作と言うしかない(解決はちょっとショボいが、このくらい頓智の利いた謎なら腹も立たない)。
個別の謎とは別に、密室殺人とか衆人監視下の殺人、アリバイ崩し等のジャンル別の謎がある。そうした中で、どうにも気になって仕方がないジャンルがある。ひとつには誰かが失踪し十年以上の月日が経ち、その後当人が発見されるが彼(彼女)はいったい何を考えどんな人生を送ってきたか、そしてなぜ逃げようとしなかったのかという謎。もうひとつは、およそ自殺などしそうにもない状況にあった人物が、いきなり自殺をしてしまいその動機が皆目分からないといった謎である。たんにわたしの個人的な関心に過ぎないのだけれど、失踪系および自殺の動機系は、とにかく気になる。考えてみれば、どちらも心理的な興味が大きく絡んでいるようだ。
それにしても、後者の「自殺の理由が見当もつかない」といった謎を据えたミステリを、わたしはあまり多く知らない。たまにしか遭遇しないが、でも決して絶滅危惧種ではない。案出が難しいのだろう。自分でも「意外な理由」をときおり考えてみるが、残念なことに、ちっとも気の利いた(しかも説得力のある)理由を思い付かない。今回は自殺ミステリを紹介し、それを通してわたしたちが自殺の理由として考えがちな動機について思いを巡らせてみたい。なおトリックは容赦なく割ってしまうので、未読かつ読む予定のある人はタイトルが出てきた時点でストップしていただきたい。
自殺の動機系としては
模範的な作品「動機」
まず、「動機」、原題は No Motiveという作品。四百字詰めの原稿用紙で九十枚以上ある。あまりにも素っ気ないタイトルだが、おそらく自殺の動機系としては模範的作品で、それはミステリという範疇においてのみ成立する話で決して純文学にはなり得ない(だから劣っているというわけではないが)ご都合主義を含んでいるといった意味でもある。
作者は英国の女流作家ダフネ・デュ・モーリア(1907~1989)で、ヒッチコック映画の原作となった短篇「鳥」と、長篇『レベッカ』あたりで知られている。「動機」は、創元推理文庫『鳥―-デュ・モーリア傑作集』(務台夏子訳2000)に収録されている。
自殺したのは妊娠中の美しい人妻メアリー・フェアレーンである。夫は会社の重役で金持ちのサー・ジョン。金持ちだから豪邸に住み、執事や使用人がいる。結婚三年目で、まだ子どもはいない、腹の中の子を除いては。夫婦仲は上手くいっていたし、悩みがありそうになかった。夫は高潔な人物で、愛人がいたとかそうしたトラブルも一切ない。周囲からは理想的なカップルと見られていた。にもかかわらず、あるウィークデイの午前十一時半ごろ、メアリーは銃器室へ赴いて夫のリボルバーを使っていきなり自殺してしまった。書置きなどはない。偽装された他殺でもない。
自殺当日だって、彼女はにこやかで幸せそうだった。そうなると、よほどショッキングな出来事ないしは知らせが引き金になったとしか考えられないではないか。でも電話や電報は受けていないし、手紙も受け取っていない。午前十一時に庭用家具の巡回セールスマンがやって来てカタログを見せ、メアリーはベンチを購入している。セールスマンが何か重要なことを伝えたり脅したりした気配もない。セールスマンが帰った直後の彼女の様子を執事が目にしているが、動揺した様子は一切なかった。
この自殺の動機は、推理のしようがない。ブラックという敏腕な探偵が夫の依頼を受けて調査を進めていくのを読者は見守るしかない。
話はいささか因縁話の様相を帯びてくる。メアリーは幼いときに両親に先立たれ、独身の伯母に育てられてきた。そのような出自であると夫は思っていた。しかしそれは嘘であった、ただし虚偽であることをメアリーは知らなかった。彼女の父親はハンプシャーの田舎町にある教会の牧師であった。母親は早いうちに亡くなり、父親に育てられた。聖職者である父は厳格かつ偏狭な、およそ優しさとは無縁の人物であったらしい。メアリーは性格の曲がった人間には育たなかったが、俗世間の知識にはいささか疎い娘になった。
十四歳のとき。彼女は寄宿舎のある学校で学び、夏休みには牧師館へ帰省していた。その時期には、ハンプシャーではホップが広く栽培されていた関係で、ロンドンから柄の悪い連中がホップ摘みに来るのが慣わしになっていた。庭師の娘と一緒に、あまりにも世間知らずだったこともあり、メアリーはホップ摘みの人たちと警戒心を抱くこともなく打ち解ける(もし父がそのことを知ったら激怒した筈だ)。彼らのパーティーに参加した晩、メアリーは生まれて初めてビールを飲み、酔って意識を失ってしまう。
意識を失っているあいだに、彼女は陵辱されてしまったのだった。初心(うぶ)なメアリー(その頃の名はメアリー・ワーナー)はそのことに気付かない。やがて寄宿舎に戻り、寮母によって妊娠していることが発見される。だがメアリーにはセックスの記憶なんかない。
ことの次第に気づき、仰天した寮母に叱責されると、メアリー・ワーナーはとまどった。彼女は寮母の頭がおかしくなったもの思ったらしい。「どういうことですか?」彼女は言った。「わたしはまだ大人じゃないし、結婚もしてないでしょう? 聖母のマリア様と同じだって言うんですか?」
彼女は生命の真理にまったく気づいていなかったのだ。
当時の道徳観に照らして、メアリーは放校される。父はコーンウォールの私立病院へ彼女を連れて行き、そこで出産させる。生まれた子どもは男の子だった。見事な赤毛だったので、病院のスタッフは「この坊やときたら、まさしくチビのにんじん坊主ですね」と言い、以後、スタッフもメアリーも「にんじん」と呼ぶようになった。
一ヵ月後、既に赤ん坊は孤児院へ移される手筈が整っていた。牧師である父の意向だった。メアリーには、子どもは急死したと告げられ、「にんじん」は連れて行かれてしまった。彼女はわが子が死んだと聞かされ激しいショックを受け、気絶する。意識を取り戻したときには、記憶は失われていた。トラウマによる逆行性健忘というわけである。そのままメアリーは、もと家庭教師の独身女性に委ねられる。父が金を払って段取りを組んだのであり、彼はそうやって「ふしだら」な娘と永遠に縁を切った。記憶を失ったメアリーは、伯母と自称する女性の言葉をすべて信じて育ち、やがてサー・ジョンと三十一歳で結婚するに至った。メアリーに暗い過去はあったものの、彼女自身がそんなことをまったく覚えていなかったのである。
さて自殺の当日。結末を明かしてしまえば、まさに数奇な運命というやつである。午前十一時にやってきた若い巡回セールスマンこそが、生まれて間もなく引き離され孤児院へ送られてしまったメアリーの息子だったのである。もちろん彼女も息子もそんなことに気がつくわけがない。だから若者に成長した赤毛の息子と出会っても、動揺なんかする理由もない。メアリーはショックなんか受けなかった。
彼女を奈落のそこに突き落としたのは、セールスマンが帰ったあとで執事が発した何気ない言葉であった。探偵ブラックと執事との会話を引用する。
「きみはなんて言ったんだ?」
「奥様はユーモアがおありなので、冗談めかして、あのセールスマンがもう一度来たら、あの髪の色ですぐわかるだろうと言ったのです。
「『あの男ときたら、まさしくチビのにんじん坊主ですね』そうわたしは申しました。そのあとはすぐにドアを閉めて、食料貯蔵庫にもどったのです」
そう、「チビのにんじん坊主」というのがまさにキーワードとなり、突如メアリーの忌まわしい記憶を立ち上げてしまったのである。妊娠中の彼女はすべてを思い出し、あのセールスマンが我が息子であったことにも思い至る。この時点で彼女は激しい衝撃を受け、発作的に自殺してしまったのだった。
こうして筋を書き出してみるとずいぶんメロドラマっぽいし、記憶喪失を都合よく使い過ぎている印象は否めない。けれども運命の悪戯といった文脈ではそれなりに説得力がある。「チビのにんじん坊主」がキーワードとなって運命の歯車が回るあたりも、つい座布団一枚! と言いたくなる。もしもこの作品を不自然であると容認出来ないようであったら、その人はおそらく世間に流通している多くのミステリを楽しめないと思う。まあそれはそれとして、「血の因縁」は殺人の動機にも自殺の動機にも使えるすこぶる便利な事案であるとは言えるだろう。
自殺ミステリ分野の
金字塔とも言える作品『天使の屍』
次は貫井徳郎の長篇『天使の屍』(角川文庫2000)である。こちらのほうがリアリティーがあり、いかにも現代的に感じられる。最初に自殺したのは、中学二年生の優等生、優馬だった。テレビで苛めによる自殺を報じていたとき、彼は反発した態度を親に示した。父とのやりとりはこんな具合である。最初の台詞が優馬だ。
「死ぬほどの勇気があるなら、正面からいじめに立ち向かえばいいじゃないかってことだよ。死ぬ気になれば、なんだってできるはずでしょ」
「……まあ、そうだな」
「そんなつまんないことなんかで死んで、どうするんだよ」
父親のほうが、たじたじである。息子のほうが、身も蓋もない正論を述べている。
にもかかわらず、優馬は三十分後にコンビニへ出かけたまま、近くのマンションの屋上から飛び降りて死んでしまう。さらに、連鎖的に彼のクラスメイトが次々に自殺してしまうのである。だが彼らを自殺へ駆り立てた原因が、さっぱり分からない。優馬の父が、息子を失った無念のあまりに自ら調査を進めることで物語は展開していく。
自殺の動機は二つある。ひとつは、中学二年生男子における欲望と恥の問題。もうひとつは、中学生ならではの思考法や価値観に基づいた苦しみである。それら双方の「併せ技」として、連鎖自殺が生じることになった。それ以上は、さすがに長篇なのでネタを割るのは差し控えたい。ただし、自殺の動機として「誰にも言うわけにはいかない羞恥心の問題」および「その人にだけ通用する価値観や思考法」は大いに説得力を持つ。じっくりと書き込まないと突飛に映ってしまいかねないわけで、それを達成しただけでも自殺ミステリ分野の金字塔と評価したい。
自殺動機ものとしては
逸品といえる「日曜の朝の死体」
三つ目は、アーサー・ポージスの短篇「日曜の朝の死体」で、これはミステリマガジン1985年3月号(347号)に沢川進の訳で掲載されたままアンソロジー等には一切収録されていない。アーサー・ポージス(1915~2006)はシカゴ生まれでもと数学教師、短篇と長篇を合わせて三百編近くを残しており、しかし我が国では『八一三号車室にて』(論創海外ミステリ2008)という短篇集が出ているだけで、そこにも「日曜の朝の死体」は収められていない。ネットを覗いても、言及しているブログはない。
けれどもこの作品の異様さは、忘れ難い。無視されてしまう理由が分からない。自殺の動機ものとしては逸品、とわたしは考えるのである。
自ら二十二口径の拳銃で命を絶ったのは、三十七歳になるビルだった。プリンストン大卒、経済的に豊かな両親に愛されて育ち、明るくて性格の良い人物となった。結婚十二年目だが夫婦仲はすこぶる良く、子どもも二人いる。銀行の頭取で、海岸沿いの豪邸に住んでいた。誰からも褒められる好人物であった。もちろん悩みや困りごともない。にもかかわらず、彼は自殺をした。
或る日曜の朝、ビルはソファでくつろいでいた。妻は、隣家へ料理カードを届けてあげるために家を出た。夫は陽気に妻を送り出した。それから二十分もしないうちに、彼は銃口を自分の口に突っ込んで引き金を引いたのだった。妻はおろか、誰にもビルがそんなことをした理由は分からなかった。
ダフネ・デュ・モーリアの物語ではブラックという探偵が真相解明に活躍した。このケースでは、クレメントと名乗る保険会社の調査員が理由を探る。もちろんいくら周囲を調べても、謎は深まるばかりである。
突破口はラジオであった。妻は隣の家に行く際に、ラジオを点けっぱなしにしていた。ビルが死体となった部屋にはニュースショーがラジオから流れていたのである。もしかすると、そのニュース番組で放送された内容がビルを死に追いやったのではないのか。そう推理したクレメントは放送内容を調査する。すると〈ヒューマン・アングル〉と題する、人間的興味をそそる話題を取り上げるコーナーで、気になる話を放送していたことを知る。
どんな放送であったのだろう。
……今朝は、予定していた内容を変更して、カリフォルニア州ゴールド・クリークの、ほとんどゴーストタウン化している小さな町、ファー・ウェストからの特だねをお送りします。
数日前、兵隊ごっこをしていた子供たちが木製の剣で丈の高い雑草を切り倒していたとき、古い自動車の残骸を発見しました。しばらくあとでその自動車に近づくと、その子供たちは車の中に人間の骸骨を発見して恐怖におののきました。
二十四年前、サム・コリッツという名のセールスマンが東部の顧客たちから注文を取り、急いで家に向かっていました――サンフランシスコの我が家へと向かっていたのです。かれは非常に急いでいました。その理由はまもなくお話いたします。それは哀れを催すようなもので、この悲しい物語の引き金となったものです。
サム・コリッツは急いでいたのですが、ゴールド・クリークの近くでハイウェーが事故のために封鎖されていました。一台の大型石油トラックのトレーラーがはずれて折れてしまったのです。サム・コリッツは待っているわけにはいかずにやきもきしていたのですが、ほとんど使われない脇道がずっと北でハイウェーにつうじているということを知りました。かれはその道に入り込み、ほとんど四分の一世紀のあいだ姿を消してしまったのです。
その日が何日だったか、みなさんにおわかりになりますか? 自動車の中の書類や領収書で、警察にはわかりました。一九四一年十二月六日。そうです、土曜日、真珠湾攻撃の前日です。
雑草に覆い隠された自動車の残骸と、その中の白骨。それは太平洋戦争開戦の前日から二十四年間、消息を絶っていたセールスマンと彼の車だった。何だか奇譚のような様相を呈し始めている。ラジオ放送の内容をさらに紹介する。
そして、どういうわけで、中に人間の乗った自動車が、それほどの年月のあいだ消えていたのでしょう? その理由は、途方もない偶然がいくつも重なったことにあります。道路封鎖が解除されたあとでは、脇道を使う自動車はほとんどありませんでした。雪が早くから降りはじめ、それもかなりの豪雪だったのです。戦争のために、とくに用事のない自動車はハイウェーから閉め出され、雪に埋もれた自動車の近くのただ一つの町、ゴールド・クリークのかなりの人口は軍需工場に駆り出されました。
それから、土砂くずれがあり、最後にオオアザミ――これはおそろしい棘を持った始末の悪い雑草ですが――それが広範囲に生い茂り、サム・コリッツの墓へ近づくことを妨害していたわけです。
それから、もう一つ不可解な点があります。なぜ、錆びた鉄線の切れはしや縒り合わせた部分が朽ち果てた自動車の内部に落ちていたのでしょうか? このセールスマン、この四十歳の不運な男は、脇道に入ったあと、余りにも睡眠不足であったために車を路上からおろして仮眠をとっていたところを強盗に襲われ、鉄線で縛りあげられ――死ぬまで放置されたのでしょうか?
まさか当時十三歳のビルがその強盗であったとも思えない。となると、車の中の白骨とビルとはどう関連してくるのだろうか。ちなみにサム・コリッツが非常に急いでいたのは、九歳の娘リンダが危篤という電報を受け取ったからだった。結局翌年の二月にリンダは亡くなり、ミセス・コリッツの行方は現在では分からずじまいだという。
調査員のクレメントは、ビルが十三歳だった頃の遊び友だちを捜し出す。ラリー・キースという公認会計士で、「わたしたちの少年時代はすばらしいものでした。つぎからつぎへとばかなことをしましたが、だれも傷つけたことはありません。おもしろい話がいくらでもありますよ」と彼は屈託なく語る。その「ばかなこと」こそが恐ろしい行為であったにもかかわらず。キースの(愉快な)思い出話を引用しよう。
「そう、あれは土曜日で、学校は午後から休みでした。あそこは学校から二マイルばかりはなれていたと思います。それはそれとして、わたしたちは鉄線の大きな輪を見つけたんですよ。軍需工場から出てきたトラックから落ちたものにちがいありません――英国向けの物資だったのでしょう。上質の鋼鉄線で、ピアノ線を太くしたようなものでした。それに、かなり量がありましたね。
ほかの子供たちだったら、小遣い銭ほしさに売ってしまったところでしょうが、ご存知のとおり、ビルは金持ちでしたし、わたしの両親も貧乏というわけではありませんでした。で、わたしたちはその鉄線の輪を持ってあてもなく歩きまわっていました。あの当時、あのあたりはすごい荒れ地だったんです。
そのうちに、わたしたちはあのポンコツ車を見つけたんです。古い未舗装道路からかなりはずれた、ユーカリ樹の木立ちの蔭に駐めてありました。そこで、わたしたちはぜんぜん苦労もせずに近づいて中をのぞいたわけです。バックシートで一人の男が眠っていました。なにかのセールスマンのようでした。サンプルケースが何個かありましたからね。その男は肥って脂ぎっていて、無精ひげをのばしていました。それに、すごい鼾をかいていました。死んだように眠りこけていたんです」
さながら映画の「スタンド・バイ・ミー」みたいな調子で、鉄線の輪を持った二人の少年は、中でセールスマンが爆睡している自動車を見つけたわけである。
「とにかく、そのときにビルがあることを思いついたんです。鉄線がたくさんありましたからね。かれは音を立てないようにしてその自動車のドアが開かないように鉄線を巻きつけはじめたんです――本当ですよ! ビルは鉄線をぐるぐると縦横に巻きつけ、あいだをくぐらせ、結び目を作り、輪にして締めつけ、からみ合わせ、最後には漁網のようにしてっしまったんです。ビルの仕事の出来映えを見せてあげたかったですね! 蛇が抜けだす隙間もなかったんですから」
さしたる理由もなく、せいぜい悪戯心で、十三歳の少年が妙に手の込んだことをするというのはいかにもありそうな話である。成り行きからこのような馬鹿げたことをしてしまうのも分からないでもない。もしかすると戦争勃発の予感みたいなものが、彼らを無意識のうちに残酷な気持ちへ駆り立てていたのかもしれない。
「ビルは、それではあまり簡単で、せっかく苦労してやった甲斐がない、と言いました(引用者注・ドアが開かなくても、中の男は窓ガラスを巻きおろして叫びさえすればすぐに助けを呼べるだろうという彼らの予想を、それではあまり簡単だと述べている)。で、かれは小枝やなにかを集めてきて、全部の窓の下の部分の隙間に詰め込んだんです――楔をかったわけですよ。ビルが仕事を終わらせたとき、あのポンコツ車はすごい見物(みもの)でしたよ、ほんとうです。
それからビルが言ったんです。いくらなんでもこれはあまりひどすぎるかもしれない。交通量はあまりないし、この男は何時間も立ち往生するかもしれない――一晩中ここにいることになるかもしれない――そして余分な出費を強いられるかもしれない、とね。そこで、その肥ったセールスマンに埋め合わせをするために、ビルは一枚の二十ドル紙幣をワイパーにはさんだんです。かれはそんな人間だったんです。ビルはいたずら好きで想像力が豊かでしたが、ぜったい他人を傷つけるつもりはなかったんです。それはわかっていただけるでしょう。かれは、いたずらをされても、その男が二十ドルを儲けたことでよろこぶだろう、と考えたんです。あの当時では相当な金額でしたからね」
これが若き日のビルの武勇伝のひとつだったわけである。自動車は、袋状のネットで何重にも包まれた石鹼のようなありさまだったのだろうか。緻密に、がちがちに編み上げられた鉄線の繭の中で、小枝や木の切れ端を隙間に詰め込まれた窓はガラスを下げることも出来ない。エンジンを掛けても自動車は動くことが叶わなかっただろう。
たとえ窓ガラスを割っても、誰も通らない見捨てられた場所である。叫び声を上げても意味がない。ましてや翌日には戦争が始まり、ガソリンが配給制となり、こんな辺鄙な場所を通る者はいなくなる。そして豪雪。餓死する前にセールスマンは凍死したのではないか。娘のリンダよりも先に死んでしまった筈だ。土砂崩れがますます人を現場から遠ざける。やがて車はオオアザミに覆われカモフラージュされてしまう。こうして二十四年後には、朽ちた車の中で男はひっそりと白骨に成り果てていた。
ビルも、友人のラリー・キースも、自分たちの悪戯はすっかり忘れていた。ところが四半世紀が経ってから、ビルだけが遠い過去の悪戯とその残忍な顛末をいきなり知ることになる。しかもそれを日曜の朝のラジオ・ショーで。
カルビン教徒的な良心の持ち主である彼は、自責感に苦しんだだろう。いや、もっと瞬間的な、ショックに近い感情に囚われただろう。朽ち果てた自動車の中の白骨という鮮やかでグロテスクなイメージも、激しい衝撃をもたらしたに違いない。おまけにセールスマンが娘の危篤に間に合うように急いでいたといったメロドラマ的な事情も、心を突き上げただろう。
発作的に銃口をくわえて引き金を引いても不思議ではあるまい。調査員のクレメントは、あえてラリーにはラジオ・ショーで放送された内容は告げなかった。たとえ教えられても、脳天気なラリーは自殺にまでは踏み切らなかったのではないか。
という次第で、アーサー・ポージスの「日曜の朝の死体」は原因不明の自殺に対する「特殊解」として大変にわたしを感心させてくれたのだった。もっとも人によっては、話に無理があるとか、いや自己正当化は図ってもそんなことで自殺なんかはしないものだよと主張するかもしれない。
◆ ◆
以上、デュ・モーリア「動機」、貫井徳郎『天使の屍』、アーサー・ポージス「日曜の朝の死体」の三作を紹介したわけだが、さて自殺の理由の共通項は何だろうか。
「動機」は過去の過ちと記憶喪失とを上手く組み合わせている。『天使の屍』は「欲望と恥」および「中学生ならではの価値観や思考法」とを上手く組み合わせている。「日曜の朝の死体」は少年時代の悪戯とラジオ・ショーがもたらした「不意打ち」とを上手く組み合わせている。これは言い換えれば、すくなくともフィクションにおいては、人を自殺へ追い込むには複数の要素が必要ということだろうか。たんなるひとつの事実だけでは、どうしても説得力が弱い。あるいはサプライズがない。そこに「神による残酷な演出」が加えられてこそ、自殺という行為は成立するのではないのか。
とはいうものの、メインの心情は、詰まるところ「もう、取り返しがつかない!」といった後悔と焦燥と混乱の混ざった気分なのではないかと思う。興味深いことに、うつ病で自殺を図った人たちから話を聴くと、彼らは最終的に「もう、取り返しがつかない!」という精神状態に陥るようなのだ。取り返しがつかない、ということは過去に大きな過ちを犯している証左だろう(実際には、わたしはサラリーマンにはなるべきでなかったとか、家族を持つ資格のある人間ではなかった、等々病的心理に導かれた痛恨が多い)。そういった形で過去を否定し、今後も挽回の余地はないと自ら未来の可能性を閉ざしている。さらに今現在は、罪深い人間として自分を断罪している。こうなっては、もはや世の中から姿を消すしか立つ瀬はない、という結論になってしまう。憤怒の果てとか、虚無感とか、幻覚妄想とか、自殺へ至るプロセスはいろいろあってそれについては追々述べていくつもりだが、それはそれとして自殺の直前において、「もう、取り返しがつかない!」は、かなり普遍的な心情だとわたしは考えるのである。
動機が見えない自殺者の物語を書こうと思ったら、いきなり「死なずにはいられない事情」「しかもその事情は、他人には気付きようがない」を案出しようとしても難しい。少なくとも読者を驚かせるような案は難しい。むしろ、登場人物が「もう、取り返しがつかない!」と突如奈落の底に突き落とされるようなシチュエーションを考え、そこから遡ってプロットを整えていくほうがアイディアは湧きやすいのではないだろうか。その後に、運命を司る神による残酷な演出について思考を巡らせてみればどうか。まあそれでも難易度は高いかもしれないが。
前回の井上靖「ある自殺未遂」の主人公には、決定的な自殺の理由はなかった。けれども、さまざまな落胆や失望の積み重ねが、些細なきっかけで「こんなろくでもない世の中で、オレの人生はもう、取り返しがつかないことになってしまった!」と精神の決壊に至ってしまったのだろう。とはいうものの第一回で書いた隆太のケースでは、彼はやはり「もう、取り返しがつかない!」といった心情に至ったのだろうか。あるいはもっと別な発想に心を支配されていたのか。経緯はいまひとつ判然としない。いや、わたしが真相を知りたくないと目を逸らしているような気もしないではないのだけれど。
(第三回・了)
 1951年京都生まれ。日本医科大学卒業。医学博士。産婦人科医を経て精神科医に。都立中部総合精神保健福祉センター、都立松沢病院部長、都立墨東病院精神科部長などを経て、現在も臨床に携わる。著書に『無意味なものと不気味なもの』(文藝春秋)、『幸福論』(講談社現代新書)、『精神科医は腹の底で何を考えているか』(幻冬舎新書)、『臨床の詩学』(医学書院)、『老いへの不安 歳を取りそこねる人たち』(朝日新聞出版)、『鬱屈精神科医、占いにすがる』(太田出版)等多数。
1951年京都生まれ。日本医科大学卒業。医学博士。産婦人科医を経て精神科医に。都立中部総合精神保健福祉センター、都立松沢病院部長、都立墨東病院精神科部長などを経て、現在も臨床に携わる。著書に『無意味なものと不気味なもの』(文藝春秋)、『幸福論』(講談社現代新書)、『精神科医は腹の底で何を考えているか』(幻冬舎新書)、『臨床の詩学』(医学書院)、『老いへの不安 歳を取りそこねる人たち』(朝日新聞出版)、『鬱屈精神科医、占いにすがる』(太田出版)等多数。