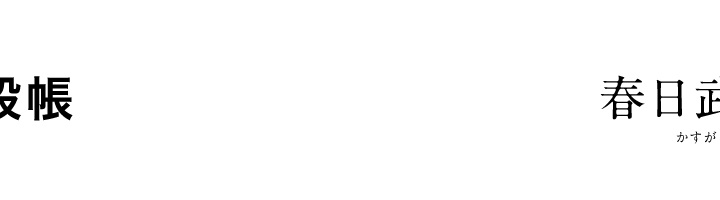精神科医、春日武彦さんによる、きわめて不謹慎な自殺をめぐる論考である。
自殺は私たちに特別な感情をいだかせる。もちろん、近親者が死を選んだならば、「なぜ、止められなかったのか」、深い後悔に苛まれることだろう。でも、どこかで、覗き見的な欲求があることを否定できない。
「自分のことが分からないのと、自殺に至る精神の動きがわからないのとは、ほぼ同じ文脈にある」というように、春日さんの筆は、自殺というものが抱える深い溝へと分け入っていく。自身の患者さんとの体験、さまざまな文学作品などを下敷きに、評論ともエッセイとも小説ともいえない独特の春日ワールドが展開していきます。
自殺に前兆はあるのだろうか。妙にふさぎ込むとか、思い詰めたように部屋を片付けはじめるとか、大切にしていた品物を親しい人たちに突然分け与えたがるとか、いきなり思い出の場所を訪れてみるとか、あとから考えてみれば納得のいくような様子が出現しがちなのだろうか。
精神科医として外来や病棟で直接担当してきた患者のうち、自殺を遂げた人は二十名を越える。そうした人々のうち、記憶をいくら探ってみても、いわゆる前兆らしきものを示した者はいない。不意に見知らぬ世界へ旅立ってしまった。わたしは死を知らされて困惑するばかりであった。
だが一人だけ、あれは(もしかしたら)自殺のサインだったのだろうかと思わせる状態を見せた青年がいた。
「最高なんですよ。ご存知ですか」
名を隆太としておく。年齢は二十代後半、もう三十に近かった。小太りで身長は165センチくらい。短めの髪は癖毛で、色白の顔には黒子が四つある。目も口も小さい。腹が出て重心が前に傾きがちで、それとバランスを取るためなのかいつも背を反らし気味にしており、その姿勢で顎を引いて相手を見る。すると、どことなく「上から目線」めいた尊大な態度に映り、しかも体型とは裏腹の甲高い声が微妙に人を苛つかせるのだった。
丈が少々足りないジーパンと深い緑色のセーターが、お気に入りの服装であった。
隆太は母との二人暮らしである。母親は肝炎を患って働きに出られず、生活保護を受けていた。隆太も働いていない。生まれてから一円も稼いだことはなかった。中学を出てからずっと引きこもりである。中学時代も不登校であった。
母の鈴江は、オルゴールの仕掛けられた白い箱に「花の絵」を描く内職をときどき請け負うと語っていた。
「今は体調が悪いので花を描く仕事はほとんど出来ませんけど、肝臓が良くなりましたら月に百万円近くは稼げる筈ですの」
いささか信じ難かったが、わたしは感心した表情を浮かべておいたのだった。
もう十年以上、隆太は引きこもっている勘定になる。自室に籠城しているわけではなく、たまに買い物に出たりすることもある。散髪にも行く。パチンコやゲームセンターには行かず、家でだらだら過ごしているだけであった(当時はまだ、ネットは普及していなかった)。将来の目標はなく、人生にことさら危機感を抱いている気配はない。母が病気で死ぬような場面すら想定していない。友人はゼロだった。もちろん童貞である(わたしが直接問い質したら、恥ずかしそうに頷いた)。
いわゆる母子密着なのだ。鈴江は息子によく似た小太りで、いつも毛糸の帽子を被っている。さすがに息子のセーターとお揃いの深緑色ではなく、紫と黄色の幾何学模様の帽子であった。赤いフレームの眼鏡を掛け、右の「つる」の途中はセロテープをぐるぐる巻いて補修してあった。レンズは汚れて曇り、肌の色は不健康に黒ずんでいる。
「夫は、熱帯魚を輸入する会社に勤めていました。優秀だったんですけど、酒癖が悪くて。おまけに若い女の事務員にそそのかされて会社の金を使い込みました。告訴されて実刑判決を受け、その時点で離婚しました。息子に悪い影響があるといけませんから。
ええ、もちろん隆太は父が犯罪に手を染めたことは知っています。それを反面教師として育ってくれたので安心はしていますけど」
父の活動的な部分も反転させて、引きこもりになってしまったということだろうか。
隆太は酒を飲まない。煙草も吸わない。珈琲も飲まず、本人いわく「僕は紅茶にうるさいんです」。しかし実際にはコンビニで買ったティーバッグを愛飲しているだけである。お気に入りのティーカップがあり、必ずそれを使う。しかも紅茶と一緒に森永チョイス・ビスケットを食べるのが至福の時と断言する。上体をふんぞり返らせながら、隆太はそれを得意げに語る。「最高なんですよ。ご存知ですか」。何だか彼の言い方には、癇に障るところがあるのだった。
「被害者は僕なんです!」
なぜ隆太は入院に至ったのか。人畜無害の態で母と静かに暮らし、あまつさえ優雅に紅茶を嗜んでいた筈なのに。
いわゆる反抗期を示したことはなかったという。素直で優しい子というのが母の評価である。優し過ぎて世間に適応しきれなくなってしまった、と。
家庭内暴力もなかったし、「こんな家、出て行ってやる!」と啖呵を切ることもなかった。性欲が鬱積して苛立つ、なんてこともなかったらしい(母・鈴江の視点によれば)。とはいうものの、彼は白い水着に強い執着があり、白い水着姿のアイドルたちのグラビア――その切り抜きを熱心に集めていた。アイドルと呼ばれるだけの可愛ささえあれば誰でも構わなかった、白い水着ならば。それが隆太のマスターベーションの材料になっていた。わたしはそういったことを結構あけすけに尋ね、渋々ながら彼は診察室で声をひそめて教えてくれたのだった。
白い水着には何らかの象徴的意味合いがあるのか、それはわたしにも分からない。もちろん「こじつけ」はいくらでも出来るが、そんなことをしても不毛なだけだろう。
十一月十二日の夕方、隆太は一人でコンビニへ行った。家を出た際の様子は普段と変わりがなかった。ジャンクフードと雑誌を買い、レジに立った。
この時点で何かが隆太の感情を刺激したらしい。彼は唐突に激怒した。店員の女性(アルバイトの美大生)が隆太を小馬鹿にし、失礼な態度を取ったということだがその詳細ははっきりせずに終わってしまった(語ろうとするたびに隆太は自制出来なくなってしまうからだった)。彼女の普段の勤務態度からは、そんな無礼な振る舞いをするような人物ではないと誰もが口を揃えて証言する。だが、少なくとも隆太はアルバイトの彼女を許せないと思った。絶対に。
大声で喚き散らし、店長が割って入ろうとした。でも隆太の怒りは収まらない。彼の甲高い声が店内に響き渡る。客たちが好奇心半分にレジを遠巻きにする。隆太は意に介しない。それどころか握りしめていた釣り銭を、彼女へ向かって節分の豆撒きのように投げつけた。その時点で店長は電話を使って警察を呼んだ。目と鼻の先にある交番から巡査が臨場し、彼を店から引きずり出した。交番で折り畳みのスチール椅子に座らされた時にもなお、隆太は「被害者は僕なんです!」と興奮していた。
母が呼ばれ、コンビニは以後出入り禁止ということで彼は家に帰された。鈴江が姿を見せてからは、隆太は一言も口を利かなくなってしまった。夕食も食べず、そのまま自室の布団に潜り込んでしまった。鈴江もその日は体調がいまひとつだったので、あえて息子にあれこれ言うことはしなかった。
夜中になってから、隆太はむっくりと起き上がった。冷たい炭酸飲料を飲もうと暗い台所へ移動した。冷蔵庫を開け、すると中から溢れ出る青白い光に腕が染まる。それを目にした途端、コンビニの女店員の姿――いや、もっと正確に言うなら彼女の腕が、ありありと脳裏に浮かんだ。薄く静脈の透けて見える彼女の腕が。
それがスイッチの役割を果たしたかのように、隆太は再び激しい興奮状態へ突入した。絶叫が始まる。彼と母親は公団住宅の三階に住んでいたが、なぜか窓を大きく開けてそこから次々に食器や時計や缶や瓶を外へ投げ落とし始めた。さながら気球の高度が下がってきたことに慌てて、乗員が手当たり次第に物を投げ捨てて浮上を図ろうとしているかのように。
ちょうど窓の下を老人が通り掛かった。深夜なのに、犬を散歩させていた。その老人の肩を、酢を詰めた瓶が直撃した。老人は崩れるように倒れ、いっぽう薄情な犬は主人の危機など意に介すことなく、これ幸いとばかりに鎖を地面に引きずったまま一目散に闇の向こうへ走り去った。割れた瓶が地面に転がり、夜気に酢の刺激臭が漂う。騒ぎに気付いて窓から顔を出した住民が何名もいて、当然のことながら誰かが警察へ通報した。結果として、またしても交番から巡査が自転車で駆けつけた。
既に、老人を介抱してくれている親切な人がいた。ご丁寧に救急車まで呼んでくれていたので怪我人はそちらへ任せることとし、巡査は公団住宅の階段を一気に駆け上がった。老人の傍らから頭上を見上げたときに、三階の窓が大きく開け放たれているのが分かり、不穏な人影も目に入ったからである。三階に達した巡査が右に曲がると、鈴江が寝間着姿のままドアの外に閉め出され、共用の廊下でおろおろしている。息子の行動を止めようとしたら、家から追い出されてしまったという。
「警察だ、ドアを開けなさい」。威圧的にドアを叩いても鍵を開けないので、仕方なく巡査は隣家からベランダ伝いに侵入してガラスを割り、土足のまま室内で隆太を保護した。今度は老人が怪我を負っていることもあり、地元の警察署へ連行した。
パトロールカーで署まで連れて行かれる間に、騒ぎ続けていた隆太は急に静かになった。薄笑いを浮かべたまま、目が焦点を結んでいない。身体がくねくねと力が抜けた具合になり、警官が二人がかりで抱えるようにしてやっと取調室まで運んだが、椅子に座らせても次第にずり落ちてしまう。放置された腹話術人形のようであった。これでは会話が成立しないし、もしかしたら何かの病気かもしれない。取調中に急死なんてことがあったら、それこそ警察が世間から指弾されてしまいかねない。
警察署から今度は救急車で救急病院へ搬送された。検査を受けるも身体的には問題がない。これまでの経緯を考え合わせると精神科領域の問題であろうと救急医は判断した。診療情報提供書を作成し、精神科での入院治療が必要と思われると文章を結んだ。こうして隆太は精神科病院へ入院となった。本人は亜昏迷状態ゆえ、母親の同意のもとに医療保護入院となったのである。
「京極夏彦の本って、手に取ったことがありますか」
入院後は拘束帯でベッドに抑制され、点滴をつながれて昏々と眠り続けた。目を醒ましたのは翌日の昼近くで、そのときには拭い去ったように興奮は消失していた。拘束帯でベッドに縛り付けられているのに気付き、あのどこか他人を苛立たせる口調で、
「あれれ、これは……うーん、驚愕ですね」
驚愕などという妙に持って回った言葉――これこそが、隆太が目覚めてからの第一声であった。
精神科急性期病棟の医師(わたしではない)は診断を心因反応とし、基盤には性格の偏りがあると考えた。まあそのあたりが妥当な見立てであろう。では落ち着きを取り戻した現在、隆太をどうすべきか。興奮がなくなったのだからそのまま退院させるといった考えがあろう。しかしそれでは今後も似たようなエピソードが繰り返されるかもしれない。もっと踏み込んだ対応をすべきではないのか。
母子密着や長期にわたる引きこもりは、やはり正常から逸脱している。少なくとも隆太にとって現状維持は取りも直さず社会からの落ちこぼれを意味する。今現在は、彼の人生に介入して修正を図らせるレアなチャンスといえるだろう。だから今回の入院を社会復帰の第一段階にしよう。そのように急性期病棟の医師と話し合い、わたしが担当を引き継ぐことになった。余計なお節介ではないかと異論を唱える向きもあろう。引きこもろうがニートだろうが本人の勝手じゃないか、と。しかし隆太も鈴江も実際のところ適切な判断力を備えているとは言い難い。そして二人で小宇宙に逼塞している。それを心情的に見過ごせなかったのである、当時のわたしは。
まずは開放病棟に移し、母子分離の地ならしを図る。隆太自身も、騒ぎを起こした気まずさもあり、しばらくは開放病棟で生活しながらデイケアに参加してみる方向性に同意した。入院形態は強制入院のひとつである医療保護入院から、本人の納得のもとに入院する任意入院へと切り替えた。母の鈴江は、一刻も早く息子を引き取りたがったが、そんなことをしたら元の木阿弥である。自宅を離れての生活が重要であるとわたしが言葉を重ねて説得した挙げ句、鈴江は恨めしそうな表情を浮かべつつ承諾をした。
こうして隆太は集団生活に放り込まれた。彼と同世代の入院患者(統合失調症もいれば、自傷行為の目立つパーソナリティー障害の患者もいた)が数名、同じ病棟にはいた。デイケアでは、女性や外来通院の患者もいる。カルチャーショックにも似た体験を三十歳近くになって彼は味わうことになったのだった。
予想はしていたことだが、隆太の「どこか他人を微妙に苛立たせる」オーラは、確実に周囲へ影響を与えつつあった。彼がことさら失礼なことを言ったり、非常識な振る舞いに及ぶわけではない。でも彼には他人に嫌われる要素が確実に備わっていた。当時、講談社ノベルスで京極夏彦がデビューし、さらに数作が出て評判になっていた。ことにどの作品もびっくりする位に分厚い本であるのが話題になっていた。隆太にそんな京極の本を読んだことがあるかと尋ねてみた。今度買おうと思っていますと言いながら、いつまで経っても買う気配がない。やがてある日、わたしにこんな事を言う。
「京極夏彦の本って、手に取ったことがありますか」
「ああ、最初から全部読んでるよ」
「あの作者の本、実はすごい特徴があるんです」
「すごい、ってどんな?」
「こうやって本を机の上に置きますとね――」
「置くと?」
「何と―― 立つんですよ! 煉瓦みたいに」
「……」
隆太は「何と」と言ってからさも勿体ぶったように沈黙し、それから少々声を低く太くして浪曲師さながら「立つんですよ! 煉瓦みたいに」と芝居がかって言ったのであった。読んだことがあると明言しているわたしに向かって、わざわざそんなことを一大事のように言うのである。しかも京極本は、既に世間でレンガ本だとかサイコロ本と称されていた。ピントがずれているというよりは、効果を期してわざわざ声のトーンを低めるような「あざとさ」が前面に出て、もうそれ以上隆太とは口を利きたくない気分にさせられる。お前、ナメてんのかよと言いたくなるのである。どうしてそんな当たり前のことをわざわざオレに向かって偉そうに言うんだよ。
当時、マラソン・ランナーの有森裕子がゴールインしてから「自分で自分をほめてあげたい」と言ったのが流行語になっていたが、デイケアでミーティングの際にこの台詞が話題に上ったら、隆太は「自分を甘やかしているように聞こえるなあ」と例の尊大な姿勢で感想を洩らした。これにはデイケアの全員が強く反発し、じゃあお前は何を努力しているんだよと総スカンを食らったのだった。しかもそのことに彼は弁解もしなければ気まずそうな態度も示さず、「そういうことですよ、うん」などと言ったので彼はますます嫌われ者になってしまったのであった。
隆太は鈍感・無神経・鉄面皮であるように思われがちであったが、実際には傷つきやすい青年であった。世の中とチューニングが上手く合わせられなかったのが、誤解を招いた原因だろう。ある日、外出して熊のプーさんの小さなヌイグルミを買ってきたとわたしに語ったことがある。
「あのヌイグルミの柔らかさって独特なんです。嫌なことも全部受け止めて勢いを吸収してくれそうな柔らかさなんです」
「じゃあ、君にとってのお守りになりそうだね」
「百個くらいあれば、そうでしょうね」
「百個ねえ。うーん、百匹と言うほうが正しいのかな……」
「先生って結構真面目なんですね」
「え?」
「あんな子ども騙し、持っているだけで馬鹿にされますよ」
母親の鈴江は、頻回に病院を訪ねてきた。着換えや雑誌を携え、息子との面会を要求する。わたしはその都度、今は会うことを控えて距離を置くようにしてくれと諭すのだった。隆太のほうは、母と離れていることで清々しているようにも見えた。
だが現実には、隆太の内面は予想以上に追い詰められていた。病棟でもデイケアでも、周囲との溝は深いものになりつつあった。言動の無神経さは、むしろ増強していた。他人との直接的な衝突はなかったものの、空気がぎくしゃくしている。年末に近い金曜日、プーさんのヌイグルミはゴミ箱に棄てられていた。寒々とした眺めであった。ゴミ箱の件で彼に問い質してみると、シニカルな調子で呟くのだった。
「あんな子ども騙し、持っているだけで馬鹿にされますよ」
担当看護師のS(四十歳の男性)が兄貴的なスタンスで丹念にアプローチしていたが、ちっとも関係性が深まらないと嘆いていた。
「顔が……」
さて問題の晩について語らなければならない。その夜、わたしは当直をしていた。あと一週間で年の終わりだった。回診を終え、病棟の診察室でカルテのチェックをしていた。消灯時間は過ぎている。
不意に、隆太が半開きのドアから入ってきた。照明はデスクの上の電気スタンドだけだったので、彼の顔は闇に溶け込んでいる。でもなぜか雰囲気だけで隆太と分かった。
「あの、先生……」
「うん?」
「ちょっと診ていただけませんか。顔が変に……」
隆太の顔が、電気スタンドの作り出す光の領域に突き出された。それを見て、わたしは息を呑んだ。
真っ先に思い浮かべたのは、胃の粘膜だった。胃の内壁には、蠕動運動をするために皺が生じる。胃粘膜の広がりが、うねうねした皺曲を形作るわけである。それに似た変化が、隆太の顔に顕れていた。顔の皮膚のあちこちが不規則な線状に太く隆起し、それが胃の粘膜みたいな生々しさを感じさせる。うつ伏せに寝ると、顔にシーツの皺がくっきりと転写されることがあるが、それとは違う。むしろ蕁麻疹の膨隆に近いが、発赤はない。顔そのものに蠕動運動が生じているとしか見えなかった。
「痒いとか、痛いとか?」
「いえ、何の感覚もないです」
「蕁麻疹じゃないよね」
「まさか」
「すまん、ちょっと分からないなあ。明日の様子次第でとりあえず皮膚科に紹介するから、とにかく今夜は休んで下さい」
「顔が……」
もともと無表情に近い隆太の顔に、蠕動運動さながらの「うねうね」が生じている。もちろんそれが動くわけではない。光の加減で陰影が強調され、何だか取り返しのつかない変化が顔面に生じているように見えた。グロテスクであった。
隆太はベッドに戻った。たった今目にしたものに、わたしは現実感を覚えられなかった。いったいあれは何だったのだろう。彼もわたしも何か錯覚を起こしていたのではなかったのか。もしも顔の皮膚の下に何匹ものミミズみたいな生物が這い込んだら、あんなふうに見えるかもしれない。でもそれだったら、痒みや痛みが生じないだろうか。
彼が立ち去った今、わたしは軽く腹を立てていた。隆太に対してなのか、それとも自分に対してなのかは判然としないが、訳の分からぬ訴えを持ち込みやがってと苛立っていた。その苛立ちには、得体の知れぬ皮膚の変化に対する恐れや無力感、生理的な不快感、漠然とした不吉さなどが含まれていた筈だ。
「息子さん、そちらへお戻りになっていないでしょうか」
翌朝。晴れて寒い日であった。
当直ナースが騒いでいた。隆太が見当たらない。昨夜、無断離院したらしい。靴がないし、リュックが消え失せている。財布も見当たらない。服や下着は新しいものに着換えていったようだ。数日前にトランプを一組購入し、〈独り占い〉に凝っていたようだったが、そのトランプも見当たらない。それ以外は、何がなくなっているかは分からない。書き置きの類もない。だが、どう考えても、自ら病院を立ち去ったとしか思えない。
それを聞かされて、わたしは当惑した。隆太は、顔に奇妙な「うねうね」を生じさせたまま病院の外へ出ていったのだろうか、と。だが昨夜のあの顔の病変を思い浮かべてみると、いったいあれは本当のことだったのかと信じられなくなってくる。実際に彼と向き合っていたときでさえ、非現実的な感覚に囚われていたのだ。それにしても、急に隆太が病院から姿を消す理由は顔面の隆起に由来しているのだろうか。むしろ外で不特定多数の人間に顔を見られることを忌避するのではないのか。それとも、わたしに素っ気ない態度を取られたのが、想像以上に彼に絶望感をもたらしたのだろうか。
可能性としては、家に帰ったと考えるのが妥当だろう。だがあの母親に「息子さん、そちらへお戻りになっていないでしょうか」と問い合わせたら、たちまち管理責任だの本人の意志の尊重だの、面倒な事を言ってくるに違いない。考えただけでうんざりする。とりあえず昼まで待ち、それでも動向が掴めないようだったら母に電話することにした。
昼になっても隆太の行方は分からない。しぶしぶ鈴江の家に電話してみたが、何度掛け直しても留守である。困ったような、でも一時的にでも面倒を避けられ安堵した気分になったりで、夕方に掛け直すことにした。当直明けなのでいったんわたしは帰宅し、しばらく寝てから自宅で電話をしてみることにした。
自宅へ帰ってベッドにもぐり込み、三時間ばかり眠り、それからシャワーを浴びてコーヒーを淹れた。妻は仕事で遅くなるし、子どもはいないので家にはわたし独りである。妻が買ってきた正月用の小さな注連飾りが、台所のテーブルに置かれている。その注連飾りを眺めながら、まず病院に電話を入れた。やはり隆太は行方不明のままで、病棟の患者やデイケアのメンバーに尋ねてみても、無断離院の心当たりはないという。コーヒーカップを持ったまま溜め息を吐き、それから隆太の母に電話をした。今度は在宅していた。こちらの名前を口にした途端、彼女の声が固くなった。
隆太が姿を消したがそちらへ戻っていないだろうかと、淡々と尋ねた。鈴江は、「まさか!」と不快そうに応じる。彼が行きそうな心当たりがあったら確認し、もし見つかったら教えて欲しい、こちらも隆太の帰院を待ち、明日の朝になっても戻らないようだったら警察に捜索願を出しますと伝えた。現在の彼は強制入院にはなっていないので、本人の意志で勝手に病院を立ち去ってもそれについて当方が責任を負う必要がないのが道理である。でも精神に不安定さを抱えた人物を預かっていたわけだから、こちらに落ち度がなかったと言い募るわけにはいかない。鈴江は怒ったり咎めたりせず、いやに淡泊に「ああ。そうですか」と抑揚なく応じて電話を切った。
もうあの人たちとは二度と口を利きたくない
結局、翌朝に隆太の捜索願を出すことになった。捜索願を出したからといって、警察が熱心に捜してくれるわけではない。身元不明の死体が出た場合に照合をしてくれるだけである。したがって隆太がどこかで自殺を図り、あるいは事故死や病死で死体がちゃんと見つかれば警察から連絡が来るというだけの話である。その時点で、わたしは隆太が自殺をする可能性はあまりないと思っていた。自殺を実行するだけのパワーがあるとは考えにくかったし、正直なところ、根幹の部分はかなりふてぶてしい人間ではないかと判断していた。顔の膨隆が消失していなかったとしても、それを苦に自死するとも思えない(捜索願で隆太の特長を伝えるとき、顔の『うねうね』のことは警察に言わなかった。いつまでそれが顔面に出現しているものか分からないし、自分でもそもそもそんなものが本当にあったのか記憶が不確かになっていたので、かえって事態を混乱させかねないと判断したからだった)。
驚いたことに、午後三時頃、警察から連絡があった。不可解なことであるが、札幌で自殺者が出た。持ち物の中に当院の診察券があった(遺書はなかった)。どうやら捜索願の出ていた隆太らしいが、確認をしたいので病院まで彼の指紋を採取に行きたい、と。
なぜはるばると北海道まで渡ったのか。隆太との会話で北海道の話題は一度も出たことがない。知人や親族が在住していると聞いたこともない。これは担当看護師のSも同様であった。それにしても指紋と言うのが分からない。顔写真で判断出来ないのか。もしかしたら顔の皺曲がとんでもなく顕著になって目鼻立ちが分からなくなっているとか?
警察から教えて貰った経緯は以下のようであった。隆太は夜中に病院から立ち去り、羽田から飛行機で冷たい海を越え、翌日の夜には札幌のビジネスホテルにチェックインした。落ち着いた物腰であったらしい。翌朝、朝食は摂らずにチェックアウトし、以後の行動は不明。午後になり、市営地下鉄の西十八丁目駅に姿を現した。ベンチに腰を下ろしたまま、下りの電車を四、五本やり過ごしたらしい。やがてゆっくりと立ち上がり、リュックを柱の脇に置いた。ちょうど次の下り電車が真っ暗なトンネルの向こうから、ぎらぎらとヘッドライトを光らせながら清潔なホームへ滑り込もうとしていた。しばらくのあいだじっと足下を見詰めていた隆太は、スイッチが入ったみたいにいきなり走り出した。体型的に俊敏とはいえず、むしろよたよたした走り方だった。そのまま左右の前腕で顔を覆うようにしながら、轟音で突進してくる電車の前の空間に、ホームの縁から身を踊らせた(目撃者が何名もいた)。声は発さなかった(叫び声を上げたのは目撃者たちと、地下鉄の運転士であった)。隆太の姿はライトに照らし出されたまま、空中に浮かんだ。既にブレーキは掛かっていた筈だがさらに制動が加えられ、鉄の擦れ合う異常な音とともに車輪からは火花が散った。隆太の身体は電車の正面に激突したが血は飛び散らなかった。今や力が抜け、ぐにゃぐにゃした肉玉のようになった隆太は、そのままシュレッダーに放り込まれるかの如く車体の下部の闇にすうっと吸い込まれ、次の瞬間には何十もの車輪によって念入りに切り刻まれた。目撃者によれば「えらく手際よく、オートメーション工場みたいに人が車輪の下に消えていったので、呆然としてしまいました」。
ほぼ完璧に、人間の姿は留めなかった。無数の肉片と化して線路に散らばった隆太に、もはや顔など存在しない。指先が見つかったので、これで指紋を確認するしかあるまいということで病院に連絡が来た次第なのであった。当時は、まだDNA鑑定は一般的でなかった筈である。
どんなふうに隆太のベッドの周囲から指紋は採取されたのだろう。歯磨き用の合成樹脂のコップからだろうか。目覚まし時計を持っていたのでベルを止めるスイッチに指紋がくっきりと残っていたかもしれない。さもなければビニール・コーティングされた雑誌の表紙だろうか。いずれにせよ、以外とすぐに結果が出た。札幌の地下鉄で鉄道自殺を遂げたのは、やはり隆太であった。その時点でもはや扱いは警察となり、母へ顛末を知らせたり事情を確かめる等はすべて警察が行うことになった。カルテの開示を求められた以外、わたしとS看護師は、殆ど取り調べらしい取り調べは受けなかった。
二日経ってから、鈴江は病院まで遺品の引き取りに来た。大晦日が、正月が目前に控えていた。居合わせたナースが、わたしとSを呼んできましょうと声を掛けたら、もうあの人たちとは二度と口を利きたくない、いまさら息子は帰ってきませんと押し殺した調子で語ったという。そうなるとこちらから無理に会おうとするわけにはいかない。あとで手紙でも出そうかと思ったが、かえって誤解が生まれそうな気がして差し控えた。葬儀にも参列しなかった。
「うねうね」
――これが隆太の自殺の一部始終なのであるが、彼の場合、自殺の予兆と呼ぶべきものはなかった。いや、たったひとつ気になるのは、隆太の顔に表れた「蠕動する胃粘膜のような、うねうねした隆起」である。あれは視覚的に強いインパクトがあった。日常を覆すような異様さがあった。果たして自殺の前にあんなものが顔面に出現するなんてことがあるのだろうか。何だか地震予知みたいな胡散臭さとリアリティーとが感じられて、わたしの胸はざわつく。
同僚に尋ねてみたが、絶句されただけであった。似たようなケースを知っていたなら、自殺の前兆(サイン)として意味を持つわけだが、やはり普遍性には欠けるらしい。自殺の決意につながるような内面の動きがああした顔面の「うねうね」として顕れるなんて、やはり信じがたい。となれば、あれは何だったのであろう。アレルギーの一種なのか。北海道に渡った時点で隆太の顔がどうなっていたのかも不詳である。精神的な煩悶に加えて、顔面の皮膚病変が本人には何やら絶望的事態として駄目押しの役割を果たし、その結果(なぜか)札幌まで行って自殺を図ったと解釈することも可能ではあろう。
それにしてもあの隆太の顔に生じた「うねうね」は、まさに精神が死に魅せられていくそのプロセスを見事に形象化していたように思えてならない。まるで身体が裏返って内臓が露出でもしてしまったような生々しさがあの顔面には窺えたのだ。もしも道を歩いていて、あの線状の隆起が何本も顔に生じている人物と行き会ったら、わたしは「あ!」と声を上げるだろう。だがそのあとどうすれば良いのか。まさか「あなたは、もしかして自殺をしようとしているのですか」と、面と向かって尋ねるわけにもいくまい。いやその前に、わたし以外の人たちにもあの顔の変化がちゃんと見えているのか、それをまず確かめるべきかもしれない。
「息子を荼毘に付したら、骨が青くなっていました」
以上、個人情報保護の上から話には改変した部分がある。むしろディティールのほうが実際の出来事に忠実かもしれない。そしていささか突飛な後日談があるのだが、これもまた基本的には「作り話」などではない。
後日談は、新年を迎え既に二月になってから起きたエピソードである。母親の鈴江は、わたしと担当看護師のSとは二度と会いたくないと宣言していたのであった。にもかかわらず、二月のある晴れたウィークデイに、彼女は病院を訪れわたしとSとに面会を求めてきた。いったいどうした風の吹き回しか。嫌な予感を覚えつつ、わたしたちは家族面接を行う広い面接室で彼女と会うことにした。
毛糸の帽子を被った鈴江は、不自然なくらいの上機嫌さで「あの節はお世話になりました」などと言う。いろいろと喋ってくるが、葬式の様子とか隆太について何か情報が新しくあったのかとか、そういった話題は巧妙に避けている。上滑りの気詰まりな会話がしばらく続いた。彼女の肝炎は、まだ体調の回復にまでは至っていないらしい。やがて鈴江は、
「今、隆太の思い出をアルバムにしようと思って、資料を集めているんですの。お世話になった先生とSさんの写真もそれに加えたいと思います。よろしいでしょうか」
と言いながら、バッグからコンパクトカメラ(当時はまだフィルム式が一般的であった)を取り出して構える。成り行きから、わたしとSは仕方なしに並んだ。レンズを前に、どのような表情を浮かべれば良いのか。笑顔ではまずかろう。無愛想な顔もよろしくないだろう。診察室の壁をバックに、柔和というか曖昧というかそんな表情を浮かべたところでシャッター音が聞こえた。やれやれこれで終わりかと思ったら、突如、鈴江の態度が一変した。その変化の様子は、芝居がかっていたと形容したほうが適切かもしれない。
「息子を荼毘に付したら、骨が青くなっていました。これは毒を飲まされていたときに起きる変化だそうです。あなたたちが毒を盛ったからこうなったのです。これからわたしは研究機関で灰を分析してもらいます。毒が検出されたら、あなたたちを訴えます。わたしは決してあなたたちを許しません。覚悟していなさい」
それだけを告げると、こちらを睨みつけてからさっさと面接室から出て行ってしまった。いったい今何が起きたのだろうかと、わたしはSと顔を見合わせた。
鈴江は息子の凄惨な自殺を受け入れきれず、また病院に反感を覚えていたこともあり、いつしか病院で毒を盛られたという考えに辿りついたのだろう。自分なりに心を鎮め納得させるための不器用な工夫と言えるかもしれない。だからわたしは彼女の気が狂ったとも思わないし文句を言う気もない。けれども、写真を撮られたことだけが「気味が悪い」。自分の姿を彼女に渡してしまったわけで、それを使って呪いでも掛けられたらホラーではないか。本気で恐ろしい。以後、しばらくは胃が痛くなったり悪い夢を見たりすると、鈴江の憎悪が思い起こされた。
時間経過を考えると、鈴江がまだ生きているかどうかは微妙なところだ。彼女はどれほどの恨みと憎しみを込めて、現像された写真を眺めたことだろう。しかしわたしとSとが写ったあの写真は最終的にはどうなったのか。針で突き刺されたり引き千切られたのか、ひっそりとセピア色に変色したのか。その成り行きが今でも気になって仕方がない。
(第一回・了)
 1951年京都生まれ。日本医科大学卒業。医学博士。産婦人科医を経て精神科医に。都立中部総合精神保健福祉センター、都立松沢病院部長、都立墨東病院精神科部長などを経て、現在も臨床に携わる。著書に『無意味なものと不気味なもの』(文藝春秋)、『幸福論』(講談社現代新書)、『精神科医は腹の底で何を考えているか』(幻冬舎新書)、『臨床の詩学』(医学書院)、『老いへの不安 歳を取りそこねる人たち』(朝日新聞出版)、『鬱屈精神科医、占いにすがる』(太田出版)等多数。
1951年京都生まれ。日本医科大学卒業。医学博士。産婦人科医を経て精神科医に。都立中部総合精神保健福祉センター、都立松沢病院部長、都立墨東病院精神科部長などを経て、現在も臨床に携わる。著書に『無意味なものと不気味なもの』(文藝春秋)、『幸福論』(講談社現代新書)、『精神科医は腹の底で何を考えているか』(幻冬舎新書)、『臨床の詩学』(医学書院)、『老いへの不安 歳を取りそこねる人たち』(朝日新聞出版)、『鬱屈精神科医、占いにすがる』(太田出版)等多数。