佐藤直樹さんは2013年3月、荻窪6次元で初の個展「秘境の荻窪」を開いた。中学2年生のときに1年間住んだことのある荻窪を歩きなおし、建物や木々、動物、地形などを木炭で描いたもの。長らくデザインの現場に身をおいてきた佐藤さんだが、それ以降、少しずつ絵を描く機会を増やしてきた。3331コミッションワーク「そこで生えている。」や、Tambourin Gallery Presents 「佐藤直樹と伊藤桂司の反展」では、毎日、会場へ通って、少しずつ絵を描いていって、その過程を披露していた。そのような試みは、純粋に、「絵ってなんだろ?」という疑問から出発している。
「絵画」というと、美術館の中だったり、画商が扱うものだったり、どこかありがたいもの、身近なものではないものに思える。でも本来は、幼児の頃、うら紙やダンボールに○や□や線を描いたり動物らしきものを描いたのも、絵のはじまりかもしれない。個人ではなく人類で考えてみると、ショーヴェの壁画はどのように描かれたものなのか? 人間がもつ根源的な欲求である「何かを描く」という行為とは何かを、自らが「絵画」を描く行為、「絵画」に入門しながら考えてみる、そんな連載である。佐藤さんの実作もお楽しみに。
型とは何なのか
本屋さんの美術書コーナーに行くと油絵とか水彩画とか日本画とかの入門書がたくさん並んでいて、デッサンはこうすればいいというような本もあります。そこにはいろいろな手順みたいなことも書かれています。けれども、私が考えている型というのはそういった手順のことではありません。
まず写し取ることについて考えてみます。ほとんどすべての入門書には「そいつをうまくやるためにはこうすればいい」というようなことが書かれています。ではそもそも、いったいぜんたい写し取るとはどういうことなのか。写真のように描いてみることでしょうか。それもひとつかもしれませんが、それがすべてであるはずもありません。
私たちは写真(昔は「光画」とも訳されていました)の存在を知っているので、カメラのような入力装置とプリンターのような出力装置に自分を模してみることができます。輸入概念としての「絵画」とはある意味そのようなものだったかもしれません。何しろ同時期に入ってきたのですから。
しかし、描くことの初源において、おそらく写実という考え方は存在していなかったはずです。何かを写し取ろうとしていたのは確かだと思いますが、写し取るなどというのはそもそもが不可能なことであって、そのような不可能にわざわざ臨んでみたのは何故なのか。そこが問題で、動いているものを止めて描いている時点で、それはもう写実というよりフィクションなわけです。
シュルレアリスムとともに浮上したフロッタージュという技法は文字通り写し取る作業です。ショーヴェの壁画に残されている手形も近い行為かもしれません。ただ、それとは別に、間接的な写しということも人は始めた。手形を残したのと同じ時期に。
「見たまんま」と言っても、対象は時間とともに刻一刻と変化しているわけですから、対象と絵は直結しません。そこで型が発生するのだと思います。ショーヴェの壁画の絵は修正なしの一発描きで見事な造形を成しています。練習の痕跡はありません。ということは壁に向かった時点でもう描けるようになっていたことになります。ではどこでどうやってその型を習得したのでしょう。それは残っていません。型は残らない部分にこそ存在していたと言えないでしょうか。
中国・清代の『芥子園画伝』には、そうした「残らない型」を巡る記述が随所に見られます。私は最初この書物を『北斎漫画』のようなものだと思っていました。しかし、『北斎漫画』が絵手本としての実例集であるのに対して、『芥子園画伝』はあくまで「画伝」なのであり、その「考え方」を伝えるために、あくまでその手掛かりとしての略画が添えられているに過ぎません。
たとえばこんな記述があります。
「絵画について論ずる時、繁密に描き込んであるのを良しとする者と、簡略なのを良しとする者とがいるが、繁密のみでも、簡略のみでもいけない。あるいは絵事は容易だとも、むずかしいともいうが、容易といってしまうのも間違っているし、むずかしいというのもまた違う。あるいはまた法式のあるのを尊重する者もあれば、法式のないのを尊ぶ者もいる。勿論、法式を無視することはいけないが、それに終始拘泥しているのはさらに良くない。ただし、まず法式が厳として存在し、そののち自由自在の域に達するのであり、有法の極が無法に帰すといえる。」(現代語訳・草薙奈津子)
ここで「法式」と書かれているものも型でしょう。それは「かつて型が存在した」という発掘化石のようなものであり、そこから現代における法式とはこれこれこういうものであるなどとすぐに復活するような話でもありません。
忘我のための型
となるとやはり現代の絵画に型を求めるのには無理があるのでしょうか。そう思えなくもありません。現代における型は個々が自分で見つけるしかないのであって、そんな話を人としても仕方ないだろう、と。しかし、現代でも少し前までは盛んに論議をしていたし、少なくとも近代に入ってからしばらくは西洋的なものとどう向き合うかを語らずにやり過ごすことはできなかったため、型の問題はその都度浮上していたのです。その状況が時代とともにだんだん変わっていった。ズレていった。無理が生じていった。通用しなくなっていった。
芳賀徹さんの『絵画の領分 近代日本比較文化研究』(一九九〇)には、日本の明治期の「絵画」概念を巡る、揺れ動きの様子が非常によく描かれています。現在に比べるとまだまだ時間はゆっくりと経過していたように感じます。その後、初めての世界大戦を経験し、様々な前衛運動が起こり、さらに二度目の世界大戦を経験します。その間の人々の意識の変化は相当なものです。
型と言えば細かく分かれた各ジャンル内の手順のことであるというのが現在の一般的な認識でしょう。ではなぜ現在そういうことになってしまったかと言えば、「絵画」の社会的な意味での存在意義が変わったからだと思います。かつて「絵画でしか表現できない」と考えられていたものが、他でも可能になった。写真や動画やVRやAIやその他もろもろの領域が勃興し精度を上げ進化し続けている。それに伴って、「絵画」とそれ以外の領域は侵蝕し合い、その境界や概念自体までもが揺れ動き続けています。すると各々自由にやるしかないという話にどうしてもなります。コンセプトだのなんだのの理由をつけて。けれども、代替され得ない部分にこそ「絵画」の本質があるのだとしたら、やはり必要になってくるはずなのです。かつて存在した型と同じようなものではなくとも、それに該当する何かが。
「天然」「アウトサイダー」「アール・ブリュット」は除外して考えざるを得ないという話を連載の第二回目でしました。「子ども」も含めてもいいと思いますが、型が必要とされない世界というものも当然あります。忘我の状態で表現されたものは、見ている側に某かの発見をもたらします。ただ、繰り返しになりますが、その領域は求めて得られるものではない。それは絵に限らず、言語表現でも身体表現でもあることで、
忘我の反対にあるのは自我や自己の意識です。これが世界を固定してしまっているのでしょう。だとしたら、これを外す必要があります。おそらく、型はそのためにこそ必要なのです。と言うより、人は何らかの型を通してこそ外からの力に感応することができる。
「自我に向き合った、その人らしい、いい絵だってあるではないか」と言う人もいるでしょう。その自我が、見る人と重なっていれば、それはそれを見る人にとっての、いい絵なのだろうと思います。しかし、自我に従属した絵というのは自由な絵と言えないのではないか。結果的に「どうしてもそうなってしまう」ものというのは、自我を超えた力に支えられているに違いありません。一方、自ら設定した自分らしさに従ったものは、絵がもともと持っているはずの力を狭い範囲に閉じ込めている。自分が描いているものを見てそう思うのです。
こう書きながら、私は今、松本竣介さんの絵を思い浮かべています。一九一二~一九四八年を生きた画家です。世界大戦の時期と一生がほぼ重なっています。生計を立てるため様々なイラストなども描きながら、どうしても描かざるを得ない絵に取り組んでいた。自我に関わる問題でもあったのでしょうが、自我に向けて描いていたのではなかったろうと思えるのです。むしろそこから逃れるためにこそ描いていたのではないか。変化する都市像とそこに生じていたであろう得体の知れない感覚。それは当時流行していたマルクス主義的な疎外(Entfremdung)の概念などではとても説明のつかない、もっと根本的で、もっと本質的な、全身に根ざした感覚であるように見えます。手探りで何かを確かめているような。中学生の時に聴力を失ったことが彼を絵に向かわせたのかどうか、その真相まではわかりませんが、そのすべてを自我や自己の意識が選び取ったのでないことだけは確かです。
どうしても描かれざるを得なかった絵。それは「絵が最初に描かれた瞬間」と繋がっているのだろうと思うのです。第二回目には個体発生と系統発生の話もしましたが、理由はわからないまでも、ある必然、ある切実さが途切れず続いていることは確かで、そこに連なることこそが「生きている」ということだと思うのです。「描けた」「描けるようになった」という、ある一線を超えた瞬間がその都度あったわけで、ではその一線とはどんな一線だったのかという話が重要になります。
ある時、それは文字通り一本の線だったでしょう。そしてそれは、稚拙ながら人間味があるといったものでは決してなく、ショーヴェの壁画に残っているような、それ以上は望むべくもない、見事な一本であったに違いないのです。そんな線など引けないまま死んでいくとしても、私(たち)はその末尾にぶら下がっているのですから、精一杯の想像力を働かせて、何とかそこに連なることを考えたい。「絵画に入門する」とは私にとって そういうことなのです。
死を意識してみる
そんな中で、私が欲している型というのは、その時に身体の中で起こるであろう、すべての連携です。そして、言うまでもなく、今の私はまだそれをうまく言葉に置き換えることができません。というのも、今は線を引く行為や面を表す行為を通して、体感的な確認を繰り返している段階に過ぎないからです。
それが体得できた時、やっと門を潜り切ったと言えるんじゃないか。ひとつの予感として、門の向こう側は死と繋がった世界なのだろうと思うのです。社会通念などと関係なく、ただ呼ばれるままに応えるだけの世界。どんな有能さからも優秀さからも除外されるのは、最終的には死だけです。門の出口はそのすれすれのところにあるに違いありません。
そう考えると、絵は夢とも関係しています。現実の世界と想像の世界があるとして、絵は常にその媒介として立ち現れる。夢がそうであるように。そして夢を見ている時、人は少しだけ死に近づいています。そこでは自己がコントロールできなくなっている。だとすると、日常の様々な自己要素の隙間から漏れ出るように生まれたのが最初の絵だったとも言えるのではないか。夢を表現に取り入れたのも先に話題にしたシュルレアリスムでしたが、あらゆる意味での「未開地」に向かおうとしていたのが20世紀初頭の芸術運動だったとも言えるわけです。そして死の概念だけが常に先送りにされてきた。一人一人の死は確実であるのに。
死をまったく意識しなくなると、喪失するものがあります。進歩していると思い込み、新しいことをやっているつもりになって、観察も感受も疎かになっていく。いつまでもただ見ているとか、いつまでもただ感じ入っているとか、そういうことがなくなってしまう。答えの出ない問いは発してはならない、成果を出さなければならない、見返りを得なければならない、業績を上げなければならない、急いで処理しなければならない、遅れてはならない、と。
その都度死んでまた向かい合うことができれば、世界を新鮮なものとして見出すことができます。その時に、自分らしい表現とか、自分ならではの創作とか、そんなサモシイものに捕われないために、型を探り当てるための模索を続ければ、どこかへと運ばれていくはずです。その移動の痕跡を絵画と呼ぶなら呼べばいいでしょう。人によっては、まったく別の表現形式になるのでしょうが。
誰の承認を得るのか
最後に触れておきたいのは承認の問題です。近代絵画については第四回目に触れましたが、私たちが抱えてしまった「作者」「作家」という自我や自己の意識に基づく呪縛の原型もこの時期の「芸術」の概念から発生しています。松本竣介さんにしてもそのような自我の意識とともにあったことでしょう。
現代の美術や絵画は、形式的には近代絵画を乗り越えたところにあるということになっているのだと思います。しかし、私(たち)はいったい近代絵画の何を乗り越えたんでしょうか。近代絵画に向き合ってきた人と比して、私(たち)にできていることとは何でしょう。何もできるようになってなどいないんじゃないか。いやむしろ、以前はできていたことまでもできなくなっているだけなのではないのか。
近代以前の世界には、神であれ王であれ、個人の力では及ばないものが必ず存在していました。近代がやってきた時、その存在をどう扱うかで四苦八苦していた。個を、自我を、確立しなければならないと言われながら、その実、何と格闘していたかと言えば、前近代的なるもののすべてだったのです。
ところが今では、前近代どころか近代すらも乗り越えられたことになっている。結果、あらゆる権威は地に落ち、ただ「誰かに認められたい」「より多くの人に認められたい」「それなりの人に認められたい」という欲求だけを抱えている。そのサモシサに絡めとられ、ついに私(たち)はどん詰まりまで来てしまった。
型がまだ残っている世界では、「型を持つ人が型を破るのが型破り」を実践すればいいと思います。しかし、「形がない」のであれば「破れば形無し」に向かうのではなく、型を求めるしかないでしょう。振り出しに戻ればいいのです。何年前にでも何十年前にでも。何百年前にでも何千年前にでも。いや何万年前にだって戻ればいい。
そうして、多少とも時空を行き来することができるようになってきたら、誰の承認を得ればいいのかも、自ずとわかってくるはずです。もちろん今の私にはまだうまく言葉にできません。だからこそ続けるしかないのです。
さて、そんなわけで、結論だか何だかわからない話でこの連載は終わります。そして次回からまた新しい連載を始めさせていただけることになりました。タイトルは「アートとデザインの間には深くて暗い川がある 」です。よろしくお願いします。
前回予告した「新作」の話を今回は書けませんでしたので、
 1961年生まれ。アートディレクション、デザイン、各種絵画制作。北海道教育大学卒業後、信州大学研究生として教育社会学と言語社会学を学ぶ。美学校菊畑茂久馬絵画教場修了。デザイン会社「ASYL(アジール)」代表。1994年に『WIRED』日本版のアートディレクターとして創刊から参加し、1997年に独立。国内外で受賞多数。2003~2010年「Central East Tokyo」プロデューサーを経て、2010年よりアートセンター「3331 Arts Chiyoda」デザインディレクター。美学校「絵と美と画と術」講師。多摩美術大学教授。著書に『レイアウト、基本の「き」』(グラフィック社)がある。雑誌『デザインのひきだし』では「デザインを考えない」を連載中。また、3331コミッションワーク「そこで生えている。」の絵画制作を2013年以来継続している。
1961年生まれ。アートディレクション、デザイン、各種絵画制作。北海道教育大学卒業後、信州大学研究生として教育社会学と言語社会学を学ぶ。美学校菊畑茂久馬絵画教場修了。デザイン会社「ASYL(アジール)」代表。1994年に『WIRED』日本版のアートディレクターとして創刊から参加し、1997年に独立。国内外で受賞多数。2003~2010年「Central East Tokyo」プロデューサーを経て、2010年よりアートセンター「3331 Arts Chiyoda」デザインディレクター。美学校「絵と美と画と術」講師。多摩美術大学教授。著書に『レイアウト、基本の「き」』(グラフィック社)がある。雑誌『デザインのひきだし』では「デザインを考えない」を連載中。また、3331コミッションワーク「そこで生えている。」の絵画制作を2013年以来継続している。
twitter / facebook



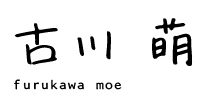 美術史家。ニューヨーク大学で西洋美術史を学んだのち、京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。現在、東京大学経済学研究科特任研究員。ルネサンス期における芸術家のイメージと、その社会的・政治的背景を研究。ルネサンス以降の芸術家像も研究対象。著書に『ジョルジョ・ヴァザーリと美術家の顕彰』。壺屋めり名義で刊行された『ルネサンスの世渡り術』も好評発売中。。
美術史家。ニューヨーク大学で西洋美術史を学んだのち、京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。現在、東京大学経済学研究科特任研究員。ルネサンス期における芸術家のイメージと、その社会的・政治的背景を研究。ルネサンス以降の芸術家像も研究対象。著書に『ジョルジョ・ヴァザーリと美術家の顕彰』。壺屋めり名義で刊行された『ルネサンスの世渡り術』も好評発売中。。