佐藤直樹さんは2013年3月、荻窪6次元で初の個展「秘境の荻窪」を開いた。中学2年生のときに1年間住んだことのある荻窪を歩きなおし、建物や木々、動物、地形などを木炭で描いたもの。長らくデザインの現場に身をおいてきた佐藤さんだが、それ以降、少しずつ絵を描く機会を増やしてきた。3331コミッションワーク「そこで生えている。」や、Tambourin Gallery Presents 「佐藤直樹と伊藤桂司の反展」では、毎日、会場へ通って、少しずつ絵を描いていって、その過程を披露していた。そのような試みは、純粋に、「絵ってなんだろ?」という疑問から出発している。
「絵画」というと、美術館の中だったり、画商が扱うものだったり、どこかありがたいもの、身近なものではないものに思える。でも本来は、幼児の頃、うら紙やダンボールに○や□や線を描いたり動物らしきものを描いたのも、絵のはじまりかもしれない。個人ではなく人類で考えてみると、ショーヴェの壁画はどのように描かれたものなのか? 人間がもつ根源的な欲求である「何かを描く」という行為とは何かを、自らが「絵画」を描く行為、「絵画」に入門しながら考えてみる、そんな連載である。佐藤さんの実作もお楽しみに。
もう一度「絵画」の意味を考えてみる
「絵画」とは明治時代になって「西洋におけるそれ」と対応させるべく「東洋におけるそれ」や「日本におけるそれ」を包括して語るために生み出された言葉です。なので厳密に言えば、明治よりも前の「それら」について「絵画」という日本語の括りで語ろうとするとどうしても無理が生じます。「それら」は「絵画」として制作されたわけではなかったのですから。
冒頭に書きました長沢芦雪さんや円山応挙さんの作も朝鮮の民画もショーヴェ洞窟の壁画も「絵画」として生み出されたわけではありません。けれどそんなふうに言ってしまうとそこに連なる術がなくなってしまいます。そこに連なるためにはやはり「絵画」という言葉を使うしかないんだろうと。なのでもう絵画なら絵画でいいと。
絵画以前の「え(絵)」の根っ子のところにプリミティブな衝動のようなものがあることは間違いないと思います。しかし上述の例にしても「プリミティブなところが素晴らしい」で尽きるものじゃありません。なぜ時空を超えてこんなにも伝わって来るものがあるのか。昨今の私たちに巣食っている「自己実現」だの「承認欲求」だのとはまるで異なった動機が存在していることだけは容易に想像できます。私たちが何の気なしに受け入れている「ニーズ」のようなものとも違い、本当に止むに止まれないものとして生み出されていたに違いありません。私たちが「止むに止まれない」と言う時、何か個人的な情念のようなものを想定しがちですが、そういうものだけではここまでの時空の隔たりは超えられないと思うのです。「個人」を超えた力が働いていることは間違いありません。いや超常現象のような話がしたいのではなくて、何というか脳の古層のようなところから発動してくる知性のようなものがあって、発する方もそれを使っているし、受ける方もそこに反応しているんじゃないか。
宮廷画家や御用絵師という存在を考えても、説明を超えた力が統治の面で必要とされていたということだと思うのです。町人文化として発達した江戸時代の浮世絵にしても、欧州の印象派の画家たちへの伝播や、国内で終焉した明治以降ですら上村松園さんやら竹久夢二さんやら小村雪岱さんやらにまで流れ込んでいるその痕跡を見るにつけ、空間も時間も超えた「原理」としか言いようのないものがあるように思えてきます。
希望の近代絵画
ただそんなふうに考えてみても、近代絵画の登場のところにある断絶を感じます。「絵画」が近代における造語なのだとしたら、「近代絵画」からこそもっとよく感じとり、考えてみるべきなのでしょう。どうも自分たちはそこのところを素通りしてきてしまっている気がしてならないのです。「近代絵画」と聞いて「古い」と感じる人もいるに違いありません。今は近代の後にやってきた現代であるし、モダニズムにしてもとっくの昔にポストモダン思想に超えられたのだからと。しかし本当にそうなんでしょうか。
ここはひとつ東京美術学校が発足した一八七〇年代あたりに立って考えてみることにしましょう。七六~七七年頃には高橋由一さんが「豆腐」や「鮭」を描いています。「豆腐」と言っても、油揚、焼き豆腐、漉しの荒い豆腐が並んでいます。「鮭」はいかにも脂の乗った荒巻鮭です。私はこの二枚の絵が油っぽくてとても好きです。油絵具に初めて触れた新鮮な感覚が迫り来ます。これ以上の対象はなかったろうと思えて来ます。この新鮮さは特別に新鮮な新鮮さです。この新鮮な感覚はその後の誰も超えていないように私には思えます。むしろ少しずつ後退していった気がします。油絵具の存在がアタリマエになってしまって。そのことに慣れてしまって。つまり「古い」のではなくて、「こんな絵はもう描けない」ということなんじゃないか。
この感覚に気づいた時、自分が「最後尾にいる」という感覚を持ちました。にもかかわらず不思議とむくむく希望が湧いて来もしたのですが。芸術には前衛思想というものがあります。前衛というのは要するに軍隊の最前線=FRONTのことです。そういうところで闘うのが大好きな人も世の中には確実に存在します。アートもそういうことでいいのかもしれません。何かを刷新して、また刷新して、さらに刷新して、というように。しかしじつは絵画に前衛はなく、つねに後塵を拝するようなことをしているのが真相なのではないか。後塵とは馬車などが走った後の土埃のことですが、それを描くには、前を馬車に走ってもらわなければなりません。自分で最前線を走っていては描けやしないのです。由一さんにしても最前線を走っていたわけではないはずで、「西洋人が使っていたものを自分も使ってみた」だけだと思うのです。しかし極めて新鮮な感覚で描かれているし、おそらくそのこと自体に驚いている。その驚きの感覚が絵画として結実しているように見えます。そうした感覚の部分なのです。結局のところ伝わって来るのは。そしてこうした例は挙げればキリがないくらいあります。
現在としての近代
近代絵画は往々にして「作者」「作家」をめぐる物語とともに語られます。「近代的自我」というものが現れ「個人表現」が可能になったためでしょう。この感覚は明治から大正にかけて日本人の間にも浸透し始めます。関東大震災後の言論統制の中でいったんは封じ込められますが、戦後になってまた一気に広がります。ズバリ『近代絵画』という本を小林秀雄さんが書いていますが、これなど読みますと、戦後すぐぐらいの日本の「絵画」をめぐる時代感のようなものがとてもよく理解できます。小林さんは大真面目に自らの問題として語っています。ボードレールを。モネを。セザンヌを。ゴッホを。ゴーガンを。ルノアールを。ドガを。ピカソを。この熱量をリアルタイムのものとして感じ取るのはなかなか難しいかもしれません。しかしその「初めて感」を何とか感じ取りたい。
「近代の社会は、色々な専門的な仕事の、独立した世界を持つ傾向に進んでいる。人間の文化的活動力の形式や領域が、互にはっきりと分離して行く、そういう近代社会の傾向を、勿論、芸術は非常に鋭敏に反映するのであって、画家ばかりではない、詩人もこれをいち早く感じて、詩の近代性について果敢な革新を試みた。近代絵画も近代詩も、これは何と言ってもフランスにその中心があったのだが、革新の運動は、先ず詩人の裡に現れた。ボードレールはマネより先輩なのである」という書き方で、小林さんは『近代絵画』の最初に詩人である「ボードレール」の章を設けています。なるほど言葉の人ですからそうなるのでしょうが、いずれにしても非常に新鮮なものとして、すべてを受け止めています。私たちも、けっして今からでも遅くはないので、どうせ見るなら、このように、自らにとって初めてのこととして、向かい合って見るべきなのです。超えた気になどなっている場合ではありません。
近代絵画としての日本画
ではその時期、日本の絵描きだったり画家だったりはどうしていたのでしょう。いろいろな人がいろいろな動きをしていたようでとてもまとめて語れることではありませんが、私は美学校に通っておりましたので、赤瀬川原平さんや中西夏之さんや高松次郎さんなどのことがすぐに思い浮かびます。これらの方々は戦後に活動を初めていて、小林さんが語っているような近代絵画に対していったんは憧れながら、その後は反発も強かったように思われます。小林さんとは三〇歳以上も違う、まだピチピチの若者だったわけなので。
しかしたとえば日本画家の奥村土牛というような人だと戦争が終わった時点で五六歳ですから小林さんよりひとまわりちょっと上くらいの世代になりまして、非常に興味深いところがあるのです。まずもって外国の絵画に対する興味関心が半端ではない。「日本画」という言葉が明治以降の「洋画」や「油画」との関係の中で生み出されていった過程も興味深いのですが、カテゴリーや様式云々より大事なのは「意識上どうだったか」でしょう。そう考えると「日本画」とは近代絵画の一形態として出現し勃興したものであると考えた方が自然なのです。
だからいいとかわるいではなく、ただそういうことだっただろうという話です。そして間違いなく、図抜けた作品を生み出しています。「日本画」をこの世で初めてのものとして引き受けた結果であると思われます。奥村さんはその最後の世代だったんじゃないか。それは伝統的なものでも何でもなかったのです。
この世代の絵に興味を持つようになったのはわりと最近のことです。少し年下の速水御舟さんなどは早くに亡くなられていますし、自らと重ねてその視線の先を追い、絵画として定着させるまでの所作に思い至ることもなかったのですが、原画を見て本当に大きな変化が起こったのでした。菱田春草さんの描き出す空間などにも心底驚かされました。複写されたものを見てわかったつもりになっていたことの怖しさを思い知りました。繰り返し書いていることですが。「近代絵画」に対しても明治以降の「日本画」に対しても私は長らく偏見だけを膨らませていたのでした。
引き裂かれたもの
私は一九六一年に生まれたのですけれども、六〇年代から七〇年代にかけてはあらゆる既存の文化に変革の波が押し寄せており、「制度的なもの」は疑われ壊されなければならないと信じて育ったようなところがあったと思います。「絵画」もまた当然のごとく格好の攻撃対象となっていました。当時の私の希望は漫画やアニメや特撮やテレビやラジオやポップミュージックといったものの中にこそありましたから、教科書に掲載されているような絵画や美術や音楽は反発の対象としてしか捉えていませんでした。そこまでが一〇代です。
八〇年代になるとそれまでカウンターカルチャー的だったものもサブカルチャーとしての性格がより強まります。日本の「絵画」を考える上で、この時期の変化は非常に重要だったと今では思いますが、個人的には一〇代の後半あたりからカルチャーと呼ばれるものに対して全般的に嫌悪感を抱き始めました。美術大学の受験といったものに対しても懐疑的になり、僻地に意識が向かいます。このあたりのことはここでは深入りしませんが、時代はバブルへと向かって行きました。「一億総中流化」などという言葉も使われていましたが、何かが大きく引き裂かれていた印象が私にはあります。八〇年代後半に起こるバブル経済前夜は、人類学や民俗学の視点が深められていた時期でもありました。寺山修司さんなども八三年までは生きていました。
絵画が運んで来る自由
少し話は飛びますが、現在の絵画市場においては「作家とはとにかく自由なもの」という考え方が大きな教義のようになっていて、生み出された作品は「社会全般の制度的なものから自由である」ということになっています。「本来的には極めて不自由なものであるところの」という前提が「素晴らしき自由表現の実践であるところの」という宣伝文句のようなものに置き換えられてしまっている。「より自由なものに高値がつくようになったから」と言っていいと思います。コンセプチュアル・アートの先駆者と位置づけられるマルセル・デュシャンも二〇代の半ばくらいまでは油絵というじつに不自由なものと格闘していたわけですが。
社会主義の実験がほぼ失敗し、資本主義に変わる制度が構想できていない以上、アートの「自由競争」はしばらく続くに違いありません。しかしそれは本当に自由なのか。というのも、この場合の自由とはつまるところ知的解釈としての自由であって、それが経済学的にも説明可能な市場を形成しているという話で、絵画が運んで来る自由というものとは種類が違うんじゃないか。
では「絵画が運んで来る自由」とは何でしょう。おそらくそれは「生命」に関わっています。いや「死」に関わっていると言った方がいいのかもしれません。同じことな気もしますが、とにかく、そこのところがちゃんと汲み取れたなら、恐れている「絵画からの破門」を逃れられるんじゃないか。というところで、次回に続きます。
 1961年生まれ。アートディレクション、デザイン、各種絵画制作。北海道教育大学卒業後、信州大学研究生として教育社会学と言語社会学を学ぶ。美学校菊畑茂久馬絵画教場修了。デザイン会社「ASYL(アジール)」代表。1994年に『WIRED』日本版のアートディレクターとして創刊から参加し、1997年に独立。国内外で受賞多数。2003~2010年「Central East Tokyo」プロデューサーを経て、2010年よりアートセンター「3331 Arts Chiyoda」デザインディレクター。美学校「絵と美と画と術」講師。多摩美術大学教授。著書に『レイアウト、基本の「き」』(グラフィック社)がある。雑誌『デザインのひきだし』では「デザインを考えない」を連載中。また、3331コミッションワーク「そこで生えている。」の絵画制作を2013年以来継続している。
1961年生まれ。アートディレクション、デザイン、各種絵画制作。北海道教育大学卒業後、信州大学研究生として教育社会学と言語社会学を学ぶ。美学校菊畑茂久馬絵画教場修了。デザイン会社「ASYL(アジール)」代表。1994年に『WIRED』日本版のアートディレクターとして創刊から参加し、1997年に独立。国内外で受賞多数。2003~2010年「Central East Tokyo」プロデューサーを経て、2010年よりアートセンター「3331 Arts Chiyoda」デザインディレクター。美学校「絵と美と画と術」講師。多摩美術大学教授。著書に『レイアウト、基本の「き」』(グラフィック社)がある。雑誌『デザインのひきだし』では「デザインを考えない」を連載中。また、3331コミッションワーク「そこで生えている。」の絵画制作を2013年以来継続している。
twitter / facebook



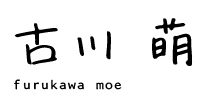 美術史家。ニューヨーク大学で西洋美術史を学んだのち、京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。現在、東京大学経済学研究科特任研究員。ルネサンス期における芸術家のイメージと、その社会的・政治的背景を研究。ルネサンス以降の芸術家像も研究対象。著書に『ジョルジョ・ヴァザーリと美術家の顕彰』。壺屋めり名義で刊行された『ルネサンスの世渡り術』も好評発売中。。
美術史家。ニューヨーク大学で西洋美術史を学んだのち、京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。現在、東京大学経済学研究科特任研究員。ルネサンス期における芸術家のイメージと、その社会的・政治的背景を研究。ルネサンス以降の芸術家像も研究対象。著書に『ジョルジョ・ヴァザーリと美術家の顕彰』。壺屋めり名義で刊行された『ルネサンスの世渡り術』も好評発売中。。