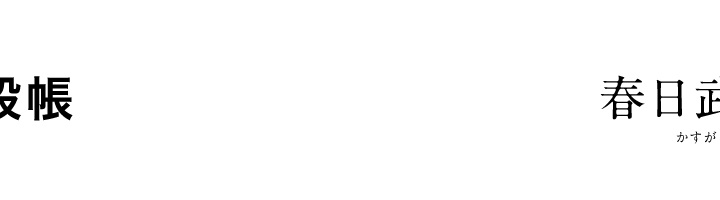精神科医、春日武彦さんによる、きわめて不謹慎な自殺をめぐる論考である。
自殺は私たちに特別な感情をいだかせる。もちろん、近親者が死を選んだならば、「なぜ、止められなかったのか」、深い後悔に苛まれることだろう。でも、どこかで、覗き見的な欲求があることを否定できない。
「自分のことが分からないのと、自殺に至る精神の動きがわからないのとは、ほぼ同じ文脈にある」というように、春日さんの筆は、自殺というものが抱える深い溝へと分け入っていく。自身の患者さんとの体験、さまざまな文学作品などを下敷きに、評論ともエッセイとも小説ともいえない独特の春日ワールドが展開していきます。
自殺について語るためには、やはり分類が必要だろう。そうしなければ話が散漫になってしまう。焦点がぼやけてしまう。だが、自殺の分類としてスタンダードなものは存在しない。そこで自己流に、原因別に、とりあえず七種類に分けてみたい。七種類というのに格別な根拠はない。思いつくタイプをあれこれ列挙してみたら自然に七つに落ち着いた。以下にそれら七つを列挙すると、
①美学・哲学に殉じた自殺。
②虚無感の果てに生ずる自殺。
③気まぐれや衝動としての自殺。
④懊悩の究極としての自殺。
⑤命と引き替えのメッセージとしての自殺。
⑥死を弄んだ挙げ句の自殺。
⑦精神疾患ないし異常な精神状態によって引き起こされる自殺。
列挙はしたものの、視点によってその自殺が二つの分類項目に跨ってしまったり(たとえば厭世自殺と呼ばれるものは②かもしれないし③や④⑥の可能性もあるだろう)、あるいは分類の困難なケースもありそうだ。それでも理念型として、こうした分類はやはり必須と思われる。人によっては、あらゆる自殺は⑦でしかないと主張するかもしれない。それも一理はあるけれども、自殺を理解するうえではそのような決めつけは粗雑に過ぎないか。
とりあえず、それぞれの項目について順番に論じていきたい。
美学・哲学に殉じた自殺
わたしの手許に一冊の古雑誌がある。『月光――LUNA』の1985年6月号で、表紙は憂い顔の短髪少女(高畠華宵の挿絵を拡大・トリミングしたもの)だ。この雑誌はいわゆる耽美派、今で言うところの腐女子御用達の雑誌であった。既に廃刊している。町田町蔵(現・作家の町田康)が率いていた人民オリンピック・ショウのインタビューが読みたくて購入したものの、雑誌全体のトーンには辟易した記憶がある。
さて件の6月号の特集は「自殺」であった。なぜそれを特集したのか、その趣旨はどこにも記されていない。唐突に「自殺」である。83年に京王プラザホテル屋上から飛び降り自殺を遂げた美形の俳優、沖雅也の養父であり同性愛関係を噂されていた日景忠男へのインタビュー「沖雅也と私」に頁がかなり割かれており、もしかするとインタビューが成功したのでそこから遡行して自殺特集が企画されたのかもしれない。
特集の巻頭には無署名で「自殺の研究」という文章が載せられ、その冒頭部分は、
フランスのダダイスト、シュールレアリストのルネ・プレヴェルは、自分の仲間達が作った芸術雑誌、『シュールレアリスム革命』が、“自殺は解決策になるか”という企画を立てて、アンケートを募ったとき、「ガス・ストーブに紅茶のポットを置く。窓をきちっと閉める。ガスの栓をひねる。マッチの火をつけるのを忘れる。悪い噂はたたないし、懺悔のお祈りを言う時間もある……」と答えた。
――となっている(アンケートが行われたのは1925年で、1936にルネ・プレヴェルは実際にその通りの方法で自殺を遂げた)。この妙に日常とシームレスにつながった自殺方法をおそらくチャーミングだと言いたい気配が窺え、それこそ「いかにも」な冒頭なのであった。したがって特集内容はまさに推して知るべし、自殺への素朴な憧憬と美化といった案配である。
さてこのような雑誌から話を始めたのは、耽美的とか孤高を愛するとか猥雑な現実を憎むとかそういったベクトルと自殺とは確かに親和性が高いと思えるからである。言い換えれば、老いや衰え、劣化、妥協や迎合や凡庸を憎み、そんなものに支配されてしまうくらいならばいっそ自死を選ぶことこそ純粋な精神のありようであるといった価値観である。さきほど名前の出た沖雅也は三十一歳で自ら命を絶ったが、超ナルシストであった彼は常々「三十歳を過ぎたら俺は死ぬ。年老いて醜い姿をしてまで生きたくはない」と洩らしていた。その覚悟を実践したというわけである。
ただし彼は精神的にかなり不安定で、死の数年前から抗うつ剤を服用し、その副作用で浮腫(むく)みや肥満、体調不良に悩まされていたという。そうなると自殺の理由は精神疾患に由来する現実検討能力の低下や副作用に基づく容姿の劣化に帰すべきかもしれない。いかに強烈な美学があったにせよ、あながち「三十を過ぎたら老醜」といった単純な話ではなかったらしい。
美学に殉じた自殺は見せかけにすぎない
年齢を重ねることを成熟とか円熟とは捉えない人たちがいる。彼らには老いることを「純粋さや瑞々しさ、柔軟さや閃き、率直さや真摯さ等の喪失」とか「俗悪な世の中に魂を汚されていくプロセス」と見なす視点があるようだ。若さはピュアで美しいと信じたくなる気持も分かる。夭折に憧れ、ロックミュージシャン27歳死亡伝説を信奉し、左翼活動家のジェリー・ルービンの言葉“Don’t trust over 30“に共鳴し、エゴン・シーレの展覧会のポスターを壁に貼り、ランボーやラディゲやサリンジャーを本棚に潜ませなければ、まっとうな青春を送ったことにはならないだろうし。
けれども、三十歳になったからオレはもはや信用に値する人間でなくなってしまった、と嘆きつつ潔く自殺した人は本当にいるのだろうか(ジェリー・ルービンはぬけぬけと変節を遂げ、ウォール街でトレーダーとなって大儲けし、やっと五十六歳で交通事故死したクソ野郎だ)。自分はオジサンやオバサンにしか見えなくなってしまったと気落ちすることはあっても、だから自ら死を選ぶ人などいるのだろうか。沖雅也にしても、実はうつ病が最大の原因で、そこに抗うつ剤の副作用とか他の要因が絡んだだけではないのか。生きながらえたまま若作りに腐心したり整形を繰り返すほうが、その見苦しい態度においてよほど人間らしくリアルだ。美学に殉じて自死するというのは、もしそんな人物がいたとしても、本当はもっと別な原因が潜んでいてそこに乗じる形で美学的問題が前景化しているだけのように思えてならない。
というわけで美学に殉じた自殺というものは、たとえあったとしてもそれはレアケースか「そのように見せかけただけ」ではないかと勘ぐりたくなる(美学をロマンチックと読み換えれば、心中の一部はなるほどロマンチックに殉じたケースでありそうな気はする。複数の人間が意気投合すると、アクション発動の閾(しきい)は急に低くなるのが通例である)。にもかかわらず、少なくともわたしは「美学に殉じた自殺」といった項目を立てずにはいられない。なぜなら自分なりの美学を貫く生き方をする人たちは決して稀ではなく、ならばその延長として「美学に殉じた自殺」といったものをもつい反射的に想定したくなってしまうからである。
だが主義としての生き方と「それに殉じて自ら死を選ぶ」こととは、決して直結しているわけではあるまい。直結させたくなる心性は、まことしやかな都市伝説に惹かれる安易な心性と大差がないだろう。やはり死は特別なことであり、死を前にすれば信念も美学も平気で撤回しかねない――そんな「人としての弱さ」を認めてこそ、世の中を理解し許容出来るようになる筈だ。
ネットで、美男美女の俳優やミュージシャンたちが加齢や病気、整形の失敗などで「こんなになっちゃいました」という残酷な写真を見つけることは簡単だ。わたしはこういった写真を眺めるのが大好きで、いったいどうやって過去の自分と現在の自分との折り合いをつけているのだろうと想像するのがまことに楽しい。ざまあ見ろといった意地悪な気持も満喫する。いや、そういったものをも提供してこそのスター稼業ではないのか。
見る影もなくなったスターたちが、絶望だか恥ずかしさだか自己嫌悪で自殺することは滅多にない。自暴自棄がせいぜいだろう。それなりに工夫して自己正当化するのか、諦めるのか無視するのか、さまざまな作戦が総動員されたに違いない。だがそんな彼らを不純で見苦しい奴らであるとわたしは思わない。やっと彼らも理解可能なリアリティーを感じさせてくれるようになったなあと、親しみを覚えることになる。自分の不細工さに絶望して自殺しなくてよかったなあと、老境のわたしは若い頃を振り返って胸をなで下ろしたくなる。
ヴィスコンティ監督の『ベニスに死す』でタジオ役を演じたビョルン・アンドレセン(1955年生まれ)は、究極の美少年的な賛美をされたが結局は一発屋的な存在に終わり、今では家庭を持ち音楽教師として生計を立てている。近影を見ると、ジゴロのなれの果てみたいで(皺だらけだが、肥満していないのはさすがである)、相応の常人離れした迫力はあるものの「あの美少年が……」と絶句する。そしてその絶句を味わいたい人がいかに多いのかは、ネットで検索すれば過去と現在の比較写真が実に沢山出てくることからも分かる。比較写真を眺める我々のほとんどは、一瞬、若さと美しさを失ったために自殺を図る三十歳のビョルン・アンドレセンという物語を反射的に思い描いてしまう筈だ。でも彼でさえ、ふてぶてしく生き続ける。カッコいい/カッコ悪いの双方を往き来しながら、両義的に生き続けるのである。
リアルタイムで『月光――LUNA』を愛読していた若者たちが、今ではコレステロール過多の鈍重な中年になり果てているのかと思うと、それもまた人生の味わいだねと訳知り顔で呟きたくなる。
哲学的自殺とは
自己愛に殉じた自殺にすぎない
哲学的自殺(美学に殉じたケースと同様、抽象的理念に導かれた自殺という分類になる)というのはどうだろうか。このテーマでは必ず取り沙汰されるのが、藤村操(みさお)(十六歳の男性です)の案件である。明治三十六年五月二十二日、当時一高(旧制第一高等学校)の一年に在学し、英語の時間には夏目漱石の講義を受けていた藤村は、日光華厳の滝へ身を投げて自殺を遂げた。
この自殺が世間の耳目を集めたのは、彼の自殺の理由が失恋や病苦、金銭的問題といった世俗的なものではなく(自宅は裕福だったし、当時の一高生は超エリートで将来を約束されていた。しかも彼は美少年であったという)、哲学的煩悶の挙げ句に死を選んだからだった。それだけではない。藤村は滝壺に近い場所に生えていた大きな楢の木の表面をナイフで削り、そこへ辞世の言葉、いわゆる「巌頭之感」を墨で書き残した。これが文の調子のみならず一種のパフォーマンスとして、おそらく世の人々には颯爽たるものと映ったのではないか。以下が「巌頭之感」の全文である。
悠々たる哉(かな)天壌、遼々たる哉古今(ここん)、五尺の小軀(しょうく)を以つて此の大をはからむとす。ホレーショの哲学竟(つい)に何等のオーソリチーに値するものぞ。万有の真相は唯(ただ)一言にて悉(つく)す、曰(いわ)く不可解。我この恨(うらみ)を懐きて煩悶(はんもん)、終(つい)に死を決するに至る。既に巌頭に立つに及んで、胸中何等の不安あるなし。始めて知る大いなる悲観は大いなる楽観に一致するを。
妙に人の心を高揚させるようなトーンに満ちている。この事件を本邦初の哲学的自殺として世間に喧伝し煽ったのは、赤新聞として知られていた『萬(よろず)朝報』の主催者、黒岩涙香であった。彼は藤村操が自殺した四日後に同紙へ「少年哲学者を弔す」という文章を寄せ、「我国に哲学者無し、此の少年に於て初めて哲学者を見る、否、哲学者無きに非ず、哲学の為に抵死する者無きなり」と賞賛した。もっとも黒岩は、自著『天人論』をこの事件に絡めて宣伝するべく筆を執ったらしいが。
大原健士郎は自殺研究の草分けとして知られる精神科医だが(故人)、彼が一般向けに書いた『自殺日本――自殺は予知できる』(地産出版1976)によると、「いずれにしても、この華厳滝は、藤村操のおかげで自殺の名所になった。その当時の村役場には、変死体第一号に〈藤村操〉の名が書かれ、その理由として〈哲学的自殺〉と書かれているそうである。その後も陸続として自殺があとを断たず、自殺者の数は流行的に、爆発的に多くなったと伝えられている」。確かに連鎖自殺は大変な勢いであったらしく、藤村の死から四年間のうちに華厳の滝へ身を投げた者は未遂を含め一八五名に達している。
どうやら哲学的自殺なるものは、藤村操のそれを契機に人が死ぬための新しい口実を提供する結果となったようなのであった。ひとつの発明と評価すべきなのかもしれない。朝倉喬司は『自殺の思想』(太田出版2005)で藤村の書いた手紙について述べる。
多出するボキャブラリーは、主観、客観、悲観、解釈、懐疑、知識、空間、時間、哲理、そして「巌頭の感」を彩って、やがて流行語のようになった煩悶、等々、抽象的な概念を表すものがほとんど。またその大部分が、明治になって西洋の諸学、諸思想を輸入する際の、いわば受け皿として、漢語や仏教用語をベースに新たに「創られた」語である。まあこれは、志望が哲学研究であり、一高入学直後のころ、安部に、「ぼくは科学、倫理、宗教を超越せる純正哲学をやるつもりだ」と豪語したのだという藤村にしてみれば、当たり前の話ではある。私の現在からする関心の焦点は、こうした、新たに「創られた」抽象言語思考を、当たり前に使いこなせるようになった藤村の世代に、(おそらくはそれゆえに)自殺の、デュルケム(引用者注 フランスの社会者・哲学者、1858〜1917、1897年に『自殺論』を刊行。)のいう新たなタイプが「創造」されたことにある。
これはなかなか興味深い指摘だろう。なるほど新たに創られた抽象言語が不安定な若者の心に独特なドライブを加え、死こそが精神の純粋さを裏書きするといった発想を励起したのかもしれない。呉智英は「虚無に向きあう言葉」という論考(別冊宝島『自殺したい人びと』宝島社1999所収)で述べる、「この文体には、自らの自意識が近代という新時代の最先端にあるという藤村操の矜持が感じられる。それが青年の客気によるものだとしても、どこか人の心に響くものがあるのはこの矜持の故である」と。
朝倉の本には、次のような記述もある。
藤村は死の一ヵ月前ころ、一高でつき合いのあった魚住影雄に「煩悶ということはその言葉さえ快い」と、ふともらしたのだという。
また、やはり一高での友人、藤原正と、上野の森を散歩しながら「願わくは悶えわれ死なむ、おつに覚りてすまさんよりは」と、歌を口ずさみ、藤原に向かって「これがぼくの辞世だよ、よく憶えておいてくれ」と言ったのだと伝えられている。
煩悶する自分に酔っていたというわけだろう。矜持もあれば自己陶酔もあった。こうなると、むしろ自己愛に殉じた自殺と見なしたほうが適切なのかもしれない。そもそも、なぜ「巌頭之感」なんて大仰なものを書き残したのか。もっとさりげなく死ねなかったのかよ、と嫌味半分に言ってみたくなる。煩悶がそんなに偉いことなのかよと問い掛けてみたくなる。硯やナイフや蝙蝠傘まで持って自殺の場所へ赴くのは、ちと「あざとい」感触が透けて見えないか。
実は失恋が本当の自殺の理由であったという説は、過去に何度も唱えられてきた。こうした俗な理由であるほうが、我々凡人には納得がいくからであろう。あるいは、源義経のように藤村操生存説といったものもいくつかある。泉鏡花の新聞連載小説『風流線』のストーリーが藤村操生存説を取り込んでいるらしいが未見である。鏡花の文章は、いまひとつ読みにくくて苦手なのである。
珍品としてはミステリ作家・斎藤栄の『日本のハムレットの秘密』(講談社1973)がある。この小説では、藤村の投身は偽装自殺であり「巌頭之感」には暗号が隠されているという奇抜な説が披露される。「巌頭之感」において「ホレーショの哲学」という語句が出てくるが、ホレーショとは戯曲ハムレットにおいて狂言回しの役で登場する人物の名前であり、その関係から書名が日本のハムレットの秘密となっている。
では肝心の暗号についてはどうか。まず「巌頭之感」を句読点を手掛かりに十のセンテンスに分ける。
悠々たる哉天壌、/遼々たる哉古今、/五尺の小軀を以つて此の大をはからむとす。/ホレーショの哲学竟に何等のオーソリチーに値するものぞ。/万有の真相は唯一言にて悉す、/曰く不可解。/我この恨を懐きて煩悶、/終に死を決するに至る。/既に巌頭に立つに及んで、胸中何等の不安あるなし。/始めて知る大いなる悲観は大いなる楽観に一致するを。
それから、それぞれのセンテンスの頭の音を拾う(遼々は、旧仮名なので「り」ではなく「れ」)。すると【ゆ れ ご ほ ば い わ つ す は】となる。で、ここから先が何だかよく分からないのだが『華厳唯心義釈義』という書物を参考に並べ直す。すると、【ごゆはすつ いわばほれ】すなわち「五湯は捨つ 岩場掘れ」となる。というわけでいきなり塩原温泉の五色の湯へ主人公は辿り着き云々、と、最後はもう話がぐだぐだで訳が分からない。藤村操がわざわざ偽装自殺をした理由も判明しないのである。とにかく終わりのほうにこんな文章がある。
藤村操は、巌頭之感に遺したように、奥塩原に、他人には言えない秘密をもっていた。そして、ある時期まで、世の中へ出ることを、自分自身で禁じてしまった。
だが、彼の秘密は、時の流れと、関東大震災の余波による山崩れで、永遠に、地底に閉じ込められたのである。
既に、生ける屍となった彼は、晩年、ひっそりと奥塩原の山林で還らぬ人となり、無縁仏の墓に眠った……。
私は、遂に、この結論をえたのである。
他人には言えない秘密が何であったかちっとも分からなかったし、暗号を残した必然性も判然としない。偽装自殺の理由も曖昧だ。尻切れトンボの実にひどい小説である。よくもまあこんなものを講談社は出版したなあと驚かずにはいられない。だが、「巌頭之感」に暗号が隠されているといった着想は悪くないし、とにかく強引にでもそのアイディアで五百枚を書き上げてしまったパワーは認めよう。これほどに「巌頭之感」は日本人の心に染み渡っているという傍証にもなるわけであるし。
能天気なインテリには哲学的自殺が
存在してほしい願望がある
哲学的自殺とは、つまり理念的・観念的な理由に基づいた自殺というわけであろう。雑誌『ユリイカ』の1979年四月号は特集が「自殺――破局への意志」となっていて、雑誌の性質上、芸術家の自殺についての論考が多く収められている。どれも浅い内容ばかりだが、浅さの極めつけは文芸評論家の故・磯田光一による「自殺と理想主義」であろう。いわく、「“Idealism ”が「理想主義」を意味すると同時に、哲学上の概念として「観念論」をも意味することは、自殺の構造を考える上できわめて示唆的なことと思われる。理想主義者の目にうつった世界は、主観によって構成された観念の世界といってよく、ここに成立しているのはゾルレンとしての観念と、ザインとしての現実界との分裂状態といってもさしつかえあるまい。このとき自殺とは、「あるべき自己」と「げんにある自己」との間に一定以上の距離ができてしまったとき、前者を証明するために後者を物理的に抹殺する行為ではないであろうか」。
いかにも上滑りな論述である。「ないであろうか」かよ、ムカついてくるな。しかも、こんなことまで磯田は書き綴るのである。
自殺のすべてが理想主義の表現であるとはいいきれない。肉体的苦痛から逃れたいための自殺は、おそらく「安楽死」に近接している。最近の自殺についていうとき、日商岩井の乗務の自殺には、「義理」「世間体」などが作用していて、内心の苦痛から逃れたいという願望も強かったであろう。
他方、某大学教授の子息が祖母を殺し、理路整然たる遺書を残して自殺したが、あの遺書は通常の道徳観念からみてどんなに歪んだものであろうと、哲学的自殺者を想わせる。そこには少なくともラスコーリニコフの思索の萌芽に相当するだけのものはある。これを裏返しの表現をとった理想主義と呼んで悪い理由があるであろうか。文学の“毒 ”は、いまやあの少年の遺書のようなところにしかなくなってしまったらしいのである。
何が文学の毒だよ、とそれこそ毒づきたくなってくる。インテリを自認する脳天気な輩が、いかに自殺を観念的に扱うかの見本としか思えない。
ここで「某大学教授の子息が祖母を殺し、理路整然たる遺書を残して自殺した」と述べられている事件は、1979年一月十四日に世田谷で起きた通称「朝倉少年祖母殺害事件」のことである。磯田が哲学的自殺者を想わせると言うからには、どんな出来事であったかとりあえず調べてみたくなるのが人情だろう。
概要は簡単である。当時十六歳(五歳下に妹がいる)、早稲田高等学院一年生の朝倉泉(男性)が六十七歳になる祖母を惨殺、ほどなく犯人の泉は飛び降り自殺を遂げたというものである。ただし、事件を特徴づける用件がいくつかあった。
まず、エリート一家で起きたということ。泉の父はお茶の水大学教授、母は津田塾大卒の脚本家、母方の祖父は東大卒の著名な仏文学者。そして父は東大で祖父の教え子でもあった。こうした人々の三世代家族で事件は起きたのである。もうひとつは、泉が長大な遺書を残して自殺したという点である。その遺書は自分をエリートと自称し、きわめて傲慢かつ誇大的なものであった。さながら中二病の延長のような遺書の存在こそが、この事件を忘れ難いものにしたと言えよう。
泉は祖母に溺愛されて育った。母は脚本家で忙しく、父は研究一筋といった調子で、両親よりも祖母が生育に熱心な家庭だったのである。泉は成績優秀で、だが中学生頃には小説に目覚めて成績が急落するも、スパルタ式の塾に通うことで学力を取り戻す。頭の良い生徒にありがちなパターンであり、だが彼は塾で誤ったエリート主義を叩き込まれてしまった気配がある。中三で両親は離婚、父が家を出て行った。そのため、なおさら祖母の過干渉が著しくなった。慶応高等部の受験は失敗、早稲田高等学院へ入学した後は成績も立派だったが、1979年一月十日に長文の遺書を完成させ、さらにはそのコピーを三部作成、「朝日」「読売」「毎日」の三大新聞社へ送りつけるつもりだったがそれは実行しないまま、同年一月十四日正午頃、祖母の部屋(彼女の部屋と泉の部屋はドア一枚でつながっており、鍵はなかった)にて彼女の頭を金槌で殴打、続いて錐や果物ナイフで滅多刺しにして失血にて死亡させた。ほどなく泉は自宅を離れ、約二キロ離れた小田急線経堂駅北口ビル十四階から飛び降り自殺をして死に至った。
さて泉が残した遺書とはどのようなものであったのか。自室からは二冊の大学ノートが発見され、一冊には犯行計画(シナリオ)が4頁にわたってメモされていた。これを読むとアリバイ作り云々などと完全犯罪を目指していたようで(どこまで本気であったのかは判然としない。また、計画通りに犯行は行われていない)、だが犯行後には自殺する意志があったこともまた記されていた。
もう一冊には、四百字詰め原稿用紙で九十四枚に相当する遺書が黒のボールペンで書き記され、字は丁寧で誤字脱字もほぼ見当たらなかったという。遺書は六章に分かれ、
第一章 総括
第二章 大衆・劣等生のいやらしさ
第三章 祖母、母
第四章 妹
第五章 むすび
第六章 あとがき
で構成されている。
第一章では、「私の、今度の事件を起こした動機をまとめておく」として以下の三つを列挙する。
1,エリートをねたむ貧相で無教養で下品で無神経で低能な大衆・劣等生どもが憎いから。そしてこういう馬鹿を一人でも減らすため。
2,1の動機を大衆・劣等生に知らせて少しでも不愉快にさせるため。
3,父親に殺されたあの開成高生(引用者注 壮絶な家庭内暴力を重ねていた当時十六歳になる開成高校生の息子を、このままでは息子は犯罪者になってしまうと憂慮した父親が1977年十月三十日に絞殺、その後自首した事件)に対して低能大衆がエリートにくさのあまりおこなったエリート批判に対するエリートからの報復攻撃。
イライラしているのは分かるが、まとまりに欠ける条文である。祖母もまた貧相で無教養で下品で無神経で低能な大衆・劣等生に属するということになるらしいが、彼女はエリートの一族の一人ではなかったのか。どうも矛盾している気配が窺える。でも本文は意外にもしっかりしていて、たとえば第三章における母親の観察などは冷静かつシニカルで上手いものである(書いた当人はまだ十六歳なのである。ただし当人は、筒井康隆の文体を借用したと第五章で述べている)。一部分を引用してみよう。
勝気という性格があまりにも強いので、普通お嬢さんとして育てられた女性が多かれ少なかれ持っているはずの「たおやかさ」とでも言うべきものが母には全くない。勝気。母のいやらしさはこの一語に集約される。勝気で、誰にも遠慮することなく育ってきたから自分の感情を奥にしまってひきさがる、というようなことが全くない。常に自分の考えを堂々と述べたてて、決して物怖じしたりしない。これは大変結構なことであるが、それが女性でしかもそれがあまりに極端だと実に不快なものである。女性の美点の一つである慎み深さというものが全くない。
何だか夫の「ぼやき」みたいだが、読んでいると次第に泉に同情したくなってくる。さらに祖母(つまり母の母)は押しつけがましく頑迷で支配的、過大な期待を孫に抱き、思春期の少年に対してあまりにも無神経であったようだ(その一例が、祖母の部屋と泉の部屋とがドア一枚でつながり、鍵をつけさせなかったというエピソードにも現れている)。そのような母と祖母とに囲まれ、どうしようもなく苛立った気分が持続していたであろうことは容易に見当がつく。
エリート一家という自覚もなかなかのプレッシャーであっただろう。泉本人は自分をエリートと自称しているが、自分がさほどでもないことはしっかりと自覚していたのではないか。そもそも早稲田高等学院在学ではエリートには該当しまい。飛び級で一高に入った藤村操のような者をエリートと称するのである。そのことも彼は分かっていただろうし、高校に進学するとろくに勉強などしなくても優秀な成績を取って「あいつ、頭の構造が違うんじゃないのか?」と驚くような同級生に出会ったりもするものだ。下手をすると自分は落ちこぼれになってしまうのではないか、多少は気の利いた文章を書ける程度の才覚は持ち合わせていても、自分は突出した人間になれるだけの器ではあるまいと恐れていたのではないか。そしてそんな危惧を素直に認められるような環境に生活していたわけではなかった。
慢性のイライラと不安が、それを打ち消すべく滑稽なほどの傲慢さとなって頭のなかに渦巻くようになったのだろう。もしかすると犯行計画と遺書は、ある種のガス抜きに近い営みとして着手されたのかもしれない。だが切実な動機に拠るそれが心を鎮め、あるいは自分を客観視しさせ苦笑に至らせるべく作用せず、余計に苛立ちを煽ってしまった。遺書を記したがゆえに、彼はむざむざと事件の実現へと足を踏み出してしまった。遺書が二人の人間の命を奪ったのである。第六章の「あとがき」をここに引用するが、これはもう自分の限界を薄々感じつつもそれを認めようとせず必死に居直っているとしか思えない。
これまでいろいろ書いてきたが馬鹿な大衆はこういうことは無視し、すぐ忘れてしまうだろう。だが果たしてそれがなんであろうか。開成高校事件また私の事件が忘れられたあとも、この受験地獄・学歴地獄はまだまだ続く。永遠に続く。大衆の馬鹿め。おまえらはこれから受験地獄にさんざん苦しめられるのだ。ざまあみろ。エリートをねたんだ罰だ。さあ苦しめ! エリートを迫害した罪だ! さあ苦しめ!
受験地獄・学歴地獄の渦中にある泉の立ち位置を考えれば、馬鹿な大衆イコール泉本人としか読めないではないか。まさに自暴自棄そのものである。
さて、以上のようなあらましを踏まえて磯田は朝倉泉を哲学的自殺者と呼び、あの遺書に対して「そこには少なくともラスコーリニコフの思索の萌芽に相当するだけのものはある」と語り、さらには「文学の“毒 ”は、いまやあの少年の遺書のようなところにしかなくなってしまったらしいのである」と言い募るのである。わたしは事件を調べるうちに、正直なところ泉の不安に満ちた「強がり」にむしろ共感に近いものすら覚えた。だからこそくだらない殺人でありショボい自殺だと思うのである。いったいこれのどこが哲学的自殺なんだよ? 文学の毒などと小賢しいことを述べる磯田の尻を蹴り上げたくなるぜ。
どうやら少なからずの人たち――ことに小難しい本を読むような人たちには、哲学的自殺といったものが存在して欲しいという願望があるのではないか。少なくとも百%ピュアな哲学的自殺は、昭和三十一年発行の十円玉とかヒトとサルとのミッシングリンク、村上春樹が言うところの「完璧な絶望」のように「ありそうでない」ものだと認識しつつも、四捨五入すれば哲学的自殺に該当しそうなケースの存在を無意識の内に求めているような気がするのである。そうでなければ人間が矮小化されてしまいそうだし、磯田のような人間が活躍出来なくなるから。
まさに四捨五入という部分が重要だと思う。切り捨てた部分に世俗的な悩みや、ときには統合失調症につながりかねない過度の抽象的な思考、思春期ゆえの情動の不安定さなどが含まれる。でもそこには目をつぶり、哲学的自殺や美学に殉じた自殺といったものを我々はどうしても抽出したくなる。ただしそれを際立たせるためには、呉智英が指摘するように「矜持の有無」と、さらにはある種の高揚こそが要になるだろう。朝倉泉には高揚こそあったが矜持を欠いてしまった。本章冒頭に記した自殺分類に従えば、彼の自殺はあたかも「⑤命と引き替えのメッセージとしての自殺」のように映るが、実際には「④懊悩の究極としての自殺」および「⑦精神疾患ないし異常な精神状態によって引き起こされる自殺」の複合ではないかと思われる。泉は精神疾患ではなかったであろうが、置かれた状況から「異常な精神状態」に追い込まれていたとは考えられるのである。
といった次第で「①美学・哲学に殉じた自殺」という分類項目は、とりあえず挙げてはおいたものの、実は山海経に載っている怪物に近い「いかがわしげな存在」と見なしておいたほうが適切でありそうに思えるのである。
(第五回・了)
 1951年京都生まれ。日本医科大学卒業。医学博士。産婦人科医を経て精神科医に。都立中部総合精神保健福祉センター、都立松沢病院部長、都立墨東病院精神科部長などを経て、現在も臨床に携わる。著書に『無意味なものと不気味なもの』(文藝春秋)、『幸福論』(講談社現代新書)、『精神科医は腹の底で何を考えているか』(幻冬舎新書)、『臨床の詩学』(医学書院)、『老いへの不安 歳を取りそこねる人たち』(朝日新聞出版)、『鬱屈精神科医、占いにすがる』(太田出版)等多数。
1951年京都生まれ。日本医科大学卒業。医学博士。産婦人科医を経て精神科医に。都立中部総合精神保健福祉センター、都立松沢病院部長、都立墨東病院精神科部長などを経て、現在も臨床に携わる。著書に『無意味なものと不気味なもの』(文藝春秋)、『幸福論』(講談社現代新書)、『精神科医は腹の底で何を考えているか』(幻冬舎新書)、『臨床の詩学』(医学書院)、『老いへの不安 歳を取りそこねる人たち』(朝日新聞出版)、『鬱屈精神科医、占いにすがる』(太田出版)等多数。