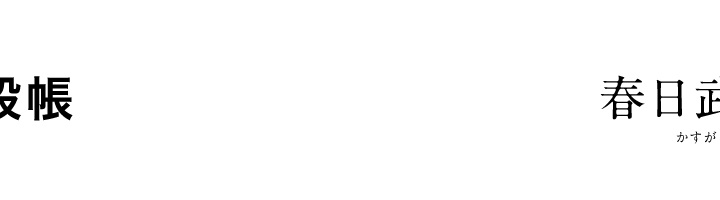精神科医、春日武彦さんによる、きわめて不謹慎な自殺をめぐる論考である。
自殺は私たちに特別な感情をいだかせる。もちろん、近親者が死を選んだならば、「なぜ、止められなかったのか」、深い後悔に苛まれることだろう。でも、どこかで、覗き見的な欲求があることを否定できない。
「自分のことが分からないのと、自殺に至る精神の動きがわからないのとは、ほぼ同じ文脈にある」というように、春日さんの筆は、自殺というものが抱える深い溝へと分け入っていく。自身の患者さんとの体験、さまざまな文学作品などを下敷きに、評論ともエッセイとも小説ともいえない独特の春日ワールドが展開していきます。
虚無感の果てに生ずる自殺
名を隆太としておく。年齢は二十代後半、もう三十に近かったいわゆる服毒(服薬)自殺には、感情の勢いにまかせて「死んでやる!」とばかりにそれを一気に呷る場合と、覚悟を決めて静かに飲み下す場合の二つがありそうな気がする。後者においては、毒を嚥下した途端に死亡するのならともかく、じわじわと効果が出てくるケースでは、当人は今こそリアルに死と(あるいは生と)対峙することになる。それはどれほど濃密な時間となるだろうか。
そんなことを思っていたら、島影盟『死の心境――遺言辞世の研究』(教材社、1937)という本に、カルモチン(一般名はブロムワレリル尿素。ブロバリンという商品名でも流通し、自殺にしばしば使われた。わたしの母親はブロバリン依存症の傾向があり、ときおりアルコールと併用して心肺停止寸前に陥っていた。これはなかなか強烈な記憶で、そうしたものが伏線となって当方は精神科医になったのかもしれないと考えることがある)で自殺を図った人物の遺書というか本人による実況中継が載っていた。「原因は不明であるが、カルモチンで自殺した職人風の男の手記」と前書きが付されている。
己は今カルモチンを飲んだ。飲みにくくて、水を飲みながら。(四時四十分)何分経つたら筆が止るか? 二分経った、何ともない。口の中に泥でも入れた様だ。三分経った。バットを一本のむ。ゲップが出る。四分、まだ何ともない。唯ラムネを飲んだ時のやうだ。五分、煙草を盛んに吸つてゐる。六分、自分の書いたものを読んでみる。七分、飲んだカルモチンの利き目がない。八分、これでは何もならない。三原山行としようか? 十分、何ともない。おけさでも一つ唄はうか? 十二分、雪の新潟吹雪で暮れる佐渡は……
とくに著者・島影のコメントはなく、ただし「ここで記録が切れているのをみると、十二分から一分か二分のところで意識を失ったのであろう」と、ひどく当たり前のことのみが書き添えられている。
この手記がどんな経路で著者の手に渡ったのかは不明である。警察関係とコネでもなければ、入手は難しいのではないか。いや人権やプライバシーの意識に乏しい時代だったから、新聞記者でもしていれば案外簡単に手に入ったのかもしれない。島影の本には、服毒自殺をした人物の、服毒後から意識消失までの間に書かれた手記がこれ以外にも三篇掲載されており、そもそも服毒自殺を図る人物は手記を書きたがるものなのかどうか。まさか捏造というわけでもあるまいが、右に引用した手記にしても「十分、何ともない。おけさでも一つ唄はうか?」なんて件はリアルそのものであるようにも、否まさに小賢しげなフィクションの証左であるようにも思えてしまう。
著者である島影盟は、検索してみるとちゃんと名前が出てくるものの経歴不詳となっている。1902年に生まれ1983に亡くなった評論家で、人生論や幸福論、運命論や手紙の書き方、宗教批判など多岐にわたる著作が数多くある。『死の心境――遺言辞世の研究』は三十五歳のときに書かれたもので、年齢の割には達観した筆致であるうえに資料がやたらと豊富なのである。興味の惹かれる人物ではある。
さて、「カルモチンで自殺した職人風の男の手記」をあらためて読んでみると、不安や絶望や悲しみや怒りといった生々しい気分や激しい感情は既に通り越し、もはや実験動物を眺めるかのように淡々と自分を観察している。「おけさでも一つ唄はうか?」などと書いても、およそユーモラスな感情など伝わってこない。芥川が述べる「僕の今住んでゐるのは、氷の様に澄み渡つた病的の神経の世界である」に近い。
底なしの虚無感に支配され、氷のように澄み渡った心境に至ってもなお、人は軽口めいたものを発してしまうようだ。昭和二十四年十一月二十四日深夜、一人の高利貸しが青酸カリを飲んで自殺した。彼は自らが営む銀座の金融会社の社長室で、香を焚き、机には背広姿の自分の写真、愛人であった八人の女性の写真をずらりと並べ、その写真と向きあうようにして(つまりいささかドラマチックな舞台を自分自身で作り上げて)、服毒前から書き始めていた遺書を書き終えようとしたのだった。
一、御注意、検視前に死体を手にふれぬこと、法の規定するところなれば京橋警察署にたゞちに通知し、検視後法に基き解剖すべし、死因は毒物は青酸カリ(と称し入手したるものなれど渡した者が本当のことをいつたかどうか確かめられたし)死体はモルモットとともに焼却すべし、灰と骨は肥料として農家に売却すること(そこから生えた木が金のなる木か、金を吸う木なら結構)
二、望みつつ心安けし散るもみじ理知の命のしるしありけり
三、出資者諸兄へ、陰德あれば陽報あり、隠匿なければ死亡あり、お疑いあればアブハチとらずの無謀かな、高利貸冷たいものと聞きしかど死体さわれば氷カシ(借自殺して仮死にあらざる証依而如件)
四、貸借法すべて青酸カリ自殺晃嗣、午後十一時四八分五五秒呑む、午後十一時四九分ジ・エン
右が遺書の全文である。ジ・エンドの「ド」を書き記す前に絶命してしまったのであろう。「陰得」と「隠匿」、「氷カシ」と「高利貸し」、「青酸」と「清算」等々無闇に駄洒落めいた言葉がちりばめられ、死に臨んでもやはり(あるいは、だからこそ)人は「軽口めいたものを発して」しまいかねないものなのだなあとあらためて複雑な気持にさせられる。
偽ニヒリストが自分で用意した
陳腐な花道が自殺だった
この高利貸しは山崎晃嗣という二十六歳の東大法学部学生で(学生にしては年齢が高いのは、学徒動員のブランクによる)、彼は通称「光クラブ事件」の主役として知られている。
山崎晃嗣(1923~1949)は典型的なエリートであった。父は裕福な医師であり木更津市長でもあったし、彼は一高東大で優秀な成績を修めた。(にもかかわらず)在学中に金融業「光クラブ」を設立、社長が東大生であり、また巧みでモダンな広告――すなわち高利貸しにつきまといがちな暗く胡散臭く怪しげな印象を払拭したイメージ戦略によって、たちまち頭角を顕した。山崎の鋭利な頭脳によって導き出された巧妙な法解釈や強気の経営方針によって勢力は拡大し、光クラブは敗戦直後の混乱の中でまさに光り輝く企業へと登り詰めた。
だが昭和二十四年に彼は物価統制令違反で逮捕される。山崎の主張が通って起訴は免れたものの出資者からの信用を失に出現した光クラブは、わずか十四ヵ月ばかり世間を大いに騒がせた挙げ句、呆気なく闇に吸い込まれてしまった。
この事件が世間の記憶に深く刻まれたのは、いわゆる「アプレゲール犯罪」のひとつと目されたからである。
アプレゲールとは、戦前戦中の保守的な価値観を否定し(いや、むしろ嘲笑し)、享楽的・退廃的・奔放横恣な、つい、以後はすべての対応が裏目に出て三千万円の債務履行が不可能となり、前述した通りに彼は青酸カリ自殺を遂げたのだった。突然変異のようまりノーフューチャーで刹那的な価値観を持つ若者たちを指す。光クラブは従来の高利貸業よりも明らかに垢抜けてカッコよかったし、社長が東大在学中という意外さも戦後の新しさとオーバーラップしただろう。そしてあれよあれよと輝きを増し、さしたる未練もなく空中分解してしまった。おまけに社長は普段からクールきわまりない発言を繰り返していたし、自死に臨んでは世間を小馬鹿にするような遺書を残した。山崎晃嗣は旧世代に対し、彼らを揶揄するかのような慇懃無礼な態度を貫いて死んでいったように映ったのではないか。
唐木順三は昭和二十五年の『展望』四月号で、山崎が座談会で発言した記録(『婦人公論』昭和二十五年一月号。座談の相手は作家の丹羽文雄と小谷剛)を雑誌で読んだ感想としてこんなことを述べている。
……山崎なる特異な人物がいつも頭のどこかを刺激してくるような思いをした。出会ったらちょっとやりきれない男だったろう。「ございます」口調の、高い鼻に銀ぶちかなにかのめがねをかけたような男、失恋してどんな気がしたかと問われて、「味わい深うございました」などと、しゃれ気もなく答える二十何歳の学生には横を向きたくなったに違いない。
しかし、戦後の無軌道な社会、既成の生活基準が崩壊し去り、新しいモラルが単に言葉としてしか用意されなかった時代にあって、みずから「合意によるものは拘束されるべし」という単純な標語をかざし、そこに生き、そこに死んでいったこの青年は、戦後の一現象としてみるだけではかたのつかないものをもっている。
不快感を表明しつつも無視し得ないという唐木の苛立ちが、ありありと伝わってくるではないか。
まったくのところ山崎晃嗣には実も蓋もないところがあり、「合意は拘束さるべきものでございますから、一度約束したものは必ず履行しなければならぬというだけで、これは私の世界観に基づく行動です。それは私の決めた基盤だからそれによって行動いたしますが、それ以外に人の決めたものには従うことはないというわけでございます」と述べたり、自分は理論通りに生きてきた自信があるがその理論の根本は信仰であるゆえ、自分が自分の理論に負けたら死ぬべきであるといった発想を開陳している。しかもその考え通りに、自分の理論に負けたときを以て彼は本当に自殺を遂げている。もしかしたらこの人は、食べ物ではなく電気で動いているのではないかと疑いたくなる。
一高時代の山崎晃嗣は、寮で暮らしていたにもかかわらず仲間に身の上話や打ち明け話など一切したことがなかったという(保阪正康『真説 光クラブ事件』角川書店、2004より。本稿の資料の多くはこの本に拠っている)。血気盛んな一高生においてこれは少々特異であろう。寮で同室であった高橋康之(数少ない山崎の友人の一人)は、「週刊朝日」昭和二十四年七月三十一日号で、山崎は「別に金に執着があるわけではない。儲けることそのものに、快感を感じていたわけでもない。彼は自分の合理主義を実証したかっただけ」と語っている。なるほど筋金入りのニヒリストといえようか。
もともとクールで超然とした山崎であったが、学徒動員による軍隊生活で彼はいよいよ人間不信を募らせたようであった。復学後の山崎は東大の授業で全科目に「優」を取るべく猛勉強を始める。その対策が常人離れをしている。彼は「時計日記」というものをつけ始めるのだ。それは一日二十四時間を三十分刻みの目盛りのついた図表とする。そして何をしたのか、どれほどの時間を要したのか、さらにはそれが自分にとって有益であったか否かの評価を記入する。経済原論やロウマ法を勉強したとか、「朝食、新聞etc」「反省、思索」「洗ひものetc」などの項目に混じって「T.Tと性交、料理食事、たはむれetc」などという記述も混ざる。女性関係でもそれが有意義に過ごせたか、それとも面白くなかったかについて記号で評価を記入している(彼は女性を性欲の捌け口としてしか見ていなかった)。どうも強迫的で、しかも日常のすべてを有益だったかどうかで点数化するなどあまり健康的な精神とは思えない。
山崎晃嗣は一高時代から「数量刑法学」なるものを打ち立てる野心があったそうである。保阪の本から「週刊朝日」昭和二十四年十二月十一日号の記事を孫引きすると、
当時(注・一高から東大法学部に合格したころ)私は数量刑法学……ともいうべき一つの学問体系をつくろうと思っていた。全刑罰法規全体を総合考察して、法定刑における刑罰数量の論理的構成を明かにして量刑上の処断を限定するもので、建築技師が対数表によって設計するように、裁判官は、この刑罰数量表によって合理的に判決できる。
つまり裁判官は判決を下す際に、さまざまな要素をマニュアルに定められた数値に換算し、その総合点を以て自動的に刑罰の重さを弾き出すというシステムである。こうすれば曖昧さや余計な感情が入り込む余地がなかろうという考え方だ。
これもある種の非情さ・超然さを反映した発想なのだろう。ただし個人的な感想を申せば、このように点数化や数値化で「合理的に」ものごとを判断するといったアイディアに取り憑かれるタイプの人間は、おしなべて「一見したところは利口だが最終的には頭の悪い」輩に多い。勤務評定や人物評価において似たような方式を導入して失敗した企業は少なくないし、精神医学における診断で同様な方式を導入したのがアメリカ精神医学会の定めるDSMという体系であるが、これまたまことに底の浅い人間理解ぶりを露呈しただけであった。閃きを欠く退屈人間が飛びつきがちな愚かしいアイディアの典型だ。
不健全で浅薄な合理主義に山崎はどっぷりと浸かっている。「時計日記」や「数量刑法学」からは、微妙に的外れで空疎なトーンが強迫的な心性とともに伝わってくる。精神科医としては、統合失調症や発達障害に親和性があるようにも思うけれど、彼が治療対象に相当するとは思えない。さらに言い添えれば、戦前であろうとこうした類の人間は一定数いた筈で、ことさらアプレゲールといったレッテルを貼る理由もあるまい。
いったい山崎晃嗣を虚無的人間、ニヒリストと見なせば彼の言動や自殺はすべて説明がつくのだろうか。
ノンフィクション作家の保阪正康は『真説 光クラブ事件』のあとがきで「山崎は戦後日本の俗物性を心から呪い、そしてそれを徹底して軽侮することによって時代に刻印を残そうと企図したのである」と述べている。彼のキャラクターには演技的な成分があり、確信犯的に世間を騒がせたのではないか。つまり冷え冷えとしたニヒリストを山崎は装っていたものの、実際には怒りや軽蔑といった人間的なものがしっかり精神に宿っていたのではないか、と。なるほど山崎をすべて虚無的といった「便利な」言葉で総括してしまってよいものかと、わたしもいささか首を捻りたくなるのだ。
そもそも虚無的であるとは、いかなる事物に対しても徹底的に意味や価値を認めない姿勢であろう。そんな人間が、なぜ東大に入ったり成績で全「優」を目指したり、あるいは高利貸しなどを営むのか。光クラブ設立について友人の高橋康之は「彼は自分の合理主義を実証したかっただけ」と語っているわけだが、実証したがった時点で自分の合理主義に意味や価値を認めてしまっているのだから、所詮山崎は中途半端なニヒリストもどきということにならないか。心底虚無的であったならば、もはや生きていること自体が億劫で「くだらない」と断じるだろう。人生など寝て起きて食べて排泄するだけの営みであると主張しなければなるまい。自殺しないのは、自殺そのものが大仰かつ面倒だからと嘯くのではないか。
考えてみれば、虚無的なんて気取っても甘えや執着が見え隠れしてしまうのが相場であろう。断固虚無的な人間、徹頭徹尾ニヒリストなんてものが存在していたとしたら、彼らは生きていること自体が矛盾のカタマリだろう。点滴を受けつつハンストをしている人物のように滑稽だ。
あれほど必死で勉強したのに、山崎は全科目に「優」を取れなかった。彼は書き残している、「教授の嗜好、気まぐれに相当依存さる優、良、可の区分に全生活をかけるのが馬鹿らしくなった」と。そして光クラブ創設へとシフトしていく。この軌跡は虚無的なんて表現には相応しくない。「拗ねている」というべきだろう。
しかし金融業創設の十四ヵ月後、経営破綻した山崎晃嗣は世の中を鼻で笑うような遺書を残して服毒自殺を遂げた。自己イメージをしっかりと保ちつつ死へダイヴしたわけで、その貫徹ぶりはそれなりに見事と評価すべきかもしれない。
結局のところ、山崎にとって虚無的であるというのは彼にとっての美学だったのではないのか。元来、彼にはニヒリストに近い素因があったのだろうし、保阪が書くように「戦後日本の俗物性を心から呪」うといった側面もあっただろう。だが最終的には、実はこの連載で前回記した【美学・哲学に殉じた自殺】に山崎のケースは相当するような気がしてならない。が、わたしは既に美学・哲学に殉じた自殺について、この分類項目は「とりあえず挙げてはおいたものの、実は山海経に載っている怪物に近い『いかがわしげな存在』と見なしておいたほうが適切でありそうに思えるのである」と疑念を呈したのだった。眉に唾をつけたのである。そうなると山崎晃嗣の自殺はどう解釈すべきなのか。
胸の内に押し隠していた自己愛や自己陶酔や怒り(それらは虚無感と対極に位置するだろう)が、もはやどうにもならない危機的状況において、美学的アイテムのひとつである「虚無的な自死」を居直りの方便として選択させただけではないのか。それは美学に殉じた自殺のニセモノでしかないだろう。贋ニヒリストが自分で用意した陳腐な花道でしかなかったのではあるまいか。
どうも虚無的という言葉には人を大いに惑わせるところがある。
虚無そのものを体現したS子は、
さりげなく自殺した
だが――わたしは、まさに虚無的という形容そのもののような人物と出会ったことがある。その人は雑居ビルの六階から飛び降りて死んだ。
S子が当該者である。四十代半ば、地方公務員の事務職であった。結婚歴はなく、実家との交流もほとんどない。職場でも仲のよい同僚はいない。つまりほぼ独りぼっちの生活で、しかしそれを苦痛に感じている気配は彼女にはなかった。
二十五歳でS子は統合失調症を発症している。幻聴や被害妄想に悩まされていた時期もあったが、数ヵ月の入院で改善し、仕事にも復帰出来た。地方公務員という、馘首される可能性の低い職に就いていたのは幸運だったとしか言いようがない。態度は素っ気ない上に声が小さく(だから窓口業務を担当させられることはなかった)、積極性はまったくなかった。が、課せられた事務仕事は黙々とこなした。出世には関心がなかった。決して残業はせず、定刻になると無言のまま職場を後にした。新人歓迎会や忘年会に出席することもなかった。「まあ、ああいう人だから」というのが周囲の評価であった。
四週間に一回、精神科病院の外来に通って再燃予防のために少量の薬を処方されていた。いくぶん変人めいたところのあったS子だけれども、トラブルを起こすことはなかった。他人に無視されても気にしなかった。喜怒哀楽を示すこともなかった。ユーモアとは完璧に無縁だった。やや背が高く、標準体重を三割程度オーバーしていた。服装は地味な色の安物で、およそ流行などには無頓着であった。黒縁の野暮ったい眼鏡を掛けていた。黒い髪は長く、それを無造作に海老茶色のバレッタで留めている。二重顎の顔に化粧っ気はなく、眉は男のように濃く太い。他人と視線を合わせようとせず、しかもいつもうつむき加減だったためなのか、妙に記憶に残りにくい目鼻立ちなのであった。
安アパートに住み、新聞は朝刊のみ定期購読していた。昼食は手作りの弁当で、でもおかずは蒲鉾に薩摩揚げが無造作に詰められているだけだったりした。退屈をまぎらわせるような趣味があるのかどうかもはっきりしなかった。
S子は、夏になると一週間ばかりアパートを離れた。が、旅行に行くわけでもないし実家を訪ねるわけでもない。彼女は休暇の一週間を、通院している精神科病院の開放病棟(大部屋)へ自ら入院して過ごすのだった。そうしたスタイルは二十年近く続いており、彼女なりのバカンスなのかもしれなかった。ことさら治療の必要もないから、朝の検温と血圧測定、それに当直医による夜の回診以外は医療者との交流もない。入院中も、ときたま散歩に出たりするものの、大概はベッドで週刊誌かスーパーのチラシを眺めていた。正直なところ、いったい何を心の拠り所にして生きているのか分からない人だった。
彼女の顔は記憶に残りにくいとさきほど記したが、そのいっぽうコミュニケーションをとろうとした者には忘れがたい印象を残した。もともと愛想がなく、何を考えているのか分からないようなところがあったが、いざ向きあってみると、まさに虚無感のかたまりのような印象を与えるのである。拒絶的ではないが、目の前の相手に微塵も関心がなく、それどころか世界全体に興味も何らかの感情もまったく覚えていないかのような雰囲気が、暗く深い洞穴から吹き出してくる冷気さながらに伝わってくる。投げやりな態度でも示してくれればまだしも理解した「つもり」になれようが、そんな分かりやすさとは無縁であった。S子に向けて発せられた言葉は、ことごとく真空の中で語られた言葉のように消え失せてしまいそうに感じられた。
誰もが、多かれ少なかれ「たじろがされた」。不吉さや禍々しさを感じ取った者もいたようだ。「何だか分からないけど、あの人は嫌」と露骨に陰口を叩く者もいた。が、だからといってS子に意地悪をする人はいなかった。そんな意欲を吸い取ってしまうようなトーンが彼女にはあったからだ。
統合失調症患者の一部には、幻覚妄想が消えて慢性期に入った後、人を寄せ付けない頑なさと強烈に虚無的な雰囲気とを身に纏うようになる人物がいる。それは症状の一部とみなすべきなのか、それとも精神疾患という経験が世界観や人生観を大きく変えてしまったのか、さもなければ脳機能に何らかの欠落が生じたのか。たとえば目の前で家族を殺されるような体験のある人が、それに呼応するように虚無的な人間になるかといえば、案外そうでもない。トラウマは抱え込んではいるだろうが、短絡的に虚無とつながるわけではない。本物の虚無は、ある種の特異体質ではないかと思えることがある。
さてS子は空が銀色に曇ったウィークデイに、駅前へ外出し、そのまま雑居ビルの屋上へ上って飛び降り自殺を遂げた。病院から屋上まで、その途中でどこかに立ち寄った形跡はない。靴を履いたまま飛び降りた。バッグは屋上に無造作に残されていた。遺書はなかったし、病院では自殺しそうな素振りなどなかった。ベッド周りが、死を覚悟したかのようにきちんと片付けられていたわけでもなかった。毎日その店の前を素通りしていたのに、ふと、当日に限ってその喫茶店に初めて足を踏み入れてみました――そんなさり気なさで、彼女は自らの命を絶った。
結局、わたしはS子のことをまったく理解出来ていなかった。自殺の理由も「きっかけ」も判然としない。虚無そのものを体現したような人間がときたまいるのだなあと思っただけであった。霊安室で彼女の実母を目にしたが、ごく普通の素朴な老女であった。自分が生んだ娘が自殺するのも相当に辛いが、我が子が虚無感のかたまりのような人物になってしまったという事実も耐え難い案件であったに違いなかろう。
わたしは光クラブの山崎晃嗣について述べた中で、「心底虚無的であったならば、もはや生きていること自体が億劫で『くだらない』と断じるだろう。人生など寝て起きて食べて排泄するだけの営みであると主張しなければなるまい。自殺しないのは、自殺そのものが大仰かつ面倒だからと嘯くのではないか」と書いたわけだが、そんな訳知り顔の理屈など蹴散らしてしまいかねないほどの激しい「負の存在感」をS子は発散していたのだった。彼女の唐突な自殺は、「やはり」といった嘆息しかわたしにもたらさなかった。
死ぬ機会を探しつつ生きる
自殺親和型の若者は存在する
四半世紀にわたって秋田大学・保健管理センターで若者のメンタルヘルスに向きあってきた精神科医がいる。苗村育郎という人で、彼の『自殺の内景――若者の心と人生』(無明舎出版、2015)にはきわめて興味深い指摘がなされている。彼によれば、「絶望親和型」「自殺親和型」とでも称すべき性格類型が存在するのではないかというのだ。
……物心がついたときから既に生きることのむなしさを強く感じ続けて、常に死ぬ機会を探しつつ生きている若者が少なからずいる。このこと自体、多くの人には理解しがたいことだろう。しかし「虚無感」との格闘が生涯のテーマであるという人は意外に多い。放蕩を尽くす人の中にもいると言われているし、他方耐え難い空しさからの救済を求めて早急に信仰の道へ入る人もいる。(中略)
絶望に先だって、強い不安を持続的に抱き続ける人もいる。この強い不安から逃れるために、呪術や宗教を必要とする人もいる。不安に強迫観念が加わって、神経症的傾向をさらに強める人もいる。不安を持ちながらも絶望には至らず、もがき続ける人もいるが、何らかのきっかけで追いつめられて死を選ぶこともある。あまりにつらい時期が長く続きすぎるのは、精神的視野狭窄と希望の喪失とをもたらす。このような状況になると、多くの人は、「もう死んで楽になりたい」と思い始めるのである。
この指摘には、強く頷きたい。率直に申して、「ああ、こういうことを考えていた精神科医がちゃんといたんだなあ」と安堵感に近いものすら覚えてしまった。実感として、たしかに自殺親和型の性格を持った人たちは存在する。苗村も述べているように、小学生のうちから心ひそかに厭世観や虚無感を深く持ち、自殺に容易に走ってしまいかねないタイプの人間を学問的に炙り出したり統計的なデータを収集するのは容易ではあるまい。自殺に踏み切るか否かの検証も至難の業だろう。こうした性格類型を受け入れるにあたって世間の強い感情的抵抗も予想されそうだし、自殺を本人の性格ゆえと言うのは無責任な発言だといった非難も予想される。
いまのところ、説得力を以てかれらを描出しているのは文学だけだろう。たとえば吉村昭の短篇「星への道」(1966)ではどうか。青年たちの動機のはっきりしない集団自殺を描いたこの作品では、環境的には恵まれているものの虚無感と倦怠感とに心を蝕まれた予備校生の圭一が、同じように(客観的には)無気力と怠惰に沈んでいた若者たちと知り合い、やがて集団自殺(海岸までトラックで旅をして、断崖から全員一緒に海へ身を投げる)へとのめり込んでいく契機が以下のように書かれている。
だが、旅立ちのことを望月が口にした時は、いつもの例とは全く異なっていた。その企てを、望月は、「死んじゃおうか」という投げやりな言葉で表現したのだ。
圭一は、唐突なその言葉に、一瞬背筋のかたく凍りつくのをおぼえ望月の顔に眼をすえていた。と同時に、かれは自分の周囲にひろがった静寂に気づいて、うろたえたように仲間たちの顔に視線を走らせた。かれらは、一様に口をつぐんでいた。表情は固くこわばり、その眼には凝固した光がはりつめていた。そして、その顔に変に弱々しい微笑が浮びはじめ、困惑しきった表情で互いに視線を逸らせ合っているのを、かれは照れ臭い気分で盗みみていた。その折の奇妙な沈黙を、圭一は、今もありありと思い起こすことができる。或る思いもかけない熱っぽいものが、それらを支配しはじめていたのだ。その中で、ただ最年少の望月だけが、自分の思いつきで口にした言葉に仲間たちが大きく心を動かされているらしいことに気づいて、眼鏡の奥の眼を嬉しそうに輝かせつづけていた。
ここで登場人物たちは、いわば自殺という選択肢を「発見」している。さもなければ、自らが自殺親和型であったことにあらためて気づいたのではないか。幼い頃からずっと死ぬ機会を窺い続けてきた人間もいれば、些細な契機で自分の自殺親和型ベクトルに目覚める人物も少なからずこの世には存在しているのではないか。ことに後者のような人々があっさりと自殺を遂げたとき、残された者たちは死の動機を捜し求めようとして激しく当惑することになるのだろう。
わたしたちの何割かは、ある日不意に自分の人生の意味に気づく。もっとも必ずしもそれが正しいとは限らず、むしろ意味に気づいたような気分になると表現すべきだろう。わたしはこういったことをするために生まれてきたんだ、とか我が人生の使命はこのようなことであるといった具合に。他方、今までの生きづらさや人生に対する違和感が実は自分が自殺親和型の精神構造をもっていたからなのだと悟ったり、「ああそうだ、自ら用意した死で決着をつけるといった生き方もあったじゃないか! これを失念していたから自分は無駄な苦しみを味わっていたのだなあ」と閃くケースもあるわけだ。そう、しばしば自殺という奇怪な妙案は天啓のようにして「発見」されるのである。
ところで自殺親和型であるということは、まったく自分自身の問題である。死に対する根源的な一体感(ときには、やすらぎ)のようなものがある。だがそのいっぽう、死を駆け引きの材料やドラマチックな要素として持ち出したがる人たちがいる。彼らにとって死は常に他者との関係性において「最強のカード」として用いられる。そうした人々は【⑥死を弄んだ挙句の自殺】であらためて述べるつもりだが、ときたま自殺親和型と区別がつきにくいことをここでは指摘しておきたい。
(第六回・了)
 1951年京都生まれ。日本医科大学卒業。医学博士。産婦人科医を経て精神科医に。都立中部総合精神保健福祉センター、都立松沢病院部長、都立墨東病院精神科部長などを経て、現在も臨床に携わる。著書に『無意味なものと不気味なもの』(文藝春秋)、『幸福論』(講談社現代新書)、『精神科医は腹の底で何を考えているか』(幻冬舎新書)、『臨床の詩学』(医学書院)、『老いへの不安 歳を取りそこねる人たち』(朝日新聞出版)、『鬱屈精神科医、占いにすがる』(太田出版)等多数。
1951年京都生まれ。日本医科大学卒業。医学博士。産婦人科医を経て精神科医に。都立中部総合精神保健福祉センター、都立松沢病院部長、都立墨東病院精神科部長などを経て、現在も臨床に携わる。著書に『無意味なものと不気味なもの』(文藝春秋)、『幸福論』(講談社現代新書)、『精神科医は腹の底で何を考えているか』(幻冬舎新書)、『臨床の詩学』(医学書院)、『老いへの不安 歳を取りそこねる人たち』(朝日新聞出版)、『鬱屈精神科医、占いにすがる』(太田出版)等多数。