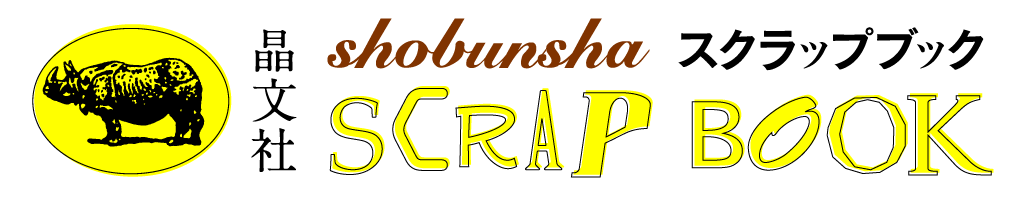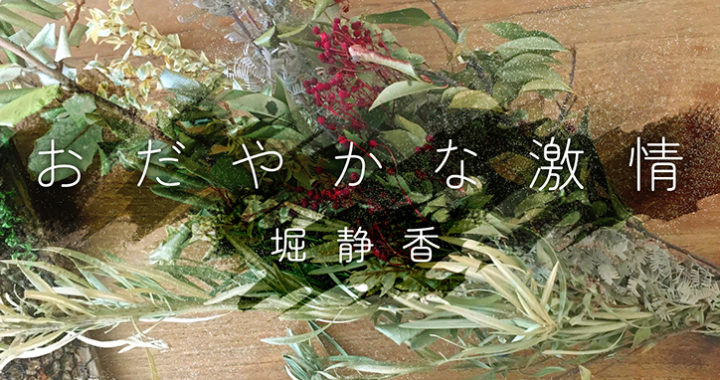やさしい夫がいて、かわいい子どもがいて、食卓には笑いがたえなくて。実家の両親はたのしく暮らしているし、おばあちゃんも気丈で元気だ。なのにどうしてこんなに不安で怖いのだろう。明日あの角を曲がると、奈落が待ち構えているのかもしれない……。誰も死んでほしくない。死なれたくない。なにげない日々の出来事から生の光と死の影が交錯する、おだやかで激しい日常の物語。
春の学校行事のひとつに、交通安全教室というものがあって、それが今日だった。
毎年新学期に入ってすぐのこの時期、ふいに授業がつぶれて、それで(ああ今年も交通安全か)と思い出す。入学したばかりの中学生のみならず、全校生徒が対象らしい。今年のわたしの担当は高三で、受験生である彼らも、だからしっかり授業返上で交通安全教室に出るという。
翌日、授業のはじめに昨日の話を向けてみる。高三にもなって「自転車のマナー」なんて今さらって感じだよねえ。自転車といえば、もういまはだれも二人乗りなんてしなくなったね。昔はみんなやっててさ、わたしも毎日後ろに友だち乗せてたよ。今はさすがに怒られるもんね。傘差しながら自転車乗る人もいつの間にかいなくなったよね。わたしいまでもやっちゃうけど。なんてつまらない話をべらべら喋ってしまう。
高三生は大人しい。授業もそうでない雑談も、黙って、同じ微笑みをたたえてわたしの話を聞いてくれる。ここ数年はたまたま中学生を担当することが多かったので、そのギャップに驚く。大人しい、というか彼らは、もうほとんど大人なのだ。十八歳の誕生日を迎えれば彼らは成人で、選挙権だってある。授業前に教室に入ると、それぞれ席に着いて単語帳を開いていたりする(中学生はたいてい騒ぎながら廊下を駆けている)。こちらに映る彼らは、とても落ち着いて、そして真面目である。
なおもつまらぬ雑談をやめないわたしを、どこか虚ろに見つめるまなざしに、ふと強烈な懐かしさを感じる。既視感と言ってもいい。いや、既視感と言いながらもそのとき、わたしはその生徒の未来を勝手に想像しているのだった。
たとえば、一番前に座る彼は自己紹介のときに大学では看護学科に進みたい、と話していた。生徒の進路を知ると、ありありとその姿が思い浮かぶことがある。真面目な彼ならきっと、上手くいくだろう。そういう勝手な確信からか、着実に勉強を重ね、受験をパスし、勉強やバイトなどに忙しくも充実したキャンパスライフを送り、そして白衣を着ていきいきと働くその姿が、手に取るように見えるのだ。
生徒の未来が脳内に早送りのように巡る。これまでにたくさんの生徒たちの卒業を見送ってきたからだろうか。ひとりの生徒の未来が、そんなふうに懐かしさを伴って、「見える」ことがある。もちろん、生徒の未来などわたしの勝手な、それも一瞬間の想像に過ぎない。だいいち、当たり前のこととして、何が起こるかなど、だれにもわからないのだ。
「もしあーちゃんがこの海のなかに飲み込まれたら、どうする?」と子どもが問う。
子は、おもちゃやお菓子やらが謎の渦にどんどん飲み込まれる、というふしぎなYouTubeを見ていたのだった(ほんとうに謎のYouTubeというのが山ほどある)。あるいは、保育園からの帰り道、線路傍を自転車で通りかかると「もし電車が脱線してあーちゃんをひいっちゃったら、どうする?」と言う。
この、「もし〜だったらどうする?」構文は子どものなかにつねにあって、何かにつけて不安とともに表明される。他の子どももそうなのか、あるいは、うちの子どもがとりわけ心配性なのだろうか。もしかして、心配性って遺伝するのか? などと真面目に考えてしまうほどに、子どもはあらゆることを案じている。そのちいさくて尊い心配が、いつしか「死」そのものへの恐怖へと結びついてしまうことを、勝手に案じている。
そうして不安そうに子どもに何かを訊かれるたびに「すぐにママが助けるから大丈夫」と返す。すると子は一応ほっとして「よかったぁ」と言う。どんな危険な状況でも、ママは飛んで助けに来ることになっている。だからわたしはそのたびに謎の渦に飛び込み、脱線した電車から子どもを救う。大げさに張り切って見せるたびに、「ママはすごいね」と子どもは感心する。
けれど、ほんとうは子ども以上にわたしは日々、「もし〜だったらどうしよう」を考えつづけている。そういう強迫的な心配性というのが子どもに伝わってしまっているのかもしれない。
もしも家族が事故に遭ったら、自分が病気になったら。起きるかもしれないことは、あくまで可能性であって、いまここにその事実は存在しない。だいたい何も起こっていないのだから、いま考えても仕方ない。起きてから考えればいい。けれど、それが起こりうるかもしれないこと自体がやっぱりどうしても、恐ろしい。
「心配事の約9割は実際には起きません」という言説を、だからわたしは頑なに信じない。目下の心配事が起こり得る現実そのものの怖さにいま支配されているのだから、それらしきデータを示されても、慰めにはならない。そんなふうにつねに何かを案じ、思い詰め、ネガティブな想像をフルに働かせるわたしは、たぶん損気なのだと思う。
小学生の頃、ふと「いま、心配なことがひとつもない」と気づいて飛び上がるくらいうれしかったことを思い出す。当時の悩みと言ってもそれはたとえば体験学習の班決めだとか席替えだとか授業のちょっとした発表だとか、いま思えば悩みとも呼べないささやかなできごとである。
といって当時の悩みを矮小化したいわけではない。むしろ子どもの頃はその世界の狭さゆえに思い詰めてしまうことも多く、そういう意味では独特のしんどさがあった。それでも目下の懸念事項は、時が経てばいつかは片づいた。授業の発表も席替えも、過ぎてしまえばなんてことはない。その日の放課後は清々しい気持ちで遊びに出かけたし、そういう真剣な小学生の日常をいたって真面目に送っていただけなのだ。「あ、いまは嫌なことがなんにもない」という、ふいに訪れるまっさらな心の快晴、その瞬間をわたしは全身でよろこんだ。そういうときはわかりやすくスキップだってした。
死がいちばんつよいなどという考えがわたしを殺すまでの青空 大森静佳
けれどいつからか、気づけばわたしの心配のすべては「いつか死ぬこと」に避けがたく結びついてしまった。死がずっと怖い。死がいちばん強い。今日をつつがなく終えることができたのだから、明日もきっと問題なくやって来るだろう。そう確信しながら、けれど油断してはならない。隙をついてそれはわたしの肩をものすごい力で摑むのではないか。あーちゃんが事故に遭ったら。夫が倒れたら。父や母に何かあったら。心配は、すればするほど自分を守ると信じて疑わない。それは、もはや強迫観念めいている。
教室で顔を合わせたばかりの高三生の、自転車のマナーなんてもう百も承知、というあの眠そうな瞳を思い出す。
彼らは進級したこの春から、それはもう嫌になるほど「受験だ受験!」と教員に尻を叩かれている。いつも眠そうで、虚ろな瞳。けれどこの苦しい受験を乗り越えれば大学生になれると信じて疑わない。もちろん、それは疑うことではない。きっと彼らには望んだ通りの、(あるいは場合によってはそうではない)けれどそれぞれの「未来」がやって来る。大きな事故に遭えば死んでしまうなんて、考えない。いや、考えなくていい。死んでしまったら大学生にも、看護師にもなれないのに、なんて勝手に不要な心配をして悲観するのはきっとわたしだけだ。
けれど毎年、ほとんど惰性の行事として、校内で「交通安全教室」をやるのは、ほんとうには生徒に事故に遭ってほしくないからだ。彼らに死んでほしくないからだ。当たり前で、当たり前すぎて考えもしないような、わたしたち大人のこのおおきな祈りを思い出して、はっとする。
二人乗りは危険なのでいけません。傘差し運転も、いまは罰則があります。自転車に乗るときは必ずヘルメットをかぶりましょう。自分の身は自分で守る、そう肝に銘じることはとても大切です。それではみなさん、これからも交通ルールを守って、安全に運転しましょう。そんな明朗な警察官の声を、わたしは想像する。
何かはいま起きて、何かは起こらない。
わたしにも、そしてあなたにも起こらなかった。でもすぐに起きるかもしれない。このひとつの深呼吸の後に。思いきり笑い合った直後に。いま目の前に広がるこの青空には裏があるのではないか。こんなにも澄み切って、風さえ心地よく吹いて、近くの小学校からは子どもたちの声が聞こえる。この空はほんとうには信じられない強さで張りつめて、張りつめていることをだれも知らない。わかり得ない。それはいま、すべて可能性でしかないのだから。
だからやっぱり、思いつめてしまう。わたしがかけられる最大限の心配を、できるだけ広い範囲の心配をかけて、守ろうとする。そしてそれは、ふだんわたしが顔を合わせるような、あるいは顔を思い浮かべることのできるような、この自分の手の、自分の想像の届く範囲の心配であり、祈りに過ぎないということを思う。何も起こりませんように、だれもかなしみませんように。飽きずに何度でも祈る。けれどそのたびに、それはつまり自分の想像の及ぶ範囲の他者への関心であるということを思ってもいる。この己の傲慢さをわたしは無視しつづけている。
青空がわたしの繭であったこと 見つめつづけて全部壊した 大森静佳
嘘みたいな青空に出くわすことがある。そのまま、嘘みたいだなと思う。思うだけで口にはしない。だってこれは現実だから。この青空は「見つめつづけ」れば、「全部壊」すことができるという。繭のように守られながら必死に守りつづけるこのわたしの青空を、わたしは壊すことができるだろうか。こんなにおだやかな青空を自分で壊すなんて。けれど自らの青空を、この嘘みたいな青空を、自らの手で壊す人はいるのだ。この先の、もっともっと先の色のない空へと自分の手を、こころを、身体を向かわせることのできる人がいるのだ。
いまここに広がる青空は、ほんとうにはぺらぺらの紙なのかもしれない。ただの紙ならば、一突きで破くことができる。それが薄っぺらい紙かもしれない、ということからいつまでも目をそらして、そらしつづけて、わたしはわたしの青空に手を伸ばすことができない。
(了)
Back Number
- 第12回 わたしの青空
- 第11回 なめらかな過去
- 第10回 ちぐはぐな部屋
- 第9回 この世の影を
- 第8回 映したりしない
- 第7回 とばされそうな
- 第6回 はらはら落ちる
- 第5回 もしもぶつかれば
- 第4回 つややかな舌
- 第3回 鴨になりたい
- 第2回 かがやくばかり
- 第1回 いまこのからだで目に映るもの